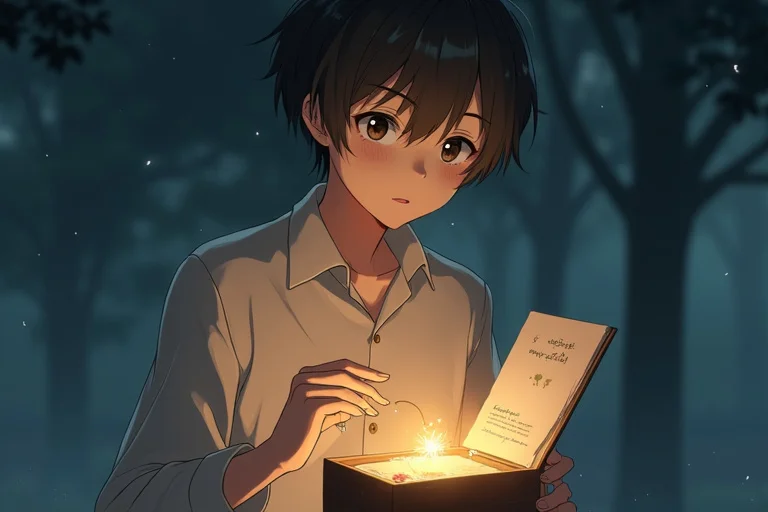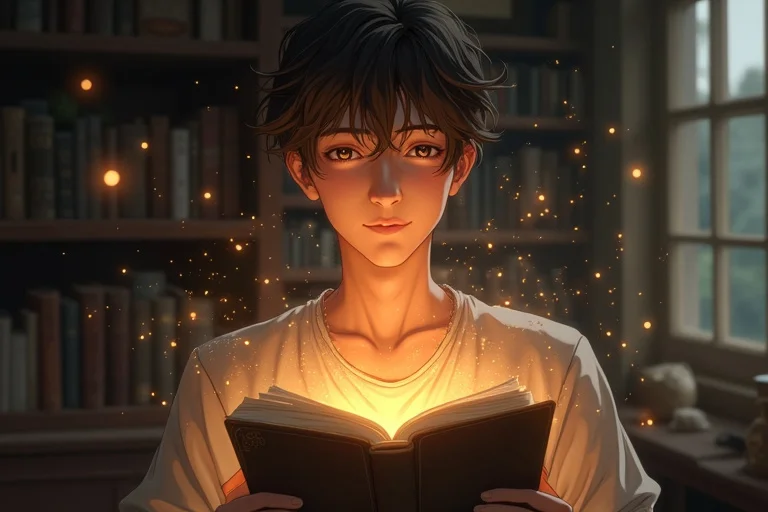第一章 甘くて塩辛いキャラメルの味
柏木湊(かしわぎ みなと)の舌は、呪われていた。
彼が遺品整理士という、死者の沈黙と向き合う仕事を選んだのは、その呪いのせいであり、また、その呪いのおかげでもあった。湊は、亡くなった人が最後に触れた物に触れると、その人が最期に抱いた感情を「味」として感じ取ることができる。喜びは蜂蜜のように甘く、悲しみは凍てつく氷のように冷たく舌を刺す。それは、他人の人生の最終章を、否応なく味わわされる拷問にも似ていた。
今日の現場は、都心から少し離れた古いアパートの一室。高遠静子、八十二歳。孤独死だった。警察の無機質な説明によれば、死後二週間が経過していたという。ドアを開けた瞬間に鼻を突く、甘ったるい死の匂いに混じって、湊は埃と古い紙の匂いを嗅ぎ分ける。部屋は驚くほど整然としていた。まるで、いつ客人が来てもいいように準備していたかのようだ。
湊は手袋をはめ、 methodical に作業を始めた。衣類をまとめ、食器を箱に詰める。その過程で、彼は極力、故人の「想い」が強く残りそうな品には触れないようにしていた。日記、手紙、写真。それらは、強烈すぎる味の爆弾だ。
しかし、書斎机の引き出しを整理していた時、彼の指が一本の古い万年筆に触れた。黒檀の軸に、金のペン先。使い込まれて滑らかになったそれは、静子の指の形に馴染んでいるように見えた。その瞬間、湊の口の中に、予期せぬ味が広がった。
それは、驚くほどに優しく、温かい味だった。
焦がした砂糖の香ばしさと、ミルクのまろやかさ。そして、後から追いかけてくる、ほんの一筋の塩味。まるで、幼い頃に祖母が作ってくれた手作りのキャラメルのような、懐かしくて胸が締め付けられるような味。湊が自身の能力で定義するならば、これは紛れもなく「幸福な追憶」の味だった。
湊は眉をひそめた。孤独死。誰にも看取られず、二週間も発見されなかった老婆が、最期に感じていた味が「幸福な追憶」? 矛盾している。この甘くて塩辛い味は、まるで幸せな記憶の涙のようだ。一体、彼女は何を想って、この万年筆を握りしめていたのだろう。
部屋の隅に置かれた小さな仏壇には、遺影すらなかった。ただ、小さな花瓶に、完全に水分が抜け落ちてカサカサになったカーネーションが一本、寂しげに刺さっているだけだった。孤独の気配しかしないこの部屋で、湊は初めて、死者の声なき声に耳を傾けたいという、強い衝動に駆られた。そのキャラメルの味の源泉を、どうしても知りたくなったのだ。
第二章 ほろ苦いチョコレートの在り処
湊は、静子の人生の断片を拾い集めるように、部屋の探索を続けた。それは通常の業務を逸脱した行為だったが、あのキャラメルの味が彼を突き動かしていた。
本棚には、宮沢賢治や新美南吉の童話集が並んでいた。どれも、何度も読み返されたのだろう、表紙が擦り切れ、ページには無数の指の跡が染み付いている。湊がその一冊に触れると、口の中に「穏やかな日向のような味」が広がった。それは平穏な日常の味だった。裁縫箱に触れれば、「少し酸っぱいレモンのような味」。何かをやり残した、小さな後悔の味だろうか。
彼女の人生は、決して不幸なだけではなかった。ささやかな喜びと、小さな後悔を積み重ねてきた、ごくありふれた人生の軌跡がそこにはあった。だが、湊が求めるキャラメルの味の核心には、まだたどり着けない。
探索は、寝室の古い桐箪笥へと行き着いた。一番下の引き出しの奥、防虫剤の匂いが染み付いた着物に隠されるようにして、一冊のアルバムが仕舞われていた。湊は息を呑み、ゆっくりとそれに触れた。
アルバムからは、様々な味がした。甘酸っぱい苺の味、爽やかなミントの味、ピリリと刺激的な山椒の味。ページをめくるたび、静子の人生が味覚となって湊の中に流れ込んでくる。そして、最後の方のページに、それはあった。
一枚だけ、台紙に貼られずに挟み込まれた写真。セピア色に変色したその写真には、若き日の静子と、学生服を着た少年が、少し照れくさそうに笑いながら写っていた。背景には、満開の桜並木が見える。湊は震える指で、その写真にそっと触れた。
途端、口の中に濃厚な味が迸った。
それは、カカオ分九十パーセント以上の、ビターチョコレートのような味。強烈な苦味の奥に、深く、そして抗いがたいほどの甘さが隠されている。それは、湊が今まで味わったことのない、複雑で、あまりにも切ない「愛情」の味だった。喜びも悲しみも、希望も絶望も、全てを溶かし込んで固めたような、凝縮された想い。
この少年だ。静子が最期に思い出していたのは、きっとこの少年との記憶に違いない。彼は誰なのだろう。息子か、あるいは、他の誰かか。湊は、このほろ苦いチョコレートの味の正体を突き止めるべく、故人の戸籍を調べるという、最後の手段に踏み切ることを決意した。それは、死者のプライバシーの最も深い部分に触れる、禁断の行為だった。
第三章 焦げ付いた砂糖の真実
数日後、湊は興信所の調査報告書を手に、自室で立ち尽くしていた。写真の少年は、高遠静子の一人息子、正人(まさと)。三十年前に、十八歳という若さで交通事故に遭い、亡くなっていた。
「やはり……」。湊の口から、乾いた声が漏れた。最愛の息子を亡くした母親。彼女が抱いていた深い愛情と切なさの味は、当然のものだった。万年筆から感じた「幸福な追憶」は、息子が生きていた頃の、幸せな日々の記憶だったのだろう。そう結論づければ、話は終わるはずだった。
だが、報告書の最後の一文が、湊の世界を根底から揺るがした。
『事故の加害車両運転手:柏木雄三(かしわぎ ゆうぞう)』
柏木雄三。それは、湊が物心ついた頃に、家族を捨てて蒸発した父親の名前だった。
全身の血が逆流するような感覚に襲われた。頭の中で、バラバラだったピースが、おぞましい形に組み上がっていく。湊の脳裏に、幼い頃の記憶が鮮明に蘇った。父親が家を出て行った日、彼の部屋には、言いようのない匂いが立ち込めていた。その部屋の机に触れた時、幼い湊の舌が感じた、あの味。
――焦げ付いた砂糖のような、救いのない絶望の味。
あの味は、父親が犯した罪の味だったのだ。人を殺めてしまったという、拭い去れない罪悪感と絶望。湊がずっと目を背けてきた父親の記憶が、三十年の時を経て、高遠静子という一人の女性の死を通して、彼の目の前に突きつけられた。
自分の父親が、彼女から最愛の息子を奪った。
そして自分は今、その彼女の遺品を整理している。
なんという皮肉だろうか。湊が「呪い」と呼んでいたこの能力は、この残酷な真実を彼に告げるために存在していたとでもいうのだろうか。湊は膝から崩れ落ちた。口の中に広がるのは、もはや何の味もしない、ただただ乾いた砂のような無力感だけだった。彼は、自分の存在そのものが、高遠静子の人生を冒涜しているように感じられた。
第四章 白湯に溶ける涙
罪悪感に苛まれながらも、湊は再び静子の部屋を訪れた。彼女の人生に、そして父親が犯した罪に、正面から向き合わなければならないと思ったからだ。彼は、調査で判明した静子の唯一の遠縁(姪にあたる女性)に連絡を取り、遺品を引き渡す約束を取り付けていた。
部屋の空気をもう一度吸い込む。そこには、初めて来た時とは違う、悲しくも澄んだ空気が流れているように感じられた。湊は、息子を亡くした日から三十年間、静子がどのような想いでこの部屋で過ごしてきたのかに思いを馳せた。
最後に、彼は意を決して、あの小さな仏壇に手を合わせた。そして、その脇に置かれていた、手のひらサイズの小さな桐の箱を手に取った。これまで、怖くて触れることができなかった、彼女の一番の宝物であろう品だ。
蓋を、そっと開ける。
中には、赤いビーズと青いビーズで不格好に作られた、子供の手作りとわかる指輪が、大切そうに綿に包まれて納まっていた。おそらく、幼い正人君が母の日に贈ったものだろう。
湊は、深呼吸を一つして、その小さな指輪に指先で触れた。
その瞬間、彼の全身を、経験したことのない感覚が貫いた。
それは、「味」ではなかった。いや、味覚を超えた、もっと根源的な感覚だった。
まるで、生まれたての赤ん坊が初めて口にする、母の温もりを含んだ白湯のような。何の雑味もなく、ただただ温かく、清らかで、すべてを赦し、包み込むような、無垢で純粋な愛情そのものだった。
苦しみも、悲しみも、絶望も、長い年月を経て昇華された果てにある、究極の愛の形。静子は、息子の死を嘆き悲しむだけでなく、彼がこの世に生を受けてくれたこと、短い間でも共に過ごせた幸せな時間を、ただ純粋に愛し続けていたのだ。
湊の目から、熱い涙が止めどなく溢れ落ちた。それは、静子の計り知れない愛情に対する感動の涙であり、彼女の人生を奪った父親への、そして何も知らずに生きてきた自分自身への、贖罪の涙でもあった。
彼の呪われた舌は、今、確かに救われた。この能力は呪いなどではなかった。声なき人々の、言葉にならない最後の想いを、心で受け止めるための、あまりにも優しい奇跡だったのだ。
数日後、姪に遺品を引き渡した帰り道、湊はふと空を見上げた。茜色に染まる空が、目に痛いほど美しい。道端に咲く名も知らぬ花の香りが、やけに甘く感じられた。これまで彼が意識的に閉ざしてきた世界が、ゆっくりと色と音と匂いを取り戻していく。
湊はこれからも、遺品整理士として生きていくだろう。死者の最後の「味」を拾い集め、それを誰かに繋いでいく。それは、彼にしかできない、静かな使命なのだ。口の中にまだ微かに残る、あの白湯のような温かい余韻を確かめながら、柏木湊は、未来へと向かって、確かな一歩を踏み出した。