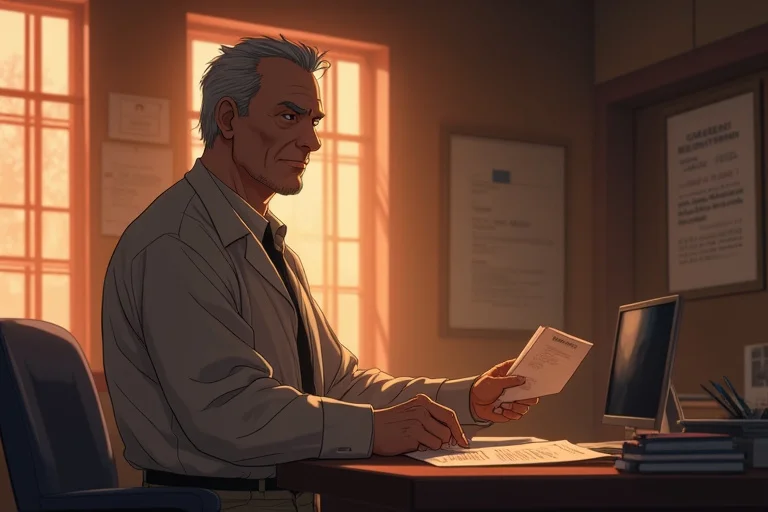第一章 人生最後の宿題
田中誠、四十五歳。中堅文具メーカーの営業課長。彼の人生は、彼が愛用する万年筆のインクのように、黒一色で塗り固められていた。生真面目、几帳面、融通が利かない。それが彼の代名詞であり、部下からは「歩く定規」、高校生の娘・美咲からは「昭和の化石」と揶揄される所以だった。彼自身、そんな自分の人生が、埃をかぶった標本のように色褪せていることを自覚していたが、変え方が分からなかった。
そんな彼のモノクロームな日常に、突然インクをぶちまけるような出来事が起きたのは、父・剛(つよし)が亡くなって一月ほど経った、蒸し暑い夏の日のことだった。厳格で、寡黙で、誠にとって絶対的な「正しい大人」の見本であった父。その遺品を整理するため、誠は実家の書斎に足を踏み入れた。
書斎は父の匂いがした。古い紙と、微かな墨の香り。整然と並ぶ法律関係の専門書。父は退職後も、地域の法律相談に乗るような、どこまでも真面目な人だった。誠は、自分という人間が、この父の鋳型から作られたのだと改めて思う。
本棚の奥、父が大切にしていたらしい古びた桐の箱を見つけた。埃を払い、蓋を開ける。中に入っていたのは、一通の黄ばんだ封筒と、数枚の厚紙のカードだった。封筒には、父の几帳面な筆跡で『人生最後の宿題 ~息子・誠へ~』と書かれていた。
「宿題…?」
誠は眉をひそめながら封を開けた。
『誠へ。
この手紙を読んでいるということは、俺はもうそっちにはいないんだろうな。まあ、寿命だ。しんみりするな。
さて、唐突だが、お前に人生最後の宿題を出す。俺からの、これが最後の親父としての仕事だ。
お前の人生は、それで面白いのか?
一度きりの人生だ。もっと馬鹿みたいに笑ったり、誰かを笑わせたりしてみろ。お前は昔、もっと面白い奴だったはずだ。
箱の中のカードに書かれた指令を、一つずつ実行すること。すべてやり遂げた時、お前はきっと、何かを見つけるだろう。
じゃあな。達者でやれ。
父・剛より』
手紙を読み終えた誠は、混乱した。面白い奴? 冗談じゃない。物心ついた時から、父に「真面目が一番だ」と叩き込まれてきたはずだ。それに、このふざけた文体はなんだ? まるで別人のようだ。
震える手で、一番上にあったカードを手に取る。そこに書かれていた指令に、誠は絶句した。
指令その一:明日、会社の朝礼で、渾身のモノマネを披露せよ
血の気が引いた。目の前が真っ暗になる。これは、父の悪趣味な冗談か? それとも、晩年は認知症が進んでいたのか? 真面目一徹だった父のイメージが、ガラガラと音を立てて崩れていく。誠は、その理解不能な指令が書かれたカードを握りしめ、ただ立ち尽くすことしかできなかった。彼の退屈な人生が、最も望まない形で、根底から揺さぶられようとしていた。
第二章 滑稽なるミッション・インポッシブル
翌朝、誠は生きた心地がしなかった。寝床で何度も寝返りを打ち、結局一睡もできずに会社へ向かう。バッグの中には、あの忌まわしい指令カードが入っている。まるで時限爆弾のようだ。
「無視しよう。そうだ、父の迷言だ。真に受ける必要はない」
そう自分に言い聞かせるが、手紙の最後の一文が脳裏にこびりついて離れない。『お前は昔、もっと面白い奴だったはずだ』。
思い出そうとしても、思い出せない。面白い自分なんて、いただろうか。ただ、高校生の娘・美咲に「パパってマジメすぎて息苦しい」と言われた時の、彼女の寂しげな顔が浮かんだ。
朝礼の時間。営業部の全員が会議室に集まる。誠が壇上に立つと、いつものようにシンと静まり返った。誰もが、いつもの退屈な訓示が始まるのだと覚悟している顔だ。
誠はゴクリと唾を飲んだ。心臓が肋骨を内側から叩いている。やるのか。本当に、やるのか。
彼の視線が、部屋の隅に立つ若手社員の田口と合った。いつも反抗的で、誠が最も苦手とするタイプの男だ。田口は、退屈そうにあくびを噛み殺している。
その瞬間、誠の中で何かが弾けた。
「……えー、諸君、おはよう」
いつも通りの硬い声。だが、続けた言葉は誰もが予想しないものだった。
「本日の連絡事項の前に、一つ。……我が社の新製品、『超速乾ゲルインクボールペン・疾風』の素晴らしさを、この方にご説明いただこう。どうぞ、若山富三郎さんです!」
シーン……。
時間が止まった。誰かのペンが床に落ちる音だけが、やけに大きく響いた。
誠は目を固く閉じ、記憶の底から引っ張り出した、幼い頃に父と見た時代劇映画のワンシーンを再現した。
「……こいつぁ、ただのペンじゃねえ。書いた瞬間に乾き、相手の心を射抜く……まさに、武士の魂よぉ……」
似ても似つかない、ただの嗄れた声。しかも、若手社員のほとんどは若山富三郎など知らない。数秒間の沈黙の後、誰かが吹き出すのを皮切りに、クスクスという笑いが漏れ始めた。それは嘲笑に近かったが、反抗的だった田口が腹を抱えて笑っているのが見えた。
「課長……マジすか……最高じゃないスか……!」
顔を真っ赤にして席に戻る誠に、田口が親指を立てた。恥ずかしさで死にそうだったが、凍りついていた職場の空気が、ほんの少しだけ溶けたような気がした。
それからというもの、誠の奇行は続いた。
指令その二:公園のハトに、ベートーヴェンの『運命』を聴かせよ
彼はラジカセを手に公園へ赴き、ジャジャジャジャーンという荘厳な調べをハトの群れに浴びせた。ハトは一斉に飛び立ち、近くでランチをしていたOLたちから変人を見る目で見られた。
指令その三:駅前の広場で、五分間サンバを踊れ
見よう見まねの滅茶苦茶なステップは、通行人の失笑を買った。しかし、一緒に手拍子をしてくれる酔っ払いや、面白がって動画を撮る若者もいた。
指令をこなすたびに、誠は大量の恥をかいた。だが、不思議なことに、彼の世界は色づき始めていた。今まで風景の一部でしかなかった人々が、表情豊かな個人として見えてきた。誰かの小さな親切が、見知らぬ人の笑顔が、アスファルトに咲く花のように心を温めた。
娘の美咲も、彼の変化に気づいていた。「最近、パパなんか変だけど……前よりはマシかな」ぶっきらぼうにそう言いながらも、食卓での会話が少し増えた。
誠は、父が遺した宿題の意味を、まだ完全には理解できていなかった。だが、この馬鹿げたミッションが、自分の人生に風穴を開けてくれていることだけは、確かだった。
第三章 父の秘密と涙のワルツ
箱に残された指令カードは、とうとう最後の一枚になった。誠は深呼吸をして、そのカードを裏返した。そこに書かれていたのは、これまでで最もシンプルで、最も難しい指令だった。
最後の指令:母さんを、心から笑わせろ
誠の母・静子は、父が亡くなってからというもの、すっかり笑顔を失っていた。日に日に口数が減り、ただ窓の外をぼんやりと眺めて過ごすことが多くなった。大好きなテレビの時代劇も、もう見ていない。誠は何度も実家に顔を出したが、母の心の扉は固く閉ざされたままだった。
「よし、やるぞ」
誠は、これまで培ってきた(?)コメディアンとしてのスキルを総動員する覚悟を決めた。
まずは十八番になりつつある、若山富三郎のモノマネ。母は一瞥しただけで、すぐに視線を窓の外に戻してしまった。次に、覚えたてのサンバ。ぎこちない腰つきに、母は「……みっともないからやめなさい」と力なく呟くだけ。渾身のダジャレ攻撃も、虚しく空を切った。
「布団が吹っ飛んだ、なんてどうかな、母さん!」
「……誠、疲れているのなら、もうお帰りなさい」
何をしても、母の心には響かない。誠は途方に暮れた。父さん、あんた、無茶だよ。こんなの、できるわけないじゃないか。
その夜、誠は答えを求めて、再び父の書斎にいた。何か、母を笑わせるヒントはないか。本棚を漁り、引き出しを片っ端から開けていく。そして、一番下の引き出しの奥に、鍵のかかった一冊の日記を見つけた。鍵は桐の箱の底に隠されていた。
日記を開いた誠は、息を飲んだ。そこには、彼の知らない父の姿が、生々しい言葉で綴られていた。
『昭和四十一年四月。今日も漫才の相方にダメ出しされた。俺には華がないらしい。悔しい。でも、客席で静子が笑ってくれる。それだけで、俺はまだ頑張れる』
『昭和四十二年一月。コンビ解散。俺の夢は終わった。静子にプロポーズした。これからは、彼女と生まれてくる子のために、真面目に生きると誓った。さよなら、俺の夢』
『平成五年七月。息子の誠が就職した。俺に似て、真面目すぎるくらい真面目な男だ。それでいい。それが幸せへの一番の近道のはずだ。だが、時々不安になる。あいつは、本当に人生を楽しんでいるのだろうか』
ページをめくる手が震えた。父は、お笑い芸人を目指していた。あの厳格な父が? 信じられなかった。彼は夢を諦め、家族のために「真面目な父親」という重い鎧を、生涯着続けていたのだ。
日記の最後の日付は、亡くなる一週間前だった。
『誠。お前の人生は、それで面白いのか? その言葉は、若い頃の俺が、鏡の中の自分に何度も問いかけた言葉だ。真面目に生きることは尊い。だが、笑って生きることは、もっと尊い。お前は面白い男なんだ。父さんが保証する。だから、最後の宿題は、お前自身が「面白い」と思う方法で、母さんを、そしてお前自身を笑わせてやってくれ。それが、父さんへの最高の手向けだ』
指令は、息子を縛るためのものではなかった。自分と同じように「真面目」という檻に囚われた息子を、解き放つための、父の最後の愛情だった。誠の頬を、熱い涙が伝った。父は厳格だったのではない。世界で一番、不器用で、優しいコメディアンだったのだ。
第四章 世界で一番、不器用なコメディアン
翌日、誠は父の日記を手に、母の前に座った。
「母さん。父さんのことで、大事な話があるんだ」
彼は、訥々と語り始めた。父が若い頃、お笑い芸人を目指していた夢の話。母の笑顔を見るために、舞台に立っていた話。そして、家族のためにその夢を封印し、たった一人で「真面目な父」を演じ続けてきた、不器用な愛情の話。
母の静子は、驚いたように目を見開き、食い入るように誠の話に耳を傾けていた。その目には、うっすらと涙が滲んでいた。
「父さん、日記に書き溜めてたんだ。誰にも見せたことのない、渾身のギャグを」
誠は照れくさそうに頭を掻くと、日記の一節を読み上げた。
「『もしもし、亀よ、亀さんよ。……え、間違い電話? 失礼しました』……どうかな」
一瞬の沈黙。誠は、また滑ったか、と顔を赤らめた。
すると、母の肩が小さく震え始めた。最初は、クスクスという忍び笑いだった。
「……ふふっ。あの人らしいわ。ちっとも、面白くない」
そう言った母の目からは、大粒の涙がこぼれていた。でも、その口元は、確かに笑っていた。
誠は続けた。
「『エレベーターで屁をこいたのは、エエ、ベーターです』」
「……ふふ、ふふふっ」
「『この羊羹、よー、噛んで食べなさい』」
「あははっ……! なにそれ……!」
父が遺した、お世辞にも上手いとは言えない、けれど愛情だけはたっぷりと詰まったギャグの数々。それを不器用な息子が、照れながら披露する。その光景が、たまらなくおかしくて、そしてたまらなく愛おしくて、静子は声を上げて笑った。それは、父が亡くなってから初めて見せる、心の底からの笑顔だった。
その笑顔を見て、誠もつられて笑った。父の不器用なギャグは、何十年もの時を超え、最高の形で母と息子を、そして天国の父を繋げた。涙と笑いが入り混じった、奇妙で温かいワルツが、二人の間に流れていた。
後日。会社の朝礼。
再び壇上に立った誠は、深呼吸を一つした。社員たちは「今日は何だ?」と、好奇と期待の入り混じった目で彼を見ている。
「えー、皆さん、おはようございます」
誠は、ニヤリと口角を上げた。それは、かつての「歩く定規」には決して見られなかった、少しイタズラっぽい笑みだった。
「ここで一つ、新しいプロジェクトを発表します。その名も…『職場ワクワク化計画』です! 第一弾として、給湯室にダーツを設置し、的の中心に当てた人は午後休暇、というルールを導入したいと思います!」
「おおーっ!」という歓声と拍手が、会議室に響き渡った。
彼の人生は、父が遺した「宿題」によって、鮮やかに塗り替えられた。モノクロームだった世界には、虹がかかっている。
誠はオフィスの窓から空を見上げ、心の中で呟いた。
(父さん、見てるか? 俺の人生、これから結構、面白くなるぜ)
その瞬間、青空の向こうから、あの懐かしい、少し照れたような父の笑い声が聞こえたような気がした。