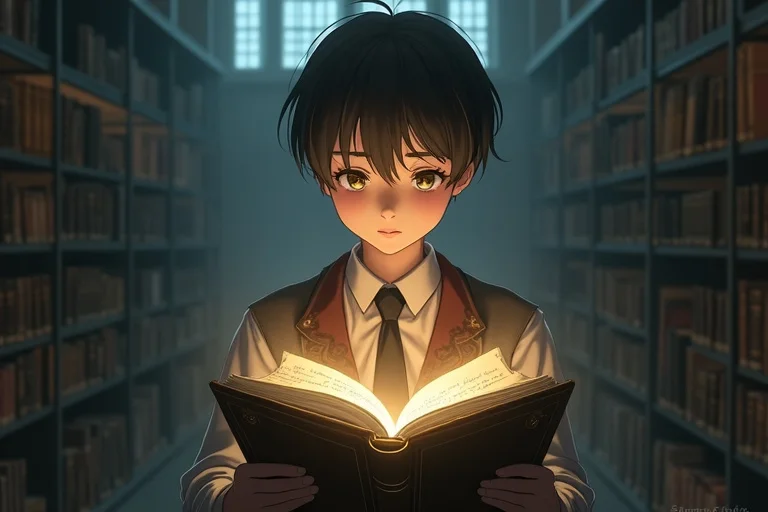第一章 触れてはならない古書
水上怜(みずかみ れい)の世界は、インクと古紙の匂いでできていた。大学院で近代史を専攻する彼は、膨大な資料の海に溺れ、事実の羅列に意味を見出せずにいた。教授からは「君の論文には血が通っていない」と、何度も突き返される始末。彼自身、感情の起伏が乏しく、他人の熱量に共感するのが苦手だった。歴史上の人物も、教科書に印刷されたただの記号にしか見えなかった。
その日も、逃げるように神保町の古書店街を彷徨っていた。埃っぽい静寂の中、怜は一冊の本に目を奪われた。書架の隅で、まるで自ら光を放つかのように佇んでいる。革と思しき黒い表紙には、タイトルも著者名もない。ただ中央に、夕焼けを閉じ込めたような、拳大の琥珀が埋め込まれていた。
「お目が高いね」
背後からの声に、怜はびくりと肩を震わせた。店の主人が、猫のように音もなく立っていた。
「そいつは、いわば迷い子でね。誰が書いたものか、いつからここにあるのかも分からん。ただ、普通の人間には読めない代物だよ」
「読めない、ですか?」
「ああ。文字はあるんだがね。読もうとすると、なぜか頭に入ってこない。まるで本の方が、読む人間を選んでいるみたいに」
主人の言葉は怜の好奇心を刺激した。手に取ると、ずしりと重い。琥珀に指先が触れた瞬間、怜は微かな温もりと、心の奥をくすぐるような奇妙な疼きを感じた。
「……これを、譲っていただけませんか」
主人は怜の目をじっと見つめ、やがて諦めたように息をついた。
「千円でいい。ただし、忠告しておく。その本に深入りしすぎるな。魂を持っていかれる」
アパートに戻った怜は、まるで禁断の果実に手を伸ばすように、机の上にその本を置いた。表紙を開くと、羊皮紙のようなざらついた紙に、見たこともない優美な書体で文字が綴られている。しかし、主人の言う通り、一文字たりとも意味を解することはできなかった。
失望しかけた怜は、無意識に、表紙の琥珀に再び指を這わせた。その瞬間だった。
世界がぐにゃりと歪んだ。目の前の壁紙が溶け、畳の匂いが消え、代わりにむせ返るような血の匂いと、土埃の味が口の中に広がった。怜は、そこにいなかった。彼は、幕末の京都、池田屋の階段を駆け上がる、名もなき長州藩士になっていた。
眼前に迫る新選組の刃。仲間が斬り伏せられる絶叫。己の心臓が早鐘のように打ち鳴らされるのを感じる。「ここで死ぬわけにはいかない」「新しい世を作るのだ」という焦燥と、若さゆえの青い理想が、奔流となって怜の意識を飲み込んでいく。それは映像ではない。知識でもない。感情そのものの洪水だった。
どれほどの時間が経ったのか。怜が我に返ると、彼は自分の部屋の床に倒れていた。頬には冷たい汗が伝い、心臓はまだ激しく脈打っている。窓の外は、すっかり夜の闇に包まれていた。
本は、何事もなかったかのように机の上で静まり返っている。
怜は呆然としながらも、一つの事実に打ちのめされていた。彼は今、歴史を「体験」したのだ。
その高揚が少し落ち着いた頃、怜はふと奇妙な感覚に襲われた。友人が貸してくれたコメディ映画を昨日見て、腹を抱えて笑ったはずだった。だが、その時の「喜び」が、どんな感覚だったか、どうしても思い出せない。まるで、心からその感情だけが綺麗にくり抜かれてしまったかのようだった。
第二章 失われた感情のパレット
怜は、琥珀の本にのめり込んだ。それは、歴史の真実に触れるという学問的探求心と、禁断の果実を味わう背徳的な快感が入り混じった、抗いがたい魅力を持っていた。
ページをめくり、琥珀に触れるたびに、彼は時空を超えた。ある時は、フィレンツェの工房で、完璧な聖母像を描けずに懊悩する無名の画家の「創造の苦しみ」を。またある時は、ピラミッドの建設現場で、家族への手紙を代筆しながら、文字を操れることに静かな矜持を抱く古代エジプトの書記官の「誇り」を。怜は、歴史書が決して語らない、名もなき人々の生々しい感情を次々と追体験していった。
彼の論文は、劇的に変わった。無味乾燥な事実の羅列は消え、まるでその時代を生きたかのような筆致で、人々の息遣いや葛藤が描かれた。血の通った文章は教授を唸らせ、怜は学内で一目置かれる存在となった。虚しかったはずの研究に、初めて意味と熱が宿ったのだ。
しかし、その栄光には、あまりにも大きな代償が伴った。本を読むたびに、怜の感情のパレットから、一色、また一色と絵の具が消えていった。
友人の悲しい知らせを聞いても、涙は流れなかった。「悲哀」という感情が、どんな手触りだったか思い出せない。理不尽な出来事に遭遇しても、腹の底から湧き上がる怒りはなかった。「憤怒」の熱を、忘れてしまった。世界は次第に色を失い、すべてが等しく平板な、灰色の風景に見え始めた。
周囲は怜の変化に気づき、距離を置き始めた。彼は食事の味も分からなくなり、音楽を聴いても何も感じず、ただひたすら本の中の他人の感情を貪ることで、自分が生きていることをかろうじて確認するだけだった。心は空っぽの器になり、その空虚を埋めるために、さらに本を求める。悪循環だった。
彼は、自分が人間ではなく、他人の感情を啜って生きる寄生虫になったような気がした。それでも、琥珀の輝きが彼を誘うのを、止めることはできなかった。
第三章 ハルという名の愛
ついに、怜は本の最後のページに辿り着いた。残されたページは、あと数枚。そこに綴られていたのは、これまで体験したどの歴史とも違う、ごくありふれた一人の女性の物語だった。
舞台は、一九四五年、春。B29の編隊が夜空を埋め尽くす、東京。主人公は、「ハル」という名だった。彼女は空襲で家と家族のすべてを失い、焼け野原のバラックで一人、息を潜めて生きていた。物語には、英雄的な行為も、歴史を動かすような事件も起こらない。ただ、飢えと絶望、そして終わりの見えない恐怖だけが、静かに描かれていた。
怜は、いつものように琥珀に触れた。彼の意識は、ハルのものと溶け合った。灰と死臭が立ち込める空気。腹の底から突き上げてくるような、どうしようもない「絶望」。怜はハルの絶望を追体験しながら、自分の空っぽの心が、その感情でさえも鈍くしか受け止められないことに気づいていた。
しかし、物語は続いた。ある日、ハルは瓦礫の山の中から、一輪だけ咲いている蒲公英を見つける。黒く焼けた土を突き破り、健気に黄色い花を咲かせている。彼女は、その小さな命に目を見張った。そして、何日も忘れていた微笑みを、その口元に浮かべたのだ。
それは、希望と呼ぶにはあまりにささやかで、しかし、何よりも強い「生への肯定」だった。絶望のどん底で、それでもなお失われなかった、命あるものへの慈しみ。怜はその感情の奔流に打たれ、息を呑んだ。
その瞬間、怜の中で何かが弾けた。それは、ハルという、歴史の中に埋もれた名もなき女性に対する、どうしようもなく切実で、温かい感情だった。彼女に生きていてほしい。あの蒲公英を見つけた時の微笑みを、守ってやりたい。それは憐憫や同情ではない。生まれて初めて、怜自身の中から湧き上がってきた、純粋な「愛」だった。
彼が他人の感情を消費するのではなく、自らの意志で誰かに心を寄せた、最初の瞬間だった。
その時、本の琥珀がこれまでになく強く、まばゆい光を放った。ページの上に、震えるような文字が浮かび上がる。
『最後の糧を求む。汝が抱いた、最も純粋なる“愛”を』
怜は悟った。この本は、単なる記録媒体ではない。歴史の波間に消えていった、名もなき人々の魂を救済するための「方舟」なのだ。そして、その方舟を未来へと漕ぎ出すためのエネルギーこそが、読者が物語の登場人物に寄せる、混じり気のない純粋な感情だったのだ。
本は、怜がハルに抱いた、たった今生まれたばかりの愛を差し出せと要求していた。差し出せば、ハルの物語は完成し、彼女が生きた証は永遠にこの本の中に刻まれる。しかし、その代償として、怜は「愛」という感情そのものを、永遠に失うことになる。彼は、完全な空虚になるのだ。
第四章 空っぽの器に残ったもの
選択の余地はなかった。いや、怜にとっては、選ぶべき道は一つしかなかった。
感情を失い、論文で成功したとして、その先に何があるというのか。灰色の世界で、ただ記号を並べ続けるだけの人生。それに引き換え、ハルの物語を未完のまま終わらせることなど、彼にはできなかった。彼女が生きた証、絶望の中で見つけた一輪の蒲公英のような愛おしい瞬間を、自分が消してしまっていいはずがない。
怜は、胸に込み上げるハルへの温かい気持ちを、壊れ物を扱うように大切に抱きしめた。そして、震える指で、そっと琥珀に触れた。
彼の内側から、温かい光が流れ出すのが分かった。ハルへの愛おしさが、涙のように、彼の魂から本へと吸い込まれていく。視界が白く染まり、意識が遠のいていく。最後に彼の脳裏に浮かんだのは、瓦礫の中で微笑むハルの姿だった。
気がつくと、朝だった。小鳥のさえずりが窓の外から聞こえる。怜は自分のベッドの上に横たわっていた。体は鉛のように重いが、不思議と気分は悪くない。
机の上には、あの古書が置かれている。ただの、何の変哲もない黒い革装の本だ。琥珀は、色褪せた飴玉のように、もう輝きを失っていた。ページをめくっても、そこには意味不明な文字が並んでいるだけで、もう何も起こらなかった。
ハル、という名前を、怜はおぼろげにしか思い出せない。彼女にどんな感情を抱いたのか、愛がどんなものだったのかも、もう分からなかった。心は、静かで、空っぽのはずだった。
しかし、何かが残っていた。空虚なはずの胸の奥に、消えない熾火のような、小さな温もりが宿っている。
怜は、書きかけだった論文の束を掴み、躊躇なく破り捨てた。そして、新しい原稿用紙に向かう。
タイトルは書かなかった。ただ、一人の女性の物語を書き始めた。焼け野原の東京で、一輪の蒲公英を見つけて微笑む、名もなき女性の物語を。
なぜこの物語を書いているのか、彼自身にも分からない。ハルの記憶はほとんどない。だが、彼女が生きた証を、誰かに伝えなければならないという、抗いがたい衝動だけが、彼の指を動かしていた。
ペンを走らせるうち、怜の頬を、一筋の何かが伝った。
それは、感情を失ったはずの彼が流した、初めての涙だった。理由の分からない、しかし、確かに存在する温かい雫。それは、愛という名を失ってもなお、彼の魂に刻み込まれた、人間性の最後の証なのかもしれなかった。
窓から差し込む朝の光が、原稿用紙の上で静かに揺れていた。