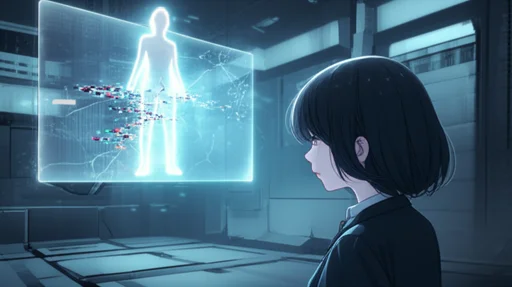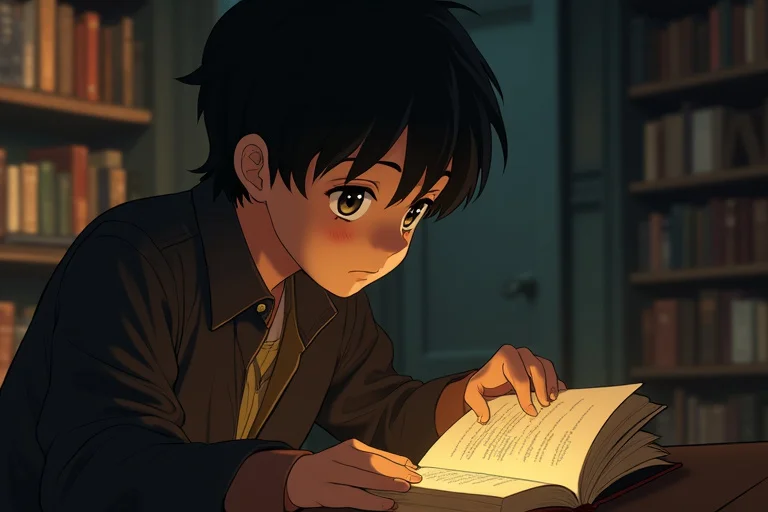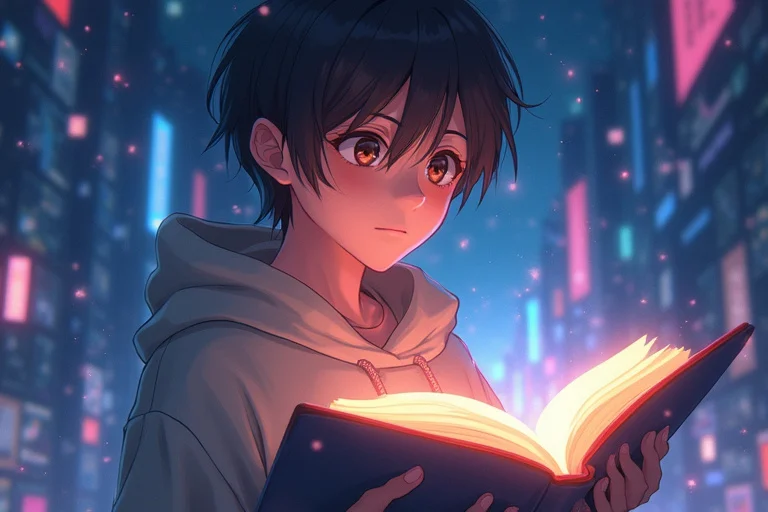第一章 存在しない死体
音葉朔太郎(おとはさくたろう)の仕事は、記憶を調律することだ。彼の営む小さなオフィス「追憶の調律室」のドアには、そう書かれた真鍮のプレートが掲げられている。彼は医者ではない。カウンセラーでもない。独自の音響療法と対話術を組み合わせ、依頼人の心に棘のように突き刺さったトラウマ的な記憶を、穏やかな追憶へと調律する、いわば記憶の専門家だった。
その日の依頼人は、これまでの誰とも違っていた。
「はじめまして、天川瑠璃(あまかわるり)と申します」
現れた女性は、まるで印象派の絵画から抜け出してきたかのような、儚さと強い意志を同居させた瞳をしていた。彼女は若くして世界的な評価を得ている芸術家で、その名を朔太郎も知っていた。彼女のまとうリネンのワンピースからは、微かに油絵の具とテレピン油の匂いがした。
「先生のことは、知人から伺いました。どんな記憶でも和らげてくださると」
「ええ、可能な限りは。どのような記憶でお悩みでしょうか」
朔太郎が促すと、瑠璃はまっすぐに彼の目を見つめ、震える唇で、信じがたい言葉を紡いだ。
「私、昨夜、殺されました。その記憶を、消していただきたいのです」
朔太郎の整然とした思考が、一瞬、停止した。目の前の女性は、血の通った温かみを持ち、確かに生きている。冗談か、あるいは何かの比喩表現か。だが、彼女の瞳は真剣そのものだった。
「…詳しくお聞かせいただけますか」
冷静さを取り戻し、朔太郎は促した。瑠璃は、堰を切ったように語り始めた。昨夜、アトリエで新作の仕上げをしていたこと。背後に人の気配を感じ、振り向こうとした瞬間、後頭部に鈍い衝撃が走ったこと。床に広がる自身の血と、急速に冷えていく体の感覚。薄れゆく意識の中で見た、犯人のものらしき革靴のつま先。そのすべてを、まるで昨日の夕食のメニューを思い出すかのように、克明に語った。
「気がつくと、朝でした。アトリエの床で、冷たくなって。でも、死んでなんかいなかった。体には傷ひとつなく、血の跡もどこにもない。警察にも相談しましたが、悪夢か、過労による幻覚だろうと、まったく取り合ってもらえませんでした」
彼女は両手で顔を覆った。その指の間から、嗚咽が漏れる。
「でも、これは幻覚なんかじゃない。あの痛みも、絶望も、今もこの中に、本物として在るんです。このままでは、筆を握ることさえできない。どうか、この『死の記憶』を、私の中から取り除いてください」
朔太郎は黙って彼女の話を聞いていた。彼の経験上、これは解離性健忘の一種か、あるいは極度のストレスが見せる幻覚症状の可能性が高い。だが、彼女の語る記憶のディテールは、あまりに生々しく、一貫していた。まるで、本当に体験したかのように。
これは、ただのカウンセリングでは終わらない。朔太郎の心の奥底で、専門家としての好奇心と、ひとりの人間としての強い違和感が、不協和音を奏で始めていた。
第二章 記憶の残響
朔太郎は天川瑠璃の依頼を引き受けた。表向きは記憶の調律、しかしその実態は、存在しないはずの事件の調査だった。彼はまず、彼女の「死の記憶」の調律を試みた。防音設備が施された静かな部屋で、特殊な周波数の音を流し、彼女の意識を深いレベルへと導く。
「思い出してください、瑠璃さん。アトリエの床の冷たさを。でも、それはあなたの記憶ではないかもしれない」
朔太郎は穏やかに語りかける。しかし、彼の技術は、瑠璃の記憶の前では無力だった。彼女の脳波は、過去の事実を想起する際に見られる典型的なパターンを示し、記憶は揺らぐどころか、より鮮明な輪郭を結んでいく。汗、恐怖、痛み。それらは朔太郎にも伝わってくるほど強烈な「事実」として、彼女の中に鎮座していた。
「駄目です…何度思い出しても、これは私の体験です」
セッションを終えた瑠璃は、疲れ切った顔でそう言った。朔太郎は、この記憶が単なる精神の産物ではないと確信し始めていた。彼は依頼の範囲を逸脱することを彼女に告げ、彼女の許可を得て、独自に調査を開始した。
舞台となったアトリエは、古い倉庫を改装した、天井の高い広大な空間だった。イーゼルには描きかけの巨大なキャンバスが置かれ、無数の絵の具のチューブが混沌と秩序の狭間で散乱している。朔太郎は、瑠璃の記憶を頼りに、現場を検証した。
「犯人は、この棚の後ろに隠れていた、と」
「はい。そして、私が振り返ろうとした瞬間…」
瑠璃が指さした床には、素人目には分からないほど微かな、不自然な染みがあった。専門家が鑑定すれば何か分かるかもしれないが、警察が動かない以上、それも叶わない。壁に立てかけられた絵の具のパレットナイフのいくつかが、不自然なほど綺麗に磨かれていることにも気づいた。まるで、何かを拭き取ったかのように。
次に、朔太郎は彼女の周辺の人間関係を洗った。浮かび上がってきたのは、三人。
一人は、瑠璃の才能に激しく嫉妬していると噂のライバル芸術家、黒川。彼はアリバイを主張したが、その態度はどこか芝居がかっていた。
二人目は、彼女の作品を高値で売りさばくことに執心する画商の冴島。彼は瑠璃が精神的に不安定になることを心から憂いているように見えたが、その目には計算高い光が宿っていた。
三人目は、最近になって彼女のアシスタントになったばかりの、物静かな青年、高村。彼は瑠璃を心から尊敬し、彼女の身を案じているようだった。誰よりも親身に、彼女の「悪夢」の話を聞いていた。
「高村くんは、本当にいい子なんです。私のことを、誰よりも信じてくれて…」
瑠璃はそう言って、彼に全幅の信頼を寄せているようだった。
朔太郎は、全員と面会したが、誰もが決定的な何かを欠いていた。まるで、深い霧の中を手探りで進むような感覚。しかし、調査を進めるうちに、朔太郎の脳裏にひとつの突飛な仮説が芽生え始めていた。もし、瑠璃の記憶が、彼女自身のものではないとしたら? もし、誰かの記憶が、彼女の脳に「上書き」されたのだとしたら?
そんな馬鹿な、と一度は打ち消す。だが、その仮説は、この不可解な事件のすべてを説明できるように思えた。彼は、かつて学会の片隅で噂として聞いた、非合法な記憶移植技術の存在を思い出していた。
第三章 移植された絶望
朔太郎の疑念は、一本の線となって繋がろうとしていた。彼は情報屋として裏社会にも通じる旧知のジャーナリストに連絡を取り、「記憶移植」の技術について探りを入れた。数日後、ジャーナリストからもたらされた情報は、朔太郎の仮説を確信へと変えた。ごく一部の富裕層や研究者の間で、脳神経科学を応用した記憶の抽出・移植技術が、非合法に取引されているというのだ。それは、被験者の同意なしに、特定の記憶を植え付けることさえ可能にする、悪魔の技術だった。
朔太郎の思考は、雷に打たれたように閃いた。犯人は、物理的に瑠璃を殺すのではなく、彼女の精神を、その芸術家としての魂を殺そうとしたのだ。そして、そのために最も効果的な凶器は、「死の記憶」そのものだった。
一体誰が、そんな残酷な計画を実行できるのか。ライバルか、画商か。いや、違う。この計画を成功させるには、瑠璃が最も心を許し、疑うことのない人物でなければならない。朔太郎の脳裏に、あの物静かな青年の顔が浮かんだ。アシスタントの高村だ。
朔太郎は再びアトリエを訪れた。瑠璃は不在で、高村がひとりでキャンバスの整理をしていた。朔太郎は、単刀直入に切り出した。
「高村さん。あなた、天川さんの記憶に何をしましたか」
高村の顔から、穏やかな表情がすっと消えた。代わりに現れたのは、凍るような冷たさと、歪んだ愉悦が混じり合った、見たこともない表情だった。
「…気づきましたか、記憶調律師さん。さすがですね」
彼はあっさりと認めた。彼は独学で脳神経科学を学び、裏ルートで手に入れた装置を使って、計画を実行したのだという。彼は瑠璃の才能に焦がれ、アシスタントになったが、間近で見れば見るほど、その圧倒的な才能との差に絶望した。嫉妬は、やがて黒い殺意へと変わった。
「あの人を殺したかった。でも、ただ殺すんじゃつまらない。彼女の魂を、あの傲慢な才能を、内側から破壊してやりたかったんです。自分が殺されたという記憶を抱いて、何も描けなくなり、狂っていく姿を、この目で見たかった」
高村は恍惚とした表情で語る。朔太郎は、その歪んだ動機に吐き気を覚えた。だが、話はそこで終わらなかった。朔太郎は、最後の、そして最も重要な問いを投げかけた。
「その『死の記憶』は、どこから手に入れた? あなたが作り出した架空の記憶か?」
高村は、狂気的に笑った。
「まさか。あんなリアルな記憶、創り出せるわけがないでしょう。あれは…本物ですよ」
彼は、息を呑む朔太郎に、戦慄の真実を告げた。
「あれは、僕が二年前に殺した、別の画家の記憶です」
二年前に失踪事件として処理された、無名の画家の女性。高村は彼女の才能にも嫉妬し、殺害していた。完全犯罪だった。彼は、その時の罪悪感と恐怖の記憶を、自らの脳から抽出し、保存していたのだ。
「この記憶を、誰かに押し付けたかった。そして、どうせなら、僕が最も憎む天川瑠璃にくれてやろうと思ったんです。彼女が僕の罪の記憶にうなされる姿は、最高の芸術ですよ。僕は、過去の犯罪を暴かれずに彼女を破滅させ、同時に、この忌まわしい記憶からも解放される。完璧な計画でしょう?」
それは、想像を絶する悪意の連鎖だった。瑠璃に移植されたのは、単なる死の記憶ではなかった。それは、一人の人間の命が奪われた、紛れもない「事実」であり、犯人自身の「罪の告白」でもあったのだ。
第四章 痛みを編むキャンバス
朔太郎は、高村の自白を録音していた。警察が駆けつけ、呆然と立ち尽くす高村を連行していく。二年越しの殺人事件と、前代未聞の記憶移植事件は、こうして幕を閉じた。
すべてが解決し、アトリエには静寂が戻った。だが、瑠璃の苦しみは終わらない。彼女の中に移植された、名も知らぬ女性の「死の記憶」は、事件が解決してもなお、生々しい残響となって残り続けていた。朔太郎の調律を何度試みても、他人の死というあまりに強烈な事実は、彼女の精神に深く根を張り、消し去ることはできなかった。
「この記憶は、もう私の一部なんですね」
ある日、瑠璃は穏やかな顔でそう言った。彼女の目には、以前の怯えはなかった。
「消せないのなら、共に生きていくしかありません。いいえ、生かすんです。この痛みを」
数週間後、彼女は再びキャンバスに向かい始めた。最初は、震える手で木炭を握るのがやっとだった。だが、彼女は描き続けた。自分の中に宿る、他人の絶望と、痛みと、そして最期の瞬間を。
事件から半年後、天川瑠璃の個展が開かれた。朔太郎も、その会場に足を運んでいた。そこに展示されていた作品群は、これまでの彼女の作風とはまったく異なっていた。色彩はより深く、線はより激しく、そして、すべての絵画から、死の気配と、それに抗う強烈な生命力が放たれている。それは、見る者の魂を根こそぎ揺さぶるような、圧倒的な力を持っていた。
中央に飾られた一枚の巨大な絵。タイトルは『無名のレクイエム』。暗い色彩の中に、微かな光が差し込み、床に倒れた女性の姿が描かれている。それは絶望の絵でありながら、同時に、鎮魂の祈りのようにも見えた。瑠璃は、自分に移植された絶望を、芸術へと昇華させたのだ。
朔太郎は、その絵の前から動けなかった。彼はこれまで、記憶を「消すべきもの」「和らげるべきもの」として扱ってきた。苦痛な記憶は、人生のノイズでしかないと。だが、瑠璃は違った。彼女は、最も忌まわしいはずの記憶を受け入れ、それを創作の源泉とすることで、乗り越えようとしている。記憶は、ただ消し去るだけが答えではない。痛みと共に生き、それに新たな意味を与えることもできるのだ。
彼は、自分の仕事の本当の意味を、初めて理解した気がした。記憶を調律するとは、単に音を整えることではない。その人の人生という音楽の中で、不協和音でさえも、意味のある響きに変えていく手伝いをすることなのだと。
会場の片隅で、静かに来場者を見つめる瑠璃と目が合った。彼女は、小さく、しかし力強く頷いた。その瞳には、芸術家としての、そして一人の人間としての、新たな覚悟が宿っていた。
朔太郎は静かに会場を後にした。街の喧騒が、今はどこか心地よい音楽のように聞こえる。彼の心にもまた、新しいメロディが生まれ始めていた。痛みを知ることでしか奏でられない、深く、豊かなメロディが。