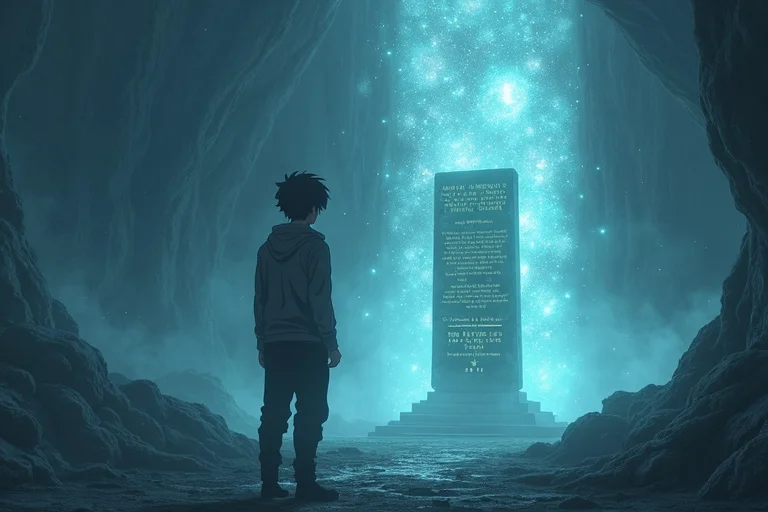第一章 錆び色の不協和音
俺、水無月 響(みなづき ひびき)の世界は、音で彩られている。先天的な共感覚(シナスタジア)の持ち主である俺にとって、音は単なる聴覚情報ではない。それは色であり、形であり、時に手触りさえ伴う、世界の骨格そのものだった。教会の鐘は金色の粒子となって降り注ぎ、恋人の笑い声は柔らかなピンク色の綿菓子のように心を包む。調律師という仕事は、そんな俺にとって天職だった。ピアノの鍵盤を叩き、狂った音程――くすんだ黄土色や、不快に尖った紫色の棘――を、澄み切った青や温かい橙色へと調律していく作業は、混沌とした世界に秩序をもたらす神聖な儀式にも似ていた。
その異変に気づいたのは、三ヶ月前の雨の夜だった。古いグランドピアノの調律を終え、アトリエ兼自宅のソファで微睡んでいた時だ。不意に、世界の色彩が僅かに濁った。耳鳴りのような、それでいて音ではない何か。それは、視界の隅にこびりついた、錆びた鉄のような赤黒い染みとして現れた。指先で擦っても消えない、網膜の傷のような色。そして、その色には「音」があった。キィィ、と金属を引っ掻くような、耳の奥で神経を逆撫でする不協和音。それはすぐに消えたが、肌に残った鳥肌はしばらく引かなかった。
それからだ。日常のあらゆる瞬間に、「錆び色の音」が侵食を始めたのは。朝のトーストを焼く軽快なポップ音に、それは一瞬、泥水のような茶色を滲ませる。街の喧騒――幾重にも重なるカラフルな音のタペストリー――の隙間から、あの赤黒い亀裂が覗く。それは日に日に存在感を増し、今では俺の世界の背景に常に薄く広がっている。まるで、美しい絵画が描かれたカンバスが、裏側からじわじわと腐敗していくように。
最も恐ろしいのは、夜だった。眠りに落ちる寸前の静寂の中で、それは最も純粋な形で現れる。もはや視界の隅ではない。目の前に、空間そのものが錆び色のノイズで満たされ、耳を塞いでも意味のない、頭蓋に直接響くような軋みを奏でるのだ。それは冷たく、ざらついていて、生命の温もりを全て吸い取っていくような絶対的な虚無の色をしていた。
医者には「過労による幻聴・幻覚」と診断された。だが、俺には分かる。これは病気などではない。もっと根源的で、悪意に満ちた「何か」だ。その「何か」は、俺が大切にしている世界の色彩を、一つ、また一つと喰らい、錆びつかせている。愛した妻、美咲が遺したオルゴールの音色。かつては透き通るような銀色だったそのメロディも、今では所々が赤黒く変色し、聴くたびに胸を締め付けるのだ。このままでは、俺の世界は、俺自身が、錆び色の不協和音に飲み込まれて、完全に無に帰してしまうだろう。
第二章 忘却のレクイエム
錆び色の音は、俺の精神だけでなく肉体をも蝕み始めた。食事は喉を通らず、夜はほとんど眠れない。鏡に映る自分は、目の下に濃い隈を刻み、まるで自分自身の亡霊のようだった。調律の仕事もままならない。鍵盤を叩くと、美しいはずの倍音が、あの忌まわしい色に汚染されて見えるのだ。顧客からの信頼を失い、仕事の依頼は途絶えた。
追い詰められたある晩、俺は半ば自暴自棄になっていた。アトリエの中央に置かれた古いピアノに向かい、鍵盤を叩きつける。怒り、絶望、恐怖。あらゆる負の感情が、濁流のような不協和音となって溢れ出した。視界は赤黒いノイズで完全に覆われ、息が詰まる。もう終わりだ。そう思った瞬間、ふと指が、ある旋律をなぞった。
それは、幼い頃、母がよく歌ってくれた子守唄だった。何の変哲もない、素朴で優しいメロディ。だが、その一節を奏でた途端、世界が息を吹き返した。鍵盤から立ち上ったのは、温かいミルクのような、穏やかな乳白色の光。その光が波紋のように広がると、視界を覆っていた錆び色のノイズが、まるで酸に溶かされるように、ジリジリと音を立てて後退していくではないか。
俺は憑かれたように弾き続けた。忘れていた歌詞まで蘇り、口ずさむ。母の温もり、揺りかごの心地よさ、安心感に包まれて眠りについた遠い日の記憶。その全てが純粋な音の結晶となり、アトリエを満たしていく。一曲を弾き終えた時、あれほど執拗にまとわりついていた錆び色の気配は、完全に消え去っていた。静寂が戻っていた。いや、ただの静寂ではない。全ての音が浄化されたような、清らかな静寂だった。
発見だった。希望の光だった。あの恐怖は、音楽で退けることができるのだ。
しかし、その安堵は長くは続かなかった。翌朝、俺は奇妙な喪失感に襲われた。何か、とても大切なものを忘れてしまったような感覚。昨夜弾いた子守唄を思い出そうとしても、メロディが全く浮かんでこないのだ。母が歌ってくれた、という事実は覚えている。だが、どんな歌だったのか、どんな気持ちで聴いていたのか、その記憶に付随する温かい感情が、ごっそりと抜け落ちていた。まるで、心にぽっかりと穴が空いたようだった。
まさか。戦慄が背筋を走った。代償。あれを退けるための代償は、音楽に込めた「記憶」そのものだったのだ。俺は恐怖から逃れるために、母との温かい思い出を「捧げた」のだ。そしてそれは、二度と戻らない。錆び色の音が再び世界を侵食し始めるまで、時間はかからなかった。次は、何を捧げればいい? 初めてのコンクールで入賞した時の喜びの曲か? 友と笑い合った日々のBGMか? 生き延びるために、俺は自分自身を少しずつ削り、売り渡していかなければならないのか。それは、緩やかな自殺に他ならなかった。
第三章 心音のソナタ
俺は、自分という存在の断片を切り売りすることで、かろうじて正気を保っていた。学生時代に夢中になったロックナンバーを捧げ、仲間との青臭い情熱を失った。旅先で聴いた民族音楽を捧げ、異国の風景と感動を忘れた。俺の内的世界は、美しい色彩を失い、少しずつ無味乾燥なモノクロームへと変貌していった。それでも、錆び色の音は、捧げられた記憶を養分にするかのように、より強く、より狡猾になっていった。もはや、生半可な思い出の音楽では、奴を退けることはできなくなっていた。より強く、より純粋で、より魂のこもった「色」を求めているのが分かった。
そして、ついに奴は、俺の聖域にまで手を伸ばしてきた。亡き妻、美咲との記憶だ。
美咲は、俺の共感覚を世界で唯一理解してくれた人だった。「響くんの世界、見てみたいな。きっと、すごく綺麗なんだろうね」。そう言って笑う彼女の声は、春の陽だまりのような、温かく柔らかな黄金色をしていた。彼女と過ごした五年間の記憶は、俺の世界で最も鮮やかで、何よりも大切な宝物だった。彼女が病でこの世を去ってからも、その記憶だけが、俺をこの世界に繋ぎ止めていた。
錆び色の音は、その黄金色の記憶にまとわりつき、黒い染みを広げ始めた。美咲の笑顔を思い出すたびに、その口元が歪み、声がノイズに掻き消される。オルゴールの音色は、もはや不気味な軋みにしか聞こえない。やめろ。それだけは、それだけは奪わないでくれ。心で叫んでも、奴は止まらない。俺は選択を迫られていた。美咲の記憶が汚され、腐り果てていくのを黙って見ているか。あるいは、自らの手で、最も美しい形のまま捧げ、永遠に忘却するか。
答えは、決まっていた。汚されるくらいなら、いっそ。
俺は震える手でピアノの前に座った。鍵盤に指を置く。深呼吸すると、目を閉じた。思い出すのは、美咲との出会いから別れまでの全て。初めて手を繋いだ時の、はにかむような桜色の和音。プロポーズした夜に流れていた、星空のような藍色のジャズ。病室で、弱々しくも俺の名を呼んだ、か細い銀色の旋律。そして、最後に俺の頬を撫でた彼女の手の感触―――それは、音のない、ただひたすらに温かい光だった。
それら全ての感情、情景、愛の記憶を、一つのソナタに織り上げていく。それは俺の人生の最高傑作であり、同時に、俺という人間の存在証明そのものだった。一音一音を紡ぐたびに、視界を覆っていた錆び色のノイズが剥がれ落ちていく。そして、鍵盤から溢れ出すのは、言葉では言い表せないほどに美しく、そして哀しい、極彩色の光だった。
弾きながら、涙が溢れて止まらなかった。さようなら、俺の愛した人。さようなら、君と生きた俺の人生。最後の和音を響かせた瞬間、アトリエはまばゆい光で満たされた。錆び色の気配は、跡形もなく消え去っていた。光が収まった後、俺はピアノの前に座ったまま、呆然としていた。涙は枯れ、心は空っぽだった。なぜ自分は泣いていたのだろう。なぜ、こんなにも胸が痛むのだろう。その理由を、俺はもう、思い出せなくなっていた。
第四章 無響のカンバス
全てを捧げた後、俺の世界から「色」は消えた。音は、ただの音になった。鳥のさえずりも、車のクラクションも、雨だれの音も、全てが無個性で平坦な情報として鼓膜を揺らすだけ。かつて世界を彩っていたシンフォニーは鳴り止み、後に残されたのは、完全な静寂と、色のないモノクロームの風景だった。
錆び色の不協和音も、二度と現れることはなかった。あの恐怖は、俺が捧げた最後の、そして最高の「色」に満足し、完全に消え去ったのだろう。俺は生き延びたのだ。恐怖からも、それに伴う苦痛からも解放された。
だが、それは本当に「生」と呼べるものだろうか。
感情の起伏は、ほとんどない。喜びも、悲しみも、怒りさえも感じない。ただ、時が流れていくのを眺めているだけ。食事をし、眠り、朝を迎える。その繰り返し。調律師の仕事に戻ることはなかった。音が色を失った今、俺には音程の狂いを聞き分けることができなくなっていた。俺は、俺を形作っていた全てを失ったのだ。
ある晴れた日、俺は漫然とアトリエの窓から外を眺めていた。ふと、ピアノの鍵盤の上に置かれた一枚の写真が目に入った。知らない女性が、優しい笑顔でこちらを見つめている。誰だろう。写真立てには埃が積もっている。だが、その笑顔を見ていると、胸の奥深くに、何か温かいものが微かに灯るような気がした。それは色も音も伴わない、残響のような、名もなき感覚だった。
俺は立ち上がり、ピアノの蓋を開けた。そして、ゆっくりと鍵盤に指を置く。何のメロディでもない。ただ、一つの音を、静かに鳴らした。
ポーン。
無色透明な音が、がらんどうのアトリエに響き渡る。それは美しくも醜くもなく、ただそこに「在る」音だった。
俺は目を閉じる。そこにはもう、錆び色の恐怖も、極彩色の思い出もない。あるのは、どこまでも広がる、真っ白なカンバスだけだ。恐怖を失い、愛を失い、全てを失ったこの何もない世界で、俺はこれから、どんな絵を描いていけばいいのだろうか。あるいは、もう何も描けないのかもしれない。
それでも、その白い静寂は、不思議と安らかだった。空っぽのカンバスに、最初の一筆を置く前の、あの静かな緊張と、ほんの僅かな可能性。俺は、その白の中に、ただ静かに佇んでいた。終わりから始まる、新しい静寂の中で。