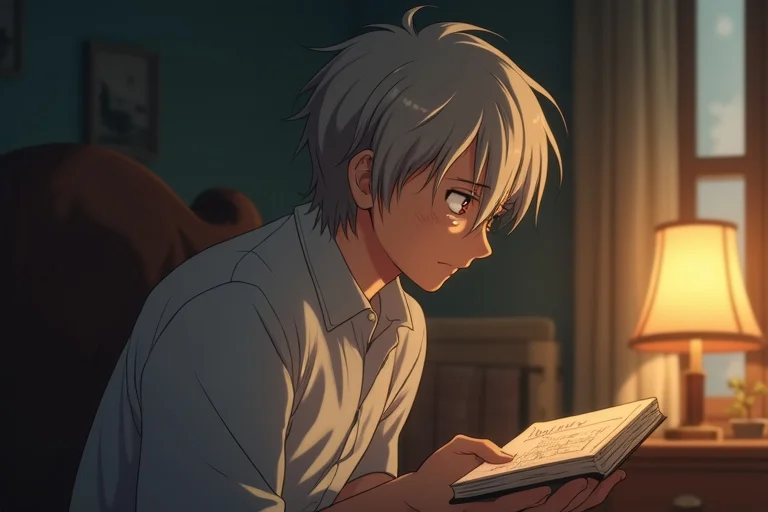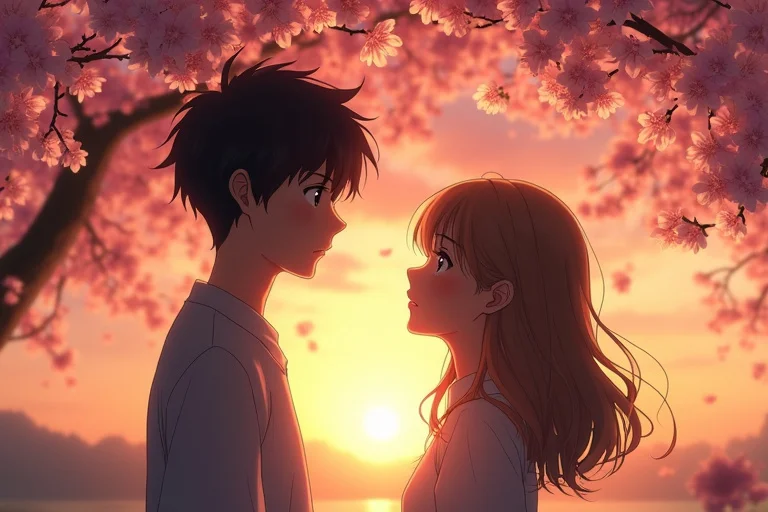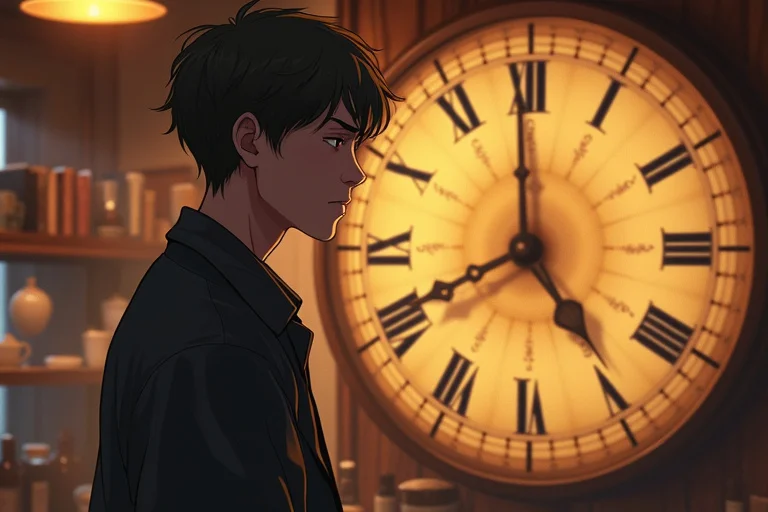第一章 プラスチックの見る夢
柏木湊(かしわぎ みなと)の日常が静かに軋み始めたのは、梅雨時の湿った空気とアスファルトの匂いが部屋にまで流れ込んでくる、そんな夜のことだった。夢を見た。いや、夢というにはあまりに生々しく、五感を直接揺さぶる体験だった。
彼は、硬く、つるりとしたプラスチックの容器になっていた。自身の内側には、食べ残された生姜焼きのタレと、数粒の米がこびりついている。コンビニのロゴが印刷された自身の「肌」が、無造作に黒いビニール袋に押し込まれる感触。揺さぶられ、他のゴミとぶつかり合い、生ゴミの甘酸っぱい腐臭に意識が遠のく。次に感じたのは、巨大な鉄の怪物――ゴミ収集車のプレス機に押し潰される、身を裂くような圧迫感だった。ギチギチと音を立てる自身の体。それは痛みというより、存在が否定される絶対的な恐怖だった。
「うわっ!」
湊はベッドから跳ね起きた。心臓が嫌な音を立てて脈打ち、全身が汗でじっとりと濡れている。部屋は静まり返り、窓の外からは遠くに救急車のサイレンが聞こえるだけ。いつもの、代わり映えのしない自室の風景だ。しかし、湊の口内には、昨夜食べたコンビニ弁当の生姜焼きの味が、まだ微かに残っている気がした。そして、あのプラスチック容器の、冷たく無機質な絶望感が、肌にまとわりついて離れなかった。
最初は、仕事のストレスだろうと片付けた。グラフィックデザイナーという仕事は、締め切りに追われ、クライアントの無理な要求に応え続ける、精神をすり減らす作業の連続だ。疲れているのだ。そう自分に言い聞かせ、湊は使い終えたペットボトルをゴミ箱に投げ入れた。ラベルも剥がさず、キャップもつけたままで。その日の夜、彼は大海を漂う夢を見た。波に翻弄され、強い日差しに焼かれ、塩水が内側に染み込んでくる。キャップの隙間から、小さな魚が入り込んでは、絶望して出ていく。永遠に続くかのような、孤独で無為な漂流だった。
目覚めた時、湊の喉はカラカラに乾き、舌は塩辛かった。確信があった。昨夜捨てた、あのペットボトルの夢だ。
彼の日常は、彼が捨てたモノたちの断末魔によって、静かに、しかし確実に侵食され始めていた。ゴミを出すという、これまで意識すらしなかった行為が、毎夜見る悪夢への招待状と化したのだ。
第二章 五感の侵食
夢は、湊の日常を着実に蝕んでいった。それはもはや単なる悪夢ではなく、過去の追体験であり、五感に刻み込まれる記憶の奔流だった。
ある夜は、読み終えて捨てた週刊誌になった。古紙回収のコンテナの中で、雨に濡れてインクが滲み、ページ同士が貼り付いていく不快感。製紙工場でどろどろに溶かされ、パルプへと還元されていく過程で、かつて自分が読んでいた記事の一文字一文字が意味を失い、ただの繊維の塊へと分解されていく感覚を味わった。目覚めた湊は、自分の指先からインクの匂いがするような錯覚に陥り、一日中、手を洗い続けた。
またある夜は、電池切れで捨てた安物の腕時計だった。他の不燃ゴミと共に埋立地へ運ばれ、重機によって地中深くへと押し込まれる。降り積もる土の重圧、暗闇、そして永遠に時を刻むことのない静寂。彼は、止まってしまった秒針の絶望と共に、土の中でゆっくりと錆びていく、途方もなく長い時間を夢の中で過ごした。その日以来、湊は部屋の時計の秒針の音が、やけに大きく聞こえるようになった。カチ、カチ、という音が、生きている証のように思えた。
湊の生活は、恐怖によって再構築されていった。コンビニ弁当を買うのをやめ、自炊を始めた。プラスチック容器の、あの焼却炉で溶ける夢を二度と見たくなかったからだ。食材は、包装の少ないものを選び、野菜の皮まで使い切るレシピを検索した。ペットボトル飲料は買わず、水筒を持ち歩くようになった。海を漂う孤独はもうこりごりだった。
彼は、モノを「捨てる」という行為そのものに、強烈な抵抗感を覚えるようになっていた。ゴミ箱を前にすると、これから見るであろう夢を想像し、手がすくむ。それは、かつて彼が何の気なしに行っていた日常の一部だったはずなのに、今ではまるで罪を犯す前の躊躇のように、重く彼にのしかかった。
彼の部屋から、使い捨ての製品が消えていった。代わりに、古びたマグカップや、何度も洗って使える布巾が増えた。消費社会の恩恵を浴びるように生きてきた彼にとって、それは不便で息苦しい生活のはずだった。だが不思議なことに、彼の心は少しずつ凪いでいった。悪夢を見る頻度が減ったのだ。モノを大切に扱うことで、悪夢から逃れられる。その単純な事実に、彼はわずかな安らぎを見出し始めていた。彼の日常は、捨てられたモノたちの声なき声によって、静かに、だが確実に、その形を変えていた。
第三章 万年筆の行方
湊が、この奇妙な現象の本当の意味に気づかされる出来事が起きたのは、そんな生活が数ヶ月続いた、秋風が肌寒い日のことだった。
デスク周りを整理していた時、彼の指が滑り、ペン立てにあった一本の万年筆が床に落ちた。それは、十年前に亡くなった祖母の形見だった。ペン先が歪み、軸には深い傷がついてしまった。湊は修理しようとしたが、どうにもうまくいかない。苛立ちと、「もう寿命だったんだ」という諦めが混じり合った感情のまま、彼はそれを他の文房具のゴミと一緒に、半ば無意識にゴミ袋に入れてしまった。
捨てた瞬間、血の気が引いた。あれはただの万年筆じゃない。祖母が、字を書き始めたばかりの幼い彼に「物書きにでもなるのかい」と笑いながら手渡してくれた、大切な思い出の品だ。湊はパニックになり、慌ててマンションのゴミ集積所へ走った。しかし、指定されたゴミ袋の山の中から、小さな万年筆を見つけ出すことは不可能だった。収集車はまだ来ていない。だが、闇の中では、自分の捨てた袋すら判別できなかった。
その夜、湊は覚悟して眠りについた。祖母の万年筆が、ゴミ処理場で無残に破壊される夢を見るのだろう。祖母の温かい笑顔が、無機質な機械の轟音にかき消される悪夢を。罪悪感で胸が張り裂けそうだった。
しかし、その夜に見た夢は、彼の予想を完全に裏切るものだった。
彼は、一枚の便箋になっていた。淡いクリーム色の、上質な紙だ。そこには、インクの滲みひとつない、流麗な文字で感謝の言葉が綴られていた。病気の自分を支えてくれた夫への、最後のラブレターだった。書き手の震える指の感触、涙が一滴落ちて紙に染みになる瞬間、そして、手紙がそっと封筒に収められ、切手が貼られるまでの、愛情に満ちた時間を、湊は体験した。だが、その手紙は投函されることなく、書き主の死後、遺品整理で家族によって捨てられてしまったらしかった。
夢の中で、便箋である彼は、ゴミ袋の暗闇の中にいた。隣に、冷たくて硬い、細長い何かが寄り添うのを感じた。湊の捨てた、あの万年筆だった。万年筆は、砕かれても、溶かされてもいなかった。それどころか、静かに、だが確かな存在感を放っていた。
その時、湊の意識に、直接声が響いた。それは一人の声ではなく、何百、何千という囁きが重なり合ったような、不思議な響きだった。
『お前は、モノに込められた想いに敏感すぎるのだ』
声は言った。
『我々は、捨てられたモノたちの記憶の集合体。役目を終え、忘れ去られたモノたちの最後の声。お前がこれまで見てきたのは、我々の旅路の断片だ』
「じゃあ、この万年筆は……?」湊は意識の中で問いかけた。
『あの万年筆は、我々の仲間にはならない。込められた想いが強すぎる。持ち主の記憶と愛情が、それをただの“ゴミ”にすることを拒んでいる。見ろ』
夢の風景が変わった。ゴミ収集所の作業員が、分別作業中に、袋からこぼれ落ちた万年筆に気づく。彼はその美しいフォルムにしばし見入った後、ポケットにそっとしまい込んだ。後日、彼はインクを入れ直し、ペン先を丁寧に修理する。そして、遠く離れて暮らす、作家を夢見る自分の娘への手紙を、その万年筆で書き始めるのだった。
『想いの込められたモノは、決して死なない。形を変え、持ち主を変え、新たな物語を紡ぎ続ける。お前が捨てたのは、モノじゃない。祖母との物語の、次の一章への扉だったのだ』
湊は、衝撃と共に悟った。自分が見ていたのは、ゴミの末路などではなかった。それは、モノに宿る「物語(モノガタリ)」の終着点、あるいは新たな始まりだったのだ。使い捨てのプラスチック容器には、作る過程の物語しかなく、だからすぐに焼却という終焉を迎える。だが、祖母の万年筆には、湊との思い出という強い物語があった。だから、ゴミにはならなかった。
彼の価値観が、音を立てて崩れ落ち、そして再構築されていく。世界は、彼が思っていたよりもずっと、多くの物語で満ちていた。
第四章 物語の住人
あの日を境に、湊は二度と奇妙な夢を見ることはなくなった。彼がモノを「捨てる」という概念を手放したからかもしれない。彼の行為は、捨てるのではなく、「次の役割へ送り出す」ための儀式に変わった。
湊の日常は、豊かになった。彼は週末になると、フリーマーケットや骨董市に足を運んだ。傷のついた木製の椅子、少し欠けた陶器の皿、動かなくなった振り子時計。彼はそれらを連れて帰り、丁寧に修理し、磨き上げた。傷は欠点ではなく、そのモノが生きてきた証、前の持ち主との物語の痕跡なのだと知ったから。彼の部屋は、かつての無機質で大量生産されたモノで溢れた空間から、一つ一つに温かい物語が息づく、小さな博物館のような場所へと変わっていった。
仕事にも変化が訪れた。彼は、ただ見た目が美しいだけのデザインを作ることをやめた。長く使われ、使う人に愛され、いつかその人の物語の一部になるような、そんなデザインを心がけるようになった。彼の作るものは、どこか温かみがあり、クライアントからの評価も格段に上がった。
ある晴れた春の朝、湊はベランダで、自身で修復した古い木製の椅子に腰掛け、コーヒーを飲んでいた。手にしているマグカップは、割れた部分を金継ぎで補修したものだ。金色の線が、まるで美しい稲妻のように走っている。
もう、捨てられたモノたちの声なき声にうなされることはない。だが、彼は決して忘れないだろう。プラスチック容器の絶望も、海を漂うペットボトルの孤独も、そして、祖母の万年筆が紡ぎ始めた新しい物語も。
湊は、カップをそっとテーブルに置いた。朝日が、部屋の中にある古びた家具や雑貨たちを優しく照らし出す。それらはただのモノではなかった。それぞれが、それぞれの時間を生き、それぞれの物語を内包した、静かな住人たちだ。
世界は何も変わっていない。相変わらず人々はモノを買い、そして捨てる。だが、湊にとっての世界は、以前とは全く違う意味を持っていた。彼は今、無数の物語に囲まれて生きている。そして彼自身もまた、手の中にあるモノたちと共に、新たな物語を紡いでいくのだ。その静かで満ち足りた日常の中に、彼は確かな幸福を感じていた。