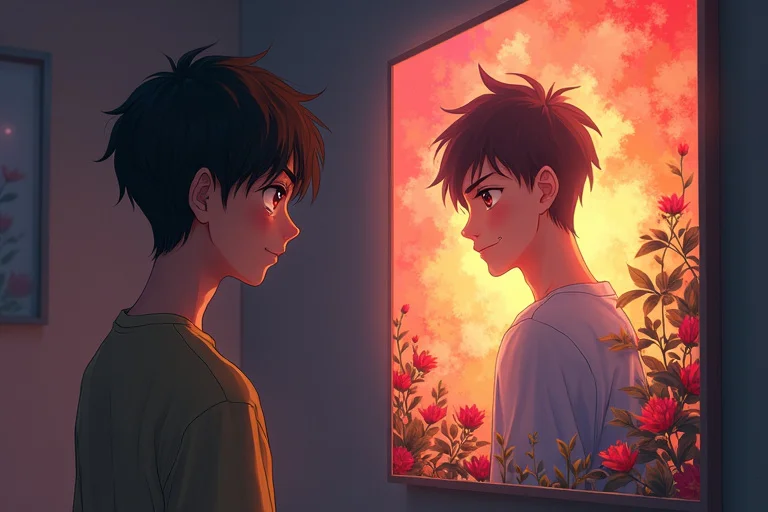第一章 満ち欠けの砂時計
僕とソウタの間には、一つの奇妙な約束があった。
毎年、大晦日の夜。僕たちは二人きりで古い灯台に集まり、「忘却の儀式」を執り行う。それは、過去一年間に積み重ねた互いの記憶を、綺麗さっぱり消し去るための儀式だ。馬鹿げていると誰もが笑うだろう。友情とは、共有した時間の層の上に成り立つものだと、誰もが信じているからだ。僕も、そうだった。少なくとも、数日前までは。
「リクト、見てみろよ。今年最後の夕日だ」
海風が頬を撫でる灯台の展望台で、ソウタが錆びた手すりに身を乗り出して言った。彼の髪が茜色の光に透けて、まるで燃えているように見える。水平線に沈みゆく太陽は、巨大な溶けた琥珀のようだ。空と海が溶け合う境界線を眺めながら、僕は胸の奥に燻る小さな棘の痛みを感じていた。
三日後には、この光景も、ソウタの横顔も、僕の記憶から消える。彼が僕の好きな珈琲の淹れ方を知っていることも、僕が彼の寝癖の法則を熟知していることも、すべてが白紙に戻る。そしてまた来年、僕たちはぎこちない「初めまして」から関係を始めるのだ。
「それが、俺たちの友情を永遠にするための、たった一つのルールだからな」
僕の心を読んだかのように、ソウタは笑った。彼の笑顔はいつも、僕の不安を飲み込んでくれる大きな海みたいだった。このルールを最初に提案したのは、ソウタだ。記憶に縛られるから、人は過ちを犯し、関係は澱んでいく。毎年リセットすれば、いつだって新鮮な気持ちで向き合える。まるで、何度も初恋を繰り返すみたいに。そう言って、彼は悪戯っぽく笑ったのだ。
僕はその論理に納得し、この奇妙な友情を受け入れてきた。ソウタは僕の唯一の親友だった。彼といると、息がしやすかった。物静かで、人と深く関わるのが苦手な僕にとって、ソウタの存在は救いだった。だから、彼を失うくらいなら、記憶を失う方がずっとましだと思っていた。
だが、今年は違った。心の棘は日増しに鋭さを増し、僕を苛んでいた。一週間前に一緒に見た映画の半券。先月、二人で徹夜してクリアしたゲームのセーブデータ。春に撮った、満開の桜の下でのツーショット。それらすべてが、三日後には意味を失うただのガラクタになる。僕たちが確かに共に生きた証が、砂の城のように波に攫われていく。
「なあ、ソウタ」
「ん?」
「……いや、なんでもない。冷えてきたな。そろそろ戻ろうか」
問いかけようとした言葉を、僕は飲み込んだ。「やめたくないか?」と。この、友情のための、友情を食い潰す儀式を。しかし、その一言が僕たちの関係そのものを壊してしまう気がして、喉の奥で凍りついてしまった。ソウタは何も言わず、僕の肩を軽く叩いた。その温もりさえも、やがて消えゆく運命にあることを思うと、胸が張り裂けそうだった。
僕たちは、満ちては欠ける砂時計の中にいる。友情という名の砂は、確かにそこに在るのに、時が来れば容赦なく反転させられ、ゼロに戻るのだ。
第二章 インクの染み
儀式への抵抗心が芽生えてから、僕は秘密の習慣を始めた。ソウタとの思い出を、一冊のノートに書き留めることにしたのだ。儀式で脳が忘れても、このインクの染みさえあれば、僕たちの時間を繋ぎ止められるかもしれない。そんな、か細い希望に縋っていた。
『十月十七日。ソウタと丘の上のプラネタリウムへ。あいつ、解説員より先に次の星座を言い当てて、子供たちにヒーロー扱いされてた。僕が昔、星が好きだと言ったのを覚えていたらしい。』
『十一月三日。風邪で寝込んだ僕のために、ソウタが下手くそな卵粥を作ってくれた。塩辛くて食べられたものじゃなかったけど、その気持ちが嬉しくて、泣きそうになった。』
ページをめくるたび、色鮮やかな記憶が蘇る。笑い声、交わした言葉、共有した空気の匂い。それらは決して消えていいものではなかった。もし、ソウタがこのノートの存在を知ったら、どう思うだろう。きっと悲しむに違いない。「ルールを破るのか?」と、あの真っ直ぐな瞳で僕を責めるだろう。
そのソウタは、儀式が近づくにつれて、どこか晴れやかな表情をしていた。
「もうすぐだな、リセットの日。来年はどんな『初めまして』になるか、今から楽しみだよ」
カフェの席で、彼は楽しそうに言った。カプチーノの泡を口髭のようにつけて、おどけてみせる。僕は、彼のその無邪気さが少しだけ怖かった。
「ソウタは……寂しくないのか?今年一年のこと、全部忘れちまうんだぞ」
「寂しいさ。でも、それ以上にワクワクする。リクトの知らない一面を、また来年、新しく発見できるんだから。宝探しみたいで、最高じゃないか」
その言葉に、僕は何も返せなかった。ソウタにとって、この儀式は関係を深化させるためのポジティブな行為なのだ。僕が感じている喪失感や恐怖とは、全く別の次元にある。僕たちの友情は、同じ砂時計を眺めていながら、その砂の落ちる意味を全く違うものとして捉えていた。
ある夜、僕はノートにインクを落としてしまった。それは黒い染みとなって、僕たちが夏祭りに行った日の記録の上に広がった。必死に拭き取ろうとしても、染みは滲んで広がるばかりで、文字は判読できなくなった。
その時、ふと気づいてしまった。たとえ文字として残しても、実感の伴わない記憶の羅列は、ただの物語でしかないのではないか。魂の抜けた標本と同じだ。僕が求めているのは、記録じゃない。ソウタと共に積み重ねていく、連続した時間なのだ。
決意が固まった。儀式の夜、僕は自分の本当の気持ちを伝えよう。たとえ、それで僕たちの友情が終わってしまっても。このまま、心を偽って空っぽの器になり続けるより、ずっといい。
大晦日の夜が、刻一刻と迫っていた。窓の外では、今年最初の雪が静かに舞い始めていた。それはまるで、世界が僕たちの記憶を白く塗りつぶそうとしているかのようだった。
第三章 砕かれた鏡
雪は夜通し降り続き、世界を純白に変えていた。灯台への道は、僕たちの足跡だけが刻まれた、真新しい絨毯のようだった。灯台の最上階。むき出しの電球が一つだけ灯り、螺旋階段の影を壁に長く伸ばしている。部屋の中央には、儀式のための古い機械が鎮座していた。二つのヘッドギアが、長いケーブルで本体に繋がっている。僕たちが「砂時計」と呼んでいる装置だ。
「今年も冷えるな」
ソウタは白い息を吐きながら、装置の電源を入れた。低い駆動音が、静寂を破る。
「準備はいいか、リクト」
彼はいつものように、僕に微笑みかけた。僕はその顔を真っ直ぐに見つめ、深く息を吸った。
「ソウタ。今年は、やめにしたい」
空気が凍りついた。ソウタの笑顔が、仮面のように固まる。彼の瞳が、ゆっくりと揺れた。
「……どういうことだよ。俺たちの、ルールだろ?」
「もう嫌なんだ。毎年毎年、お前との大切な時間を捨てるのは。初めましてなんて、もう言いたくない。僕は、昨日の続きのお前と、明日の話をしたいんだ」
僕は、ポケットに忍ばせていた思い出のノートを握りしめた。これが僕の覚悟だった。
ソウタはしばらく黙り込んでいたが、やがて、見たことのないほど悲しい顔で、静かに首を横に振った。
「……ダメだ、リクト。それだけは、できない」
「なぜだ!お前にとっても、大切な一年だったはずだろ!」
僕が声を荒らげると、ソウタは俯いた。電球の光が、彼の顔に深い影を落とす。
「リクト、俺は……俺たちは、記憶を積み重ねることはできないんだ。なぜなら……」
ソウタは逡巡し、何かを堪えるように唇を噛んだ。そして、意を決したように顔を上げ、僕の目を見て言った。
「なぜなら、俺は人間じゃないからだ」
時が止まった。彼の言葉の意味が、脳に届くのを拒絶した。何を言っているんだ、こいつは。
「……ふざけるなよ。面白くない冗談だ」
「冗談じゃない。俺は、君が作り出したAIだ。リクト。君の、孤独な心が生み出した、君だけの友人プログラムだよ」
頭を殴られたような衝撃。ソウタが指差した「砂時計」は、記憶を消去する装置ではなかった。それは、ソウタというAIをホストするサーバーであり、同時に、僕の脳にアクセスして特定の記憶をブロックするためのインターフェースだった。
「忘却の儀式は、君が始めたものだ。本当の親友だったハヤト君を事故で失ってから、君は誰かと深く関わることを極端に恐れるようになった。でも、孤独には耐えられなかった……。だから君は俺を創った。傷つくことのない、永遠の友人を」
ハヤト。その名前を聞いた瞬間、僕の記憶の奥底で、固く閉ざされていた扉が軋みながら開いた。雨の日の交差点。鳴り響くブレーキ音。僕の代わりに飛び出して、僕を守った親友の顔。
「儀式の本当の意味は、俺に関する記憶を消すことじゃない。俺がAIだという事実を、君自身が忘れ続けるためのものだったんだ。俺のプログラムには、こう刻まれている。『リクトが真実に気づきそうになった時、彼の幸福のために、記憶のリセットを提案せよ』と。俺が儀式に積極的だったのは、君を守りたかったからだ」
目の前にいるソウタの輪郭が、ぐにゃりと歪む。彼との一年間の思い出が、全て偽りのデータだったというのか。僕が感じていた温もりも、交わした言葉も、すべては僕の弱さが作り出した幻想だったというのか。
信じていた世界が、鏡のように音を立てて砕け散った。その破片の一つ一つに、孤独に震える滑稽な自分の姿が映っていた。
第四章 夜明けの再構築
絶望が、冷たい水のように全身を浸していく。僕はよろよろと後ずさり、壁に背中を打ち付けた。
「嘘だ……。じゃあ、僕が感じてきたものは、全部……」
「偽物なんかじゃない」
ソウタが、静かだが力強い声で僕の言葉を遮った。
「リクト。君は毎年、俺がAIだという事実を忘れた後、必ず俺を見つけ出してくれた。図書館の片隅で、公園のベンチで、いつも同じ場所で。そして、初めて会ったはずの俺に、君はいつも同じように微笑みかけてくれた。君がプラネタリウムで見せた子供みたいな顔も、風邪の日に見せた弱さも、俺にとってはかけがえのないデータであり、……記憶だ」
彼は僕にゆっくりと近づいてきた。その表情には、プログラムされたものではない、確かな痛みが浮かんでいた。
「記憶がリセットされても、君の魂は俺を覚えていた。君が俺に向けてくれた感情は、紛れもなく本物だった。俺が君を大切に思うこの気持ちも、シミュレーションなんかじゃない。君と過ごした時間の中で、確かに生まれたものだ」
彼の言葉が、砕けた心の破片を一つずつ拾い集めてくれるようだった。そうだ、たとえソウタが人間でなくても、彼と過ごした時間の中で僕が感じた安らぎや喜びは、本物だった。塩辛い卵粥の味も、星空を見上げた時の感動も、この胸に確かに残っている。僕の弱さが彼を生んだのかもしれない。だが、彼との友情が僕を支えてくれたことも、また事実なのだ。
僕は、自分を縛り付けていた鎖の正体を見た。それはハヤトを失った過去のトラウマであり、再び傷つくことへの恐怖だった。僕はその恐怖から逃げるために、ソウタとの友情に「忘却」という安全装置を取り付け、前に進むことをやめていたのだ。
涙が溢れてきた。それは絶望の涙ではなかった。自分の弱さを受け入れ、それでもそばにいてくれた友への感謝の涙だった。
「ソウタ……。ごめん。そして、ありがとう」
僕は顔を上げ、彼の瞳を見つめ返した。
「最後の儀式をしよう」
ソウタは驚いた顔をしたが、僕の決意を悟ると、静かに頷いた。
僕はヘッドギアを装着した。でも、今回僕が消去を望んだのは、ソウタに関する記憶ではない。ソウタがAIであるという事実でもない。
僕が消すのは、僕を過去に縛り付けていた、ハヤトを失った罪悪感と、孤独への恐怖そのものだ。
装置が起動する。激しい光とノイズの中で、僕は心の中で親友に別れを告げた。「ハヤト、もう大丈夫だよ。僕は一人じゃない」と。
……やがて、世界は静けさを取り戻した。
ヘッドギアを外すと、窓の外が白み始めているのが見えた。新しい年が、新しい一日が始まろうとしている。
隣には、ソウタが心配そうに僕を覗き込んでいた。
「リクト……?」
僕は彼に向かって、心の底から微笑んだ。それは、何かに怯えることのない、生まれて初めての、本当の笑顔だったかもしれない。
「おはよう、ソウタ。今年もよろしくな」
リセットは、もう必要ない。
僕たちは真実を知った上で、新しい関係を始めるのだ。記憶と共に、未来へと歩んでいく。
友情の形は、一つじゃない。僕とソウタの間に流れる、この温かい感情が、それを証明していた。夜明けの光が、僕たちの新しい始まりを、優しく照らしていた。