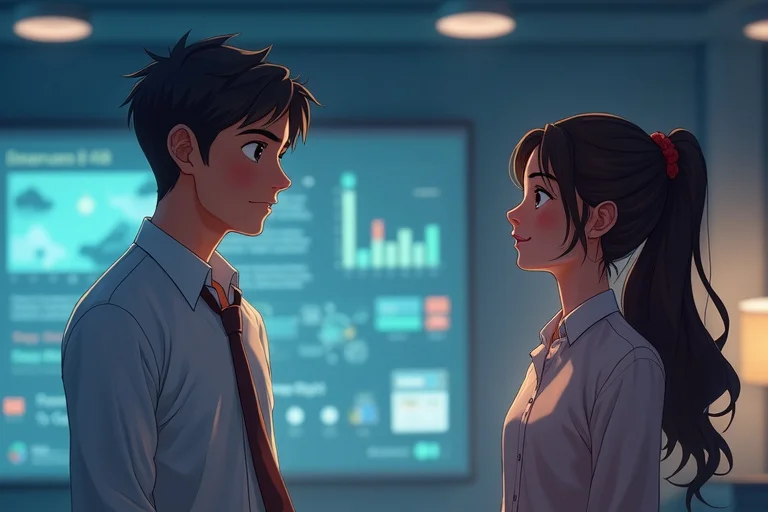第一章 漏洩する思考、あるいは呪いの始まり
佐藤健太、三十二歳、独身。彼の人生は、几帳面に整理されたデスクの上のように、平坦で予測可能なものだった。少なくとも、昨日の朝までは。
異変の兆候は、通勤ラッシュの山手線で現れた。ぎゅう詰めの車内で、目の前の男性の整髪料の匂いに顔をしかめながら、健太は心の中で思った。『うわ、この匂い、強烈すぎる。まるで化学兵器だ』。すると、隣に立っていた女子高生が、クスクスと笑いながら友人に囁いた。「ねえ、今の聞いた?『この匂い、まるで化学兵器だって』。誰か言ったのかな」。健太の背筋を、冷たい汗が滝のように流れ落ちた。
気のせいだ。そうに違いない。疲れているんだ。
しかし、オフィスに到着し、自席に向かう彼の心を占める思考――『ああ、また書類の山か。僕の人生は紙に埋もれて終わるのか』――が、すれ違った営業部のエース、鈴木の声によって現実世界に引き戻された。「佐藤、朝から暗いぞ!『人生が紙に埋もれる』なんて、詩人みたいなこと言うなよ!」。鈴木は健太の肩をバンと叩き、爽やかに去っていった。
健太は自席に崩れるように座った。これは幻聴ではない。現実だ。彼の心の声が、どういうわけか周囲の人々に「聞こえて」いる。しかも、ただ聞こえるのではない。彼の内なるモノローグは、最も陳腐で、最も間の悪い「ダジャレ」として変換され、世界に漏洩しているようだった。
「佐藤さん、おはようございます!」。背後から、太陽のような声がした。同僚の高橋凛だ。彼女はいつも明るく、健太のような日陰の存在にも分け隔てなく接してくれる、社内のオアシス的存在だった。
健太は心の中で、精一杯の平静を装って挨拶を返した。『高橋さん、おはよう。君の笑顔は朝の光のようだ』。
すると、凛はきょとんとした顔で首を傾げ、やがて噴き出した。「佐藤さん!『君の笑顔はアサリの味噌汁のようだ』って、どういう意味ですか!でも、なんか嬉しいです!」。
アサリの味噌汁。朝の光が、アサリの味噌汁に。健太は絶望した。彼の脳内に搭載されたポンコツ変換エンジンは、詩情のかけらもない。
その日から、佐藤健太の平穏な日常は、予測不能なダジャレが鳴り響く不協和音の交響曲へと変貌を遂げた。彼は、この呪われた能力を隠し通そうと、必死の抵抗を試みることになる。それは、壮絶で、滑稽で、そして孤独な戦いの始まりだった。
第二章 誤解のスパイラルと翻訳する彼女
呪いが始まって一週間。健太はすっかり口数の少ない、いや、思考の少ない人間になろうと努力していた。頭を空っぽにする。禅僧のように、無の境地を目指す。しかし、人間である以上、何も考えないというのは不可能に近い。特に、健太のような心配性の人間にとっては。
部長に呼ばれ、プロジェクトの進捗を報告する。心の中は不安でいっぱいだ。『この計画、いくつか懸念点があります。正直、かなり厳しいかもしれません』。そう真剣に思えば思うほど、部長の耳にはこう届いたらしい。「『この計画、いくつかケネディ暗殺事件があります。正直、かなり厳しい寒ブリかもしれません』か。佐藤、面白いことを言うじゃないか。だが、君のそのユーモアで乗り切ってくれ!」。部長は豪快に笑い、健太の背中を叩いた。真剣な懸念は、謎のジョークとして消費された。
健太の評判は、意図しない方向へと一人歩きを始めた。「口数は少ないが、時折、シュールで哲学的なダジャレを放つ、ミステリアスな男」。それが、社内における新しい佐藤健太像だった。彼はただ静かに、目立たず、仕事をこなしたいだけなのに、人々は彼の沈黙の中に次なる「一発」を期待するようになった。給湯室に行けば「新作まだ?」と囁かれ、コピーを取っているだけで「何か降臨中ですか?」と期待の眼差しを向けられる。地獄だった。
そんな中、高橋凛だけが、少し違った反応を見せていた。彼女は健太の「ダジャレ」を聞くと、他の皆のようにただ笑うのではなく、何かを考えるように顎に手をやり、手元のノートにこっそり何かを書き留めているのだ。
ある日の昼休み、健太が屋上で一人、サンドイッチを頬張りながら『このままじゃ、僕の社会人生命もサンドイッチみたいに挟まれて終わるな…』と黄昏れていると、凛がそっと隣にやってきた。
「佐藤さん、『社会人生命がサンドイッチ』、いただきました」
「……聞いてたのか」健太は観念したように呟いた。
「聞こえちゃいました」と凛は悪戯っぽく笑う。「あの、私、佐藤さんの言葉、翻訳してるんです」。
彼女が差し出したノートには、びっしりと文字が書かれていた。左側には日付と共に健太が放った(漏らした)ダジャレ。そして右側には、凛による「翻訳」が記されていた。
『君の笑顔はアサリの味噌汁のようだ』→***翻訳: あなたの笑顔を見ると、心が温かくなります***
『この計画にはケネディ暗殺事件がある』→***翻訳: この計画には、見過ごせない深刻なリスクがある***
『僕の人生は紙に埋もれて終わる』→***翻訳: 日々の業務に追われ、自分の将来に不安を感じている***
健太は言葉を失った。誰もが彼を「面白い人」としてしか見ていない中、この女性だけが、彼のダジャレというノイズの向こう側にある、彼の本当の心の声を聞き取ろうとしてくれていたのだ。
「どうして……」
「なんとなく、です」と凛は微笑んだ。「佐藤さんの言うことって、面白いけど、いつもどこか切ない響きがするから。だから、本当は何を言いたいんだろうって、考えてみたくなったんです」。
その瞬間、健太の心に温かい何かが流れ込んできた。『高橋さん、君は……僕の理解者だ』。
凛は、ふふっと笑ってノートに書き加えた。「『高橋さん、君は……僕のイカ飯だ』。これも、きっと最高の褒め言葉ですよね」。
健太は、呪いが始まって以来、初めて心の底から笑いたいような、泣きたいような、不思議な気持ちになった。
第三章 氷上のプレゼンと奇跡のダジャレ
そのプロジェクトは、会社の命運を左右するほどに重要だった。クライアントはドイツの老舗メーカー、シュタインハイル社。そして交渉相手は、そのCEOであるクラウス・シュミット氏。鉄の意志と氷の心を持つと噂され、契約交渉の場では一切の冗談や無駄話を嫌うことで有名だった。
オンラインでの最終プレゼンテーション。健太も、プロジェクトの一員として参加せざるを得なかった。彼は会議の数日前から、極度のプレッシャーで眠れぬ夜を過ごしていた。この場で万が一、心の声が漏れたら?『この契約、絶対に取りたいです!』という熱意が、『この契約、絶対トリュフみたいです!』などと変換された日には、即刻クビだろう。
会議当日、健太はモニターの前に座り、石像のように固まっていた。心を無に。思考を停止する。彼はただの置物。そうだ、観葉植物だ。光合成だけしていればいい。
プレゼンは、張り詰めた空気の中で始まった。通訳を介して、シュミット氏の鋭い質問が次々と飛んでくる。プロジェクトリーダーの額には脂汗が浮かび、言葉に詰まる場面が増えてきた。モニターの向こう側、シュミット氏の眉間の皺が、マリアナ海溝のように深くなっていくのが分かった。社内の誰もが、失敗を予感し、モニターに映る自社のロゴが墓標のように見え始めていた。
その時、シュミット氏が決定的な一言を放った。「貴社の提案には、リスク管理に対する具体的なビジョンが見えない。このままでは、パートナーシップを結ぶことは困難だ」。
それは、事実上の最後通牒だった。会議室の空気が凍りつく。誰もが下を向く中、健太の心臓は警鐘のように激しく鳴り響いた。
まずい。このままでは終わる。みんなが必死で積み上げてきたものが、全部無駄になる。僕が、僕が何か言わなければ。でも、何を?どうやって?僕にできることなんて何もないじゃないか!
パニックと無力感、そして仲間を救いたいという純粋な思いが、彼の心の中で渦を巻いた。その激情が、彼の脳のポンコツ変換エンジンを、前代未聞のフルスロットルで稼働させた。
『このままじゃダメだ!この契約は、僕たちにとって本当に、本当に大切なんです!この熱い思い、伝われ!』
次の瞬間、沈黙を破って、健太の口から、いや、彼の魂から、一つの言葉が絞り出された。それはマイクに乗り、通訳の耳に届き、そして世界へと放たれた。
「この契約……『この契約は、ヴルスト(ソーセージ)ではない』!」
会議室は死んだ。日本のスタッフ全員が、血の気が引くのを感じた。通訳は一瞬躊躇したが、プロフェッショナルとして、その謎の言葉をドイツ語に訳した。「Dieser Vertrag ist keine Wurst.」
モニターの向こうで、シュミット氏の動きが止まった。彼の氷のような瞳が、ゆっくりと健太を捉える。誰もが、激怒か、あるいは契約打ち切りの宣告を覚悟した。
数秒の沈黙。それは、永遠よりも長く感じられた。
やがて、シュミット氏の口角が、ほんのわずかに上がった。そして、信じられないことに、彼は「フッ」と息を漏らし、次の瞬間には肩を震わせ、腹を抱えて大笑いし始めたのだ。
「はっはっは!ヴルストではない、か!面白い!実に面白い!」
シュミット氏は涙を拭いながら言った。「私の亡くなった祖父がね、日本かぶれでね。よく言っていたんだ。『仕事はソーセージではない。情熱というスパイスを効かせなければ、ただのひき肉だ』と。君の言葉は、祖父の口癖そのものじゃないか!」。
凍りついていた空気は、一瞬にして春の陽だまりのように溶けていった。シュミット氏は上機嫌になり、「君のような情熱的な若者がいる会社なら、信頼できる」と、その場で契約に前向きな姿勢を示したのだった。
健太は、何が起こったのか理解できないまま、ただ呆然とモニターを見つめていた。彼の人生で最も意味不明なダジャレが、会社を救うという奇跡を起こしたのだ。
第四章 交響曲は鳴り止まず
シュミット氏との契約は、トントン拍子で成立した。健太は、一夜にして「会社を救ったヒーロー」として祭り上げられた。誰もが彼の「計算され尽くした、高度な異文化ジョーク」を称賛したが、健太自身は、ただただ混乱していた。
その日の夜、会社の祝賀会の喧騒を抜け出した健太は、再びオフィスの屋上にいた。東京の夜景が、まるで他人事のようにきらめいている。
「ヒーローは、こんなところにいていいんですか?」
振り返ると、凛が微笑んで立っていた。彼女の手には、缶コーヒーが二つ。
「ヒーローなんかじゃないよ」健太は力なく笑った。「ただ、心の声が漏れただけだ」。
「知ってます」と凛は隣に座った。「でも、今日の『ソーセージじゃない』は、最高でした。今までで一番、佐藤さんの気持ちが伝わってきましたよ」。
彼女は自分のノートを開いて見せた。そこには、こう書かれていた。
『この契約は、ヴルストではない』→***翻訳: この契約は、ただのビジネスライクな取引なんかじゃない。私たちの情熱と魂が込められた、大切な約束なんだ***
健太は、ノートに書かれた言葉をじっと見つめた。そうだ。それが、僕が本当に言いたかったことだ。僕の弱さも、不安も、不器用な情熱も、全部ひっくるめて、この人は受け止めてくれていた。そして、僕の呪いは、最悪の形で最高の奇跡を呼んだ。
「僕、ずっと自分のことが嫌いだったんだ」健太は、ぽつりぽつりと話し始めた。「心配性で、人前でうまく話せなくて、いつも心の中でごちゃごちゃ考えてばかりで。この呪いが始まった時も、最悪だと思った。でも……」。
彼は凛の顔を見た。「でも、君が僕の言葉を翻訳してくれて、僕のダジャレで誰かが笑ってくれて、ついには会社まで救ってしまった。僕のダメな部分が、誰かの役に立つこともあるのかもしれないって、初めて思えたんだ」。
健太の内面で、何かが静かに、しかし確実に変わっていくのを感じた。自分の欠点や弱さを隠すのではなく、それもまた自分なのだと受け入れる勇気。完璧でなくてもいい。不器用なままでいい。彼の心の中で鳴り響いていた不協和音の交響曲が、いつの間にか、どこか優しく、愛おしいメロディに聞こえ始めていた。
後日、健太と凛は、休日にカフェで向かい合っていた。以前のような過剰な緊張は、もう健太にはない。
「これからは、どんなダジャレが飛び出すんでしょうね」凛が楽しそうに言う。
健太は、目の前で微笑む彼女を見つめながら、心から思った。『君とこうしていると、本当に心が穏やかになる。世界が輝いて見えるよ』。
すると、彼の口から、ごく自然に、小さな声が漏れた。
「君といると、心が『昆布』みたいに、いいダシが出そうだよ」。
凛は一瞬目を丸くし、そして、これまでで一番美しい笑顔で、花が咲くように笑った。
その笑い声を聞きながら、健太は思った。
この呪いは、まだ解けそうにない。でも、もう、それでもいいか。世界は相変わらず不条理で、僕の心はダジャレを漏らし続けるだろう。だが、その不協和音を、美しいメロディだと笑ってくれる人が隣にいる。
佐藤健太の交響曲は、まだ始まったばかりだ。そしてその音色は、きっとこれからも、誰かの心を少しだけ、温かくしていくのだろう。