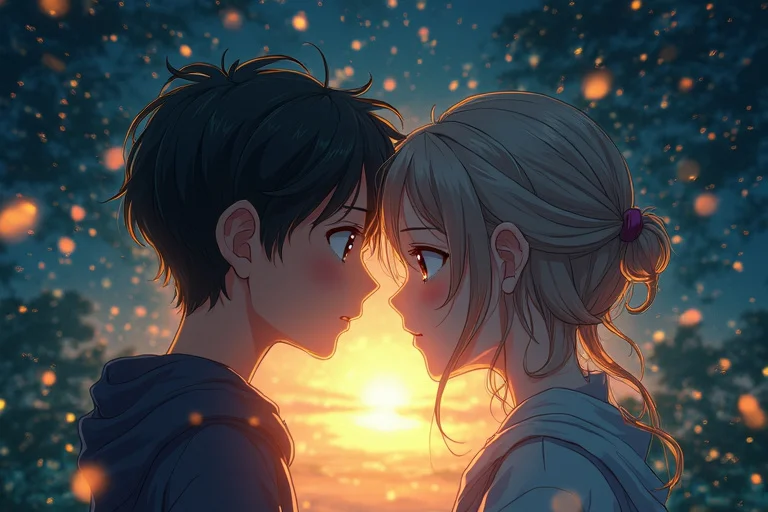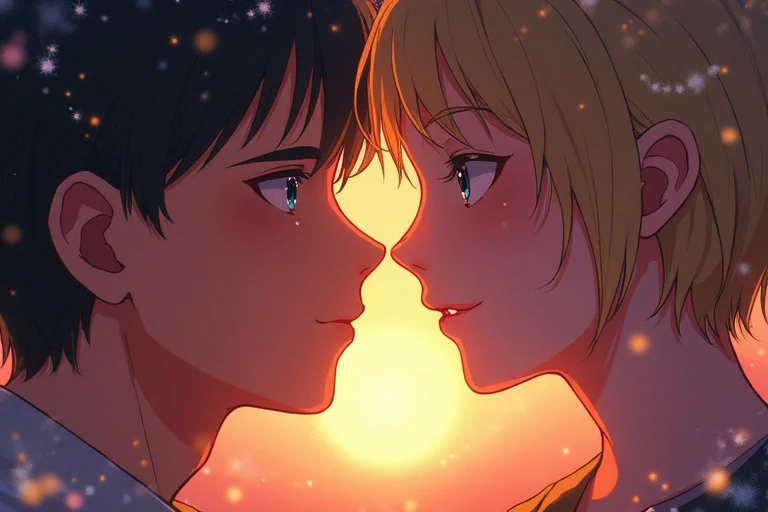第一章 虹色のシャボン玉と黒曜石の悲鳴
僕たちの世界では、言葉は形を持つ。
教室の空気は、絶えず無数の「言葉の欠片」で満たされている。朝の挨拶である「おはよう」は、虹色にきらめくシャボン玉となってふわりと浮かび、数秒後には儚く弾けて消える。他愛ない噂話は、乾いた落ち葉のようにカサカサと音を立てて床を転がり、授業中の真剣な問いかけは、澄んだ水晶の粒となって先生の机にこつんと落ちる。
僕は、蒼井湊(あおいみなと)。この世界で、できるだけ無害な言葉だけを選んで生きてきた。僕の口から生まれるのは、いつだって軽いシャボン玉だけだ。誰かを傷つけたくない。もっと言えば、言葉の持つ「重さ」が怖かった。不用意な一言が、石ころとなって相手の心を打つのを何度も見てきた。悪意のこもった言葉が、黒いガラスの破片となって飛び散り、誰かの肌を浅く切り裂く光景に、息を呑んだことも一度や二度じゃない。
だから僕は、当たり障りのない、中身のない、軽い言葉だけを吐き出す術を身につけた。そうしていれば、誰かを傷つけることも、誰かから傷つけられることもない。空っぽの僕の周りには、いつも虹色のシャボン玉だけが舞っていた。
そんな僕の世界に、天野陽菜(あまのひな)はいた。
彼女は、僕とは正反対だった。いつもクラスの中心で、太陽のように笑い、その口からは色とりどりの言葉が溢れ出した。友達を励ます言葉は、温かい光を放つ小さな真珠となって相手の手に収まり、面白い冗談は、ポップコーンのようにはじけて教室中に笑いを振りまいた。もちろん、時には鋭い言葉が小さな矢となって飛んでいくこともあったが、それすらも彼女の魅力の一部に見えた。彼女の周りには、常に生命力に満ちた言葉たちが、きらきらと舞っていた。僕はそんな彼女から、目が離せなかった。
あの日、忘れ物を取りに放課後の教室へ戻った僕は、偶然、美術室の扉が少しだけ開いていることに気づいた。静まり返った廊下に、微かな嗚咽が漏れている。吸い寄せられるように中を覗き込むと、そこにいたのは陽菜だった。
イーゼルの前に一人しゃがみ込み、肩を震わせている。夕陽が差し込む室内には、絵の具の匂いと、彼女の悲しみが満ちていた。いつも快活な彼女からは想像もつかない姿に、僕は息を呑んだ。声をかけることもできず、ただ立ち尽くす。
やがて彼女はゆっくりと立ち上がり、涙を拭って美術室を出ていった。僕の存在には気づかなかったようだ。彼女が去った後、僕は恐る恐る部屋に入った。彼女がいた場所に、何かが落ちている。
それは、僕がこれまで見たどんな言葉よりも、異質な存在だった。
ずっしりと重そうな、歪な形をした黒曜石。光を全く反射せず、周囲の明るさを吸い込んでしまうような、底なしの闇を宿している。手を伸ばしかけて、ためらった。それはあまりにも冷たく、あまりにも重い悲鳴のように見えた。その石は、紛れもなく『助けて』という一つの言葉が結晶化したものだった。
僕は、その黒い石をそっと拾い上げた。ポケットに入れると、まるで鉛の塊のように、制服のズボンが片方だけずしりと重くなった。
第二章 ポケットの中の重力
あの日以来、僕の日常はポケットの中の重力に支配されるようになった。黒曜石の『助けて』は、僕の太ももにその冷たさと重さを絶えず伝え続け、陽菜のことを考えずにはいられなくさせた。
しかし、陽菜自身は、翌日にはいつもの太陽のような笑顔で学校に現れた。彼女の周りでは、昨日と同じようにカラフルな言葉たちが楽しげに舞っている。あの美術室での姿は、まるで僕が見た幻だったかのようだ。
「蒼井くん、おはよう!」
彼女が僕に笑いかける。その口から生まれた「おはよう」は、完璧な球体のシャボン玉となって僕の目の前でふわりと揺れた。僕は慌てて、当たり障りのないシャボン玉を返す。
「あ、うん。おはよう」
僕の言葉は、いびつな形で生まれ、すぐにぱちんと弾けて消えた。陽菜は気にした様子もなく、友達の輪の中へと戻っていく。その背中を見送りながら、僕はポケットの中の石を強く握りしめた。この重さだけが、彼女の笑顔の裏にある真実を知っている証だった。
なぜ彼女は『助けて』なんて言葉を生み出したのだろう。誰かにいじめられているのか? それとも、家庭に何か問題を抱えているのか? 疑問は尽きないが、僕には確かめる術がない。僕の言葉はあまりにも軽く、彼女の心に届く前に消えてしまうだろうから。
どうすれば、言葉に「重み」を持たせることができるんだろう。
僕はその日から、まるで何かに取り憑かれたように、言葉について調べ始めた。図書館の片隅で、古びた民俗学の本をめくった。『言霊の質量に関する一考察』というタイトルの論文にはこう書かれていた。「言葉の質量は、発話者の感情エネルギーの総量に比例する。中でも『覚悟』と『純度』が最も重要な変数となる」
覚悟と、純度。今の僕に決定的に欠けているものだった。僕はいつも、当たり障りのない言葉の影に隠れ、自分の本心と向き合うことから逃げてきた。僕の言葉が軽いのは当然だった。
週末、僕は街のはずれにあるという「言葉職人」の工房を訪ねた。そこは、記念碑に刻む重い言葉や、代々伝わる家訓などを、依頼を受けて作り出す職人がいる場所だ。工房の主である老人は、僕が差し出した黒曜石の『助けて』を一目見て、深く長い溜息をついた。
「これは…途方もない悲しみが結晶になったもんじゃな。これほどの言葉は、ワシでも滅多にお目にかかれん」
老人は、皺だらけの手で石をそっと撫でながら言った。「坊主、言葉に重みが欲しいか。じゃがな、重い言葉は諸刃の剣じゃ。人を救うこともあれば、人を深く傷つけ、時にはその重みで自分自身を潰してしまうこともある。その覚悟はおありかい?」
老人の言葉が、ずしりと僕の胸に落ちてきた。僕は何も答えられなかった。ただ、ポケットの中の石が、また一段と重くなった気がした。
第三章 鉛の鎖と無力な言葉
文化祭が近づき、学校全体が浮き足立った空気に包まれていた。陽菜は実行委員として、誰よりも忙しそうに校内を駆け回っていた。その笑顔は一層輝いて見えたが、僕には時折、彼女の足取りがひどく重そうに見えることがあった。
事件が起きたのは、文化祭を二日後に控えた雨の日の放課後だった。クラスの装飾準備が長引き、僕は最後の片付けをしていた。ほとんどの生徒が帰った後、準備室で備品を返却しようとした時、廊下の向こうから押し殺したような声が聞こえてきた。
そこにいたのは、陽菜と数人のクラスメイトだった。
「あんたが一人でいい顔するから、こっちの仕事が増えるんだけど」
「そうそう、全部自分でやりますって顔して、結局できてないじゃん」
クラスメイトたちの口から放たれた言葉は、どれも薄汚れたガラスの破片となって、陽菜の周りに降り注いだ。それは床に落ちては、嫌な音を立てて砕ける。陽菜は、降りしきるガラスの雨の中で、ただ黙って俯いていた。
僕はカッとなって、思わず飛び出していた。
「やめろよ!」
僕の口から飛び出した言葉は、大きなシャボン玉になった。だが、それはあまりにも頼りなく、ガラスの破片に触れた瞬間に虚しく弾け飛んだ。
「彼女だって頑張ってるだろ! 大丈夫か?」
「大丈夫?」という言葉もまた、虹色の泡となって陽菜の肩に届く前に消滅した。僕の言葉は、何の力も持たなかった。無力感が全身を貫く。悪意に満ちたガラスの破片は、僕の空虚なシャボン玉を嘲笑うかのように、降り続けた。
クラスメイトたちは僕を睨みつけ、つまらなそうに舌打ちをすると、その場を去っていった。
静寂が戻った廊下で、僕は陽菜に駆け寄ろうとした。だが、その時だった。顔を上げた彼女の表情を見て、僕は凍りついた。
彼女は、泣いていなかった。その瞳は驚くほど穏やかで、床に散らばるガラスの破片を、まるで他人事のように静かに見つめている。そして、彼女は僕に向かって、小さく、しかしはっきりとした声で言った。
「ありがとう、蒼井くん。でもね、本当に怖いのは、誰かからの言葉じゃないの」
読者の予想を裏切る瞬間だった。僕は、彼女が心無い言葉に傷つけられているのだと、固く信じていた。しかし、彼女はゆっくりと自分の胸を指差した。
「本当に重くて、私を縛っているのは……私が、私自身に言い聞かせている『言葉』なんだ」
そう言って彼女が足元に視線を落とす。僕は、その光景に息を呑んだ。
彼女の足元には、数え切れないほどの言葉が、まるで鉛でできた鎖のように絡みついていたのだ。『大丈夫』『平気』『私が我慢すればいい』『期待に応えなきゃ』『完璧でいなきゃ』。一つ一つが、鈍い光を放ち、彼女の足首に食い込んでいる。それは他人の言葉ではない。彼女自身が、自分を鼓舞し、追い詰めるために生み出し続けた、自己犠牲の言葉の数々だった。
美術室で見たあの黒曜石の『助けて』は、誰かに向けられたものではなかった。この鉛の鎖にがんじがらめにされた、彼女自身の心が発した、誰にも届かない悲鳴だったのだ。
第四章 きみの名前を呼ぶ、ということ
陽菜の告白は、僕の世界を根底から覆した。言葉は、他者を傷つけるだけではない。時には自分自身を縛り付け、心を殺していく最も重い足枷にもなるのだ。僕はこれまで、言葉の持つ外向きの力ばかりを恐れていた。しかし、本当の毒は、内側でこそ育つのかもしれない。
彼女を縛る鉛の鎖。それを断ち切れるのは、上辺だけの軽いシャボン玉ではない。僕はずっとポケットの中で握りしめていた、あの黒曜石の冷たさと重さを、改めて感じていた。彼女の悲しみの結晶。僕がずっと持っていた、彼女の心のかけら。
僕は、深く、深く息を吸った。
僕に何ができるだろう。大それたことは言えない。気の利いた慰めも思いつかない。でも、ただ一つだけ、今、僕が紡がなければならない言葉があった。
それは、僕の全ての想い。彼女の笑顔が好きだという気持ち。彼女の苦しみに気づけなかった後悔。それでも、彼女のそばにいたいという切実な願い。その全てを、たった一つの言葉に込める。
言葉職人の老人が言っていた。「覚悟」と「純度」。
僕は、覚悟を決めた。僕の言葉で、彼女がどう思うかなんて考えない。ただ、僕の心を、ありのままの形で届ける。
「陽菜」
僕の唇から、その音が滑り落ちた。
それは、シャボン玉でも、石ころでもなかった。
僕の目の前に現れたのは、暖かな光を内包した、小さな琥珀の塊だった。それは僕が初めて生み出した、確かな質量と温度を持つ言葉。僕の心そのものだった。
琥珀の「陽菜」は、ゆっくりと、しかし真っ直ぐに彼女の元へ飛んでいく。そして、彼女の足元に絡みついた鉛の鎖に、ことんと触れた。
その瞬間、金属が砕けるような甲高い音が響き渡った。陽菜の足枷となっていた無数の鉛の言葉たちが、一斉にひび割れ、粉々に砕け散っていく。解放された彼女の足元には、ただ夕陽の光だけが優しく差し込んでいた。
陽菜の大きな瞳から、ぽろぽろと涙が溢れ出した。それは、美術室で見た嗚咽とは違う。全ての我慢から解き放たれた、初めて見る本当の涙だった。
僕たちの青春は、たぶん、その瞬間から始まった。
数日後、僕たちは並んで夕暮れの帰り道を歩いていた。まだ、多くの言葉を交わすわけじゃない。でも、僕が時々紡ぐ言葉は、もうシャボン玉ではなかった。彼女が好きだと言っていた映画の話をすれば、小さな真珠が生まれ、彼女が笑えば、僕の口からも温かい光の粒がこぼれた。
僕たちの間には、琥珀や真珠のような、ささやかだけれど確かな重みを持った言葉たちが、静かに生まれては宙を舞っている。言葉と共に生きていくのは、きっとこれからも難しいだろう。人を傷つけ、自分を縛ることもある。それでも、たった一つの言葉が、誰かの心を救えることもあるのだと、僕は知っている。
ポケットの中は、もう空っぽだった。あの黒曜石の重さの代わりに、今は彼女の名前を呼んだ時の、琥珀の温かい感触が、僕の胸にいつまでも残っていた。