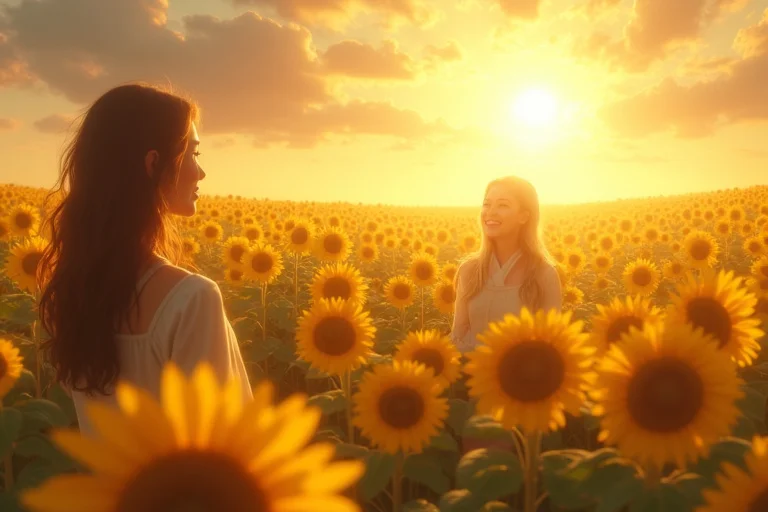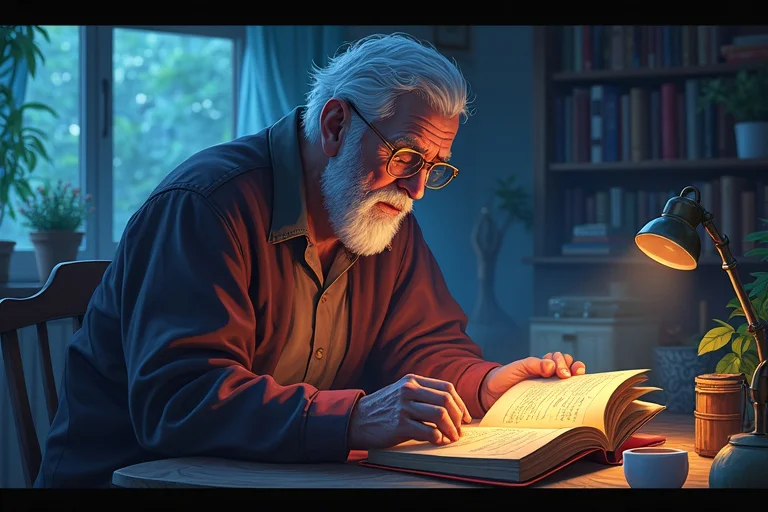第一章 死者のエコー
桐谷響(きりたに ひびき)の仕事は、死者の声を聴くことだった。もちろん、オカルトや霊能力の類ではない。彼は遺品整理士として、故人の持ち物に触れた瞬間、そのモノに込められた「最後の言葉」を知覚する、という奇妙な才能を持っていた。
「……桐谷さん、何か聞こえましたか?」
西陽が差し込む古びた和室で、老婆が皺だらけの手を組み合わせ、祈るように響を見つめていた。響の手の中には、ずしりと重い銀の懐中時計がある。一週間前に亡くなった、老婆の夫の愛用品だ。響は目を閉じ、意識を集中させる。冷たい金属の感触と共に、掠れた声が脳内に直接響いてくる。それは言葉というより、強い想いの残響――響はそれを「エコー」と呼んでいた。
『……君の、味噌汁が、もう一度……』
穏やかで、少し照れたような、優しいエコーだった。響はゆっくりと目を開け、老婆に告げた。
「ご主人は、『君の味噌汁が、もう一度飲みたかった』と。そう仰っています」
その言葉を聞いた瞬間、老婆の目から大粒の涙が溢れ落ちた。
「あんなにしょっぱいって、文句ばっかり言ってたのに……あの人は、本当に……」
嗚咽を漏らす老婆を前にしても、響の心は凪いだままだった。彼はこの能力を、感傷を排した単なるツールとして扱っている。死者の最後の未練を拾い上げ、遺族に届ける。それは時に感謝され、時に気味悪がられたが、響にとっては他の誰にもできない、確かな仕事だった。
人の強い感情は、ひどく消耗する。愛も、憎しみも、後悔も、生の最後の瞬間に凝縮された想いは、刃物のように鋭く、響の精神を削った。だから彼は、心を閉ざした。聞こえてくるエコーに共感せず、ただの音として翻訳する。そうやって、自分を守ってきた。
その日の仕事を終え、アパートに戻ると、留守番電話のランプが点滅していた。無機質な電子音に続いて聞こえてきたのは、遠い親戚からの事務的な声だった。
「……桐谷奏佑(そうすけ)さんが、昨夜、心不全で亡くなりました。つきましては、ご子息である響さんに、ご遺品の整理を……」
その名を聞いた瞬間、響の周りの空気が凍りついた。奏佑。十数年間、まともに口も聞いていない父親の名前。かつて将来を嘱望されたチェリストであり、そして、響の人生に最も暗い影を落とした男。
電話の向こうで、親戚が何かを続けていたが、彼の耳には届かなかった。胸の奥で、ずっと蓋をしていた冷たい感情が、軋みを上げて動き出す。父が、死んだ。その事実が、何の感興も、悲しみすらも、彼の心にもたらさないことに、響は鈍い痛みを感じていた。
第二章 沈黙の家
父が一人で暮らしていた家は、響が幼い頃に過ごした記憶のまま、時が止まったように静まり返っていた。埃の匂いと、古い木の匂い、そして微かに松脂の香りが混じり合った空気が、訪れる者を拒むように淀んでいる。響は誰に許可を得るでもなく、合鍵を使って中に入った。
リビング、書斎、寝室。どの部屋も、父という人間の不在を雄弁に物語っていた。読みかけの本、飲みかけのコーヒーカップ、無造作に置かれた楽譜。まるで、ついさっきまで彼がそこにいたかのような生々しさが、かえって響の心をざわつかせた。
響は、父との確執を思い出していた。幼い頃、響はピアノに類稀な才能を見せた。どんな難曲も一度聞けば弾きこなし、コンクールでは常に一番だった。しかし、父は一度として響を褒めなかった。それどころか、彼の演奏を聴くたびに、苦虫を噛み潰したような顔でこう言った。
「お前の音には、魂がない。ただ指が動いているだけだ」
その冷たい言葉が、どれだけ幼い響の心を抉ったことか。やがて響はピアノに触れるのをやめ、父との会話もなくなった。音楽を捨て、家を出た。それが、響と父の最後の記憶だった。
「魂、か……」
響は自嘲気味に呟きながら、遺品整理に取り掛かった。父の愛用していた万年筆、眼鏡、チェロの弓。響は一つ一つ手に取ってみたが、何も聞こえてこなかった。何の「エコー」も響いてこない。
(あの人には、言い残すことなんて何もなかったのか。俺に対してはもちろん、誰に対しても……)
虚しさが募る。あれほど強烈な自我を持っていた男が、何の想いも残さずに消えてしまうものだろうか。まるで、父の人生そのものが空っぽだったと告げられているようで、奇妙な苛立ちが響を襲った。
リビングの隅に、古びたチェロケースが立てかけてあった。父の分身とも言える楽器だ。響は、これに触れることに僅かな躊躇いを覚えた。だが、意を決して革の取っ手を握る。
しかし、やはり何も聞こえない。沈黙だけがそこにあった。響はケースの留め金を外し、蓋を開ける。
中は、空っぽだった。
赤いビロードの型押しだけが、そこに楽器があったことを示している。父の魂とも言えるチェロは、どこにもなかった。そのがらんどうの空間は、響と父の関係そのものを象徴しているように思えた。
第三章 偽りの遺言
諦めかけた響が、最後に足を踏み入れたのは、一番奥にある書斎だった。壁一面の本棚と、中央に置かれた重厚なデスク。父が最も長く時間を過ごした場所だ。デスクの上を何気なく整理していると、引き出しの奥から一本の古びた万年筆が転がり出てきた。父が若い頃に使っていた、深い青色の万年筆。響が子供の頃、それで楽譜を書いていた姿をぼんやりと覚えている。
それを手に取った、瞬間だった。
『……あの子の指から、神様の音がする。私が、失ってしまった音が……』
雷に打たれたような衝撃が、響の全身を貫いた。それは間違いなく、若い頃の父の声だった。だが、響が知っている父の声とは違う。そこには、嫉妬と、驚嘆と、そして深い絶望が滲んでいた。
「最後の言葉じゃ、ない……?」
響の能力は、死の間際の想いを拾うもののはずだった。だが、今聞こえたのは、明らかに何十年も前の想いのエコーだ。
混乱した響は、書斎にある他の遺品に次々と触れていった。ベートーヴェンの弦楽四重奏曲の楽譜。ページが擦り切れるほど読み込まれている。
『なぜだ。なぜ、私にはもう、あんなふうに奏でられない……!』
それは、響が生まれる前の、ソロリサイタルに失敗した後の父の苦悩の叫びだった。
次に触れたのは、テーブルの隅に置かれたコーヒーカップ。響が家を出る数年前に、母が買ってきたものだ。
『響、すまない。お前の才能が、眩しすぎたんだ……』
憎しみではなかった。それは、自分の才能の枯渇を嘆き、息子の輝かしい未来を妬む、惨めで、しかしあまりにも人間的な父親の慟哭だった。
響は、その場に崩れ落ちそうになった。自分の能力を、ずっと誤解していたのだ。これは、死者の「最後の言葉」を聞く能力などではない。そのモノに込められた、持ち主の「最も強い想い」を聞く能力だったのだ。父の遺品が今まで沈黙していたのは、日常の中にあったモノには、一つの強烈な想いが宿るほどの出来事がなかったからだ。だが、父の人生の節目に共にあったモノたちは、その時の彼の魂の叫びを、今もなお響かせ続けていた。
父は、響を憎んでいたのではなかった。彼の才能を誰よりも認め、それゆえに苦しんでいた。自分の夢を息子が代わりに叶えてくれることへの期待と、自分が失ったものを息子が容易く手に入れていることへの嫉妬。その二つの巨大な感情の狭間で、彼は歪んだ形でしか息子に接することができなかったのだ。
「魂がない」という言葉は、響に向けられたものではなかった。それは、音楽の神に見放されたと絶望した、父自身の心の叫びだったのだ。
響は涙も出ないまま、部屋を見渡した。そして、本棚の隅に、まるで隠すように置かれた一つのカセットテープを見つけた。ラベルには、震えるような文字で『天使の指』とだけ書かれている。
響は近くにあった古いラジカセにテープを入れ、再生ボタンを押した。
ノイズ混じりの音と共に聞こえてきたのは、拙いピアノの音だった。つっかえながらも、必死に弾いている。それは紛れもなく、五歳か六歳の頃の自分の演奏だった。そして、そのピアノの音に重なるように、微かな音が聞こえる。息を殺して、何かを堪えるような音。それは、父の嗚咽だった。静かに、ただ静かに涙をすする、男の泣き声だった。
響は震える手で、再生中のテープに触れた。熱い奔流のように、父の想いが流れ込んでくる。
『この音を、守りたい。どうか、この子を私のようにしないでくれ。音楽の魔物に、魂を食い尽くされるような人生を送らせたくない……』
第四章 父のレクイエム
全ての誤解が解けた時、響の胸を満たしたのは、怒りでも悲しみでもなく、途方もないほどの愛おしさだった。父は、不器用な愛情で自分を守ろうとしていたのだ。音楽の世界の栄光と残酷さを誰よりも知っていたからこそ、息子が同じ道に進み、傷つくことを恐れた。自分の才能に絶望したからこそ、息子の才能が世間の評価という濁流に呑まれることを怖れた。
「魂がない」という呪いの言葉は、響を音楽から遠ざけるための、父なりの歪んだ防波堤だったのだ。
響は、ゆっくりとリビングに戻った。そこには、埃をかぶったアップライトピアノが静かに佇んでいた。何年も開けられることのなかった、重い蓋。響はそっとそれを持ち上げた。白と黒の鍵盤が、月明かりを浴びて鈍く光っている。
響は椅子に腰かけ、鍵盤に指を置いた。
その瞬間、ピアノそのものから、父の最後の、そして最も純粋な想いが聞こえてきた。
『響、お前の音だけが、私の光だった』
一筋の涙が、響の頬を伝った。
彼は目を閉じ、静かに鍵盤を弾き始めた。それは、かつて父が愛し、そして弾けなくなったバッハの無伴奏チェロ組曲を、響自身がピアノ用に編曲したメロディだった。
もう、「魂がない」とは言わせない。
一音一音に、父への赦しを込めて。父の苦悩と、孤独と、そして不器用な愛情の全てを受け止めて。響の指から紡ぎ出される音は、ただの技術の羅列ではなかった。それは、父と息子の数十年にわたる断絶と和解を物語る、鎮魂歌(レクイエム)だった。
その音は、誰もいない静まり返った家に、そしておそらくは、天国で耳を澄ませているであろう父親の魂に届くかのように、どこまでも優しく、そして力強く響き渡った。
数週間後、響は再び遺品整理の現場に立っていた。しかし、彼の表情は以前とは全く違っていた。冷めた諦観は消え、そこには静かで、深い優しさが宿っている。
彼はもう、モノから聞こえる声を「エコー」とは呼ばない。それは、遺された人々の心を繋ぐための、「想いの旋律」なのだと知ったからだ。
響は、モノの声に耳を澄ませる。彼はもう、単なる遺品整理士ではない。彼は、言葉にならない想いを翻訳し、心を繋ぐ旋律を調律する、「ラスト・ワーズの調律師」なのだ。彼の指先が、また一つ、新たな物語を紡ぎ出そうとしていた。