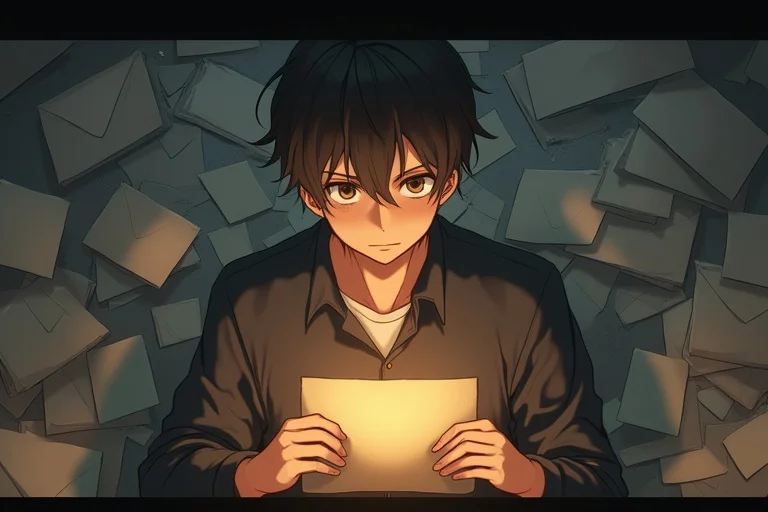第一章 泥の味の「ありがとう」
僕、橘響(たちばなひびき)には秘密がある。僕は、言葉に「味」や「手触り」を感じる。共感覚と呼ばれるものらしいが、僕の場合は少し、いや、かなり歪んでいた。例えば、街角で交わされる「愛してる」という囁きは、舌の上に腐った卵の味が広がり、「おめでとう」という祝福は、乾いたヘドロを素手で掴むような不快な感触を僕にもたらす。
美しい言葉ほど、醜悪な感覚を伴う。中でも最悪なのが、「ありがとう」という感謝の言葉だ。それは決まって、冷たい泥の味と、喉の奥にこびりつく砂の感触を連れてくる。純粋な善意から発せられたものであっても、だ。だから僕は、人との関わりを極力避けて生きてきた。感情の機微が生まれる場所から、できるだけ遠くへ。
僕の仕事は、古書の修復師。古い紙の乾いた匂い、ひび割れた革表紙の滑らかな手触り、インクのかすかな香り。言葉が化石になったその世界は、僕にとって唯一の安息の地だった。無機質で、静かで、誰も僕に不快な味の「ありがとう」を言わない。
その日も、僕は工房の窓から差し込む午後の光の中で、18世紀の植物図鑑の修復に没頭していた。ピンセットで脆くなったページをそっと持ち上げる。その静寂を破ったのは、ドアベルの澄んだ音だった。
ドアを開けると、そこに立っていたのは、肩まで伸びた黒髪と、大きな瞳を持つ少女だった。歳は10歳くらいだろうか。その瞳は、まるで深い森の泉のように静かで、僕の歪んだ感覚を刺激するどんな感情の揺らめきも映していなかった。
少女は何も言わず、ただ、大切そうに抱えていた一冊の絵本を僕に差し出した。それは、表紙も擦り切れ、ページはところどころ破れて、見るも無惨な状態だった。彼女は僕の目をじっと見つめる。その瞳が「これをお願いします」と、音もなく語りかけていた。
言葉を発しない彼女に、僕は奇妙な安堵を覚えていた。この少女との間には、あの泥の味がする言葉は介在しないだろう。僕は黙って頷き、そのボロボロの絵本を受け取った。その瞬間、少女の唇の端が、ほんのわずかに綻んだ気がした。
第二章 沈黙の対話と絵本の謎
翌日から、少女――陽菜(ひな)と名乗るようになった。筆談で教えてくれたのだ――は毎日、学校が終わると僕の工房へやってくるようになった。彼女は決して喋らない。ただ、工房の隅にある古い木製のスツールにちょこんと座り、僕が絵本を修復する様子を瞬きもせずに見つめているのだ。
僕は黙々と作業を進めた。破れたページを和紙で丁寧に補強し、外れた背表紙を特殊な糊で接着していく。カッターが紙を切る乾いた音、刷毛が糊を伸ばす微かな摩擦音、そして陽菜の静かな呼吸だけが、午後の工房に満ちていた。
言葉を交わさない陽菜との時間は、不思議と心地よかった。僕の感覚を乱すものは何もない。しかし、時折、僕が上手くページを繋ぎ合わせると、彼女は小さく息を呑み、その瞳をキラキラと輝かせた。その純粋な喜びの気配は、僕の舌の上に、微かな砂の感触の「予兆」をもたらした。僕はそのたびに、無意識に奥歯を噛み締めていた。
修復が進むにつれて、絵本の物語が少しずつ姿を現してきた。それは、生まれつき声を失った一羽の小鳥の物語だった。森の仲間たちが美しい声で歌い交わす中、小鳥だけが歌えない。悲しみに暮れる小鳥だったが、ある日、風の音、木の葉のざわめき、川のせせらぎに耳を澄ますことで、自分だけの「心の歌」を見つけ出す。声には出せないけれど、その歌は仲間たちの心に確かに届き、森全体を優しく包み込む、という話だった。
僕は、その歌えない小鳥に、言葉を避けて生きる自分を重ね合わせずにはいられなかった。僕にとっての安息は、この静かな工房だ。だが、この小鳥は、沈黙の中で世界と繋がる方法を見つけ出した。僕と、何が違うのだろう。
作業は順調に進み、残すは物語の結末が描かれた、最後の見開きのページだけとなった。しかし、その肝心のページが、どこにも見当たらないのだ。陽菜が持ってきた時点で、それは失われていた。物語は、小鳥が「心の歌」を見つけ出したところで、唐突に終わってしまっている。
「陽菜ちゃん、最後のページはないんだ。これ以上は…」
僕が筆談用のメモ帳にそう書くと、陽菜はふるふると首を横に振った。そして、初めて僕の前で焦ったような素振りを見せ、おぼつかない手つきで、必死に何かを伝えようとし始めた。それは、僕の知らない、指の言葉――手話だった。
第三章 言葉が生まれる前の光
陽菜の小さな手は、空中で複雑な軌跡を描いた。焦りと、懇願と、そして何か深い悲しみが、その動きから滲み出ていた。僕にはその意味が全く分からなかったが、彼女が伝えたいことの重さだけは、痛いほど伝わってきた。
やがて彼女は諦めたように手を下ろすと、僕の作業着の袖をくい、と引いた。そして、工房の外を指差す。ついてきて、と、その大きな瞳が訴えていた。僕は、まるで魔法にかけられたように、彼女の後をついて歩き始めた。
陽菜に導かれてたどり着いたのは、街外れにある古い総合病院だった。消毒液の匂いが鼻をつく、静かな廊下を抜け、ある病室の前で彼女は立ち止まる。ドアには「五十嵐」というプレートが掛かっていた。
彼女は僕を振り返り、一度だけ深く頷くと、静かにドアを開けた。
病室のベッドには、一人の女性が眠っていた。陽菜によく似た、穏やかな顔立ちの女性。おそらく彼女の母親だろう。部屋は簡素だったが、壁の一箇所だけが、たくさんの写真や子供の絵で彩られていた。その中心に、一枚の絵が、まるで宝物のように大切に飾られていた。
僕は息を呑んだ。それは、あの絵本の失われた最後のページだった。
そこには、声の出ない小鳥が、歌う代わりに、その全身から七色の光を放っている姿が描かれていた。その光は、森の木々を、花々を、仲間たちを優しく照らし、世界全体が祝福に満ちている。言葉ではない、けれど、何よりも雄弁な「歌」がそこにはあった。
陽菜は、僕が持ってきた修復済みの絵本を受け取ると、眠る母親の手にそっと握らせた。そして、僕の方に向き直ると、小さなスケッチブックを取り出し、たどたどしい文字を書き始めた。
『ママは、わたしのこえが、きこえないの。じこで。ことばも、むずかしいの』
僕は、頭を殴られたような衝撃を受けた。陽菜が話さないのは、話せないからではなかった。声が聞こえない母親に、自分の言葉が届かないと知っているから。そして、おそらくは事故のショックで、彼女自身も声を出すことができなくなってしまったのだろう。
この絵本は、声も言葉も超えて、想いを伝えるための唯一の希望だったのだ。
陽菜は、僕に向かって、深く、深く、頭を下げた。そこに言葉はなかった。ただ、純粋な、混じり気のない感謝の「想い」そのものが、凝縮された塊となって、静かな病室の空気を震わせた。
その瞬間、僕の世界は反転した。
予期していた泥の味も、砂の感触も、どこにもなかった。代わりに僕の全身を包んだのは、生まれて初めて感じる感覚だった。
それは、真綿のように柔らかく、温かい陽だまりのような匂い。舌の上で溶ける、上質な蜂蜜のかすかな甘み。そして、頬を撫でる春風のような、優しい手触り。
言葉を介さない、人間の感情の原石。それは、こんなにも美しく、感動的なものだったのか。
僕が今まで味わってきた不快な感覚は、「言葉」という器に盛り付けられる過程で混入した、嘘や見栄や打算の味だったのかもしれない。だが、今ここにあるのは、陽菜という少女の心から溢れ出た、純度100パーセントの「ありがとう」の光そのものだった。
涙が、僕の頬を静かに伝っていった。
第四章 雨上がりの土の匂い
あの日以来、僕の世界は少しだけ色を変えた。相変わらず、街で交わされる上辺だけの言葉は、不快な味と感触を伴った。しかし、僕はもうそれを呪いだとは思わなかった。それは世界の真実の一面に過ぎず、その奥には、陽菜が見せてくれたような、光り輝く感情の原石が眠っていることを知ったからだ。
数週間後のある晴れた午後、工房の窓をコンコン、と叩く音がした。見ると、陽菜が少し照れくさそうに立っていた。僕は窓を開け、彼女を中に招き入れる。
彼女は僕の前に立つと、何かを決心したように、小さな口を数回、開け閉めした。そして、掠れた、か細い、それでも確かな声で、こう言った。
「……あり、がと」
僕は、反射的に身構えた。泥の味が来る。そう覚悟した。
しかし、僕の感覚に訪れたのは、あの忌まわしい泥の味ではなかった。
それは、少しざらりとしていた。だが不快ではない。むしろ、雨が降った後の、湿った土の匂い。生命の息吹を感じさせる、どこか懐かしくて、優しい匂いだった。そして舌の上には、ほんの少しだけ、土の味がした。完璧に甘美な蜜の味ではない、不器用で、それでも懸命に芽吹こうとする若葉のような、ささやかな温もりがあった。
陽菜の、絞り出した「ありがとう」。それは、完璧に精製された感情ではなかった。そこには、彼女の戸惑いや、緊張や、声を取り戻すことへの怖れも混じっていたのだろう。だが、それら全てをひっくるめて、彼女の「本当の言葉」だった。
僕は、その不完全で、だからこそ愛おしい「感触」を、全身で受け止めていた。
そして気づけば、僕は笑っていた。心の底から、何のためらいもなく、微笑んでいた。
陽菜は驚いたように目を丸くし、それから、つられるようにして、はにかんだ笑顔を見せた。その笑顔は、僕にとって、どんな言葉よりも雄弁な、春の陽だまりの味がした。
僕はこれからも、この奇妙な感覚と共に生きていく。きっと、腐った卵の味の「愛してる」に顔をしかめ、ヘドロの手触りの「おめでとう」に辟易することも続くだろう。だが、もう絶望はしない。世界のどこかには、そして僕のすぐそばにも、雨上がりの土の匂いがする「ありがとう」が、確かに存在することを知ったのだから。僕はただ、その一瞬の感動を探して、この世界と向き合っていけばいい。