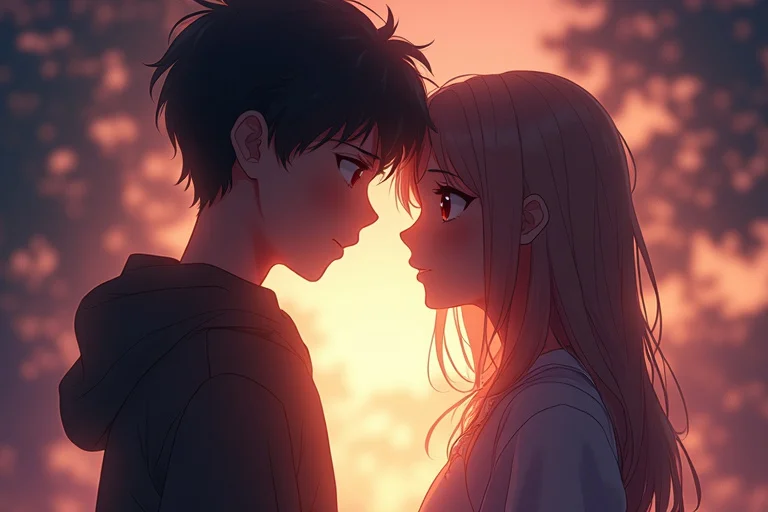第一章 虹色の嘘
埃っぽい放課後の教室は、西陽に照らされて、あらゆるものの輪郭を曖昧に溶かしていた。机の傷、チョークの粉が舞う空気、友人の気怠げな横顔。俺、相田航(あいだわたる)は、そんなありふれた風景の一部として、息を潜めるように存在していた。将来の夢なんて、まだ靄のかかった遠い山のようだ。周りが「大学はどこそこ」「将来はIT系」などと騒ぐ中、俺だけが取り残されたような焦燥感に駆られていた。
「で、航はどうなんだよ? なんか考えてんの?」
話題の矛先が、突然俺に向いた。クラスの中心グループの一人、高木がニヤニヤしながら問いかける。その視線には、どうせお前なんかに大した夢はないだろう、という侮りが透けて見えた。カッと頭に血が上る。ここで「特にない」なんて言えば、この教室での俺の序列は、さらに底辺へと沈んでいくだけだ。
喉まで出かかった弱音を飲み込み、俺はほとんど無意識に、禁じられた扉を開けていた。
「あ、ああ……。実は、ちょっとだけな。写真、やってて。最近、プロのカメラマンにスカウトされたんだ」
シン、と教室が静まり返る。数秒の沈黙の後、爆発的な驚きの声が上がった。
「マジで!?」「すげえじゃん、相田!」「どこの誰だよ、そのカメラマン!」
質問の嵐に、俺は冷や汗をかきながら、雑誌で偶然見かけた著名な写真家の名前を口にした。俺の言葉が、現実を侵食していく。俺のついた嘘は、いつだって本当になるのだから。
この奇妙な能力に気づいたのは小学生の頃だ。「明日は絶対に晴れる」と母に嘘ぶけば、翌日は土砂降りの予報を覆して快晴になった。「テストで百点をとった」と見栄を張れば、答案用紙の数字がひとりでに書き換わっていた。便利に思えるこの力には、しかし、致命的な欠陥があった。それは、ディテールをコントロールできないことだ。嘘がどんな形で現実になるのか、俺にも予測できない。かつて「宝くじが当たる」と嘘をついたら、当選番号は合っていたものの、そのくじをなくしてしまった、なんてこともあった。以来、俺はこの力を恐れ、極力使わないように封印してきたのだ。
だが、今、封印は破られた。翌日、俺の下駄箱には一通の封筒が入っていた。差出人は、俺が昨日口にしたばかりの写真家、篠宮ユキヒロ。中には、彼の個展の招待状と、「君の才能に興味がある。今度開催される若手コンテストに、ぜひ作品を出してみてくれないか」という直筆のメッセージが添えられていた。
嘘が、現実を歪めてしまった。俺は、生まれてこの方、スマートフォンのカメラ以外で写真を撮ったことなんて、一度もないというのに。
クラスでの俺の扱いは、一日で劇的に変わった。誰もが俺を「才能ある写真家の卵」として見るようになった。そして、何よりの変化は、月島汐里(つきしましおり)が俺に話しかけてくれるようになったことだった。
「相田くん、すごいね。篠宮さんに認められるなんて」
放課後、一人でカメラ雑誌をめくっている俺に、彼女は柔らかな声で言った。夕陽が彼女の髪を琥珀色に染め、その微笑みは俺の心臓を不規則に跳ねさせた。美術部に所属する彼女は、クラスの誰からも好かれる、手の届かない存在。そんな彼女が、俺のすぐ隣にいる。
「い、いや、そんなことないよ。まぐれだから」
「謙遜しなくてもいいのに。……私、写真見るの好きなんだ。今度、相田くんの作品、見せてもらってもいいかな?」
嘘が生んだ偽りの栄光。その甘美な響きに、俺は溺れていた。本当のことなど言えるはずもなく、ただ曖昧に頷くことしかできなかった。コンテストという、逃れられない締め切りが迫っていることにも、気づかないふりをしながら。
第二章 ファインダー越しの真実
俺は生まれて初めて、なけなしの小遣いをはたいて中古の一眼レフカメラを買った。ずしりと重い金属の塊は、俺のついた嘘の重さそのものだった。説明書を読んでも専門用語が頭に入ってこない。シャッタースピード、絞り、ISO感度。まるで未知の言語だ。それでも、俺は必死だった。汐里の期待を裏切りたくない、その一心だけで、錆びついた頭を無理やり回転させた。
放課後、俺はカメラを首から下げて、誰もいない屋上や、光が差し込む渡り廊下、夕暮れのグラウンドを彷徨った。ファインダーを覗くと、見慣れたはずの風景が四角く切り取られ、特別なものに見えるから不思議だった。だが、シャッターを切っても、そこに写るのは凡庸な現実の断片ばかり。俺の写真には、魂がこもっていなかった。
「航くん、最近ずっとカメラと一緒だね」
ある日の帰り道、汐里が俺の隣に並んで歩きながら言った。「航くん」という響きに、また心臓が跳ねる。
「うん、まあ……。コンテストが近いから」
「無理しないでね。でも、何かに夢中になってる航くん、すごくキラキラして見えるよ」
彼女の言葉は、乾いた心に染み渡る水のように優しかった。俺たちは並んで、茜色に染まる河川敷を歩いた。汐里は時々立ち止まっては、スケッチブックを取り出して、風景を素早く写し取っていく。
「見ても、いい?」
俺が尋ねると、彼女は少し恥ずかしそうに頷いて、スケッチブックを開いて見せてくれた。そこに広がっていたのは、驚くほど色彩豊かな世界だった。燃えるような夕焼け、深い緑の木々、淡い紫色の紫陽花。鉛筆の線画に、水彩絵の具で命が吹き込まれている。
「すごいな……。月島さんの絵は、色が生きているみたいだ」
「ありがとう。……私、いつか自分の絵で、たくさんの人を感動させるのが夢なんだ」
夢を語る彼女の横顔は、真剣で、ひたむきで、目が眩むほど美しかった。嘘で塗り固められた自分が、ひどくちっぽけで、惨めに思えた。このまま能力に頼って、一夜漬けの才能でコンテストを乗り切るべきか。それとも、すべてを打ち明けるべきか。答えの出ない問いが、頭の中をぐるぐると巡る。
だが、俺は気づき始めていた。最近、世界の彩度が、ほんの少しだけ落ちていることに。目に鮮やかだったはずの信号機の赤が、どこか朱色がかっている。夏の空の突き抜けるような青が、薄い膜を一枚隔てたように、くすんで見える。最初は気のせいだと思っていた。しかし、その違和感は日に日に増していき、俺の心に不穏な影を落としていた。
コンテストまで、あと三日。俺はついに、最後の嘘をつく覚悟を決めた。「俺の撮った写真が、コンテストでグランプリを獲る」。そう呟けば、すべては解決するはずだ。偽りの自分を、本物にしてしまえばいい。俺は震える唇を、ゆっくりと開こうとした。その時だった。
「航くん、明日、話したいことがあるの」
スマートフォンの画面に表示された汐里からのメッセージ。その短い文面に、俺はなぜか、言いようのない胸騒ぎを覚えた。
第三章 モノクロームの告白
翌日の放課後、俺たちは美術準備室で向かい合っていた。絵の具と油の匂いが混じり合った、静かな空間。窓から差し込む光が、床に長い縞模様を描いている。汐里は、いつもよりずっと緊張した面持ちで、一枚の古い写真立てをテーブルの上に置いた。
「これ、見てくれる?」
写真には、俺よりも少し年上に見える、快活そうな青年が写っていた。彼の隣には、まだ幼い汐里がはにかむように笑っている。
「お兄ちゃん。写真家になるのが夢だったんだ」
彼女の声は、微かに震えていた。
「でも、三年前、事故で……。この写真は、お兄ちゃんが最後に撮った一枚なの」
写真に写っているのは、ありふれた海辺の風景だった。しかし、構図も、光の捉え方も、素人の俺が見ても息を呑むほどに完璧だった。そして何より、その写真からは、潮の香りや、波の音、肌を撫でる風の温かさまでが伝わってくるようだった。
「私ね」と汐里は続けた。彼女は一度、深く息を吸い込むと、真っ直ぐに俺の目を見て、衝撃的な言葉を口にした。
「私、世界の色が、見えないの」
時間が、止まった。彼女が何を言っているのか、すぐには理解できなかった。
「先天性の、色覚特性で……。私の世界は、ずっと白と黒と、その間の灰色だけでできてる。絵を描くときの色はね、全部お兄ちゃんが教えてくれた色の名前と、本で読んだ知識を頼りに、想像で塗ってるんだ」
俺は言葉を失った。あれほど鮮やかで、生命力に満ちていた彼女の絵が、色のない世界で生まれたものだとは、信じがたかった。
「お兄ちゃんは、いつも私に、世界がどれだけ美しい色で溢れているかを話してくれた。夕焼けのオレンジ、新緑の黄緑、紫陽花の青……。だから、私もいつか、自分の目でその色を見てみたいって、ずっと思ってた」
彼女は俺の手を取り、そっと自分の胸に当てた。
「航くんがスカウトされたって聞いた時、すごく驚いた。しかも、あの篠宮ユキヒロさんに。篠宮さんは、お兄ちゃんが一番尊敬していた写真家だったから。それで、航くんの写真を見たら、なんだか、お兄ちゃんが撮る写真と同じ匂いがしたの。すごく……温かい色が、そこにある気がした」
その瞬間、雷に打たれたような衝撃が俺の全身を貫いた。
点と点が繋がり、恐ろしい真実が姿を現す。
俺が世界から失いかけていた、色彩。
あれは、気のせいなどではなかった。
俺の能力の「代償」。それは、嘘を現実に変えるたびに、俺自身の世界から「色」が一つ、また一つと奪われていくことだったのだ。汐里が色を失っているのではない。俺の世界が、モノクロームに近づいていたのだ。
もし、俺が「グランプリを獲る」という、これまでで最も強力な嘘をついてしまったら? おそらく俺の世界は、完全に色を失い、汐里と同じモノクロの世界に閉じ込められてしまうだろう。
皮肉なことだ。俺が嘘で手に入れた偽りの才能に、色のない世界を生きる彼女が、誰よりも色彩豊かな希望を見出してくれていたなんて。俺は、彼女の純粋な想いさえも、嘘で汚してしまっていたのだ。
第四章 君がくれた世界の色
コンテスト当日。俺は会場の隅で、一枚の写真を静かに見つめていた。それは昨夜、能力に頼らず、必死で撮った一枚。夜明け前、街がまだ眠りから覚めやらず、光と影の濃淡だけで構成された、モノクロームの世界を写したものだ。俺が今、見ている世界に最も近い風景だった。
結果発表の時が来た。もちろん、俺の名前が呼ばれることはなかった。偽りの栄光は、あっけなく幕を閉じた。周りから聞こえてくる、「なんだ、大したことなかったな」という囁き声が、不思議と痛くなかった。むしろ、重い鎧を脱ぎ捨てたような解放感があった。
会場を出ようとした俺の腕を、誰かが掴んだ。振り返ると、息を切らせた汐里が立っていた。
「航くんの、写真……見たよ」
彼女は、俺が出展したモノクロの写真が載ったパンフレットを握りしめていた。
「この写真、すごく好き。……なんだか、安心する。私が初めて、見たままを描ける世界だから」
彼女は、そう言って柔らかく微笑んだ。その笑顔を見て、俺はもう、嘘をつき続けることはできないと悟った。
俺は、すべてを話した。自分が持っている能力のこと。見栄を張るためについた嘘のこと。そして、その代償として、自分の世界から色が失われつつあることを。
汐里は、黙って俺の話を聞いていた。軽蔑されるだろうか。それとも、気味悪がられるだろうか。だが、彼女の反応は、俺の予想とは全く違うものだった。
「そっか……。大変だったね」
彼女は、ただ静かに、そう言った。その瞳には、憐れみも、驚きもなかった。ただ、深いいたわりの色が浮かんでいるように見えた。
「大丈夫だよ」と彼女は続けた。「これからは、私がお兄ちゃんにしてもらったみたいに、航くんに色の名前を教えてあげる。夕焼けはね、燃えるようなオレンジと、優しいピンクが混ざった色なんだよ。私の絵みたいにね」
その言葉は、俺のモノクロームの世界に差し込んだ、最初の光だった。
俺たちは並んで、夕暮れの道を歩き始めた。世界の色彩は、これからも少しずつ俺の視界から消えていくのかもしれない。空の青も、木々の緑も、いつかは灰色に変わってしまうだろう。
けれど、もう怖くはなかった。
俺の隣には、失われた色を言葉で、心で、鮮やかに描き出してくれる人がいる。虚飾を捨て、ありのままの自分を受け入れた時、俺の本当の青春が始まった。
世界の色彩を失う代わりに、俺はたった一つの、かけがえのない光を見つけたのだ。それは、これから先、どんなに色褪せた世界に生きることになっても、俺の人生を照らし続けるであろう、消えることのない、君という名の光だった。