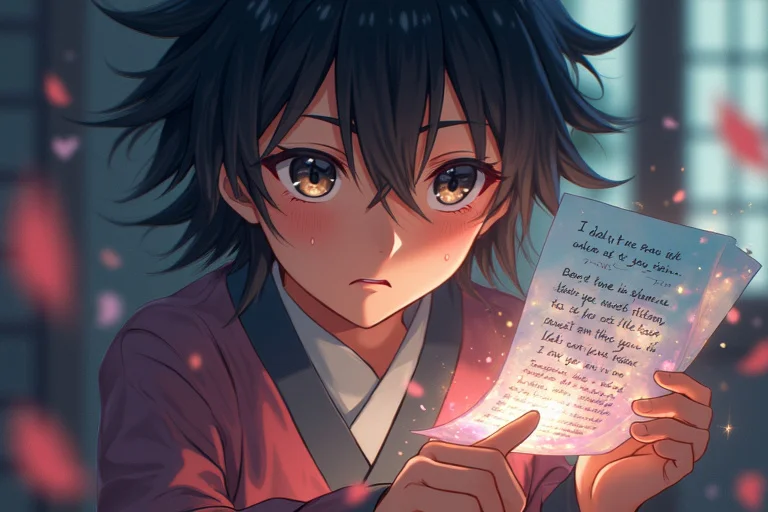第一章 鉄と幻聴
江戸の片隅、神田の鍛冶町に、龍之介の工房はあった。朝日が障子を白く染める頃には、もうもうと立ち上る蒸気と、鋼を打つ甲高い残響が路地に満ちる。父を三年前の流行り病で亡くして以来、龍之介はたった一人でこの「龍泉工房」を守ってきた。まだ二十歳を過ぎたばかりの若者だが、その腕は確かだと評判だった。彼の打つ刀は、父譲りの実直さで、地鉄の肌は潤うように滑らかで、刃文は静かな水面のように澄んでいた。
しかし、ここ半年ほど、龍之介は誰にも言えぬ秘密の苦悩を抱えていた。
それは、刀を打つ、まさにその瞬間に訪れる。精神を研ぎ澄まし、槌を振り下ろす鉄床(かなとこ)のリズムと一体になろうとすると、決まってあの「音」が聞こえてくるのだ。
キィン、という鋼の悲鳴の合間に、それは割り込んでくる。ある時は、けたたましい鐘の音にも似た、しかしもっと甲高く、長く尾を引く金属的な叫び声。またある時は、ぽつ、ぽつ、と規則正しく玻璃を叩くような、冷たく無機質な音。最近では、女の声とも童の声ともつかぬ、不可思議な旋律までが聞こえる始末だった。
それは市場の喧騒でも、隣家の赤子の泣き声でもない。この江戸のどこを探しても、決して存在するはずのない音だった。初めは耳の病かと思った。医者にかかったが、首を傾げられるだけ。次に、物の怪の仕業を疑った。工房の隅に塩を盛り、毎夜のように祈りを捧げたが、幻聴は止むどころか、ますます鮮明になっていく。
「心で鉄の声を聞け。鉄と語らえ。さすれば、おのずと道は開ける」
父の口癖が、槌音と共に脳裏で反響する。だが、今の龍之介には、鉄の声よりも、あの忌まわしい幻聴の方が大きく聞こえてしまうのだった。
そんな折、江戸一番の呉服問屋「越後屋」の主人、徳兵衛が工房を訪れた。破格の手付金と共に彼が差し出したのは、天下の名刀と謳われる「三日月宗近」の写しの製作依頼だった。
「龍之介殿、亡き親方様の腕は江戸随一だった。その血を引くそなたなら、この大任を果たせると信じておる」
徳兵衛の期待に満ちた眼差しが、龍之介の心を重く突き刺す。これは工房の浮沈を賭けた大仕事だ。断る選択肢はない。しかし、この耳で、果たして至高の一振りを打つことができるのだろうか。
龍之介は深々と頭を下げ、依頼を引き受けた。だが彼の心の中では、不安という名の冷たい鉄が、幻聴の槌によって何度も何度も打ち据えられていた。その夜、玉鋼に向き合った彼の耳に、またしても新たな音が響いた。地を這うような低い唸り声と、断続的に鳴り響く、鋭い警告音。まるで、見えざる何かが、彼の正気を嘲笑っているかのようだった。
第二章 聞こえぬ声を探して
三日月宗近の写しに取りかかってから、ひと月が過ぎた。龍之介は工房に籠りきりだったが、仕事は一向に進まなかった。選び抜いた玉鋼を折り返し鍛錬するたび、幻聴は彼の集中を無慈悲に引き裂く。槌筋は乱れ、火加減を見誤り、何度鍛え直しても、鋼は鈍い光を放つばかりで、あの月光のような澄んだ輝きを宿そうとはしなかった。
「なぜだ……なぜ、俺にだけ聞こえるのだ」
打ち損じた鉄塊を前に、龍之介は膝から崩れ落ちた。汗と煤にまみれた顔を上げると、工房の壁に飾られた父の形見の小刀が目に入る。生前、父もまた、時折何か考え込むように、遠くの音に耳を澄ませるような仕草をしていたことを、ふと思い出した。あれは一体、何だったのだろうか。
焦燥感に駆られた龍之介は、気分転換も兼ねて、幻聴の正体を探しに町へ出た。甲高い金属音、規則正しい電子音、不可思議な旋律。それらの音が聞こえた瞬間に辺りを見回すが、人々は何も気づかぬ様子で往来を行き交っている。やはり、自分がおかしくなってしまったのか。孤独感が、じわりと心を蝕んでいく。
藁にもすがる思いで、彼は町外れにある古寺の老僧、玄海を訪ねた。玄海和尚は博識で知られ、人の悩みを聞くことにかけては右に出る者がいないと言われていた。
「ほう、奇妙な音、とな」
龍之介の話を静かに聞いていた玄海は、茶を一口すすると、皺深い目元を細めた。
「龍之介殿。お主の槌音は、魂がこもっておる。それ故、常人には届かぬものが届くのかもしれぬな」
「と、申しますと?」
「音とは、空気を震わせるもの。だが、魂を震わせる音もある。お主が聞くのは、あるいは、まだ生まれぬ『未来(さき)』の世の音やもしれぬぞ」
未来の世の音。あまりに突拍子もない言葉に、龍之介は呆気に取られた。しかし、玄海の揺るぎない瞳に見つめられていると、ただの戯言とは思えなかった。
「未来……」
「恐れることはない。むしろ、その音と向き合ってみることじゃ。それは呪いではなく、天からの授かりものかもしれぬ。鉄の声を聞くのと同じように、その音にも耳を澄ませてみるのじゃ」
玄海の言葉は、暗闇に差し込んだ一筋の光のようだった。幻聴は、振り払うべきものではなく、受け入れるべきものなのかもしれない。龍之介の心に、小さな、しかし確かな変化の兆しが芽生えていた。工房に戻った彼は、深呼吸を一つすると、再び火床に向かった。今度は、逃げずにあの音と対峙するために。
第三章 時を超える槌音
納期が迫る満月の夜、龍之介は最後の鍛錬に臨んでいた。玄海の言葉を胸に、彼は意識の全てを耳に集中させた。逃げない。聞くのだ。鉄の声も、そして、あの幻聴も。
槌を振り下ろし、火花が滝のように舞う。キィン、という鋼の歌声。その瞬間、いつものように幻聴が押し寄せてきた。甲高い警笛、人の声ではない機械的な音声、そして、空を切り裂くような轟音。しかし、龍之介はもはや怯まなかった。彼は目を閉じ、音の奔流にその身を委ねた。
すると、信じられないことが起きた。
音と共に、鮮烈な「映像」が脳裏に流れ込んできたのだ。
鉄の箱(自動車)が、黒い道を驚くべき速さで駆け抜けていく。人々は、手のひらに収まる輝く板(スマートフォン)を覗き込み、笑い、あるいは眉をひそめている。夜空は不夜城のように煌めき、巨大な鉄の鳥(飛行機)が雲を貫いて飛んでいく。見たこともない衣服、聞いたこともない言語、目まぐるしく変化する光と色彩の洪水。
「こ、これは……未来の世……!」
龍之介は槌を落とし、その場に立ち尽くした。幻聴は、時空の壁を越えて響いてくる、数百年後の世界の音だったのだ。自分の苦悩は、狂気の証などではなかった。それは、時を超えて繋がる、稀有な才能の証だった。
全身の力が抜けていくような安堵と、世界が根底から覆るような衝撃に、彼はしばらく動けなかった。そして、はっと気づく。父だ。父もまた、この音を聞いていたに違いない。あの遠くを見つめる目は、未来の光景を見ていたのだ。
龍之介は震える手で、父が遺した古い桐の箱を開けた。中には、刀の設計図が何枚も入っている。そのほとんどは見慣れたものだったが、一枚だけ、奥底にしまい込まれていた図面があった。そこに描かれていたのは、龍之介が知るどんな刀とも違う、異様な姿をしていた。反りは浅く、切っ先は鋭角で、全体が滑らかな流線形を描いている。それはまるで、先ほど脳裏で見た、鉄の鳥の翼を思わせる形だった。
父は、未来の音から着想を得て、この時代の常識を覆すような、全く新しい刀を生み出そうとしていたのだ。「心で鉄の声を聞け」という言葉の真の意味を、龍之介は今、ようやく理解した。父が聞いていたのは、鉄の声であり、同時に、時を超えた未来の声だったのだ。
孤独ではなかった。父も同じ道を歩いていた。涙が、煤けた頬を伝って流れ落ちた。それは、長年の苦悩からの解放と、偉大な父への敬慕が入り混じった、熱い涙だった。
龍之介は顔を上げ、決意の光を目に宿した。彼が打つべきは、名刀の「写し」ではない。未来の音を宿した、この世にただ一つの「真作」なのだ。
第四章 未来を鍛える
夜が明ける頃、龍之介は三日月宗近の写しを打つことをやめた。彼は脇目もふらず、父の遺した謎の設計図と、自らの耳に響く未来の音だけを頼りに、新たな刀を打ち始めた。
彼の工房は、まるで様変わりしたかのようだった。槌音は、もはや迷いや苦悩を含んでいなかった。未来の都市の喧騒、高速で走る乗り物のリズム、電子音楽の旋律。それら全てが、龍之介の槌を導く壮大な交響曲となった。彼の動きは舞うように滑らかで、鋼を打つ音は、まるで歌っているかのように工房に響き渡った。
焼き入れの儀式。赤々と焼かれた刀身が水に浸けられると、ジュッという音と共に白い蒸気が立ち上る。その水面に映った刃文は、伝統的な丁子や互の目ではない。それは、夜空を流れる光の軌跡、あるいは、電子回路を思わせる、複雑で美しい幾何学模様を描いていた。
数日後、完成した一振りを携え、龍之介は越後屋を訪れた。刀を検分した徳兵衛の顔は、みるみるうちに怒りに染まった。
「龍之介殿!これはどういうことだ!儂が頼んだのは三日月宗近の写しのはず。こんな奇妙な形の刀、見たこともないわ!」
無理もなかった。その刀は、優美でありながら、どこか冷徹な機能美を宿していた。伝統的な日本刀の魂を持ちながら、明らかに異質な、未来の空気を纏っている。
「旦那様。恐れながら、申し上げます」
龍之介は静かに、しかし毅然として言った。
「これは、まだ生まれぬ世の音を聞いて打った刀にございます。父が夢見、私が受け継いだ、時代の先を行く一振り。名を、『時響(ときひびき)』と申します」
そして、彼は徳兵衛を庭先に促し、試し斬りを願い出た。徳兵衛が半信半疑で時響を振るうと、刀は空気を切り裂くのではなく、まるで空間そのものを滑るように走り、置かれた竹を一筋の光と共に両断した。その断面は、鏡のように滑らかだった。
徳兵衛は言葉を失い、ただただ刀身に見入っていた。その異質な美しさと、常軌を逸した切れ味に、彼の商人の魂が震えた。これは、歴史に名を残す一振りになるやもしれぬ。
「……見事だ。龍之介殿、儂の負けだ。この『時響』、我が越後屋の家宝とさせてもらう」
龍之介は、父から受け継いだ工房で、今日も一人、槌を振るう。耳には相変わらず、数百年後の未来の音が響いている。だが、それはもはや彼を苛む幻聴ではない。新たな創造を促す、心地よい音楽だ。彼は、過去の伝統と、まだ見ぬ未来を繋ぐ、唯一無二の刀鍛冶となった。
夕暮れの空を見上げると、聞こえるはずのない、ジェット機の甲高い飛行音が澄んだ空に響いているように感じられた。それは、時を超えて彼に送られる、未来からのエールなのかもしれない。龍之介は、そっと笑みを浮かべた。