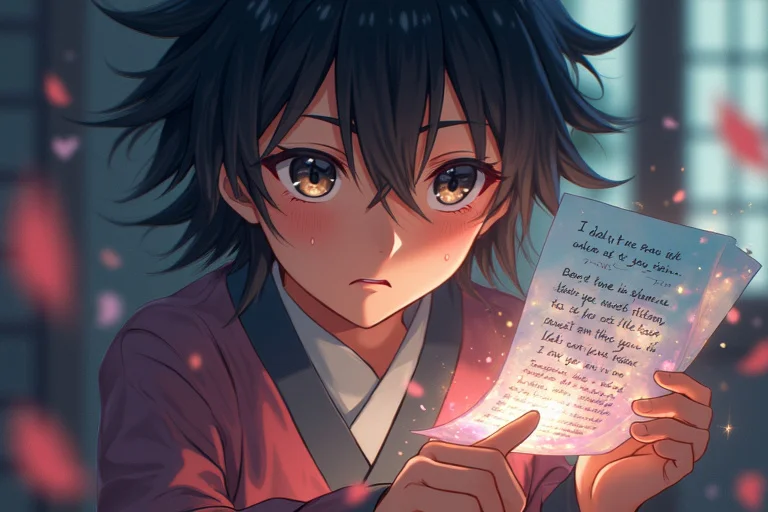第一章 竜胆の文
江戸の空は、いつもどこか煤けていた。神田の片隅に屋敷を構える小禄の御家人、桐山誠一郎にとって、その空は自らの心の写し鏡のようであった。かつて敏腕の目付として名を馳せた父・正継が、大掛かりな汚職事件の濡れ衣を着せられ、潔白を訴えることも叶わぬまま腹を切ってから五年。誠一郎の時間は、あの日から止まったままだった。
剣の腕は道場随一と謳われたが、出世への望みはなく、ただ無為に日々をやり過ごす。父が遺した数少ない蔵書の中でも、彼が唯一手に取るのは、使い古されて角の丸くなった一冊の『本草綱目』。薬草の精緻な絵を眺めている時だけが、息苦しい現実から逃れられるひと時だった。
そんな生気のない日常を破ったのは、ある雨上がりの昼下がりだった。玄関先に、ぽつりと置かれた一通の文。差出人の名はなく、上質な和紙にはただ一輪、紫紺の竜胆の花が押し花として添えられているだけ。誠一郎の心臓が、錆びついた扉のように軋みながら大きく脈打った。
竜胆。それは、父が死の床で、朦朧とする意識の中から最後に彼に託した言葉の花だった。
「誠一郎……竜胆の花の、花言葉を知っているか。〝悲しんでいるあなたを愛す〟……そして、〝正義〟だ。もしこの先、道に迷うことがあらば、竜胆の気高さを思い出せ。父との、約束だ」
震える手で文を開くと、そこには墨痕鮮やかに、ただ一言だけ記されていた。
『北町奉行所、古井戸』
父の死。竜胆の花。そして謎の文。それは偶然ではありえない。誠一郎の内に燻っていた何かが、ちろりと小さな炎を上げた。父の死は、単なる不運ではなかったのではないか。この文は、五年という歳月を経てなお、父の無念が自分を呼んでいる声ではないのか。
「……父上」
呟きは誰に聞かれるでもなく、湿った空気に溶けて消えた。しかし、彼の瞳には、長らく失われていた光が、確かに宿り始めていた。澱んでいた日常が、音を立てて動き出す。誠一郎は、埃を被っていた刀を手に取り、静かに帯に差した。向かう先は、父がその正義を貫こうとして散った場所、北町奉行所。彼の運命を大きく揺るがすとは、まだ知る由もなかった。
第二章 父の影
北町奉行所の裏手、人の訪れも稀な一角にその古井戸はあった。苔むした石積みの縁に腰を下ろし、誠一郎は深く暗い闇を覗き込む。水面は遥か下で、僅かな光を反射しているだけだ。文の意図が読めぬまま、彼は井戸の周囲を丹念に調べ始めた。
やがて、一つの石が僅かに浮き上がっていることに気づく。力を込めてそれを引き抜くと、裏側に窪みが作られており、油紙に包まれた小さな桐の箱が姿を現した。箱を開けると、中には父の筆跡で書かれた手記の断片が数枚、大切に仕舞われていた。
『……巨悪の根は、我らの足元、深く暗い場所にまで伸びている。南蛮渡りの品々が、正規のルートを介さず、この江戸に大量に流れ込んでいる。その利権を巡り、幕閣の重鎮までもが関与している疑いが濃い。証拠はまだない。だが、奴らは巧妙にその身を隠している』
手記はそこで途切れ、最後の一枚には暗号めいた一文だけが記されていた。
『影は光を喰らい、香は真を隠す』
影は光を喰らう。香は真を隠す。誠一郎は何度もその言葉を口の中で転がした。父は一体、何を伝えようとしていたのか。この手記こそが、父を死に追いやった元凶に違いない。父の無念を晴らす。その決意が、誠一郎の心を支配した。
手がかりを求め、誠一郎は父の古い知人を訪ね歩いた。だが、誰もが口を噤み、あるいは気まずげに顔を背けるばかり。父の事件は、未だに多くの者にとって触れてはならない禁忌なのだ。失意の中、彼が最後に訪ねたのは、父の無二の親友であり、今は茶道の師範として静かに隠居生活を送る梅崎宗観(うめざきそうかん)だった。
「おお、誠一郎殿か。よく来てくれた。父上の面影が、確かにある」
市中の喧騒が嘘のような静寂に包まれた茶室で、宗観は柔和な笑みを浮かべて誠一郎を迎えた。彼は誠一郎から事情を聞くと、痛ましげに眉を寄せた。
「正継殿の無念、儂も断腸の思いだった。力になれず、誠に申し訳ない……」
誠一郎が父の手記に記された暗号を告げると、宗観はしばし目を閉じ、やがて何かを思いついたように顔を上げた。
「『香は真を隠す』……。香、か。誠一郎殿、日本橋に近江屋という豪商がいる。表向きは香木を商っているが、裏では南蛮渡りの品々を扱っていると専らの噂だ。正継殿が追っていたのは、その近江屋のことではないだろうか」
宗観の言葉は、暗闇に差し込んだ一筋の光明だった。
「近江屋……!」
「うむ。だが、相手は手強い。くれぐれも油断召されるな。何かあれば、いつでも儂を頼るがよい」
力強い宗観の言葉に、誠一郎は深く頭を下げた。父の親友というだけでなく、その思慮深い眼差しと落ち着いた物腰は、誠一郎に大きな安心感を与えた。父が遺した影を追う孤独な戦いに、初めて信頼できる味方が現れたのだ。彼は決意を新たに、近江屋という巨大な闇へと踏み込んでいくのだった。
第三章 香の裏切り
梅崎宗観の助言は的確だった。誠一郎は町人に身をやつし、近江屋の周辺を探った。数日にわたる内偵の末、彼は近江屋の蔵が深夜、密かに開かれ、得体の知れぬ荷が運び込まれている現場を押さえる。それは紛れもなく密貿易の証拠だった。黒幕は近江屋で間違いない。父を陥れた者たちに、正義の鉄槌を下す時が来た。
決行前夜、誠一郎は報告と礼を兼ねて宗観の屋敷を訪れた。
「見事だ、誠一郎殿。さすがは正継殿の御子息。さあ、今宵は祝いだ。門出に、儂が心を込めて一服点てよう」
宗観に促されるまま、誠一郎は静謐な茶室に通された。釜の湯がしゅんしゅんと鳴る音、そして焚かれた白檀の香りが、彼の高ぶる神経を和らげていく。差し出された深い緑の茶を、誠一郎は感謝と共に一気に飲み干した。
その直後だった。視界がぐにゃりと歪み、手足の力が急速に失われていく。何かがおかしい。懸命に意識を保とうとする誠一郎の耳に、宗観の冷え切った声が響いた。
「『影は光を喰らい、香は真を隠す』……。実に、見事な謎かけだったな、君の父上は」
畳に崩れ落ちた誠一郎が見上げた先には、これまで見たこともないような、氷のような嘲笑を浮かべた宗観が立っていた。
「な……ぜ……」
「まだ分からぬか。哀れな男よ」
宗観はゆっくりと誠一郎に歩み寄り、その顔を覗き込んだ。
「『影』とは、光である正継殿に常に寄り添い、その功績を妬み続けた儂自身のことよ。『光』とは、正義を振りかざし、まばゆいばかりに輝いていた君の父。そして『香』……それは、この茶の湯の香りだ。この香りで心を偽り、儂は裏で近江屋を手引きし、密貿易を操っていた。真実を隠す、何よりの香だったというわけだ」
衝撃が、雷となって誠一郎の全身を貫いた。信じていた唯一の味方。父の無二の親友。その男こそが、父を裏切り、死に追いやった元凶だったのだ。父は、死の間際に友に裏切られた絶望の淵で、それでも息子に真実を伝えようと、命を賭してこの暗号を遺したのだ。
「父上は……あなたを、信じていた……!」
絞り出した声は、怒りと悲しみに震えていた。父が感じたであろう、裏切りの痛みと孤独が、今、五年という時を超えて誠一郎の胸に突き刺さる。これはもはや、単なる悪党退治ではない。信じた者に裏切られ、孤独のうちに死んでいった父の魂を、この手で救い出すための戦いなのだ。
朦朧とする意識の中、誠一郎は刀の柄を強く握りしめた。彼の瞳の奥で、父が託した竜胆の花が、悲しくも気高い紫紺の炎を燃やし始めていた。
第四章 暁の決着
薬の効果は、誠一郎の強靭な精神力の前では完全ではなかった。彼は残された最後の力を振り絞り、ふらつきながらも立ち上がった。茶室の静寂が、張り詰めた殺気で満たされる。
「なぜだ、梅崎殿……!父とあなたは、友ではなかったのか!」
「友、か。正継殿は常に正しく、常に輝いていた。その光が、儂の影をどれほど濃くしたか、あの男に分かるものか。正義などというものはな、誠一郎殿、持つ者の立場によって色を変える幻に過ぎん。儂は、儂の正義を生きたまでよ」
宗観は茶釜の横に立てかけてあった仕込み杖を抜き放った。静かな茶室が、一瞬にして死闘の場と化す。誠一郎の剣は父から受け継いだ正統なもの。対する宗観の剣は、型にはまらぬ、闇討ちを得意とする邪剣だった。
刃と刃が交錯するたびに、火花が散り、白檀の香りが乱れる。誠一郎の脳裏に、父と共に稽古に励んだ日々が蘇る。父の教えが、声が、彼の剣に力を与える。
「竜胆の正義を、思い出せ!」
父の幻の声が聞こえた気がした。その瞬間、誠一郎の剣が迷いを振り払うかのように閃く。それは、憎しみでも怒りでもない、ただ父の魂を鎮め、真の義を貫くための一閃だった。
宗観の仕込み杖が宙を舞い、彼の胸を誠一郎の切っ先が深く貫いた。
「見事……だ。正継殿に、よく……似て……」
それが、宗観の最期の言葉だった。
夜が明け、暁の光が障子を白く染め上げる頃、誠一郎は一人、静かにその場を後にした。彼は宗観の罪を公にしなかった。それが幕府を揺るがす醜聞となり、多くの者が傷つくことを望まない。それはきっと、父も望まないだろう。父が守ろうとしたのは、法の秩序そのものであって、個人の名誉ではなかったはずだ。誠一郎は、自分自身の判断で、この事件に幕を引いた。
数日後、誠一郎は父の墓前にいた。墓石の傍らには、朝露に濡れた一輪の竜胆の花が、凛として咲いている。彼の顔には、もうかつてのような無気力な影はない。父の死の真相を知り、人の心の光と闇の深淵を覗き、そして自らが拠って立つべき「正義」を見出した男の、静かで力強い表情がそこにあった。
誠一郎は屋敷に戻ると、刀を刀掛けに置き、父が遺した『本草綱目』を手に取った。頁をめくると、竜胆の項目に、父の筆跡で小さな書き込みがあった。
『癒しの力あり。されど、その根には毒も宿す』
光と影、正義と裏切り、そして薬と毒。万物は一つの顔だけではない。父もそれを知っていたのだ。
誠一郎は、江戸の町を見下ろせる小高い丘に立った。空は、まるで昨日までの淀みが嘘のように、どこまでも青く澄み渡っている。それは、まるで竜胆の花の色そのものだった。
これからは、剣で人を斬るのではなく、この薬草の知識で、人を救う道もあるのではないか。
誠一郎の心に、新たな誓いが静かに芽生えていた。父の死を乗り越え、彼は今、自分の足で、自分の未来へと歩き始める。その道の先に何が待つのかは分からない。だが、彼の見上げる空には、希望の光が満ち溢れていた。