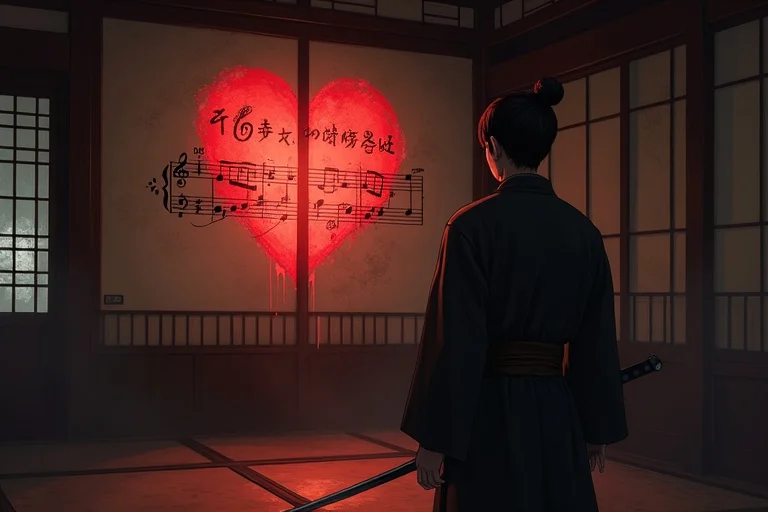第一章 月下の依頼人
神田の片隅、武家屋敷が立ち並ぶ一角に、朽ちかけた長屋があった。その一室で、間宮誠一郎は息を殺して筆を握っていた。家禄だけでは食えぬ下級武士の彼が、糊口をしのぐために始めた「代筆屋」。それは、武士の誇りを捨てた行いだと自嘲しながらも、彼の唯一の拠り所であった。
月明かりだけが頼りの静かな夜。戸を叩く音が、闇の底から響いた。こんな夜更けに誰だろうか。用心深く戸を開けると、そこに立っていたのは、深編笠で顔を隠した大柄な男だった。男は名乗らず、ずしりと重い銭袋を畳に置いた。
「代筆を頼みたい」
低く、地の底から響くような声だった。男が懐から取り出した手本は、上質な美濃紙に流れるような筆致で書かれた和歌。その文字を見た瞬間、誠一郎は息を飲んだ。十五年前に亡くなった父、正之の筆跡と瓜二つだったのだ。父は剣の達人であると同時に、達筆家としても知られていた。しかし、ある疑獄事件に連座し、潔白を主張することなく、家名を守るためにと腹を切った。
「この筆跡を真似て、一通、書いてもらいたい」
「これは…なぜこの筆跡を」
「詮索は無用。できるか、できぬか」
男の放つ圧に、誠一郎は唾を飲み込んだ。父の筆跡で、一体何を。不審と恐怖が胸を渦巻く。しかし、目の前の銭袋は、病に伏せる母の薬代を思えば抗いがたい魅力を持っていた。
「……承知、いたしました」
依頼された内容は、日本橋の大店『越後屋』の主人、徳兵衛が、その妻おとよに宛てた離縁状であった。家族への詫びと、店の将来を案ずる言葉が綴られていたが、その文面にはどこか冷たい響きがあった。誠一郎は、父の面影を紙上に蘇らせるように、一文字一文字、心を込めて書き写した。父の癖、力の入れ具合、線の僅かな震えまで。書き上げた離縁状は、まるで父が冥府から戻って書いたかのような出来栄えだった。
男は完成した書状を無言で受け取ると、風のように去っていった。畳に残された銭の重みが、誠一郎の罪悪感をいや増すように、ずしりと心にのしかかった。なぜ、父の筆跡で。なぜ、越後屋の離縁状を。不吉な予感が、夏の夜の生ぬるい空気のように、彼の肌にまとわりついて離れなかった。
第二章 偽りの遺書
数日後、誠一郎の予感は最悪の形で現実のものとなった。越後屋の主人、徳兵衛が、蔵の中で自ら命を絶ったという報せが江戸の町を駆け巡ったのだ。枕元には、妻への別れを告げる遺書が残されていたという。
誠一郎は血の気が引いた。あの離縁状が、遺書として扱われたのだ。己の筆が、人を死に追いやった。その事実に打ちのめされ、彼は数日間、仕事も手につかず自室に閉じこもった。あの夜の男の顔も知らぬ。ただ、父の筆跡を真似たという事実だけが、重い枷となって彼を苛んだ。
そんな折、彼は一つの噂を耳にする。徳兵衛の死には不審な点が多く、奉行所も内々に調べているらしい、と。さらに、越後屋はかつて、誠一郎の父・正之が世話になった商家であったことを思い出す。父の死と、越後屋。そして、父の筆跡。点と点が、闇の中で不気味な線を結び始めようとしていた。
居ても立ってもいられなくなった誠一郎は、越後屋の周辺を密かに探り始めた。そこで彼は、一人の女性と出会う。徳兵衛の一人娘、お絹。彼女は、気丈にも店の後始末に奔走していたが、その瞳の奥には、父の死に対する深い疑念と悲しみが宿っていた。
「父は、自ら死を選ぶような人ではございません。あの遺書も…父の字に似てはおりますが、どこか違う。まるで、心を失った抜け殻のような文字なのです」
お絹の言葉は、誠一郎の胸を鋭く抉った。心を失った抜け殻。それは、父の筆跡をただなぞっただけの、己の文字そのものではなかったか。罪悪感から、誠一郎は彼女に素性を明かせなかった。しかし、彼女の悲しみに触れるうち、この事件の真相を突き止め、彼女を救いたいという思いが、武士としての本分や代筆屋としての立場を超えて、強く芽生え始めていた。
二人は密かに協力し、徳兵衛の身辺を調べ始めた。帳簿の不審な金の流れ、徳兵衛と揉めていたという曰く付きの商人たち。だが、真相は深い霧の向こうに隠されたまま、決定的な証拠は見つからなかった。ただ、調べるほどに、徳兵衛の善良な商人という表の顔の裏に、冷酷で強欲な別の顔が見え隠れしていた。
第三章 真実という刃
お絹との調査が行き詰まりを見せていたある夜、再びあの男が誠一郎の前に現れた。しかし、今宵の男は深編笠を被ってはいなかった。月光に照らされたその顔を見て、誠一郎は言葉を失った。
「…源吾殿」
そこにいたのは、父・正之の最も信頼厚い部下であった、元武士の田所源吾だった。父が切腹した後、彼は禄を返上し、行方をくらましていた。
「誠一郎様、よくぞご無事で。…あなた様を、このような企てに巻き込んでしまったこと、平にご容赦を」
源吾は深く頭を下げ、静かにすべてを語り始めた。その口から紡がれたのは、誠一郎の信じてきた世界を根底から覆す、驚くべき真実だった。
十五年前、誠一郎の父・正之は、越後屋徳兵衛が幕府の要人と結託して行っていた不正な米の買い占めに気づき、それを告発しようとしていた。しかし、その動きを察知した徳兵衛に先手を打たれ、逆に不正の首謀者という濡れ衣を着せられたのだ。主君や家名に累が及ぶことを恐れた正之は、弁明もせず、すべての罪を被って自ら腹を切った。潔い死ではなく、無念の死だった。
「殿の無念を晴らすため、十五年、この日を待っていた」と源吾は言った。「徳兵衛は不正の証拠を、屋敷のどこかに隠しているはずだった。それを世間に公表し、殿の名誉を回復させる。それが拙者の生涯を賭けた悲願」
源吾は長年の探索の末、ついに徳兵衛が不正の証拠を蔵の隠し金庫に保管していることを突き止めた。しかし、厳重に警備された金庫を開けることはできない。そこで彼は、徳兵衛自身に金庫を開けさせるための策を講じた。それが、あの偽の遺書だった。
「徳兵衛は用心深い男。しかし、己の死を偽装して姿をくらますという筋書きならば、必ず乗ってくると踏んだ。そして、偽の遺書には、殿の筆跡を用いた。己を破滅させた男の文字で自らの死が告げられることこそ、奴への最大の復讐。そして、殿が徳兵衛を許し、自ら身を引いたという美談に仕立て上げることで、殿の名誉を守るため…」
誠一郎は愕然とした。父の名誉は、自分が書いた偽りの書状によって守られようとしている。自分が加担したのは、殺人ではなく、父の無念を晴らすための、壮大な復讐劇だったのだ。
「武士として、法に則って裁かれるべきだったのかもしれん。だが、法は殿を守ってはくれなかった。ならば、我らが刃で裁きを下すまで」
源吾の瞳は、静かな狂気を宿して燃えていた。
誠一郎の足元が、ぐらりと崩れた。武士としての正義とは何か。真実を白日の下に晒すことか。それとも、父の名誉を守るために、この巨大な偽りを完遂させることか。彼の信じてきた価値観が、音を立てて砕け散った。
第四章 筆は剣よりも
数日、誠一郎は地獄のような苦悩の中を生きた。お絹に真実を話すべきか。いや、話せば彼女はさらに傷つくだろう。源吾の計画は、もはや止められない。ならば、己はどうすべきか。
答えが出ないまま、彼は筆を握った。心を鎮めるため、ただ無心に父の文字をなぞった。その時、ふと気づいた。父の文字は、ただ美しいだけではない。その一本一本の線に、決して揺らぐことのない強い意志と、深い情が込められている。父は、剣だけでなく、この筆に魂を込めていたのだ。
誠一郎の中で、何かが吹っ切れた。彼は源吾のもとへ走った。
「源吾殿。私にも、手伝わせていただきたい」
「誠一郎様…?」
「父上の無念を晴らすのが、子の務め。ですが、偽りの美談で父上の名誉を飾るのは、父上が最もお望みにならないことでしょう。真の正義は、真実によってのみもたらされるべきです」
誠一郎は、ある策を提案した。それは、もう一通、父の筆跡で「第二の遺書」を書くというものだった。その遺書には、徳兵衛が自らの罪を悔い、不正の証拠が隠された金庫の場所と開け方を記す。それを奉行所に届け、公儀の力で裁きを下させるのだ。源吾の復讐心と、誠一郎の求める正義が、一つに重なった瞬間だった。
誠一郎は、生涯のすべてを懸けて筆を走らせた。今度の文字は、単なる模倣ではなかった。父の無念、源吾の忠義、お絹の悲しみ、そして己の決意。すべての想いを墨に込め、紙に叩きつけた。完成した書状は、もはや父の筆跡を超え、凄絶な気迫を放っていた。
計画は成功した。第二の遺書は匿名で奉行所に届けられ、越後屋の隠し金庫から不正の証拠が次々と発見された。関係した幕府の要人も失脚し、徳兵衛の悪事は白日の下に晒された。同時に、間宮正之の潔白も証明され、十五年の時を経て、その名誉は完全に回復された。
すべてが終わった後、源吾は誠一郎に深く一礼し、江戸の闇に姿を消した。彼もまた、己のやり方で主君への忠義を貫いたのだ。
季節は巡り、桜が咲く頃。誠一郎は代筆屋を続けていた。彼の評判は静かに広まり、彼の書く文字には人の心を動かす力があると噂された。彼はもう、父の影を追いかけるだけの弱い男ではなかった。父から受け継いだ筆を、己の信じる正義のために振るう「武士」となっていたのだ。
お絹とは、それきり会うことはない。彼女は彼女の道を進み、強く生きていると風の噂に聞いた。それでいい、と誠一郎は思った。
ある春の日、貧しい身なりの娘が、彼のもとを訪れた。
「病の母に、桜が綺麗だと、早く元気になって一緒に見たいと…手紙を書いていただけますでしょうか」
「承知した」
誠一郎は静かに頷き、硯に水を差す。彼の筆先から生まれる一文字一文字が、誰かの心を温める小さな灯火となることを信じて。武士の魂は、鞘に収められた刀にではなく、今、己が握るこの一本の筆にこそ宿っている。
窓の外では、墨で描いたかのように淡い桜が、江戸の空に静かに咲き誇っていた。