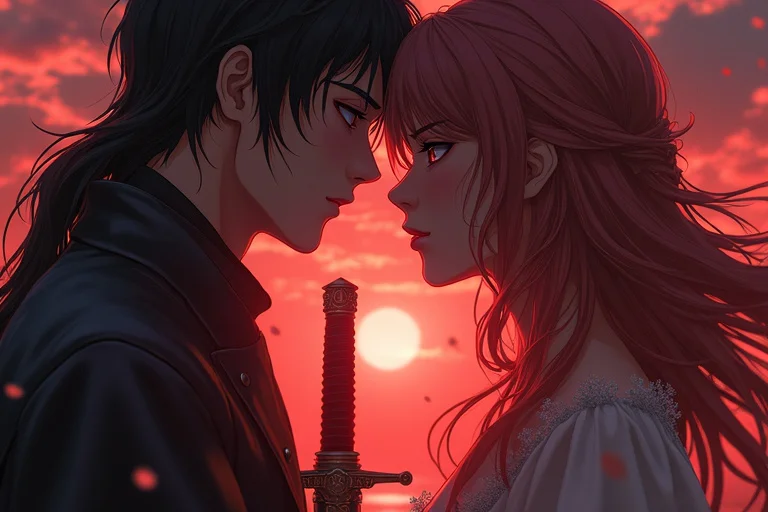煤と油の匂いが染みついた江戸の裏通り。その一角に、からくり工房「幻操堂」はあった。主である源内が病に伏してより、店を切り盛りしているのは娘のお絹だった。父譲りの器用な指先で壊れた人形の腕を繋ぎながら、お絹はため息を隠せずにいた。薬代は嵩む一方で、暮らしは日増しに苦しくなる。
その日、工房の引き戸をがらりと開けて入ってきたのは、上等な絹の着流しをまとった厳つい顔の武士だった。お絹が動揺する間もなく、男は黒漆塗りの精巧な木箱を無言で台の上に置いた。
「これは、我が主君、黒田家老様の持ち物だ。仕掛けが壊れ、開かなくなった。これを修理せい」
高圧的な口調に、お絹は小さく身をすくませる。箱からは、微かに異国の香木のかおりがした。
「報酬は五十両。ただし、条件が一つある」
武士は冷たい目を向けた。
「修理が終わるまで、決して箱の中を覗いてはならぬ。もしその禁を破れば、お主の命はないものと思え」
五十両。その金額に、お絹の心は揺れた。それだけあれば、父に高価な薬を買ってやれる。命はない、という言葉の重みに喉が渇くのを感じながらも、お絹はこくりと頷いていた。
父の薬代のため、と自分に言い聞かせ、お絹は絡繰箱の修理に取り掛かった。夜を徹して箱と向き合う日々が続く。それは、ただの箱ではなかった。寸分の狂いもなく組み合わされた木片、巧妙に隠されたいくつもの仕掛け。父の仕事を見て育ったお絹でさえ、舌を巻くほどの精緻さだった。
作業を進めるうち、お絹の胸に言いようのない疑念が渦巻き始めた。箱を揺らすと、中で微かに紙が擦れるような音がする。黒田家老といえば、強欲で民を顧みないという悪評を耳にしたことがあった。この美しい箱には、その評判にそぐわぬ、何か暗い秘密が隠されているのではないか。
そんな折、父の容態が急変した。往診に来た医者は、手に入る限りの最上の薬を試さねば、この冬を越すのは難しいだろう、と告げた。お絹は目の前が暗くなるのを感じた。一刻も早く報酬を得なければ。しかし、焦れば焦るほど、指先は震え、箱の最後の仕掛けがどうしても解けなかった。
追い詰められたお絹は、父が書き遺した設計図の束を夢中でめくった。その中に、見覚えのある意匠を見つけた。「禁忌の箱」と走り書きされたその図面には、今まさに自分が格闘している絡繰箱と瓜二つの構造が描かれていた。そして、最後の仕掛けを解くための鍵が、そこには記されていたのだ。
ふと、父の言葉が脳裏に蘇る。
『いいか、お絹。技というものは、ただの道具ではない。真実を見極める目を持ち、人を救うために使ってこそ、魂が宿るのだ』
父の薬代。黒田家老との約束。そして、父の教え。お絹の心は千々に乱れた。しかし、彼女の瞳に宿ったのは、迷いではなく強い決意の光だった。
父の図面を頼りに、最後の一手を打つ。カチリ、と乾いた音が響き、箱の蓋が静かに開いた。息を呑んで中を覗き込むと、そこには異国の商人との密貿易を記した帳簿と、幕府を欺く計画が綴られた密書が収められていた。
「……やはり」
お絹が呟いた、その瞬間だった。
工房の引き戸が蹴破られ、数人の刺客が雪崩れ込んできた。先頭に立つのは、あの厳つい顔の武士だった。
「見たな、小娘ッ!」
抜かれた刃が、薄暗い工房の中で鈍い光を放つ。口封じのために襲い掛かる刺客たちを前に、お絹は絶望に目を閉じた。
だが、彼女の足が踏みしめた床板の下で、何かが静かに作動した。それは、父が万一のためにと工房の至る所に仕掛けておいた、防衛のための絡繰仕掛けだった。
「今よ!」
お絹が叫ぶと同時に、刺客たちの足元の床が抜け落ち、壁からは細い竹の矢が放たれ、天井からは目潰しの煙玉がいくつも落下した。悲鳴と怒号が入り乱れる中、工房全体が巨大な罠となって刺客たちを翻弄する。
お絹はその隙に密書を固く懐に抱きしめ、裏口から闇夜へと飛び出した。向かう先はただ一つ。清廉潔白で知られる、若き町奉行の屋敷だった。震える手で門を叩き、事の次第を訴え、証拠の品を差し出した。
数日後、黒田家老の悪事は白日の下に晒され、藩を揺るがす大事件となった。お絹には奉行所から内々に多額の報奨金が与えられ、父は江戸で一番と言われる医者の治療を受けることができた。
寝台の上で、少しだけ血の気の戻った父は、お絹の手を弱々しく握った。
「お前の技が、わしを……そして、多くの民を救ったのだな。お絹、お前はもう、わしを超える立派なからくり師だ」
父の目からこぼれた涙が、お絹の手の甲を温かく濡らした。
朝日が差し込む幻操堂で、お絹は新しい設計図を引いていた。その横顔にはもう迷いはない。父が教えてくれた技と魂で、今度は誰かの心を動かす、楽しく、そして優しいからくりを作ろう。そう心に誓いながら、彼女の指先は、未来を描くように軽やかに紙の上を走っていた。