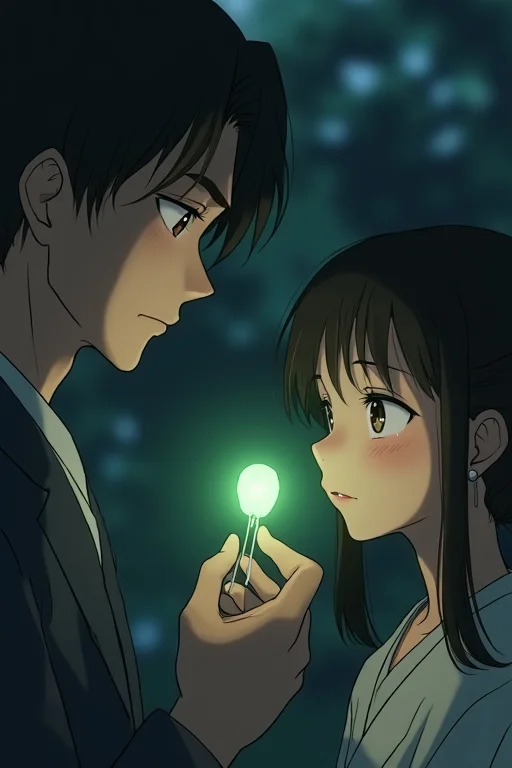煤と鉄の匂いが染みついた鍛冶場に、夕暮れの赤い光が差し込んでいた。源斎は、火床に残る熾火(おきび)をぼんやりと眺めていた。齢七十をとうに超え、その背中は丸まり、かつて名工と謳われた腕も今や農具や刃こぼれした包丁を直すのが関の山だった。
若い頃は、腕を振るうことが誇りだった。己が打った刀が名のある侍の腰に収まり、武勲を立てたと聞けば、胸が熱くなった。だが、いつからだろうか。鋼を打つ槌の音が、人の命を断つための凶器を産み出す音にしか聞こえなくなったのは。太平の世とは名ばかりで、人の諍いは絶えない。源斎の打った刀もまた、多くの血を吸ってきたはずだった。その重みが、彼の魂を少しずつ蝕んでいた。
「もう、刀は打たぬ」
そう決めて十年。弟子も取らず、江戸の片隅でただ静かに朽ちていくのを待つばかりの日々だった。
そんなある日、一人の若い侍が、源斎の寂れた仕事場を訪れた。まだ二十歳を少し過ぎたばかりだろうか。着流しは質素だが、その立ち姿には一点の曇りもない。
「源斎殿とお見受けいたします。拙者は榊原誠一郎と申す者。貴殿の噂を聞き、一振りお願いしたく参上いたしました」
源斎は顔も上げずに答えた。
「生憎だが、もう刀は打たん。鍬や鎌なら、明日までに直してやるが」
「いえ、刀でございます。ぜひとも、貴殿の魂がこもった一振りを」
「帰れ。儂の魂など、とうに煤けて消え果てたわ」
追い返そうとする源斎に、しかし榊原は食い下がった。
「お願いしたいのは、人を斬るための刀ではございませぬ」
その言葉に、源斎は初めて顔を上げた。榊原の目は、驚くほど真っ直ぐだった。
「人を斬らぬ刀だと? 馬鹿を申せ。刀は、そのためにあるものだ」
「ならば、『人を活かす』ための刀を。力とは、振るうためにあるのではなく、守るためにこそあると、そう信じられるような刀を打ってはいただけませぬか」
榊原は静かに語り始めた。かつて道場で、些細なことから友と口論になり、売り言葉に買い言葉で真剣を交えてしまったこと。己の未熟さゆえに勢い余って友を斬り、命を奪ってしまったこと。以来、彼は刀を握れなくなったという。
「力は、時に人を傲慢にいたします。拙者は、二度と過ちを犯したくない。この手に握るべきは、自らを戒め、守るべきものをただ守るための、静かなる魂。そのような刀が欲しいのです」
榊原の瞳の奥に宿る深い悔恨と、それでも前を向こうとする意志の光に、源斎の心の奥底で何かが小さく音を立てた。人を活かす刀。長年、刀を打つことの虚しさに苛まれてきた源斎にとって、それはあまりにも眩しい響きを持っていた。
「……面白いことを言う若造よ。分かった。お主のその戯言に、この老いぼれの最後を賭けてみよう」
その日から、鍛冶場に再び命の火が灯った。源斎は蔵の奥から、長年眠らせていた極上の玉鋼を取り出した。火床に風が送られ、炎が龍のように舞い上がる。カン、カン、と響き渡る槌の音は、かつてなく澄んでいた。
夜も昼もなく、源斎は鋼を打ち続けた。流れる汗が目に染み、疲労で膝が笑う。だが、心は不思議と晴れやかだった。これは、人を殺めるための仕事ではない。一人の若者の再起と、己の人生の答えを探すための、神聖な儀式だった。折り返し、鍛え、焼きを入れる。鋼が水の中で鋭い音を立てるたび、源斎は榊原の真っ直ぐな瞳を思い出していた。この刀は、血ではなく、誇りを吸って輝くのだ。
三月後、ついに一振りの刀が完成した。
鞘から抜き放たれた刀身は、月光を吸い込んだかのように静かな光を放っていた。恐ろしいほどの切れ味を内に秘めながら、威圧するような殺気は微塵も感じられない。ただただ、美しかった。
完成した刀を手に、榊原が再び訪れた。彼は刀を手に取ると、しばし無言で見入っていた。やがて、そっと刀身を抜き、月明かりにかざす。
「……これは。なんと静かな刀でしょう。まるで、水面のようです」
「ああ」と源斎は頷いた。「だが、ひとたび嵐が来れば、その水面は荒れ狂う波となるだろう」
「はい。この刀には、魂が宿っております。人を斬るためではなく、守るべきもののためにこそ抜くべき魂が」
榊原の言葉に、源斎は満足げに微笑んだ。
「その刀の名は『守心(しゅしん)』だ。お主の心を、守る刀だ。決して、己の誇りや怒りのためには抜くな。守るべき義のためにのみ、抜け」
榊原は刀を鞘に納めると、源斎に向かって深々と頭を下げた。
「この御恩、生涯忘れませぬ」
そう言って去っていく若侍の背中を、源斎は黙って見送った。
火の落ちた鍛冶場に、源斎は一人佇んでいた。長年、胸に突き刺さっていた棘が、ようやく抜け落ちたような気がした。人を斬る道具を作り続けてきたこの両手が、最後に、人を活かすためのひと振りを産み出した。それで、もう十分だった。
窓から差し込む朝の光が、皺だらけの源斎の顔を優しく照らしていた。その口元には、穏やかな笑みが浮かんでいた。