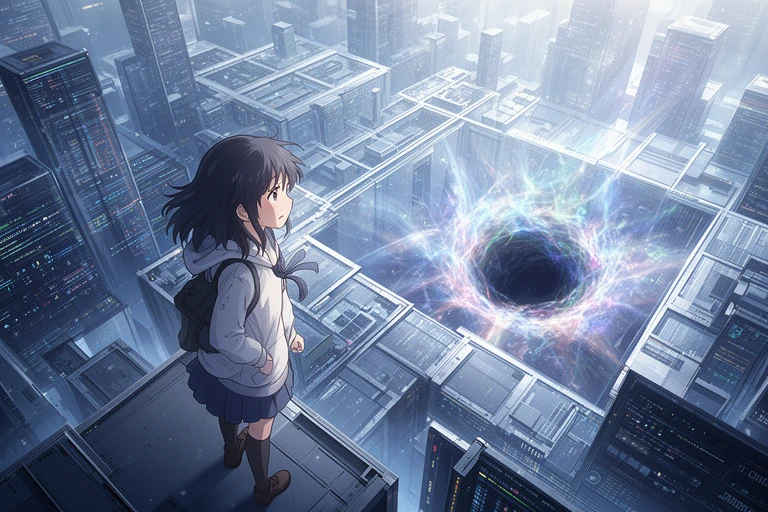モニターの青白い光が、水野航平の顔を無機質に照らし出していた。彼の職場であるウェブメディア「ファクト・コンパス」の編集部は、キーボードを叩く音と、時折響く誰かの深いため息だけで満たされている。水野の仕事は、インターネットという名の濁流から、真実という名の砂金を掬い上げること。しかし、流れ着くのはほとんどが泥やヘドロだ。
「水野くん、これ頼む」
編集長の武田が、タブレットをデスクに置いた。画面には、地方都市で進められている環境事業「グリーンリーフ計画」に反対するSNSの投稿が、爆発的に拡散している様子が映し出されていた。
『計画に使われる新素材から有害物質が検出! 子供たちの未来が危ない!』
ショッキングな文言と共に、発疹が出た子供の腕とされる写真が添えられている。
「典型的なデマの匂いがする。だが、今回は拡散の仕方が妙に組織的だ。発信源を特定して、カウンター記事を出してくれ」
水野は頷いた。これが彼の日常だ。感情に訴えかける嘘を、無味乾燥な事実で打ち砕く。正義感はある。だが、この作業が人々の心に巣食う不安そのものを消し去るわけではないことも、彼は知っていた。
調査は困難を極めた。発信源とされる市民活動家のアカウントは、いくつもの匿名アカウントを経由しており、実態が掴めない。水野は、計画に反対するオンラインコミュニティに偽名で参加した。そこには、純粋な不安と義憤を語る普通の人々がいた。我が子の健康を案じる母親、故郷の自然を憂う老人。彼らの言葉に触れるたび、水野の胸は鈍く痛んだ。この人たちは、悪意の加害者ではなく、むしろ被害者なのではないか。
調査に行き詰まった水野は、尊敬するジャーナリストの大御所・神崎にアドバイスを求めた。かつて大手新聞社で数々のスクープを飛ばした神崎は、引退後もシンクタンクの顧問として情報社会に警鐘を鳴らし続けている。水野にとっては、灯台のような存在だった。
「焦るな、水野くん」電話口の神崎の声は、いつものように穏やかで深かった。「情報の流れを丁寧に追うんだ。蛇の道は蛇、というだろう。だが、どんな嘘にも、必ず綻びがある。そして忘れるな。真実は一つでも、正義は人の数だけあるものだ」
その言葉に背中を押され、水野はもう一度、拡散された画像データの解析に没頭した。何十枚もの写真のメタデータを一つずつ検証していく。それは、砂漠で一本の針を探すような作業だった。何時間経っただろうか。疲労がピークに達した彼の目に、ある違和感が飛び込んできた。一枚だけ、撮影機器の情報が他のものと明らかに異なっている。さらに深く解析を進めた水野は、息を呑んだ。その画像のオリジナルデータに埋め込まれていたGPS情報は、日本の地方都市ではなく、東南アジアの、とある工業地帯を指していたのだ。
これが嘘の起点だ。興奮と使命感に震えながら、水野はデータの痕跡を辿った。発信元のIPアドレス。プロキシサーバーの壁をいくつも突き破り、ついに大元のサーバーに辿り着いた。そのアドレスに見覚えがあった。何度も見たことがある。神崎が顧問を務める、あのシンクタンクのサーバーだった。
血の気が引いた。全身が急速に冷えていく。まさか。震える指で、さらに調査を進める。デマの拡散を加速させたインフルエンサーたちへの金の流れ。その金の出所も、シンクタンクが管理するダミーカンパニーへと繋がっていた。
全ては、神崎が描いたシナリオだったのだ。
翌日、水野は神崎を訪ねた。都心を見下ろす高層ビルのオフィスで、神崎は静かに水野を迎え入れた。
「気づいたかね」
神崎は、窓の外に広がる灰色のビル群を見つめながら、静かに言った。悪びれる様子は微塵もない。
「グリーンリーフ計画そのものに害はない。だが、あれを推進する企業は、海外で大規模な環境破壊を行っている。それを国内で告発しても、誰も見向きもしない。だから、少しだけ世論を『誘導』してやったまでだ。小さな嘘で、より大きな悪を叩く。これもまた、一つの正義だと思わないかね?」
「それは……ただの世論操作だ! 人々の不安を煽って!」
「不安だと?」神崎は初めて水野の方を向き、冷ややかに笑った。「彼らは最初から不安だったのさ。社会に、未来に。私は、彼らが望む『物語』を与えてやっただけだ。君が信じる『事実』などというものより、よほど人の心を救う、強力な物語をね」
灯台だと思っていた光は、船を暗礁に乗り上げさせるための、偽りの灯りだった。水野の中で、何かが音を立てて崩れ落ちた。尊敬、理想、そしてジャーナリズムへの信頼までもが。
一週間後、「ファクト・コンパス」に一本の記事が掲載された。
『拡散された環境デマ、その巨大な発信源を追う』
水野が書いたその記事は、特定の個人名を出すことは避けながらも、シンクタンクが組織的にデマを生成・拡散していた事実を、動かぬ証拠と共に詳細に報じるものだった。それは、尊敬する恩師を社会的に抹殺する、水野自身の決断だった。
記事は社会に大きな衝撃を与えた。神崎は失脚し、シンクタンクは解散に追い込まれた。だが、世界が良くなったわけではなかった。デマを信じていた人々は梯子を外され、今度は「メディア不信」という新たな物語に傾倒していった。何が真実で、何が嘘なのか。その境界線は、以前よりもさらに曖昧になってしまった。
水野のデスクに、次々と新しい調査依頼が舞い込んでくる。モニターの向こう側では、今日も無数のサイレント・ノイズが生まれ、人々の心を静かに蝕んでいる。水野は、カップに残った冷たいコーヒーを飲み干した。彼の戦いに終わりはない。この虚構が鳴り響く世界で、耳を澄まし、かすかな真実の音を探し続ける。その瞳には、かつての理想に燃える輝きはなかった。ただ、現実の重さを引き受けた者の、静かで、諦念にも似た強い光だけが宿っていた。