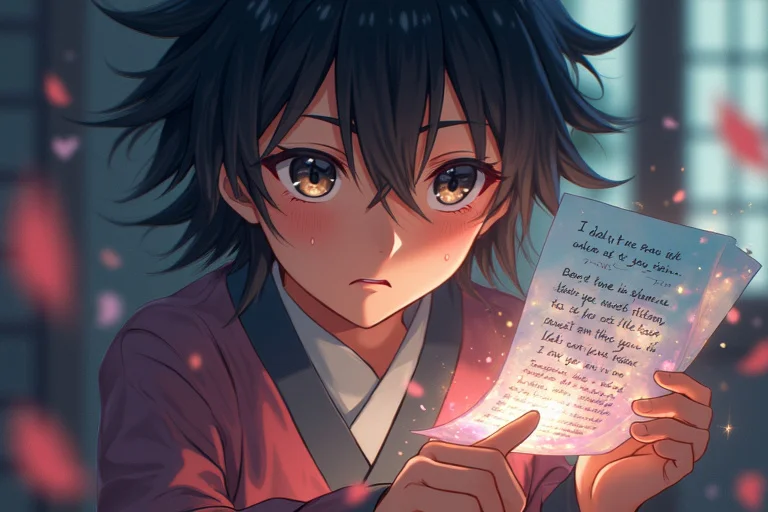神隠しか、はたまた妖術か――。
江戸の夜を、不気味な噂が覆っていた。富商の蔵が、一夜にして空になる。しかし、扉の錠は破られておらず、番人たちは皆、口を揃えてこう証言した。「濃い霧の中から、鬼火のようなものが無数に現れ、気づいた時には気を失っていた」と。
人々は、その神出鬼没の盗賊を「不知火(しらぬい)」と呼び、怖れた。
大店「近江屋」の主、徳兵衛もその一人だった。今宵、不知火が狙うは我が店、という予告状が、今朝方、枕元に置かれていたのだ。腕利きの用心棒を十数人も雇ったが、妖術相手では心許ない。万策尽きた徳兵衛が最後に頼ったのは、神田の裏通りで細々と工房を構える一人の男だった。
「機巧屋(からくりや)の、甚兵衛(じんべえ)と申します」
戸を開けると、油と木の香りが混じった匂いと共に、飄々とした顔が徳兵衛を迎えた。齢は三十半ばか。身なりはただの職人だが、その瞳の奥には、道具を検分するような鋭い光が宿っていた。工房の中は、奇妙な歯車やばね、鳥の形をした木偶(でく)などが所狭しと転がっている。
徳兵衛が震える声で事情を話すと、甚兵衛は顎を撫でながら言った。
「妖術、ねぇ。そいつは面白そうだ。引き受けやしょう。ただし、お代は弾んでいただきやすぜ」
その夜、近江屋の屋敷は死んだような静けさに包まれていた。用心棒たちは固唾を飲んで闇を見つめている。屋敷の広間に一人座す甚兵衛は、まるで夜釣りでも楽しむかのように悠然と茶をすすっていた。彼の周りには、昼間に運び込まれた奇妙な箱や筒が、獲物を待つ獣のように配置されている。
子の刻を過ぎた頃、それは来た。
どこからともなく、白く濃い霧が屋敷を包み込み始める。視界は瞬く間に奪われ、用心棒たちの悲鳴が上がり始めた。霧の中、燐光を放つ青い火の玉が、踊るように飛び交っている。
「出たぞ! 不知火だ!」
徳兵衛が叫ぶ。だが、その声も霧に吸い込まれてかき消えた。
火の玉が広間に侵入し、宙を舞ったその時。
「――芸がねぇな」
甚兵衛が呟き、足元の板を軽く踏んだ。
瞬間、床下に仕込まれた巨大な鞴(ふいご)が轟音と共に作動し、凄まじい風が巻き起こった。濃霧は一息に吹き飛ばされ、呆気なく正体を晒す。ただの水蒸気と、発煙筒の煙だ。
飛び交っていた鬼火も、風に煽られて地に落ちた。それは、細い糸で吊るされた、燐を塗っただけの紙玉だった。
「なっ……!?」
驚愕の声と共に、黒装束の一団が姿を現す。その中心に立つのは、能面のような白い化粧を施し、紅を引いた、中性的な顔立ちの頭目。あれが「朧(おぼろ)」か。
「貴様、何者だ!」
朧が鋭い声で問う。
「ただの機巧屋だよ」
甚兵衛は立ち上がり、懐から掌サイズの鉄の箱を取り出した。
「お前さんたちの奇術(トリック)はもう見切った。さあ、お縄につくか、それとも――俺のからくりと、もう少し遊んでいくかい?」
「面白い!」
朧が指を鳴らすと、黒装束たちが一斉に斬りかかってきた。
甚兵衛は笑みを崩さぬまま、背後の柱に手をかけた。柱に隠された滑車が回り、天井から巨大な網が降り注ぐ。一網打尽、とはいかないまでも、数人の動きを封じた。
さらに床板を踏めば、壁に仕込まれた筒から粘着質の液体が射出され、敵の足元を奪う。畳の下からは、刃の代わりに墨を塗った竹槍が飛び出し、黒装束たちを次々と無力化していく。それは、殺さず捕らえるための、精密に計算された仕掛けの連鎖だった。
残るは朧ただ一人。
「見事な腕だ。だが、これで終わりだ!」
朧は懐から小太刀を抜くと、目にも留まらぬ速さで甚兵衛に迫る。
それに対し、甚兵衛が手にしていたのは、奇妙な鉄の棒。彼が棒の柄を握ると、先端から三本の鉤爪が「カシャン!」と音を立てて飛び出した。それは、元は蔵の高い場所にある荷物を取るための道具を改造したものだった。
金属音が闇に響き渡る。小太刀の鋭い切っ先を、甚兵衛は鉤爪で巧みに受け流し、絡め取る。舞うような朧の剣技と、無骨だが合理的な甚兵衛の動き。それはまるで、幻想と現実の戦いのようだった。
一瞬の隙を突き、甚兵衛は鉤爪で朧の小太刀を弾き飛ばした。そして、空いた片手で懐の鉄の箱を投げつける。箱は空中で弾け、目も眩むほどの閃光と轟音を放った。
「ぐっ……!」
目が眩んだ朧の懐に、甚兵衛は滑り込み、その喉元に鉤爪の先端をぴたりと突きつけた。
「……そこまでだ」
捕らえられた朧は、化粧の下から汗を流しながら、静かに語った。
元は旅芸人の一座だったこと。芸で人を喜ばせるのが生き甲斐だったが、時代の流れで立ち行かなくなり、路頭に迷った仲間を養うために、その芸を盗みに使ったこと。
「俺たちの技は……人を笑顔にするためのものだったはずが……」
「技に罪はねえよ」
甚兵衛は静かに言った。「どう使うか、だ。お前さんたちの技なら、きっとまた人を喜ばせられる日が来る」
その言葉に、朧はただ、静かに涙をこぼした。
数日後。神田の工房では、甚兵衛が子供たちのために、ぜんまい仕掛けで羽ばたく蝶を作っていた。
「甚兵衛さん、大店の化け物騒ぎ、あんたが解決したって本当かい?」
長屋の子供に尋ねられ、甚兵衛は飄々とした顔で答える。
「まさか。俺はただのしがない機巧屋さ」
その手の中で、色鮮やかな鋼鉄の蝶が、まるで本物のように軽やかに舞い上がった。江戸の空は、今日も青く澄み渡っている。