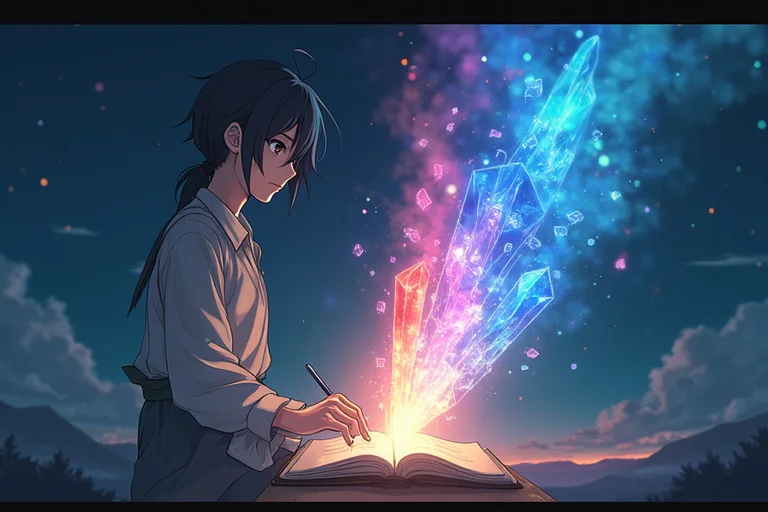神田の裏通りに、その古道具屋はあった。名を「からくり堂」。埃をかぶったガラクタが所狭しと並ぶ店先で、主の銀次は今日も気怠げに煙管をふかしている。昼間から酒気を帯びた顔は、およそ商人のそれではない。
「銀次さん、また昼寝かい」
「おう、八兵衛か。良い天気は眠くなるもんだ」
魚売りの八兵衛との軽口も、この界隈では見慣れた光景だった。だが、この銀次に裏の顔があることを知る者は少ない。表向きはぐうたらな古道具屋。しかし、ひとたび月が影を落とす刻、彼は「絡繰り師」へと姿を変える。どんな錠前も指先で歌わせ、いかなる仕掛けも見破る、江戸一番の錠前破りであった。
その日の夕暮れ、店に一人の娘が駆け込んできた。息を切らし、涙で化粧も崩れている。
「あ、あの……絡繰り師の銀次様はいらっしゃいますか」
銀次はゆっくりと目を開けた。娘の名はお絹。日本橋で名の知れた呉服問屋「伊勢屋」の一人娘だった。
話はこうだ。強欲で知られる金貸しの越後屋が、伊勢屋に罠を仕掛けた。偽の証文で多額の借金を負わせ、店の権利書をまんまと奪い取ったのだという。その証文は、越後屋の屋敷にある「開かずの蔵」に仕舞われている。
「あの蔵は、南蛮渡りの『龍の顎(りゅうのアギト)』という絡繰り錠で守られていると聞きます。誰も開けられたことがないと……。どうか、父の、伊勢屋の魂を取り戻してくださいまし!」
お絹は畳に額をこすりつけた。
銀次は煙管の灰を落とすと、静かに立ち上がった。その瞳から、昼間の怠惰な光は消え失せ、剃刀のような鋭さが宿っていた。
「……面白ぇ。龍の顎、ね。ちいとばかし、腕が鳴らぁ」
報酬はいらぬ、と銀次は言った。代わりにと、店先にあった煤けた小さな櫛をお絹に手渡す。「お代は、仕事が終わってからで結構だ」と。
三日後の夜。闇が江戸の町を飲み込む刻限。
黒装束に身を包んだ銀次は、越後屋の屋敷を見下ろす瓦の上にいた。風の音に紛れ、猫のようにしなやかに屋敷へ侵入する。警備の者の息遣いを読み、影から影へと渡る。
目指す「開かずの蔵」は、屋敷の最も奥にあった。分厚い漆喰で固められた壁。そして、その中央に鎮座する異様な錠前。龍が顎を開いたような複雑な形をしており、不気味な威圧感を放っている。これが「龍の顎」か。
銀次は懐から細長い鉄の棒を数本取り出した。先端の形がそれぞれ違う、彼の手製の道具だ。一本を鍵穴に差し込み、耳を扉に押し当てる。全神経を指先と耳に集中させ、内部の機械の声を聴く。
カチリ、と微かな音が響く。一つ目の仕掛けが外れた。額に汗がにじむ。龍の顎は、一つの鍵穴に七つもの筒が内蔵された複雑怪奇な代物だ。一つでも手順を間違えれば、全ての仕掛けが元に戻ってしまう。
息を詰めること、半刻(はんとき)。
月が雲に隠れ、辺りが一層深い闇に包まれた、その瞬間。
――カチン。
最後の一際軽い音と共に、重々しい錠が静かに開いた。
銀次は安堵の息を吐く間もなく、蔵の中へ滑り込んだ。蝋燭の灯りを頼りに帳簿の山を探る。あった。伊勢屋の名が記された権利書だ。それを懐に収めた、まさにその時。
「――見事な腕前だ。褒めてつかわす」
背後から、氷のように冷たい声がした。振り返ると、そこには闇よりも黒い着流しを纏った侍が立っていた。いつの間に。気配が全くしなかった。
越後屋が雇う用心棒、「影法師」の甚内。音もなく人を斬ることから、そう呼ばれる男だ。
「その錠を開けた者は、お主が初めてだ。故に、ここで死んでもらう」
甚内の刀が、月光を吸ってぬらりと光る。絶体絶命。銀次の手にあるのは、か細い鉄の道具だけ。
だが、銀次は不敵に笑った。
「そいつはどうかな。あんた、面白いもんを踏んでるぜ」
甚内が怪訝な顔で足元を見る。その一瞬の隙を、銀次は見逃さなかった。
懐から鉄製の玉を二つ取り出し、甚内の足元へ投げつける。玉は硬い音を立ててぶつかり合い、火花を散らした。同時に、床板の一部が音を立てて跳ね上がる。銀次が錠を開ける前に仕掛けておいた、小さな罠だった。
体勢を崩した甚内の脇を、銀次は疾風のごとく駆け抜ける。
「絡繰りは、錠前だけじゃねえんでな!」
蔵を飛び出し、闇に紛れる。背後から怒りの声が聞こえたが、もう遅い。
翌朝、からくり堂の店先で、銀次はまた気怠げに煙管をふかしていた。そこに、お絹が駆け込んでくる。
「銀次様! 権利書が……役所に届いておりました! 越後屋は奉行所に引っ立てられ……」
涙ながらに礼を言うお絹に、銀次はひらひらと手を振った。
「ああ、そうかい。そりゃよかった。で、例の櫛のお代だが……そうさな、五十文でどうだい」
あっけにとられるお絹を尻目に、銀次は大きなあくびを一つ。
からくり堂には、またいつもの時間が流れる。だが、悪人たちの心には、月夜に舞う「絡繰り師」の噂が、新たな恐怖として刻み込まれたのだった。