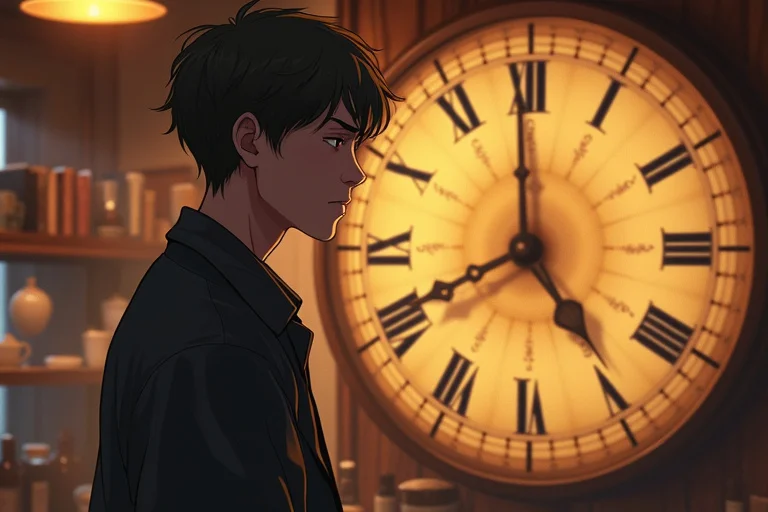第一章 触れられない日常
水島湊の日常は、薄い布一枚を隔てて世界と繋がっていた。彼が愛用する灰色のコットン手袋は、単なるファッションではない。それは、彼の世界が不意に他人の感情の奔流に飲み込まれないようにするための、脆弱な防波堤だった。
古書店『時紡ぎ堂』の静寂は、湊にとって数少ない安息の地だ。埃と古紙の匂いが混じり合った独特の空気、背表紙に刻まれた褪せた金文字、そして何より、インクが染み込んだ紙の乾いた感触。本だけは、彼に過剰な情報を与えなかった。物語はすでに完結し、感情は言葉の檻の中に静かに収まっている。だから彼は、この場所を愛していた。
その日も、夕暮れの光が店内に長い影を落とす中、湊はカウンターの奥で黙々と本の整理をしていた。雨が降り始めたのか、窓を叩く微かな音が聞こえる。客の姿はもうない。閉店作業を始めようとしたその時、彼はカウンターの隅に置かれた一本の傘に気づいた。黒い、ごくありふれたビニール傘。おそらく、先ほどの学生が忘れていったのだろう。
無意識だった。ほんの出来心で、彼は手袋を外した右手で、その冷たいプラスチックの柄に触れてしまった。
瞬間、世界が反転した。
ザー、という雨音が増幅され、鼓膜を激しく打つ。アスファルトの湿った匂い。焦燥感。胸を締め付けるような、誰かを待つ切ない期待。改札口の喧騒、電光掲示板の無機質な光、そして「ごめん、今日は行けなくなった」という冷たいメッセージの残像が、網膜に焼き付く。感情の洪水が、湊の脳を直接揺さぶった。
「うっ……!」
湊は短い呻き声を漏らし、傘から手を離した。視界がぐらつき、カウンターに手をついてかろうじて体を支える。心臓が早鐘を打ち、額には冷たい汗が滲んでいた。数秒前の静寂が嘘のように、他人の落胆と孤独が、まるで自分の体験であるかのように全身を駆け巡っていた。
これが、水島湊の呪いであり、日常だった。物に触れると、その物が最後に宿した記憶や感情を、追体験してしまう。幼い頃から続くこの奇妙な体質は、彼を人や物から遠ざけ、自らの殻に閉じこもらせるには十分すぎる理由だった。
息を整え、彼は慌てて手袋をはめ直す。指先に残る他人の記憶の残響を振り払うように、彼は買取品の段ボール箱に手を伸ばした。気を紛らわしたかった。箱の中には、古びた専門書や文庫本が雑多に詰め込まれている。その中で、何かが鈍い光を放った。
それは一本の古い万年筆だった。銀色の軸は細かな傷で覆われ、使い込まれた年月を物語っている。ペン先はわずかに摩耗し、キャップの天辺には小さな三日月の意匠が彫られていた。まるで、誰かの大切な宝物だったかのような、静かな存在感。
なぜだろう。湊は、それに強く惹きつけられた。まるで磁石に引き寄せられる砂鉄のように、彼の指がゆっくりと伸びていく。手袋越しの感触では物足りない。もっと、直接。
彼は再び手袋を脱ぎ、覚悟を決めてその銀色の軸をそっと握った。
次の瞬間、彼の全身を突き抜けたのは、これまで経験したことのないほど深く、濃密な感情の奔流だった。それは単なる落胆や焦燥ではない。もっと根源的な、魂が引き裂かれるような『喪失感』。そして、どうしても伝えられなかった言葉への、身を焦がすほどの『後悔』。陽の当たる窓辺、インクの甘い香り、紙の上を走るペンの微かな音、そして、ぽつりと落ちて滲んでいく、熱い涙の記憶。
それは、見知らぬ誰かの記憶のはずなのに、なぜかひどく懐かしく、湊自身の心の奥底を揺さぶるのだった。
第二章 銀の万年筆が囁く記憶
その日から、湊の日常は銀の万年筆を中心に回り始めた。彼はそれを売ることも、元の持ち主を探して返すこともしなかった。まるで憑りつかれたように、仕事が終わると店の奥の私室に持ち帰り、机の上のペン立てにそっと置いた。そして、夜が更けるまで、ただそれを眺めているのだった。
手袋を外してそれに触れる行為は、危険な儀式に似ていた。触れるたびに、あの強烈な喪失感と後悔が彼を襲う。しかし、痛みと同時に、そこには不思議な安らぎと、もっと知りたいという抗いがたい欲求があった。それは、他人の感情に苦しめられてきた彼にとって、初めて抱く感覚だった。
断片的なビジョンが、触れるたびに鮮明になっていく。
――陽光が差し込む、書斎のような部屋。使い込まれた木製の机の上には、原稿用紙が数枚置かれている。
――新しいインクがペンに満たされる。色は、深い海の底を思わせるミッドナイトブルー。
――震える手。万年筆を握る指は、何かを恐れるかのように、あるいは何かを慈しむかのように、力が入りすぎている。
――「愛する……へ」。書き出しの文字。その後に続くはずの、大切な誰かの名前。
――そして、必ず最後に流れ込んでくる、涙の染み。インクが滲み、言葉が形をなさなくなる瞬間の、絶望的な静寂。
湊は、この万年筆の持ち主の物語を想像せずにはいられなかった。きっと、大切な人に宛てて、人生を懸けた手紙を書こうとしていたのだろう。しかし、何らかの理由で、その想いを綴り終えることはできなかった。残されたのは、伝えられなかった言葉の残骸と、どうしようもない後悔の念。
「一体、あなたに何があったんですか……」
湊は、冷たい銀の軸を撫でながら、誰にともなく呟いた。いつしか彼は、この見ず知らずの持ち主に深い共感を寄せ、その無念を晴らしてあげたいとさえ思うようになっていた。人との関わりを避け、他人の感情から逃げ続けてきた自分が、他人の物語にこれほどまでに心を動かされている。その事実自体が、湊にとっては大きな驚きだった。
彼は万年筆の手がかりを探し始めた。拡大鏡を使い、傷だらけの軸を丹念に調べる。すると、クリップの付け根のあたりに、極めて微かな刻印が残っているのを見つけた。摩耗してほとんど読めなかったが、目を凝らすと、アルファベットの筆記体で『M.M』と刻まれているように見えた。
『M.M』。
それが唯一の手がかりだった。この万年筆は、いつ、誰がこの店に持ち込んだものなのか。もしそれが分かれば、持ち主の人生の輪郭が少しは見えるかもしれない。湊は店の奥にある、分厚い買取台帳の棚へと向かった。埃っぽい台帳をめくり、過去の記録を遡るという、途方もない作業が彼の前に横たわっていた。それでも、彼の心は不思議と軽く、使命感のようなものに満たされていた。それは、他人のためでありながら、同時に、自分自身の空虚な何かを埋めるための、初めての旅路だった。
第三章 鏡の中の追憶
買取台帳との格闘は、数日に及んだ。古い記録は手書きで、インクは掠れ、判読は困難を極めた。湊は閉店後の静まり返った店内で、ページをめくる音だけを響かせながら、ひたすら『万年筆』や『筆記具』という文字を探し続けた。
そして、ある夜更け、ついにその記述を見つけ出した。今からちょうど十年前の、初夏の日付。そこには『古書三十冊、文具一式(万年筆含む)』と記され、買取相手の欄には、懐かしい名前があった。
『水島 佳代子』。
それは、湊の母親の名前だった。
湊は息を飲んだ。全身の血が逆流するような感覚。なぜ、母が? 混乱する頭で記憶をたどる。十年前。それは、父方の祖母が亡くなり、遺品を整理していた時期と重なる。おそらく、母はその時に出てきた不要な品々を、息子の働くこの店に持ち込んだのだろう。
つまり、あの万年筆は、祖母の持ち物だったのか? いや、違う。祖母が万年筆を使う姿など、記憶のどこにもない。それに、祖母のイニシャルは『M.M』ではない。では、誰のものだ?
震える指で、湊はスマートフォンの画面をタップし、実家の番号を呼び出した。深夜にもかかわらず、数回のコールの後、眠たげな母の声が聞こえた。
「……もしもし、湊? こんな時間にどうしたの」
「母さん、ごめん、夜遅くに。一つだけ、聞きたいことがあるんだ」
湊は、声の震えを抑えながら、店で古い万年筆を見つけたこと、そして買取台帳に母の名前があったことを伝えた。銀色で、三日月の意匠が彫られていて、イニシャルは『M.M』だと。
電話の向こうで、母が息を飲む音が聞こえた。長い、重い沈黙が流れる。
「……湊。その万年筆、まだ持っていたのね……」
「え?」
「それはね……あなたのお父さんのものよ」
父。
その言葉は、湊の胸に鈍い痛みとともに突き刺さった。湊の父親、水島誠(みずしま まこと)は、彼が七歳の時に交通事故で亡くなっている。湊にとって父親の記憶は、古いアルバムの中の笑顔の写真と、断片的な温かい手の感触くらいしかない。事故のショックで、父に関する記憶の多くが、靄のかかった風景のように曖昧になっていた。
母は、重い口をゆっくりと開いた。
「あなたのお父さん、作家になるのが夢でね。いつもその万年筆で、机に向かっていたわ。あなたが生まれてからは、あなたのための物語を書いていたのよ」
声が、遠くなる。
「あの日……事故があった日、お父さんはあなたに手紙を書いていた。あなたに、どうしても伝えておきたいことがあるって。でも、それを書き終える前に……」
その瞬間、湊の脳裏で、バラバラだった記憶の破片が激しい音を立てて繋ぎ合わされた。
陽の当たる窓辺。それは、幼い自分が住んでいた家の、父の書斎。
インクの甘い香り。父がいつも使っていたインクの匂い。
震える手。それは、事故に遭い、薄れゆく意識の中で、息子への手紙を書き終えようとしていた、父の最後の抵抗。
『M.M』。水島 誠(Makoto Mizushima)。水島 湊(Minato Mizushima)。それは父と息子の、同じイニシャルだった。
万年筆が宿していた記憶は、見ず知らずの誰かのものではなかった。
それは、死の淵にあった父親が、愛する幼い息子へ宛てた、最期のメッセージの記憶。
そして、湊が感じていたあの強烈な『喪失感』と『後悔』は、父自身の無念であると同時に、父を失い、その記憶に蓋をしてしまった、七歳の湊自身の悲しみそのものだったのだ。
第四章 インクに溶けた言葉
すべてのピースが、あるべき場所にはまった。湊はカウンターに崩れるように座り込み、銀の万年筆を両手で強く握りしめた。もう、手袋は必要なかった。
流れ込んでくる記憶は、もはや苦痛ではなかった。それは、言葉にならなかった父の愛情そのものだった。
『大きくなれ』
『強く、優しく生きろ』
『お前は、私の誇りだ』
声にならない声が、インクの染みから、軸の傷から、冷たい金属の感触から、とめどなく湊の心に染み渡ってくる。父は、死の瞬間まで息子のことを想い、言葉を紡ごうとしてくれていた。そして自分は、その記憶から目を逸らし、二十年以上もの間、孤独な殻の中に閉じこもっていた。
この奇妙な能力は、呪いなどではなかったのかもしれない。父を失った衝撃が、閉ざされた記憶の扉をこじ開けるための鍵として、湊にこの力を与えたのだとしたら。それは、父が残してくれた、最後の絆だったのではないか。
涙が、とめどなく頬を伝った。それは、悲しみの涙ではなかった。失われた時間を取り戻すかのような、温かくて、少しだけ塩辛い涙だった。
夜が明け、朝の光が店の窓から差し込む頃、湊は立ち上がった。その足取りは、昨日までの彼とはまるで違って、確かで、力強いものだった。彼は新しいインクボトルを開け、スポイトで深く美しいミッドナイトブルーのインクを吸い上げる。そして、二十年の時を経て乾ききっていた万年筆のペン先に、ゆっくりと命を吹き込んでいった。
真っ白な原稿用紙を一枚、机の上に置く。手袋を外した素手で、父の万年筆を握る。ひんやりとした銀の感触が、今はただ心地よかった。それはもう、他人の記憶を媒介する異物ではない。父の温もりと、自分の血潮が通う、体の一部だった。
彼の日常は、これからも変わらないだろう。古書店で働き、物に触れれば、誰かの記憶が流れ込んでくるかもしれない。しかし、彼の世界の見え方は、根底から覆された。触れることから逃げるのではない。そこにある声なき物語と、静かに向き合っていく。彼の孤独だった日常は、無数の人々の喜びや悲しみに満ちた、豊かで、少しだけ切ない世界へと変貌を遂げたのだ。
湊は息を吸い込み、ペン先を紙に下ろした。
インクが、白い紙に静かに染みていく。
『父さんへ。
僕は、元気です。』
その一文は、失われた父への返事であり、同時に、これから始まる水島湊自身の、新しい物語の始まりを告げる、最初の一行だった。