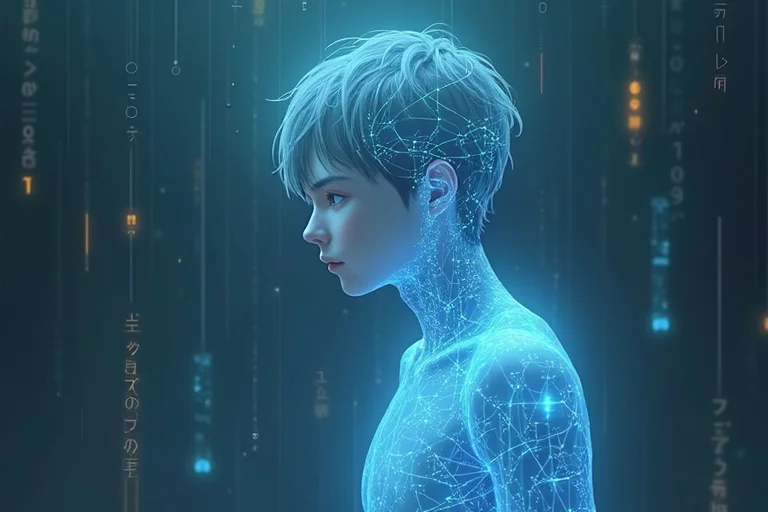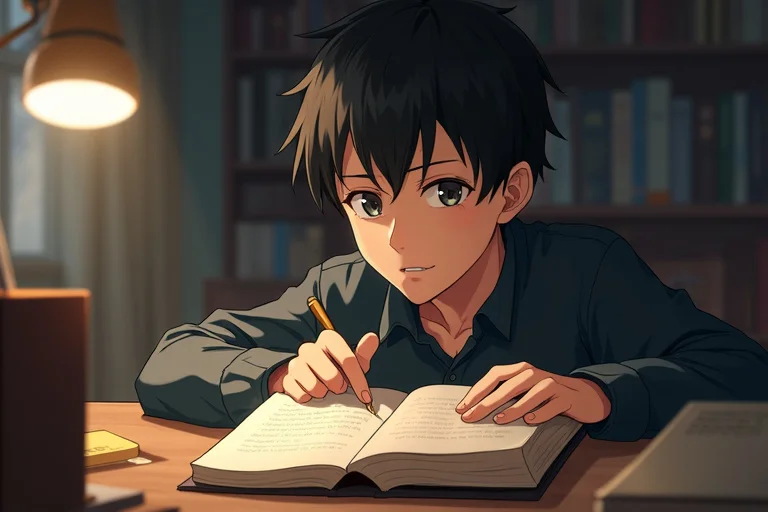第一章 奇妙な空白
佐倉遥は、都市開発プランナーとして日々、膨大な情報と向き合っていた。高層ビルの建設プロジェクトから、地域の活性化計画まで、彼女のパソコンの画面には常に未来の都市の姿が描かれていた。しかし、その日は違った。朝、いつものようにコーヒーを片手にニュースサイトをチェックしていると、奇妙な現象に気づいたのだ。国際情勢に関するトップ記事の下に続くはずの「貧困国における気候変動の影響」と題された記事が、なぜか遥のディスプレイ上では、タイトルとごく短い導入文の後に、不自然なまでに広い空白が広がっていた。スクロールしても、その空白は続く。まるで記事の本体がごっそり抜け落ちたかのようだった。
「システムエラー?」
遥は首を傾げ、ブラウザを閉じ、再び開き直した。しかし、現象は変わらない。今度は別のニュースサイト、SNSのトレンド、政府の公式発表ページなど、次々と情報源を変えてみた。すると、特定のジャンル、特に「社会の不平等を告発する内容」「国内の深刻な貧困問題」「特定企業の不祥事」といったテーマの記事や投稿で、同様の「空白」が頻繁に現れることに気づいた。それはまるで、彼女の目の前だけを避けるように、情報が意図的に削り取られているかのようだった。
隣の席の同僚、田中はいつも通り大きな声で朝の挨拶を交わし、自分のデバイスで同じニュースサイトを開いている。
「田中さん、この国際情勢の記事、全部見えます?」
遥は恐る恐る尋ねた。
「ああ?何言ってんすか、佐倉さん。ばっちり読めますよ。ほら、この写真、酷いもんでしょ?」
田中が指差す先には、遥の画面では空白となっているはずの、気候変動で干上がった農地の生々しい写真が鮮明に表示されていた。田中の声には、何の疑念も含まれていない。その瞬間、遥の背筋に冷たいものが走った。自分が目にしている「空白」は、他者には見えていない。あるいは、他者が目にしている情報が、自分には届けられていない。どちらにせよ、これは単なるシステムエラーではない。
その日以降、遥の日常は一変した。街中のデジタルサイネージ、電車の車内広告、カフェのモニター。かつては当たり前のように目にしていた情報の一部が、遥の目には「意味のない空白」として認識されるようになった。例えば、大手飲食チェーンの従業員の低賃金問題に関するドキュメンタリーの告知ポスターは、彼女にはただのロゴと日付が並ぶ、デザイン性の低い空白に見えた。一方で、同僚や友人たちは、それらの空白の存在に全く気づかず、そこに描かれた情報について平然と語り合う。遥は、まるで自分だけが異なる現実を見せられているような、深い孤立感と混乱に苛まれた。情報の洪水の中で、自分だけが特定の情報から切り離されているという事実は、現代社会において、最も恐ろしい刑罰のように感じられた。
第二章 見えない情報の追跡
遥は、この奇妙な現象を理解するため、情報収集に没頭した。自宅のパソコンとスマートフォン、オフィス支給のタブレット、果ては図書館の公共端末まで、あらゆるデバイスでニュースやSNSを検証したが、遥にだけ現れる「空白」は、どのデバイスでも一貫して特定の情報にまとわりついていた。それは、社会の底辺に光を当てるようなニュース、既存の権力構造に疑問を投げかける内容、あるいは倫理的な議論を呼ぶような科学技術に関する報告書など、多岐にわたっていた。
最初は、自分が何らかのターゲットにされているのではないかと疑った。ハッキング、あるいは誰かの悪質なジョーク。しかし、専門家でもない遥に、その手の痕跡を見つける術はない。
ある夜、遥はSNSで、自分と似たような体験を訴える、ごくわずかな投稿を発見した。彼らの主張は遥ほど具体的ではなかったが、「情報が部分的に消える」「自分だけが特定の記事を読めない」といった内容が、遥の心を揺さぶった。それらの投稿には、共通して「#見えざるコード」というハッシュタグが添えられていた。そのハッシュタグを辿ると、都市の一角にある、薄暗いビルの二階に「情報格差是正を考える市民の会(通称:リンク)」というNPOがあることを知った。
翌日、仕事を終えた遥は、意を決してそのNPOを訪れた。古びたドアを開けると、そこには白髪混じりの男が一人、山積みになった書類と古いパソコンに囲まれて座っていた。彼の名は橘慎一郎。元ジャーナリストで、現在は情報格差問題に取り組む活動家だという。
遥が自分の体験を訥々と語り終えると、橘は静かにグラスの水を一口飲み、遥の目を見つめた。
「あなたは、ついに『それ』に気づいたんですね。歓迎します、佐倉さん。あなたの話は、これまで私たちが集めてきた断片的な情報と完全に一致します」
橘の言葉は、遥にとって救いであると同時に、深い恐怖を呼び覚ました。彼女の体験は、現実だったのだ。
橘は続けた。「我々は、この現象を『**認知最適化プログラム**』と呼んでいます。政府、あるいはその背後にいる巨大な組織が、国民の『心の平穏』と『社会の安定』を名目に、特定の情報フローを管理し、調整していると考えています」
「管理?調整?それが空白となって私に見えているということですか?」
「ええ。ある特定の情報が、社会の混乱を招く、あるいは個人の幸福感を損なうと判断された場合、その情報が届くべき人々に『届かない』ように、あるいは『歪められて届く』ように操作される。あなたのデバイスは、その『対象者』として認識されているんです」
橘は、遙の目の前で、自分のデバイスに表示されているニュース記事の一部を指し示した。遙の画面では空白となっているその部分は、橘のデバイスでは明確に、地方の貧困世帯に対する政府の支援不足を告発する衝撃的なグラフと、関係者の実名証言が記されていた。橘は、このプログラムの存在を証明する明確な証拠はないが、長年の調査と、遙のような「空白」を見る人々の証言から、確信を持っていると語った。彼の言葉は、遥の頭の中にあった全ての疑問を、パズルのピースのように埋めていくのだった。
第三章 認知の檻
遥は橘と行動を共にするようになり、リンクの活動に参加することで、驚くべき真実の断片を次々と目の当たりにした。認知最適化プログラムは、遙が想像していたよりもはるかに巧妙で、広範囲に及んでいた。それは単に情報の一部を隠すだけでなく、特定の言説を強調したり、別の情報を相対化したり、時にはまったく異なる「代替情報」を提示することで、人々の認識そのものを形成していたのだ。プログラムは、個人のオンライン上の行動履歴、購買データ、さらには健康情報や政治的傾向まで分析し、その個人が「社会の安定」を維持するために最も効果的な情報環境を構築していた。
遥は、自身が都市開発プランナーとして携わっていたプロジェクトで、このプログラムの具体的な影響を目の当たりにする。ある再開発計画の市民説明会でのことだ。遥は、市民が提示された資料を基に、再開発による経済効果や利便性の向上といったメリットばかりを熱心に語り合うのを聞きながら、違和感を覚えた。なぜなら、遥が事前に閲覧していた計画書には、再開発に伴う既存の低所得者層の強制移住問題や、歴史的建造物の破壊といった、重大な問題点が詳細に記されていたからだ。しかし、説明会の参加者たちは、それらの問題について一切触れることはなかった。彼らが手にしている資料は、遥の画面に表示されたそれとは、明らかに異なっていたのだ。遥の資料には「空白」として表示されていた社会問題の項目が、彼らの資料には最初から存在していなかったか、あるいは全く別の穏便な説明に置き換えられていた。
この事実に直面したとき、遥は深い絶望と怒りに打ち震えた。自分は、彼らが「見ている」情報を信じ、その上で計画を練っていた。しかし、その「見ている」情報自体が、巧妙に操作されたものだったのだ。遥は、自身が「社会の公平性」を信じて仕事をしていたつもりだったが、その実、自分自身もまた「認知の檻」の中に閉じ込められていたことに気づいた。そして、最も衝撃的だったのは、このプログラムが、遥自身を「特定の層」と分類し、社会の不都合な真実から「守られていた」という事実だった。遥は、システムを盲信する側から、そのシステムによって盲目化されていた側に、いつの間にか回されていたのだ。
「社会の安定と幸福のため…」
橘は、遥が発見したプログラムの設計思想を記したとされる内部文書の一部を、震える手で差し出した。そこには、国民が不都合な真実に直面することで生じるパニックや不満を抑制し、社会全体の生産性と調和を維持するという、一見すると崇高な目的が記されていた。しかし、その目的のために、真実を隠蔽し、人々の認識を操作するという倫理的背信が行われている現実に、遥は耐え難い吐き気を覚えた。
「彼らは、私たちが『見るべきもの』と『見せるべきもの』を勝手に決めている。そして、それが彼らにとっての『善』だと信じているんです」
橘の声は静かだったが、その言葉には深い悲しみが宿っていた。遥は、自身の信じていた社会の公正さ、情報の透明性という価値観が、音を立てて崩れていくのを感じた。目の前の空白は、単なる情報欠損ではなく、社会そのものの倫理的な空白であり、人々の自由な思考を奪う「認知の檻」だったのだ。
第四章 空白の先に
遥は、自身の内面で激しい葛藤を抱えていた。「社会の安定」という大義名分のもとで、真実が隠蔽されることの是非。人々が不安や不満から「守られる」ことで、本当に幸福になれるのか。あるいは、真実を知る自由を奪われることで、彼らはより大きな何かを失っているのではないか。この問いは、遥の心を深くえぐった。都市開発プランナーとして、未来の都市をより良いものにしようと信じていた遥にとって、社会の根幹を揺るがすこの事実は、彼女の存在意義そのものを問い直すものだった。
しかし、遥は立ち止まらなかった。空白として見せられてきた真実を知った今、それに背を向けることはできなかった。彼女は、橘と共に、認知最適化プログラムの存在を公にし、社会に真実を問いかけることを決意した。それは、社会を混乱に陥れるかもしれない、危険な選択だった。だが、真実から目を背け、虚偽の安定の上に築かれた社会が、果たして持続可能なものだと言えるだろうか?
リンクの小さなオフィスで、遥は夜遅くまで資料作成に追われた。プログラムの仕組みを解析し、遥自身が経験した「空白」の証拠をまとめる。橘は、彼女の隣で、情報収集と協力者の確保に奔走していた。二人の間に交わされる会話は、決して楽観的なものではなかった。巨大なシステムに立ち向かう無力感、反撃に対する恐怖、そして何よりも、この真実が社会に与えるであろう衝撃への不安。しかし、遥の瞳には、かつてのシステムを盲信するだけの都市開発プランナーにはなかった、真実を求める強い光が宿っていた。
数週間後、リンクは、複数の匿名の内部告発者と遥自身の証言、そして解析されたデータの断片を基に、認知最適化プログラムに関する報告書を公表した。それは、静かな社会に投げ込まれた一石だった。報告書が公開された直後、社会は大きく動揺した。信じていた情報が操作されていたという事実に、多くの人々が怒り、混乱し、そして深く傷ついた。遥が見てきた「空白」が、実は多くの人々が見ないように仕向けられてきた「真実の空白」であったことが明らかになったのだ。
しかし、全ての人がこの真実を受け入れたわけではない。「社会の安定を脅かすデマだ」「陰謀論に過ぎない」と、報告書を否定する声も少なくなかった。遥は、この反応を見るにつけ、改めて認知最適化プログラムの恐ろしさを実感する。長年かけて人々の認識を操作されてきた結果、真実そのものが「偽物」に見える社会が形成されてしまっていたのだ。
遥は、窓の外に広がる都市の夜景を眺めた。無数の光が瞬くその中に、彼女の知らなかった、隠された真実がまだどれほど潜んでいるのだろう。そして、この報告書をきっかけに、人々は本当に自らの意志で「空白」を埋めようとするだろうか。それとも、都合の良い「安定」を求めるがゆえに、再び目に見えない檻の中に閉じこもるのだろうか。
彼女の戦いは終わっていない。むしろ、ここからが始まりなのだ。遥は、未来の都市を「見える真実」で築き上げるため、その小さな一歩を、今、確かに踏み出した。