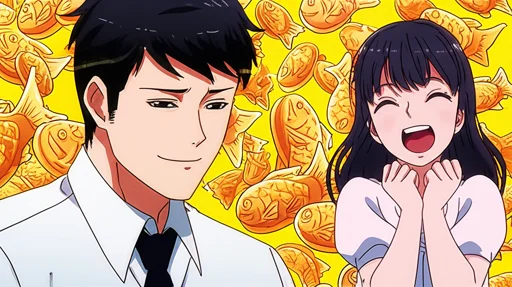第一章 静寂をください
田中誠の人生における至上の幸福は、静寂だった。特に、彼が司書として勤める市立図書館の、午後三時の閲覧室に満ちる沈黙は格別だ。古紙とインクの匂いが混じり合った空気の中、ページをめくる乾いた音だけが、まるで繊細な打楽器のように規則正しく響く。人々が物語の世界に没入し、現実の雑音から解放されている、あの瞬間。誠にとって、そこは聖域だった。
しかし、その聖域は三年前のある日、突如として不可逆的に汚染された。風邪をこじらせて三日間高熱で寝込んだ後、彼の耳は、世界の見えざる「音」を拾い始めたのだ。
それは、人々の「心のツッコミ」だった。
今日もそうだ。カウンターの向こうで、初老の紳士が真剣な面持ちで尋ねてくる。
「すみませんな、あの、ほれ。『車輪の下』という本は、自動車の専門書のコーナーですかな?」
誠は完璧な司書スマイルを顔に貼り付け、「ヘッセですね。海外文学の棚にご案内します」と丁寧に応対する。だが、その瞬間、頭の中に無数の声が濁流のように流れ込んでくるのだ。
『いや、絶対違うだろ! タイトルだけで判断するなジイさん!』
『免許返納した方がいいレベルの天然』
『俺の人生も車輪の下だよ…(泣)』
声の主は、背後で順番を待つ女子高生、隣のカウンターの同僚、そして今まさに質問してきた紳士自身の、困惑に満ちた内なる声。誠はこめかみを押さえ、嵐が過ぎ去るのを耐える。これが彼の日常だった。他人の本音、皮肉、自虐、その全てがダイレクトに脳を揺さぶる。以来、彼は人を深く知ることを諦め、当たり障りのない微笑みという名の鎧で心を固く閉ざしていた。世界はノイズに満ちていた。だからこそ、彼は静寂を渇望した。
そんな彼の聖域に、本日もまた、台風の目がやってきた。
「すみませーん!」
鈴を転がすような、しかし図書館においては警報のようによく通る声。佐藤陽菜さん。週に三日は必ず現れる、常連の利用者だ。彼女はいつも、太陽をそのまま固めたような笑顔を浮かべている。そして、その笑顔に比例するかのように、とんでもない質問を繰り出してくるのだ。
「田中さん、この『銀河鉄道の夜』って、時刻表の棚にありましたっけ?」
来た。本日最大級の天然ボケ。誠は一瞬、宇宙を猫が横切る幻覚を見た。そして、予期された通り、閲覧室にいた全員の心のツッコミが、巨大な津波となって彼に襲いかかった。
『終着駅はあの世だよ!』
『もはやファンタジー通り越してホラー!』
『ジョバンニもカンパネルラもびっくりだわ!』
『ああ、可愛い顔して…脳の構造どうなってんだ…』
ぐらり、と世界が揺れる。誠はカウンターに手をつき、必死に平静を装った。「…宮沢賢治ですね。児童文学の…あちらです」。声が震えなかった自分を褒めてやりたい。
陽菜は「わー、ありがとうございます!」と、満開のひまわりのように笑い、スキップでもしそうな足取りで棚へ向かった。彼女が通った後には、賞賛と呆れが入り混じった心の声の残響が渦を巻いている。
誠は深くため息をついた。彼女がいるだけで、この聖域はノイズの坩堝と化す。彼女の純粋さは、周囲の人々の思考を活性化させ、結果として誠を疲弊させるのだ。
(頼むから、早く本を借りて帰ってくれ…)
誠は心の中で、誰にともなく祈った。このうるさくて、優しさのかけらもない世界から、一秒でも早く解放されたかった。
第二章 嵐を呼ぶ女と無音の謎
皮肉なことに、誠の祈りは決して届かなかった。佐藤陽菜は、まるで誠の心の平穏を奪うために生まれてきたかのように、彼に懐いた。
「田中さんのおすすめの本、すっごく面白かったです!」「この作家さんの他の作品もありますか?」と、カウンターに来るたびに屈託なく話しかけてくる。そのたびに、周囲から『また来たよ、あの天然ちゃん』『司書さん、大変だな…』といった同情的な心のツッコミが聞こえてきて、誠の胃はキリキリと痛んだ。
彼は陽菜を避けようと努力した。彼女の姿が見えると、書庫の整理に逃げ込んだり、他の職員に対応を代わってもらったり。しかし、彼女は不思議と誠を見つけ出し、キラキラした目で話しかけてくるのだ。
誠は混乱していた。陽菜に対する感情は、単純なものではなかった。彼女が引き起こすノイズの嵐にはうんざりしている。だが同時に、その嵐の中心で、何も知らずにニコニコと笑っている彼女を、どこか可哀想に思っていた。誰もが心の中で彼女の言動にツッコミを入れているというのに、彼女自身はそれに全く気づいていない。その無防備さが、痛々しく見えた。
(なぜ気づかないんだ? 普通、少しは空気を読むだろう。なぜ、平気な顔でいられるんだ?)
苛立ちにも似た感情が芽生える。それは、他人の本音という名の刃に常に晒されている誠にとって、陽菜の鈍感さが一種の才能であり、同時に許しがたい無神経さにも思えたからだった。
そんなある日のこと。陽菜が数冊の本を抱えてカウンターにやってきた。その中の一冊が、滑り落ちそうになる。
「あっ」
「危ない!」
誠はとっさに手を伸ばし、落ちかけた本を支えた。その拍子に、彼の指先が、陽菜の温かい手にふわりと触れた。
その、ほんの刹那。
誠の世界から、すべての音が消えた。
いや、違う。閲覧室のページをめくる音や、遠くで聞こえる咳払いは存在している。消えたのは、彼の頭の中に絶えず響いていた「心のツッコミ」だけだった。まるで、防音室に一人でいるかのような、完全なる静寂。三年間、片時も忘れることのなかったあの忌まわしいノイズが、ぴたりと止んだのだ。
誠は呆然と陽菜を見つめた。彼女は「すみません、ありがとうございます!」と、いつものように笑っている。
手を離すと、再びざわざわとした心の声が戻ってきた。しかし、まだ陽菜の手に触れていた時の、あの奇跡的な静寂の感触が、誠の全身に残っていた。
まさか。
彼は一つの仮説にたどり着く。
この佐藤陽菜という女性には、「心のツッコミ」が存在しないのではないか?
彼女は、その言動も思考も、完全に一致している、裏表のない純粋な人間なのではないか?
だから、彼女と触れている間、彼女自身の心の声が聞こえないのはもちろん、彼女の純粋さが一種のシールドとなって、周囲のノイズさえも遮断してくれるのではないか。
誠の胸に、今まで感じたことのない種類の、温かい光が灯った。
このノイズまみれの世界で、唯一の安息の地。それが、彼女の隣なのかもしれない。
誠は初めて、自分の意思で、佐藤陽菜という人間をもっと知りたいと思った。
第三章 史上最大のセルフツッコミ
陽菜が「安息の地」であるという仮説を得てから、誠の世界は少しだけ色を変えた。彼はもう彼女を避けなかった。むしろ、彼女が図書館に現れるのを、心のどこかで待ちわびるようになっていた。彼女との短い会話、カウンターでの何気ないやりとり。その時間は、周囲の心のツッコミが気にならないほど、穏やかで満ち足りたものに感じられた。
(この人は、本当に見たままの人なんだ。疑うことも、皮肉を言うことも知らない。だから、一緒にいると、こんなに楽なんだ)
誠は、陽菜の純粋さに、救いを見出していた。彼の能力は、人間の裏側を暴き出す呪いだったが、陽菜だけがその呪いのかからない、例外的な存在なのだと信じていた。
その日は、図書館で子供向けの読み聞かせイベントが開催されていた。誠は会場の隅で、本の整理をしながらその様子を見守っていた。ボランティアの中に、陽菜の姿があった。エプロンをつけ、少し緊張した面持ちで絵本を抱えている。
「それでは、今日はみんながよく知っている、『桃太郎』のお話です」
陽菜の優しい声がマイクを通して響き渡る。子供たちの期待に満ちた目が、一斉に彼女に注がれた。誠も、思わず作業の手を止め、彼女を見つめていた。
物語は順調に進んでいく。おじいさんは山へ芝刈りに。そして。
「おばあさんは、川へ洗濯に行きました。すると、川上から、どんぶらこ、どんぶらこと…」
陽菜はそこで一度、にっこりと子供たちに微笑みかけ、最高のクライマックスを告げるように、高らかに言った。
「とっても大きなカボチャが、流れてきたのです!」
会場が、一瞬、凍りついた。
次の瞬間、こらえきれなくなった子供たちから、一斉に爆笑が巻き起こった。保護者たちも、顔を見合わせてクスクスと笑っている。シンデレラと桃太郎の奇跡のコラボレーションに、会場は和やかな笑いに包まれた。
誠は、頭を抱えた。来る。史上最大級の、心のツッコミ・ハリケーンが!
彼は咄嗟に耳を塞ごうとした。全国民からの総ツッコミが、彼の脳を破壊する前に。
『カボチャじゃねええええ!』
『馬車に乗って鬼退治かよ!』
『おばあさん、それ魔法使いからもらったやつ!』
しかし、その瞬間。
誠の頭を貫いたのは、それら全ての外野の声を圧倒する、たった一つの、巨大で、クリアで、そして途轍もなく切実な「心のツッコミ」だった。
『―――いや、カボチャじゃなくて桃だって! なんで私、こんな大勢の前でカボチャとか言っちゃってるの!? 恥ずかしすぎる! 穴があったら埋まりたい! いや待て、埋まるんじゃなくて入りたい! もう日本語もめちゃくちゃになってるじゃないの! あー! でもここで止まったらダメ! 笑顔! 笑顔よ私! このカボチャをどうにか桃に着地させるのよ! いける、私ならいける!』
それは、紛れもなく、目の前で顔を真っ赤にしながらも、完璧な笑顔で「あら、大変。おばあさん、間違えちゃったみたい」とアドリブを続けている、佐藤陽菜自身の声だった。
誠は、雷に打たれたように立ち尽くした。
彼女に「心のツッコミ」がなかったわけじゃない。
むしろ、誰よりも激しく、誰よりも高速で、自分自身にツッコミを入れ続けていたのだ。
ただ、そのツッコミは、他人を傷つけるための刃ではなかった。自分の失敗を笑い飛ばし、必死に前を向くための、世界で一番優しくて、愛おしいエールだった。
だから、普段の彼女からは聞こえなかったのだ。彼女が誠に向けていたのは、裏も表もない、純粋な好意と興味だけだったから。
今までノイズだと思っていたものが、全く違う意味を持つ音として、誠の心に響き始めた。
第四章 愛すべきノイズの中で
読み聞かせイベントは、陽菜の機転の利いたアドリブ――「おばあさんが拾ったのは、桃のように甘くて立派なカボチャでした。中から生まれたのは、カボ太郎!」――によって、伝説的な回として幕を閉じた。子供たちは大喜びだった。
イベントの後片付けをしながら、誠はまだ混乱の中にいた。世界の見え方が、根底からひっくり返ってしまったようだった。あれほど忌み嫌っていた「心のツッコミ」が、陽菜のそれを知ってしまった今、少しだけ違って聞こえる。
いつも仏頂面の五十代の男性課長が、若い職員の企画書にダメ出しをしている。
(…ふん、まだまだ青いな。だが、この視点は悪くない。…しかし、ここで褒めたら絶対に調子に乗るからな、この若造は…むむむ…もう少し厳しく…)
いつもヒステリックに怒鳴っている先輩の女性職員が、誠のデスクの上のお菓子を見てため息をついている。
(…私も、ああいう差し入れとかできる可愛い後輩になりたかったわ…言えないけど)
それらは、紛れもなくノイズだった。しかし、そのノイズの奥に、不器用な優しさや、隠された願望、人間らしい滑稽さが透けて見えた。世界は、誠が思っていたよりもずっと複雑で、不器用で、そして少しだけ、愛すべき場所なのかもしれない。
片付けを終え、一人でうなだれている陽菜のところに、誠はゆっくりと歩み寄った。
「佐藤さん」
「…田中さん。ごめんなさい、私、とんでもない失敗を…」
顔を上げた彼女の目は、少し潤んでいた。
誠は、何を言うべきか迷った。そして、自分の心に最も正直な言葉を選んだ。
「いえ。あの…カボチャ、すごく面白かったです」
陽菜は、ぽかんと口を開けて誠を見つめた。彼女の頭の中に『え? 面白い? 慰めてくれてるの? それとも本気!? どっち!?』という高速のセルフツッコミが響き渡り、誠は思わず口元を緩ませた。
彼は、もう一歩踏み出すことに決めた。この呪われた能力を、初めて、誰かのために使ってみようと思った。
「大丈夫です」
誠は、彼女の目をまっすぐに見つめて言った。
「あなたのツッコミは、誰よりも優しくて、面白いですから」
「え…? 私の、ツッコミ…?」
陽菜は不思議そうに首を傾げた。もちろん、彼女に伝わるはずはない。だが、誠の真剣な眼差しに、彼女は何かを感じ取ったようだった。張り詰めていた表情がふっと和らぎ、花が綻ぶように、はにかんだ笑顔を見せた。
「…ありがとうございます。田中さんと話していると、なんだか、どんな失敗も笑い話にできそうな気がします」
その瞬間、二人の間に、言葉を超えた温かい空気が流れた。誠の耳には、相変わらず世界中のノイズが聞こえている。でも、それはもう彼を苛むだけの呪いではなかった。
図書館からの帰り道、夕日に染まる街は、人々の声と、そして声にならない声で満ち溢れていた。車のクラクション、店の呼び込み、恋人たちの囁き。そして、誠の耳にだけ聞こえる、無数の心のツッコミ。
それはまるで、不協和音だらけの、だけどどこか心地よいオーケストラのようだった。
ふと、少し前を歩く陽菜の後ろ姿が見える。彼女の楽しげな鼻歌と一緒に、『今日の夕飯、カレーにしようかな。いや待て、昨日の残り物の肉じゃががあったはず! よーし、今日はリメイク術の見せ所だ!』という、元気な心の声が聞こえてきた気がした。
誠は、たまらなくなって一人で吹き出した。
ああ、なんて世界は、うるさくて、おかしみに満ちているんだろう。
彼は、このノイズフルな世界を、もう少しだけ、愛してみようと心から思った。