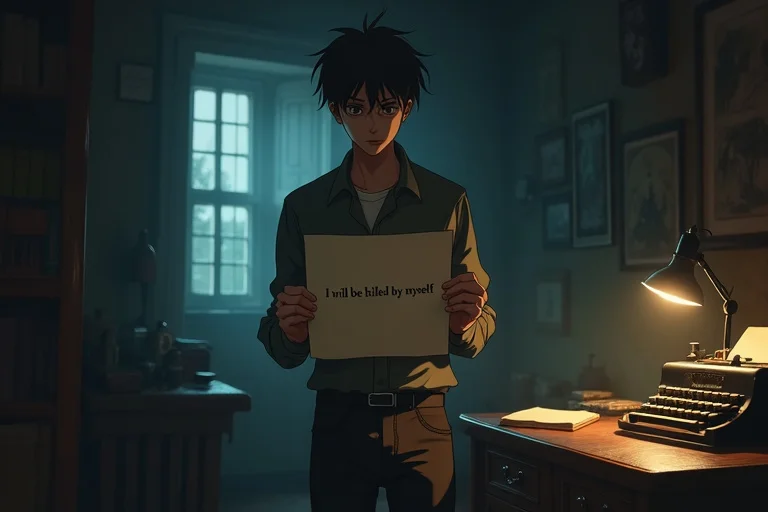第一章 硝子の追憶
警視庁捜査一課の桐谷朔(きりたに さく)が現場のアパートに足を踏み入れた瞬間、死の匂いではなく、微かな潮の香りが鼻腔をくすぐった。被害者は初老の男性。ベッドの上で、まるで眠るように穏やかな顔で息絶えていた。外傷も、毒物の痕跡もない。ただ、静かすぎる死がそこにあった。
異様だったのは、枕元に置かれた一つのオブジェだ。
それは、手のひらに収まるほどの、精巧なガラス細工だった。波打ち際で砕ける白波、濡れた砂の質感、そしてその上にちょこんと乗った小さな巻貝。まるで、夏の日の海岸の一瞬をそのまま切り取って、封じ込めたかのようだ。陽光を受けてきらめくそれは、死の現場にはあまりに不釣り合いなほど美しかった。
「また、これか……」
先輩刑事の渋い声が、桐谷の思考を現実に引き戻す。これで三件目だった。孤独死と処理されかけた最初の事件から、一貫して現場には、被害者の人生における「最も幸福だった瞬間」を具現化したかのような、謎のオブジェが残されている。最初の被害者は元音楽教師で、傍らにはショパンのノクターンが聞こえてきそうな、月光に濡れるピアノの鍵盤のオブジェが。二件目は山岳愛好家で、夜明けの山の稜線を映したかのような、紫水晶のオブジェが。
メディアはこれを「追憶殺人」と名付けた。犯人は被害者の最も美しい記憶を盗み見て、それを形にして残していく、まるで詩人のような殺人鬼。桐谷は、そんな感傷的な見方を鼻で笑いたかった。殺人は殺人だ。そこに詩情など入り込む余地はない。現実はもっと無機質で、動機は金か、怨恨か、あるいは単なる狂気か。彼は事実と証拠だけを信じる。オブジェは犯人が残した自己顕示欲の塊、ただの遺留品だ。そう自分に言い聞かせながらも、桐谷はそのガラスの波間に、見たこともないはずの遠い夏の日の眩しさを感じ、胸の奥が微かにざわつくのを止められなかった。この事件は、彼の信じる世界の輪郭を、静かに溶かし始めている。
第二章 見えざる芸術家
捜査は難航を極めた。三人の被害者に直接的な接点は見当たらず、犯人に繋がる物証は何一つない。共通しているのは、穏やかすぎる死と、あの美しいオブジェだけだ。桐谷は被害者たちの過去を徹底的に洗い直すことにした。デジタルな足跡だけでなく、日記や手紙、知人への聞き込みといった、アナログな情報の海に潜っていった。
そこで、奇妙な共通点が浮かび上がってきた。三人は皆、不治の病を宣告され、余命いくばくもない状態にあったのだ。彼らは絶望の淵で、ある一つの噂に辿り着いていた。
「記憶彫刻家」
それは、インターネットの片隅で都市伝説のように囁かれる、匿名の芸術家の名前だった。依頼人の最も大切な記憶を聞き出し、それを唯一無二の芸術作品にしてくれるという。しかし、そのアトリエの場所も、コンタクト方法も、すべては謎に包まれていた。被害者たちは皆、死の直前、この「記憶彫刻家」を探していた痕跡があった。
「つまり、犯人はこの芸術家を名乗り、終末期にある人間に近づいて殺害した、ということか」
捜査会議で桐谷は断定的に言った。弱った心につけ込み、財産を奪うか、あるいは歪んだ支配欲を満たすための連続殺人。オブジェは被害者を懐柔するための道具に過ぎない。桐谷の推理は明快で、論理的だった。多くの捜査員がその線で頷いたが、彼の心の片隅では、あのオブジェの静謐な輝きがちらついていた。あれは、人を欺くための小道具にしては、あまりにも魂が込められすぎているように思えた。
桐谷は「記憶彫刻家」の正体を追うことに全力を注いだ。特殊なガラスや樹脂を扱う工房、個人の芸術家、アンダーグラウンドのコミュニティ。情報の糸を一つ一つ手繰り寄せていく。そして、数週間後、ついに一つの綻びを見つけ出す。被害者の一人が最後に訪れていた、都心から離れた静かな街。その片隅にある、蔦の絡まる古いレンガ造りのアトリエ。桐谷は確信と共に、その重い扉を叩いた。正義を執行するために。彼の信じる、絶対的な正義を。
第三章 告白のレクイエム
アトリエの中にいたのは、桐谷の想像とは全く違う人物だった。屈強な男でも、狂気を宿した老人でもない。そこにいたのは、水月湊(みづき みなと)と名乗る、透き通るような瞳をした穏やかな青年だった。アトリエには、陽光が差し込み、磨き上げられたガラスの欠片が虹色の光を散らしていた。死の気配などどこにもない、むしろ生の輝きに満ちた空間だった。
「あなたが、記憶彫刻家ですね」
桐谷の問いに、湊は静かに頷いた。「そして、あなたが探している男です」
彼は、あまりにもあっさりとすべてを認めた。三人の死に関わったこと。オブジェを制作したこと。しかし、彼の口から語られた言葉は、桐谷が構築してきた事件の構図を根底から覆すものだった。
「私は、誰も殺してはいません」
湊は言った。彼の声は、アトリエに満ちる光のように、穏やかで澄んでいた。
「私は、人生の最後を迎えようとしている方々から依頼を受け、彼らの物語を聞くのです。人生で最も輝いていた瞬間、魂が震えた記憶。そのお話を伺いながら、共にその情景を心に描き、この手で形にする。それが私の仕事です」
彼が作るオブジェは、特殊な樹脂とガラスを組み合わせたもので、完成までに数週間を要するという。その間、依頼人と湊は、何度も対話を重ねる。それは、死を目前にした人間にとって、自らの人生を肯定し、尊厳を保つための、最後の儀式だった。
「彼らは、自分の人生が確かに美しかったのだと確信して、旅立ちたかった。痛みや苦しみの中ではなく、最も幸せな記憶に包まれて、眠りにつきたかったのです」
湊が差し出したのは、依頼人たちが自らの意思で署名した契約書と、穏やかな表情でオブジェを手に取る彼らの写真だった。湊は彼らの最期を、ただ静かに看取っただけなのだ。殺人ではない。依頼に基づいた、終焉の介添え。
「法がそれを、嘱託殺人というのなら、私は甘んじて罰を受けましょう。ですが桐谷さん、あなたには分かりますか。法という物差しだけでは測れない、魂の形というものが、この世にはあるのです」
桐谷は言葉を失った。彼の信じてきた正義が、白と黒の世界が、ガラガラと音を立てて崩れていく。目の前にいるのは、殺人鬼などではない。人の心の最も深い部分に寄り添う、あまりにも純粋な芸術家だった。何が正義で、何が悪なのか。その境界線が、目の前の虹色の光の中で、急速に溶けていくようだった。
第四章 雨上がりのプリズム
「今夜、最後の依頼を終えます」
湊は、まるで天気の話でもするように告げた。末期の癌を患う老婦人が、彼を待っているという。
桐谷は葛藤した。刑事として、彼を止め、現行犯で逮捕するべきだ。それが職務であり、法だ。しかし、彼の脳裏には、安らかな死に顔と、その傍らで輝いていたオブジェが焼き付いていた。湊の行為を止めることは、一人の人間が望む「幸福な死」を奪うことにはならないか。
数時間の沈黙と逡巡の末、桐谷は一つの決断を下した。彼は警察には連絡せず、一人で湊が向かった古い洋館を訪れた。扉を開けると、そこにはベッドに横たわる老婦人と、その手を握る湊の姿があった。部屋には、優しいアロマの香りが満ちている。
婦人の枕元には、小さなオルゴールのオブジェが置かれていた。亡き夫との初デートで聞いた、思い出の曲を奏でている。
「ありがとう、湊さん。これで、安心してあの人のところへ行けるわ……」
婦人は、オブジェを胸に抱きしめ、微笑みながら、ゆっくりと目を閉じた。それは、桐谷がこれまで見てきた、どの死よりも穏やかで、尊厳に満ちた最期だった。
湊は静かに立ち上がり、桐谷に向かって言った。「私の仕事は、終わりました」
彼は抵抗することなく、桐谷に両手を差し出した。
数年後。桐谷は捜査一課を離れ、犯罪被害者やその遺族の心のケアを専門とする部署にいた。彼のデスクの上には、小さなガラスの置物が一つある。それは湊が作ったものではない。ただのガラスの塊が、光を受けて七色のプリズムを描いているだけだ。
桐谷は、今も時折、考える。法とは何か。正義とは何か。そして、人が生き、死ぬことの意味とは何か。答えはまだ見つからない。だが、彼は知っている。この世界は、白と黒だけで割り切れるほど単純ではないことを。その間にある無限のグラデーションの中にこそ、人の心の痛みや、愛や、そして魂の輝きが隠されているのだということを。
雨上がりの空にかかる虹のように、儚く、そして美しいその輝きを、彼はもう見失うことはなかった。