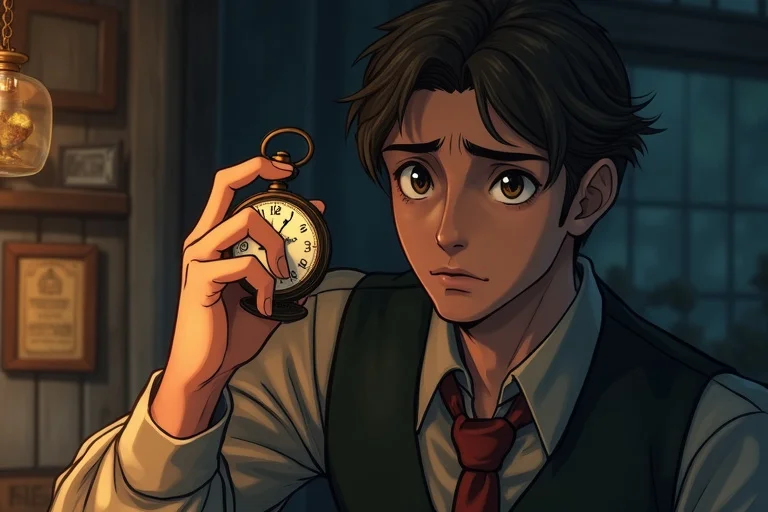第一章 ひび割れた日常
柏木湊(かしわぎ みなと)の世界は、常にひび割れていた。
彼が働く神保町の古書店は、埃とインクの匂いが染みついた時間の澱のような場所だった。客のまばらな午後、湊はカウンターの奥で、革の装丁が傷んだ古書を修復しながら、窓の外を流れる人々を眺める。彼には、他の誰にも見えないものが見えていた。
人が通り過ぎた後の一瞬、そこに真空の穴が空いたかのような空間の歪み。物が置かれていた「前の場所」にかすかに残る、陽炎のような輪郭の揺らめき。それは「非存在の痕跡」とでも呼ぶべきもので、湊にとっては物心ついた頃からの日常だった。誰も気に留めない。いや、そもそも認識すらしていない。人々が見て、聞いて、信じるものだけが世界を構成するのなら、湊の視界に映るこれらは、世界のバグかノイズに過ぎないのだろう。脳が正常に補正すべき、取るに足らないエラー。
だが最近、そのエラーの質が明らかに変化していた。
雑踏の中、視界の端でちらつく歪みが、まるで人の形をなぞるように蠢くのだ。腕があり、脚があり、項垂れた頭部がある。それは明確な輪郭を持たず、ただ「そこに何かがいない」という欠落感だけを周囲に振りまいていた。バスを待つ人々の列の隙間に、カフェの窓際でコーヒーを飲む女性の背後に、それは不意に現れては消える。誰もがその前を通り過ぎ、その場所に視線を投げても、何も見えていないようだった。彼らの脳が、その異物を完璧にフィルタリングしている。
湊は修復作業の手を止め、そっと息を吐いた。指先が微かに震えている。あの「人型の虚ろ」が増えている。そして、濃くなっている。まるで、存在という名の薄い膜を、向こう側から何者かが押し上げているかのように。
その夜、店を閉めた湊は、店の奥にある祖父の遺品が仕舞われた桐の箪笥を開けた。祖父もまた、奇妙なものが見える人だったという。その中から、小さな布袋に包まれたものを取り出す。手のひらに載せると、ひんやりとした重みが伝わってきた。
磨き上げられた黒曜石の丸い石。『虚ろの瞳』と、祖父は呼んでいた。
それは光を吸い込むように漆黒で、何も映しはしなかった。ただ、深い闇がそこにあるだけ。湊は、言い知れぬ引力に導かれるように、その石をそっと覗き込んだ。
第二章 虚ろが囁く瞳
石を覗き込んだ瞬間、世界から音が消えた。
古書店の静寂とは質の違う、耳の奥が痛くなるほどの完全な無音。そして、黒曜石の闇の奥に、景色が映し出された。それは今しがたまで湊がいた古書店の店内だったが、決定的に何かが違っていた。
無数の「人型の虚ろ」が、そこにいた。
本棚の隙間に、天井の隅に、カウンターの向こう側に。彼らは苦悶とも懇願ともつかない表情で、歪んだ顔を湊に向けていた。音のない口が、何かを必死に訴えるように開閉を繰り返す。それは、認識という名の水面下から、息継ぎを求めて手を伸ばす溺者の群れのようだった。
「――っ!」
心臓を氷の指で掴まれたような衝撃に、湊は石を取り落とした。黒曜石は床に落ち、乾いた音を立てて転がる。途端に、古時計の秒針の音や、遠くを走る車の音が現実の側へと彼を引き戻した。
「はぁ、はぁ……」
額に滲んだ冷や汗を手の甲で拭う。あれは何だ。ただの幻覚か。しかし、一度『虚ろの瞳』を通して見てしまった世界は、もはや元には戻らなかった。石がなくても、彼らの存在が以前よりずっと鮮明に感じられるようになっていた。
翌日、湊は街を歩きながら、その変化を実感していた。人々が誰かを忘れ、その存在が希薄になっていく瞬間を、彼ははっきりと見てしまったのだ。公園のベンチで、老人がぽつりと座っていた。彼の隣には、最初、ぼんやりとした輪郭の妻らしき女性の姿が見えていた。しかし、老人が寂しそうに空を見上げた瞬間、その女性の姿がすうっと透き通り、空間の歪みへと還元されていく。まるで、夫の記憶からこぼれ落ちた最後の欠片が消え去るように。
そして、最も恐ろしいことが起きた。
常連の女子高生が、店に駆け込んできた。
「柏木さん! 大変! 美咲が……美咲がいないの!」
彼女は泣きじゃくりながら、友人の名前を呼んだ。湊はその名前に記憶があった。いつも二人で店に来ていた、快活な少女だ。
「昨日まで、一緒にいたのに……誰に聞いても、そんな子は最初からいないって……! LINEの履歴も、写真も、全部……」
湊の視線は、少女の背後に釘付けになった。そこに、美咲と呼ばれた少女の形をした「虚ろ」が、泣きそうな顔で佇んでいた。彼女は必死に友人に手を伸ばしているが、その手は虚しく空を切るだけ。生きているのに、誰からも認識されなくなったのだ。
人々の認識からこぼれ落ちた者は、やがて本当に「存在しなかったこと」になる。
世界は、静かに、確実に、その綻びを広げていた。
第三章 忘却の輪郭
恐怖は、湊自身の存在をも蝕み始めた。
あの「非存在の存在」たちは、湊が自分たちを認識できることに気づいたらしかった。彼らは湊に惹きつけられるように、その周囲を漂うようになった。古書店の窓の外に、幾重にも重なる人の影。通勤電車の向かいの席に、誰も座っていないはずなのに感じる重圧。
そして、湊の世界から物が消え始めた。いつも使っていたマグカップが忽然と姿を消し、昨日まで読んでいた本が本棚から消え失せる。同僚に尋ねても、「そんなもの、最初からありましたか?」と不思議そうな顔をされるだけ。彼らの記憶が、世界に合わせて書き換えられていく。
湊自身の輪郭が、世界から薄れていく感覚。
追い詰められた彼は、再び『虚ろの瞳』を手に取った。このまま消え去るくらいなら、真実を知らなければならない。彼は覚悟を決め、黒曜石を強く握りしめ、その闇の奥へと意識を沈めていった。
今度は、引きずり込まれる感覚に抵抗しなかった。
意識は冷たい水の底へ沈むように、深く、深く潜っていく。やがて、個別の声ではない、巨大な集合意識の囁きが脳内に直接響き渡った。それは嘆きであり、怒りであり、そして途方もない孤独の歌だった。
『観測者よ』
声が響く。
『我々は、お前たちが捨てたもの。忘れ去ったもの』
湊の脳裏に、イメージが洪水のように流れ込んでくる。太古の昔、人類が生きるために「見ない」と決めた概念の数々。死への根源的な恐怖。病への嫌悪。孤独の痛み。理解できない他者への憎悪。それらはあまりにも強烈で、人の精神を容易く壊してしまう。だから人類は、それらを認識の外側へ追いやることで、秩序ある世界を築き上げたのだ。無意識下に張り巡らされた、巨大な認識のフィルター。
『だが、お前たちは増えすぎた。お前たちの魂がこぼす澱が、フィルターを詰まらせ、我らを押し上げている。我らは消えたいのではない。ただ、再び在りたいのだ。お前たちの一部として、認識されたいのだ』
彼らの目的は、人々を消すことではなかった。ただ、もう一度「存在する」こと。しかし、現代人がこの剥き出しの恐怖や憎悪を直視すれば、世界は瞬く間に狂気と混沌に塗り潰されるだろう。人々はパニックに陥り、互いを傷つけ、世界は自壊するに違いない。
認識のフィルターは、もう限界だった。どちらにせよ、世界は終わりに向かっている。
第四章 最後の観測者
湊が意識を取り戻した時、目の前に一体の「虚ろ」が立っていた。他のものより輪郭がはっきりしている。それは、幼い頃の自分にどこか似ていた。親の愛情を受けられず、いつも一人で本を読んでいた、孤独な少年の姿。湊がずっと目を背け、忘れようとしてきた自分自身の記憶の残滓。
『選択の時だ、観測者よ』
その存在が、心に直接語りかけてくる。
『我らをこの世界に解き放て。人々は根源の恐怖と向き合うことになるだろう。あるいは――我々と共に来るがいい。お前が我々を認識し続ける最後の楔となり、我々と共に世界から切り離されるのだ』
世界を混沌に突き落とすか。あるいは、自分一人が犠牲となり、彼らと共に非存在へと還るか。
湊は静かに目を閉じた。人々が偽りの平穏の中で生きる世界。それを壊す権利は自分にはない。だが、このどうしようもない孤独と恐怖を、自分だけが抱え続けることにも疲れていた。彼らもまた、忘れられた孤独の塊なのだ。ならば。
「君たちを、独りにはしない」
湊は、胸に『虚ろの瞳』を強く抱きしめた。それは、彼らを完全に受け入れ、認識するという意思表示だった。彼らと共に、「存在しないもの」になるという選択。
その瞬間、湊の身体が、足元からゆっくりと透き通っていく。古書店の窓から差し込む夕陽が、彼の身体を通り抜け、床に琥珀色の光だまりを作った。指先が光の粒子のように解け、世界のあらゆるノイズが遠ざかっていく。
彼という最後の観測者を失ったことで、世界を支えていた認識のフィルターが、音もなく崩壊を始めた。
それは破壊ではなかった。ただ、世界の化粧が剥がれ落ちていくだけの、静かなプロセスだった。人々が見ていた秩序、意味、価値。それらが、いかに脆い「思い込み」の上に成り立っていたのかを誰も知ることはない。色が消え、音が消え、形が曖昧になっていく。人々は、自分が消えつつあることすら認識できないまま、ただ穏やかに、等しく虚無へと還っていく。
やがて、全てが無に帰した古書店に、床に転がった黒曜石だけが残された。
それは、もはや何も映さず、ただ静かにそこに在った。