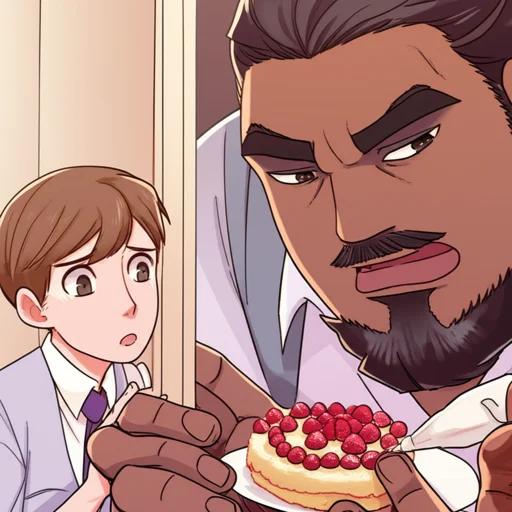第一章 親父の、スベり知らずの遺言
田中健司(たなか けんじ)、四十二歳、独身。市役所の固定資産税課に勤める彼の人生は、まるで寸分の狂いもなく組まれたエクセルの計算式そのものだった。朝六時半に起床し、七時十五分に家を出る。寸分違わず同じ電車に乗り、同じ車両の同じドアの前に立つ。昼食は愛妻弁当ならぬ〝愛自分〟弁当。夜は栄養バランスを計算した自炊。彼の世界では、予定外の出来事はバグであり、即刻修正されるべきエラーだった。
そんな彼の完璧な日常に、最大のシステムエラーが発生したのは、一月前のことだ。十年前に母を亡くして以来、一人暮らしをしていた父、雄一郎が、あっけなくこの世を去った。享年七十二。病院からの電話は、健司が翌年の家計簿の予算を立てている、まさにその最中にかかってきた。
父の遺品整理は、健司にとって苦痛な作業だった。几帳面な自分とは正反対の、雑然とした実家。ガラクタとしか思えないものが、部屋のあちこちに積み上がっている。押し入れの奥から出てきた段ボール箱には、古びたカセットテープが一本、埃をかぶって眠っていた。マジックで、父の丸っこい字でこう書かれている。
『人生最後のネタへ』
健司は眉をひそめた。ネタ? 父が冗談を言う姿など、記憶の限り一度もない。厳格で、無口で、感情を表に出さない人だった。興味本位で、そばにあったラジカセにテープを入れる。再生ボタンを押すと、ジーッというノイズの後に、咳払いが一つ。そして、聞き慣れた父の声が響いた。
「えー、どうも。天国亭福笑(てんごくてい ふくしょう)です」
健司は思わずラジカセを止めた。天国亭福笑? なんだそれは。再び再生すると、父は立て板に水、とは到底言えないたどたどしさで、親父ギャグを連発し始めた。
「布団が吹っ飛んだ!…えー、続きまして、アルミ缶の上にあるミカン…」
絶望的に、面白くなかった。スベっているとか、そういう次元ではない。聞いているだけで眉間のシワが深くなるような、純度百パーセントの駄洒落の連鎖。健司はこめかみがズキズキ痛むのを感じながら、テープを止めようとした。その瞬間、父の声のトーンが変わった。
「…健司、これを聞いているか。俺の、人生最後の願いだ」
健司は息を呑んだ。
「このテープに録音したネタを、お前が、浅草演芸ホールの舞台で、俺の代わりに披露してくれ。頼む。これが、親父のたった一つの遺言だ」
ブツッ、と音を立ててテープは終わった。静寂が部屋を支配する。健司は、ラジカセの前で立ち尽くした。脳内の処理能力を完全に超えた命令。父は、売れないコメディアンに、なりたかった…? あの厳格な父が? そして、この、面白さの欠片もないネタを、真面目一徹の自分が、演芸場の舞台でやれ、と?
これはバグだ。人生最大のバグに違いない。健司はそう結論付け、ラジカセの電源を切り、遺言を心のゴミ箱にドラッグ&ドロップした。
第二章 笑えない男とウケないネタ
遺言を無視して一週間。しかし、父の最後の言葉は、健司の脳内にウイルスのように潜伏し、彼の完璧なルーティンを少しずつ蝕んでいた。電車の吊り広告を見れば「このキャッチコピーはスベってるな」と考え、上司の退屈な朝礼を聞きながら「これも一種のネタか」と分析している自分に気づき、愕然とする。
健司はついに根負けし、再び実家を訪れた。父の書斎だった部屋を改めて探すと、本棚の裏から、使い古された大学ノートが数冊出てきた。表紙には『ネタ帳』と書かれている。
ページをめくると、そこにはカセットテープに録音されていた駄洒落が、びっしりと書き込まれていた。だが、それだけではなかった。ネタの横には、小さな文字で、日々の出来事が日記のように添えられていたのだ。
『昭和五十五年四月十日。健司、生まれる。俺に似ず、泣き声がデカい。将来はオペラ歌手か。…よし、今日のネタ。「赤ちゃんが泣いてる理由は、あ、母ちゃんがいないから」…うーん、却下』
『昭和五十六年五月三日。健司、立った。二本の足で立った! 人類の進化を見た。…ネタ。「立った健司に、拍手喝采(拍手貸っさい!)」…よし、採用』
ページをめくるたび、健司の知らない父の姿が現れた。不器用な文字で綴られる、息子への愛情。厳格な父の仮面の下で、こんなにもおどけて、こんなにも温かい眼差しを自分に向けていたのか。健司は、ノートのインクが滲んだ跡を見つめながら、知らず知らずのうちに涙が頬を伝っていることに気づいた。
健司は、ノートに書かれたネタを一つ、声に出して読んでみた。
「幽霊の弱点って、なーんだ?…答えは、霊に不言実行(例に不実行)…」
声に出した途端、そのあまりのくだらなさに、フッと息が漏れた。それは、笑いと呼ぶにはあまりに不格好な、しかし紛れもない笑いだった。
数日後、健司はネタ帳に書かれていた住所を頼りに、浅草の場末にあるスナック「止まり木」のドアを叩いた。カウンターの中には、紫色の髪をした、年齢不詳のママが座っていた。
「雄一郎さんの息子さんかい。面影があるねえ」
ママはそう言うと、健司に一杯のウーロン茶を出してくれた。
「お父さんね、いっつもカウンターの隅で、新しいネタを考えては、あたしに披露してくれたよ。まあ、一度もウケたこたぁなかったけどね」
ママはカラカラと笑った。
「でもね、あのお父さんの周りには、いつも人がいたんだ。スベるんだけど、一生懸命でさ。その姿がなんだかおかしくて、愛おしくて、みんな、お父さんのことが大好きだったんだよ」
ママの言葉は、健司の胸に温かいインクのように染み込んでいった。父は、スベり続けていた。それでも、人を笑わせようとし続けていた。その不器用な情熱が、人を惹きつけていた。
健司はウーロン茶を飲み干すと、顔を上げた。その目には、これまで見せたことのない光が宿っていた。
「ママさん。浅草演芸ホールの支配人、ご存知ないですか」
第三章 たった一人のためのアンコール
本番当日。浅草演芸ホールの楽屋は、線香と古い木の匂いがした。鏡の前に座る健司は、いつもの寸分の狂いもない七三分けではなく、少しだけ無造作に整えられた髪をしていた。心臓が、これまで経験したことのない不規則なリズムで高鳴っている。市役所の窓口でどんなに怒鳴られても動じなかった自分が、今、数分後のステージに足がすくむほどの恐怖を感じていた。
ママさんの口添えで、平日の昼間の、客が一番少ない時間帯に「新人お試し」という名目で五分だけ時間をもらうことができた。それでも、舞台は舞台だ。
「本当に、ウケるんだろうか…」
健司は、お守りのように持ってきた父のネタ帳を、震える手で開いた。最後の確認だ。一つ一つのネタを目で追い、ブツブツと呟く。そして、最後のページにたどり着いた時、健司は息を呑んだ。これまで気づかなかった、ページの隅に、鉛筆で書かれた走り書きがあった。それは、他の文字よりもずっと新しく、そして弱々しい筆跡だった。
『健司へ。
もし、万が一、お前が本当にこの馬鹿げた遺言を実行してくれたなら。
親父からの、最後の種明かしだ。
このネタは、ウケなくていい。いや、ウケるはずがない。
これは、たった一人の観客…つまり、お前を笑わせるためのネタなんだ。
お前は昔から真面目すぎて、眉間にシワを寄せてばかりだったからな。
親父の最後の悪ふざけで、腹の底から『くだらない!』って笑ってくれれば、それで本望だ。
達者でな。
父、雄一郎より』
健司の目から、大粒の涙がぼろぼろとこぼれ落ち、ネタ帳の上に染みを作った。
そうか。そうだったのか。
父の目的は、観客を沸かせることではなかった。売れないコメディアンの無念を晴らすことでもなかった。すべては、この、笑うことが下手くそな、たった一人の息子のために仕組まれた、壮大で、不器用で、そして最高に優しい「フリ」だったのだ。
人を笑わせなければ、という重圧が、すぅっと消えていく。代わりに、胸の奥から、温かい何かが込み上げてきた。それは、父への感謝と、愛おしさと、そして計り知れないほどの愛情に対する、どうしようもない可笑しさだった。
「…次は、本日が初舞台! 天国亭福笑ジュニアの登場です! 皆様、温かい拍手を!」
舞台袖から、張りのある声が聞こえた。健司は涙を拭うと、すっくと立ち上がった。その顔にはもう、恐怖の色はなかった。
第四章 カーテンコールのない人生で
スポットライトが眩しい。客席は、まばらだった。十数人の客が、物珍しそうにこちらを見ている。健司はマイクの前に立つと、深々と頭を下げた。
「どうも。天国亭福笑ジュニア、と申します」
一瞬の間。健司は、客席の片隅で心配そうに見守るママの姿を捉えた。そして、息を吸い込む。
「先日、親父が亡くなりまして。遺言が、『俺のネタをやれ』と。…というわけで、一席、お付き合いください」
健司は、父のたどたどしい口調を真似るのではなく、ただ淡々と、まるで市役所で書類を読み上げるかのようにネタを始めた。
「幽霊の弱点って、なーんだ?…霊に不言実行(例に不実行)」
シーン。客席は、完璧な静寂に包まれた。誰一人、笑っていない。だが、健司の心は不思議と穏やかだった。
「続きまして。校長先生が、絶好調!」
シーン。
健司は、ネタを一つ言うたびに、父との思い出がフラッシュバックした。キャッチボールをした公園。初めて自転車に乗れた日。叱られた時の、あの大きな背中。そして、ネタ帳に綴られた不器用な愛情。
厳格だと思っていた父が、陰でこんなくだらないことを考え、それを自分に披露する日を夢見ていた。その滑稽さと愛おしさに、健司の口元が自然と綻んだ。
「アルミ缶の上にある、ミカン…」
言いながら、クツクツと笑いが込み上げてくる。涙が滲み、視界が歪む。
「布団が、ふっ、飛んだ…!」
ついに、こらえきれずに吹き出してしまった。涙を流しながら、肩を震わせて笑う健司の姿に、客席は完全に困惑している。なんだ、この状況は。あの芸人は、自分で言ったネタで泣き笑いしているぞ。
それでも健司は、最後のネタまでやりきった。涙でぐしゃぐしゃの顔で、もう一度、深々と頭を下げる。拍手は、なかった。ただ、やりきったという晴れやかな満足感だけが、胸を満たしていた。
舞台袖に戻ると、ママが泣き笑いの顔で立っていた。
「健司ちゃん…。あんたの親父さん、今日初めて、大爆笑とったじゃないか。あんた、っていう最高の観客からさ」
後日。健司は市役所の窓口に座っていた。
「俺たちの税金で食ってるくせに、なんだその態度は!」
市民からのクレームに、以前の健司なら「規則ですので」と無表情に返していただろう。だが、今の健司は違った。心の中で、フッとこう思った。
(うまいこと言うなあ。座布団一枚、かな)
人生は、エクセルの計算式のように計画通りにはいかない。エラーやバグだらけだ。でも、その予測不能な不条理さこそが、案外、面白いのかもしれない。
その夜、健司は自宅の仏壇に置かれた父の遺影に向かい、線香をあげた。そして、少し照れながら、こう言った。
「親父、聞いてくれるか。…仏壇に飾る花が、仏頂面してるよ」
誰もいない部屋に、健司の声だけが響く。完璧なまでに、スベっていた。
しかし、健司は満足そうに微笑んだ。その顔から、長年住み着いていた眉間のシワは、綺麗さっぱり消え去っていた。人生というカーテンコールのない舞台で、彼は確かに、笑いの楽しみ方を知ったのだ。