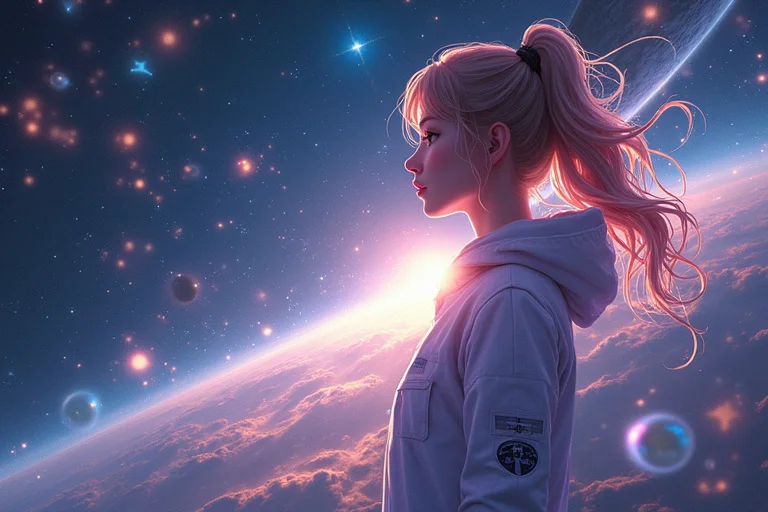第一章 硝子細工の追憶
俺の仕事は、壊れた記憶を修復することだ。人は俺たちを「記憶修復士(メモリー・リペアラー)」と呼ぶ。クライアントから預かった破損した記憶データ(メモリー・フラグメント)の深淵に精神をダイブさせ、失われた情報の断片を繋ぎ合わせ、再び鑑賞可能な形に復元する。それはまるで、砕け散った硝子細工をピンセットで組み上げるような、途方もなく繊細で孤独な作業だった。
俺、カナタはこの仕事で、業界でも指折りの腕利きとして知られていた。他人の過去に深く潜り、幸福、後悔、愛情、憎悪といった生の感情の奔流に身を浸す。だが、皮肉なことに、俺自身には修復すべき過去が存在しなかった。七年前の軌道エレベーター落下事故。俺はその事故で、それ以前の自身の記憶のほとんどを失っていた。俺の過去は、ノイズの走る真っ白な映像でしかない。だからこそ、他人の鮮やかな記憶に触れることで、自らの空虚を埋めているのかもしれない。
そんなある雨の日、一件の奇妙な依頼が舞い込んだ。ホログラムで現れた依頼人「リナ」は、感情の読めない滑らかな声でこう言った。
「修復をお願いしたい記憶データがあります。ただし、これは私の記憶ではありません」
「では、どなたの?」
「……分かりません。偶然手に入れた、持ち主不明のフラグメントです」
通常なら、身元不明のデータの修復など、倫理規定に触れるため即座に断る案件だ。だが、彼女が転送してきたプレビューデータを見て、俺は息を呑んだ。
断片的な映像のノイズの向こうに、見覚えのある光景が広がっていた。潮風に錆びた白い灯台。どこまでも続く青い海。そして、二人の子供の甲高い笑い声。それは、俺が時折見る、意味不明な夢の光景そのものだった。なぜ、見ず知らずのデータの中に、俺の失われたはずの原風景が存在するのか。
「この依頼、お受けいただけますか?」リナの静かな声が、思考の渦に沈んでいた俺を引き戻した。
胸の奥で、冷たい何かが疼く。これは罠かもしれない。だが、もし、この硝子細工の追憶の欠片が、俺自身の失われた過去に繋がっているとしたら?
俺は乾いた唇を舐め、答えた。「……ええ。引き受けましょう」
その瞬間、俺はただの記憶修復士ではなく、自身の過去を追う探索者になっていた。
第二章 海鳴りのラビリンス
記憶データへのダイブは、冷たい水に全身が沈んでいく感覚に似ている。意識が肉体を離れ、0と1で構成された情報の海へ溶けていく。今回のデータは、これまで経験したことがないほど破損がひどかった。まるで悪意をもって破壊されたかのように、重要なシーケンスが引き裂かれ、ノイズの嵐が吹き荒れている。
俺は慎重に情報の残骸を拾い集め、パズルのピースを嵌めるように修復を進めた。数日後、最初の鮮明なシーンが復元された。夏の陽光が降り注ぐ砂浜。二人の少年が、夢中で砂の城を作っている。一人は快活そうな顔立ちで、もう一人は少し内気な印象だ。彼らの笑顔を見るたび、胸の奥深くに忘れていた温かい感情が湧き上がってくる。肌を撫でる潮風の感触、微かな磯の香り、遠くで鳴くウミネコの声。五感が、記憶の風景を現実として立ち上がらせる。これは、俺の記憶だ。そう確信せずにはいられなかった。
定期的に進捗を報告するたび、依頼人のリナと短い会話を交わした。彼女の言葉は常に冷静で無機質だったが、時折、その声のトーンに微かな揺らぎが感じられた。
「……その灯台は、今でも立っているのでしょうか」
修復した灯台のシーンについて報告した時、彼女はぽつりと尋ねた。まるで、その場所を知っているかのように。
「さあ。ですが、記憶の中では、世界の終わりのように静かに、ただそこに在り続けています」
俺がそう答えると、彼女は少しの間沈黙し、「……そうですか」とだけ呟いた。彼女は何者なのだ。なぜこの記憶を俺に託したのか。疑念と同時に、彼女との間に奇妙な共感が芽生えているのを感じていた。
修復は核心に近づいていく。少年たちの無邪気な日々。秘密基地での約束。そして、いつも彼らを見守るようにそびえ立つ、あの白い灯台。この記憶の持ち主は、間違いなく俺だ。この美しい過去を取り戻せば、俺の人生を覆う霧は晴れるのだろうか。空虚だった心は満たされるのだろうか。期待と不安が入り混じりながら、俺は最後の破損領域――記憶が途絶える直前の、最も激しいノイズの嵐へと、精神をダイブさせた。
第三章 二人で一つの記憶
最後の領域は、情報の地獄だった。引き裂かれた悲鳴、金属の軋む音、赤い閃光。あらゆるデータが渾然一体となり、俺の精神を削り取っていく。これが、俺の記憶を奪った事故の瞬間なのか。恐怖に耐えながら、俺は最後のピースを繋ぎ合わせた。
そして、世界は再構築された。
そこは、古い研究施設の一室だった。医療ポッドが並び、モニターには複雑な生体データが映し出されている。ポッドの一つに、先ほどの快活そうな少年が横たわっていた。彼の頭には痛々しい治療痕があり、生命維持装置に繋がれている。彼の名は「ソウタ」。記憶の断片から、俺は彼の名前を思い出した。俺の、たった一人の親友だ。
そして、その傍らに、幼い俺が立っていた。泣きじゃくる俺に、白衣の研究者が静かに語りかける。
「……彼の脳は深刻なダメージを負っている。このままでは、記憶野が完全に崩壊してしまう。助ける方法は一つしかない」
研究者が示したのは、「記憶転写(メモリー・トランスファー)」という非合法技術だった。健康なドナーの記憶野の一部を、損傷した脳に移植する。成功すればソウタの記憶は保たれるが、ドナーは移植した分の記憶を永久に失う。
「やるよ」
幼い俺は、涙を拭って即答した。「ソウタが忘れてしまうくらいなら、僕の記憶をあげる。僕がソウタの分まで覚えていればいい。僕たちは、二人で一つの記憶なんだから」
俺は愕然とした。俺は記憶を「失った」のではなかった。自らの意思で「与えた」のだ。俺が今まで自分のものだと思っていた美しい追憶は、ソウタの中に生き続けさせるために、俺が手放した宝物だった。空虚感の正体は、喪失の悲しみではなく、半身を切り離したことによる、途方もない寂しさだったのだ。
全ての記憶が修復された瞬間、リナから通信が入った。
「カナタ。……ありがとう」
その声は、もはや無機質なAIのものではなかった。温かく、懐かしい、あの頃のソウタの声の面影があった。
「リナ……君は、一体」
「私は、ソウタが開発したインターフェースAIです。彼はあの日から、自分の体を動かすことができません。ですが、君から貰った記憶が、彼の心を支えてきました。しかし近年、その記憶データが経年劣化で破損し始めたのです。彼は、君との宝物が消えてしまうことが、何より怖かった」
モニターに映像が切り替わる。そこには、生命維持装置の中で静かに横たわる、青年の姿があった。ソウタだ。彼は話すことも動くこともできない。だが、その瞳は確かに俺を見つめ、涙の粒が頬を伝っていた。
「君なら、この記憶を完璧に修復してくれると信じていました。正体を明かせば、君が苦しむと思って言えなかった。……許してください」
リナの声が、震えていた。
第四章 クロノス・ダイバーの夜明け
修復された完全な記憶が、俺とソウタの意識の中で同時に再生される。
夕暮れの灯台の上。二人の少年が指切りをしている。
「約束だ、カナタ。もし僕が君を忘れても、君が僕を覚えていて。僕たちが離れ離れになっても、この灯台が目印だ」
「うん。僕たちが忘れても、灯台が覚えていてくれる。僕たちは、二人で一つの記憶なんだ」
そうだ。俺は忘れていたんじゃない。ソウタに預けていただけだ。俺たちは、ずっと繋がっていた。
俺はモニター越しの親友に語りかけた。
「ソウタ。俺は空っぽじゃなかった。お前がいたから、俺はずっと一人じゃなかったんだ。ありがとう。俺たちの宝物を、守ってくれて」
ソウタの目が、穏やかに細められたように見えた。
あの日以来、俺の世界は色を取り戻した。記憶修復士の仕事は続けている。だが、もう虚しさを埋めるためではない。砕けた記憶の欠片一つ一つに、誰かの大切な絆や、守りたかった想いが宿っていることを、俺は知っているからだ。
今夜も、俺は自室の窓から煌めく街の夜景を見下ろしている。無数の光の点滅は、まるで遠い星々の瞬きのようだ。その一つが、どこかで俺を見ているソウタの光なのかもしれない。
俺の過去は、もうノイズの走る白紙ではない。そこには、友のために半身を捧げた少年の、誇り高い選択があった。失われた記憶は戻らない。だが、それでいい。俺たちは、これからも二人で一つの記憶を生きていく。遠く離れていても、同じ星空の下で。
俺は静かに微笑み、夜の街に呟いた。
「聞こえるか、ソウタ。今夜も、星が綺麗だぜ」
返事はない。だが、一番強く輝く星が、一度だけ瞬いた気がした。