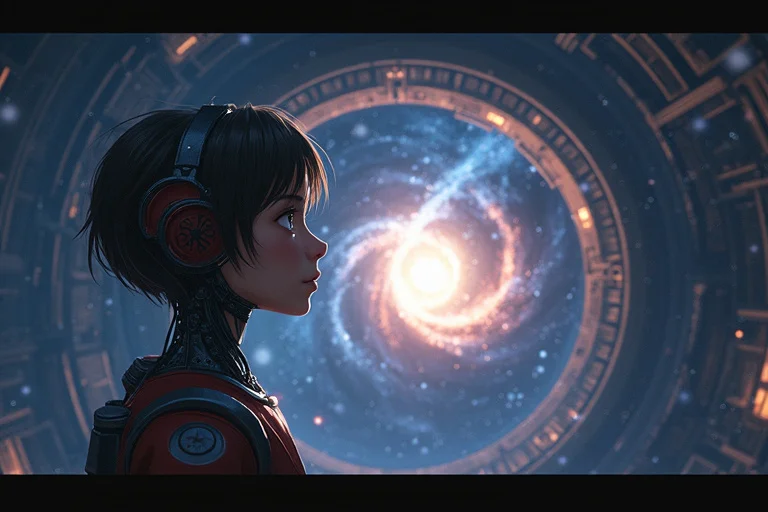第一章 霧と琥珀の欠片
灰色の霧が、世界のすべてを覆い尽くしていた。毎朝、人々は昨日の自分を失って目覚める。忘却の霧は、思い出という名の脆い砂の城を、容赦なく洗い流していくのだ。だが、魂を揺さぶるほどの激情だけは、胸の奥で硬質な「記憶の結晶」となり、かろうじて「私」という存在の輪郭を繋ぎとめていた。
俺の名は、おそらくカイという。それすらも、霧の中で拾い上げた誰かの記憶の残響かもしれない。俺には、他者の記憶の断片を精神に取り込み、その過去を追体験する呪いとも祝福ともつかぬ能力があった。だが、その代償は重い。誰かの生をなぞるたびに、俺自身の存在の記録はインクが滲むように薄れていく。鏡に映る顔の輪郭は日に日に曖昧になり、街の喧騒の中で、俺はまるで幽霊のように誰にも気づかれずにすり抜けられるようになっていた。
俺をこの世界に繋ぎとめているのは、たった一つの謎。己の精神の奥底、決して霧に溶けることのない、一つの強固な記憶の結晶。それは、誰かの温かい手に包まれた感触。雨上がりの土の匂い。そして、耳の奥で微かに響く、優しい子守唄のようなメロディ。この琥珀色の結晶が誰のもので、なぜ俺の中にあるのか。それを知ることだけが、俺の唯一の存在理由だった。
右手に握りしめた古びた真鍮製の「残響計(エコーグラフ)」が、冷たい感触を伝えてくる。懐中時計のようなその蓋を開くと、ガラス盤が静かに脈動した。霧の中に漂う微弱な記憶の波動を捉え、感情の色彩を光の波紋として映し出す装置。俺は針が示す方角へと、音もなく歩き出した。今日の残響は、古い図書館の裏手、蔦の絡まる石壁から放たれている。
壁に手を触れ、残響計をかざす。ウィーン、と澄んだ音叉のような音が鳴り、ガラス盤に柔らかな光の波紋が広がった。――琥珀色。また、あの日と同じ色だ。
俺は躊躇わず、その記憶を精神に流し込んだ。
世界が歪む。視界に映るのは、俺のものではない光景。インクの匂いが満ちる静かな部屋。窓辺には一輪挿しの白い花。そして、一人の女性が、ペンを走らせながら静かに微笑んでいる。その指先が、ふと、窓の外の灰色の空を見上げた。
『あなたを、忘れないために』
声にならない声が、魂に直接響く。その瞬間、俺の身体から何かが抜け落ちていく感覚に襲われた。足元が揺らぎ、世界が遠のく。俺は石壁に背を預け、荒い息をついた。また一つ、俺は俺でなくなっていく。
第二章 器の輪郭
琥珀色の残響を追い求める旅は、俺自身の存在を削り取る旅でもあった。市場の片隅で見つけた「初めて林檎を齧った喜び」。水辺に佇む老婆から流れ出た「愛する人を喪った深い哀しみ」。それらの記憶に触れるたび、俺は一時的に満たされ、そして次の瞬間には、より深い空虚に突き落とされた。
奇妙なことに、俺が追い求める琥珀色の記憶の断片には、不思議な共通点があった。いつもどこかに「一輪挿しの白い花」が映り込んでいる。決まって「雨上がりの土の匂い」がする。そして、背景には必ずあの「子守唄のようなメロディ」が微かに流れているのだ。
まるで、一人の人間が遺した、人生という名の物語の散らばったページを集めているかのようだった。
「お前さん、またそこにいたのかい」
パン屋の女主人が、怪訝な顔で俺を見た。俺は彼女の店の前で、何時間も立ち尽くしていたらしい。
「すまない」
俺はそう呟いたが、声は掠れてほとんど音にならなかった。女主人は首を傾げ、すぐに興味を失ったように店の中へ戻っていく。彼女の瞳には、俺の姿がほとんど映っていなかったのかもしれない。
存在が薄れていく。それは、死よりも静かで、残酷な恐怖だった。誰からも忘れ去られ、霧の中に溶けて消える。それが、俺の定められた運命。
それでも、足を止めることはできなかった。琥珀色の結晶の正体を知るまでは。あの温かい手の持ち主に、辿り着くまでは。
残響計の針が、今度は街で最も高い、古い鐘楼を指して震え始めた。これまで感じたことがないほど強く、そして切ない波動。まるで、俺を呼んでいるかのように。俺は覚悟を決めた。これが、最後の欠片になるだろう。
第三章 鐘楼の慟哭
螺旋階段を駆け上がるたびに、心臓が激しく打ち鳴らされる。それは恐怖か、それとも歓喜か。鐘楼の頂上に辿り着いた時、忘却の霧は眼下に海のよう広がっていた。その中央、巨大な鐘の下に、最後の残響が琥珀色の光を放ちながら揺らめいていた。
残響計をかざす。装置が悲鳴のような甲高い音を立て、ガラス盤が砕けんばかりに輝いた。俺は目を閉じ、精神のすべてを解放する。
――閃光。
奔流となって、膨大な記憶が俺の中に流れ込んできた。
愛する人と出会った春の日。共に過ごした夏の夜。喧嘩をした秋の雨。そして、世界が忘却の霧に覆われ始めた、絶望の冬。
それはすべて、リアという名の女性の記憶だった。彼女の視点から見た、愛する男との幸福な日々と、やがて来る忘却への恐怖。
『お願い、消えないで』
リアの悲痛な祈りが響く。霧は日に日に濃くなり、愛する男の顔さえも思い出せなくなっていく。彼女は自分の「記憶の結晶」が、一つ、また一つと失われていくのを感じていた。
そして、彼女は決意する。
最後の結晶が消える前に。この愛の記憶のすべてを、永遠に遺す方法を。
『私のすべてをあなたに捧げる。私の記憶、私の感情、私の存在そのものを器として、あなたという物語を未来へ遺す』
映像の最後、リアは涙を流しながら、愛する男――霧に覆われる前の、確かな輪郭を持った「俺」――に向かって微笑んだ。
『だから、恐れないで。たとえあなたがすべてを忘れても、この愛は、あなたの中で生き続ける』
そこで記憶は途切れた。
俺は、俺ではなかった。
俺はカイではなかった。俺は、リアがその存在のすべてと引き換えに創り出した、彼女の記憶を留めるための「器」だったのだ。俺が追い求めていた琥珀色の結晶は、失われた誰かの記憶などではなかった。それは、この器を形作るための、設計図そのものだった。
「ああ……あああああああ!」
慟哭が、霧の立ち込める空に響き渡った。俺という存在は、愛する人を忘れたくないと願った一人の女性の、悲しくも美しい執念の産物。俺の孤独も、俺の探求も、すべては彼女の愛の残響に過ぎなかった。
涙が、止まらなかった。それは俺の涙か、それとも、俺の中で目覚めたリアの涙か。もう、分からなかった。
第四章 忘れ得ぬあなたへ
鐘楼の下に、一人の女性が佇んでいた。霧の中でも消えることのない、強い光の結晶を胸に宿した女性。リア。俺という器が完成したことで、彼女は最後の記憶の在り処を思い出したのだ。
彼女の瞳が、俺を捉える。その表情は、懐かしさと、深い悲しみに彩られていた。
「……あなただったのね」
俺は静かに頷いた。もう、言葉は必要なかった。俺の役目は終わったのだ。このバラバラになった愛の記憶を、本来の持ち主へ返す。それが、俺という存在の、最初で最後の使命。
俺は彼女に向かって、ゆっくりと歩み寄った。一歩進むごとに、俺の身体の輪郭が光の粒子となって霧に溶けていく。俺が再構築した記憶のすべてが、リアへと流れ込んでいく。
彼女の瞳から、大粒の涙が零れ落ちた。失われたはずの愛の日々が、その温もりが、鮮やかに蘇っていく。
「忘れない……もう、決して忘れないわ」
リアが俺に触れようと手を伸ばす。だが、その指先は、実体を失い始めた俺の胸を、空しくすり抜けた。
「ありがとう」
俺は、生まれて初めて心からの微笑みを浮かべた。
「僕を、見つけてくれて」
それが、俺の最後の言葉だった。身体は完全に光の粒子となり、忘却の霧の中へと溶けて消えた。俺という、愛の記憶の器は、その役目を終えて無に還った。
世界から、カイという存在の記録は完全に消え去った。
しかし。
リアの胸の奥深く。彼女が取り戻した温かい記憶の結晶の隣に、一つの新しい結晶が、静かに生まれていた。
それは、自分を救うためだけに生まれ、そして消えていった、名もなき器との出会いと別れの記憶。忘却の霧が決して溶かすことのできない、琥珀色の、切なくも愛おしい感情の結晶。
世界は変わらず、忘却の霧に覆われている。人々は明日になればまた多くを忘れるだろう。
だが、その灰色の世界で、たった一つだけ。
初めて「忘れ去られることのない愛の感情」が、永遠の光として、確かに生まれた瞬間だった。