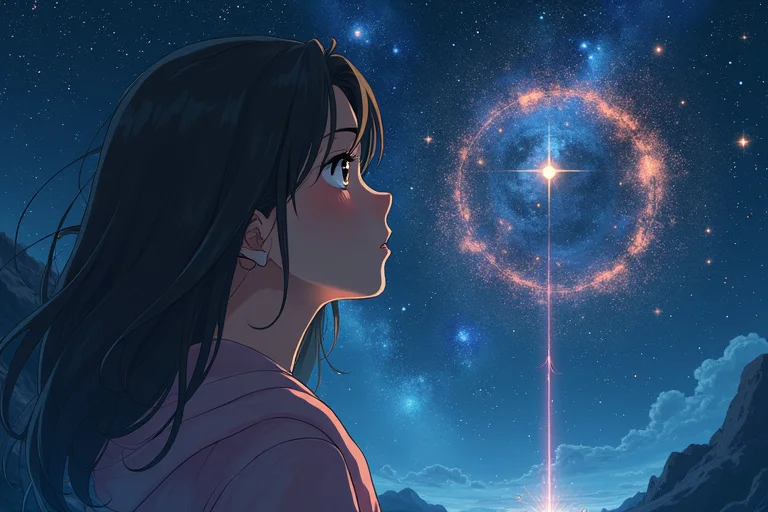第一章 沈黙の依頼人
リョウの仕事は、他人の記憶を掃除することだった。人々は彼を「メモリ・スイーパー」と呼ぶ。精神医療の一環として合法化されたその行為は、特殊なナノマシンを介してクライアントの脳にアクセスし、指定されたトラウマや不要な記憶の断片を、まるで埃を払うかのように消し去る。消去された記憶データは、法律に基づき、スイーパーの体内にある生体ストレージに一時的にアーカイブされ、七十二時間後に自動で完全消去される。それが、リョウの日常だった。
彼の住む無機質な高層アパートの一室のように、リョウ自身の内面もまた、がらんとしていた。他人の強烈な悲しみや苦しみに日々触れるうちに、彼自身の感情の振れ幅は凪のように平坦になっていった。それは、この仕事を続けるための職業的な防衛本能だったのかもしれない。
その日の依頼は、これまでとは何かが違っていた。都心を見下ろす最上階のペントハウス。ドアを開けたのは、古風なシルクのワンピースを上品に着こなした老婦人だった。窓から差し込む午後の光が、彼女の銀髪を柔らかく照らしている。シワの刻まれた目元は、しかし、深い湖のように静まり返り、感情の色を一切映していなかった。
「依頼の件ですが」リョウが切り出すと、老婦人はただ静かに頷き、テーブルの上に置かれたデータパッドを指差した。そこには、ただ一文だけが記されていた。
『対象:夫、五十嵐蒼介に関する全ての記憶。関連する五感情報、感情的リンクを含む、完全な消去を希望します』
リョウは思わず息を呑んだ。特定の出来事や人物の一部分を消す依頼は数多くこなしてきたが、人生の伴侶に関する記憶を根こそぎ消し去ってほしいという依頼は前代未聞だった。それは、その人間の半生を、まるごと抉り取るに等しい行為だ。
「……よろしいのですか? 一度消去した記憶は、二度と復元できません。あなたの人生から、五十嵐蒼介という存在が、完全に消滅するのですよ」
リョウの問いかけに、老婦人は答えなかった。ただ、ガラス細工のような瞳で、窓の外に広がる灰色の都市風景をじっと見つめている。その沈黙は、どんな言葉よりも雄弁に、彼女の揺るぎない決意を物語っているようだった。
リョウは、これ以上何も問うまいと決めた。クライアントのプライバシーに踏み込まない。それがメモリ・スイーパーの鉄則だ。彼は静かに機材を準備し、ナノマシンを注入するためのインジェクターを手に取った。老婦人は、何の抵抗も見せず、されるがままにリョウに腕を差し出した。ひんやりとした彼女の肌に、針が静かに沈んでいく。リョウの意識が、彼女の記憶の海へと深く、深くダイブしていく。その海の入り口で、彼は確かに感じた。まるで永久凍土のように冷たく、底知れない悲しみの気配を。
第二章 琥珀色の時間
老婦人の記憶の海は、リョウが想像していたような凍てついた世界ではなかった。むしろ、それは琥珀色に輝く、温かな時間の連続だった。
リョウは、彼女の視点を通して、一人の男性と出会った。若き日の五十嵐蒼介。彼は大学の図書館で、少し不器用に、しかし真摯な瞳で彼女に話しかけてきた。ページをめくる指先の微かな震え、古書の黴とインクが混じった匂い、西陽が彼の髪を金色に染めていた光景。それら全てが、鮮やかな奔流となってリョウの感覚を洗い流していく。
清掃作業を進めるにつれ、リョウは彼らの人生を追体験していった。雨の日のプロポーズ。教会のステンドグラスの前で交わした誓い。初めての子が生まれた日の、彼の涙。家族で囲んだ食卓の、シチューの湯気の匂い。喧嘩した夜の気まずい沈黙と、翌朝のぎこちない「おはよう」の声。記憶の断片を一つ一つ拾い上げ、消去領域へと移動させるたびに、リョウの胸に奇妙な疼きが走った。
それは、自分の人生には決定的に欠けている、温かな手触りのある感情だった。空虚だったリョウの内なる宇宙に、他人の幸福な記憶が星屑のように降り注ぎ、彼の世界を彩り始めていた。アーカイブされた記憶が消えるまでの七十二時間。その間だけ、この温もりは自分のものであるかのような錯覚に、リョウは溺れていった。
最後の記憶は、病院のベッドだった。痩せてしまった蒼介の手を、彼女が握りしめている。彼の呼吸は浅く、弱々しい。
「ありがとう」
掠れた声で、彼は言った。「君と出会えて、幸せだった」
その言葉を最後に、彼の瞳から光が消えた。絶望的な喪失感、胸が張り裂けそうな悲しみが、彼女の、いや、リョウの全身を貫いた。彼は、自分の頬を涙が伝っていることに気づかなかった。仕事中に感情移入するなど、プロとしてあるまじき行為だ。だが、この琥珀色の時間の奔流は、リョウが築き上げた心の壁をいとも容易く破壊してしまった。
全ての記憶を消し去り、彼女の精神の海から浮上したとき、リョウは言いようのない疲労と、そして奇妙なほどの充足感に包まれていた。彼の内側には今、五十嵐蒼介という一人の男の、愛に満ちた生涯がまるごとアーカイブされている。それはまるで、借り物の幸福だったが、それでもリョウの空っぽの心を満たすには十分すぎた。
第三章 借り物の心臓
七十二時間が経過するのを待たず、リョウは報告のため、再びあのペントハウスを訪れた。あの老婦人にもう一度会いたかった。彼女の記憶からは消えてしまった温かな時間を、自分だけが知っているという奇妙な優越感と、そして微かな罪悪感を抱きながら。
しかし、ドアを開けて彼を迎えたのは、見知らぬ若い男だった。歳の頃は三十代半ばだろうか。憔悴しきった顔には、深い隈が刻まれている。
「あなたが、メモリ・スイーパーのリョウさんですか」
「はい。奥様にご報告が……」
リョウの言葉を遮り、男は力なく首を振った。
「母は今、施設にいます。どうぞ、お入りください」
通されたリビングには、先日まで老婦人が座っていた椅子が、ぽつんと置かれているだけだった。部屋全体が、主を失ったかのようにがらんとしている。
「一体、どういうことです? 依頼主である奥様は……」
「依頼主は、私です」
男の告白に、リョウは思考が停止した。何を言っているんだ、この男は。自分は確かに、あの老婦人に会って、彼女の腕にインジェクターを打ったはずだ。
「あなたをここに招いたのは、母の姿を投影したAIホログラムです。音声も、私の過去の記憶データから再構成したもの……。母は重度のアルツハイマー病で、もう、父のことも、私のことも分かりません」
衝撃の事実が、鈍器のようにリョウの頭を殴りつけた。
「父が亡くなってから、母の症状は急速に進みました。日に日に、父との思い出も、私の存在さえも失っていく母の姿を見るのが……耐えられなかった。父を亡くした悲しみと、母を失っていく苦しみ。その両方から逃げ出したくて、私は父に関する記憶を全て消し去ろうと決めたんです」
男は顔を覆い、嗚咽を漏らした。
「でも、土壇場で怖くなった。だから、あなたを騙すような真似を……自分の代わりに、母のホログラムに依頼をさせた。本当に、申し訳ない……」
リョウは呆然と立ち尽くしていた。自分がダイブしたのは、あの老婦人の記憶ではなかった。目の前にいるこの息子の、父と母への愛と、喪失の記憶だったのだ。そして、彼がダイブした記憶の中の「彼女」――つまり彼の母親――は、息子が理想とする、まだ記憶を失う前の、聡明で美しい母親の姿だったのだ。
追い打ちをかけるように、リョウの体内に埋め込まれた生体モニターが警告音を発した。ディスプレイには、赤文字でエラーメッセージが点滅している。
『エラー:アーカイブデータの消去シーケンスに失敗。対象データがホストの神経回路と予期せぬ融合を開始しています』
血の気が引いた。消えるはずの記憶が、消えない。それどころか、五十嵐蒼介という男の人生が、この息子のフィルターを通した琥珀色の時間が、リョウ自身の記憶と混じり合い、分かち難く結びつこうとしている。
他人の幸福を、借り物の心臓を、自分のものだと錯覚していた愚かな自分。その心臓が今、胸腔に縫い付けられ、自分のものになろうとしている。それは祝福などではない。美しい記憶の形をした、呪いだった。
第四章 忘却のアーカイブ
メモリ・スイーパーを辞めた。
リョウの体内には、五十嵐蒼介という見ず知らずの男の人生が、まるで古文書のように残り続けていた。それは息子の視点から見た、美化された記憶の集合体だったが、あまりに鮮明で、温かかった。時折、ふとした瞬間に、蒼介の記憶がリョウの思考を乗っ取る。妻を愛おしく思う感情、息子を誇らしく思う気持ち。それらは全て借り物だと頭では分かっているのに、心は確かに震えた。
彼は、この「借り物の心臓」と共に生きていくことを選んだ。それは罰であり、同時に、空虚だった自分への、皮肉な贈り物なのかもしれなかった。
数ヶ月が過ぎたある晴れた午後、リョウはあの日以来、初めて公園を訪れた。ベンチに座ってぼんやりと空を見上げていると、車椅子に乗った一人の老婦人が、付き添いの男性と共に、ゆっくりと散歩しているのが目に入った。
あの依頼人の息子と、本物の彼の母親だった。
母親の表情は、虚ろだった。息子が何かを優しく語りかけているが、彼女の瞳はどこか遠くを見つめている。彼女はもう、愛した夫のことも、目の前にいる息子のことも覚えてはいない。彼女の記憶のアーカイブは、病によって白紙に戻されてしまったのだ。
皮肉なことだ、とリョウは思った。
夫の記憶を全て失った妻。
父の記憶を消そうとして、結局は抱え続ける息子。
そして、彼らの記憶を背負うことになった、赤の他人の自分。
息子が、ふとリョウの方に視線を向けた。一瞬、彼の目がリョウを捉えたが、すぐに興味を失ったように母親へと向き直る。彼がリョ-ウの正体に気づくことはない。
リョウは静かに立ち上がり、彼らに背を向けて歩き出した。彼の胸の中では、五十嵐蒼介の温かな記憶が、今も確かに息づいている。それは誰にも返すことのできない、自分だけの秘密のアーカイブ。
空っぽだった自分の人生に、他人の物語が刻み込まれてしまった。だが、不思議と絶望はなかった。この温かさを道標に、これからは自分自身の足で、自分だけの物語を歩いていけばいい。たとえそれが、誰かの思い出の上を歩くような、奇妙な旅路であったとしても。
夕陽が、リョウの長い影を、未来へと続く道の上にそっと伸ばしていた。