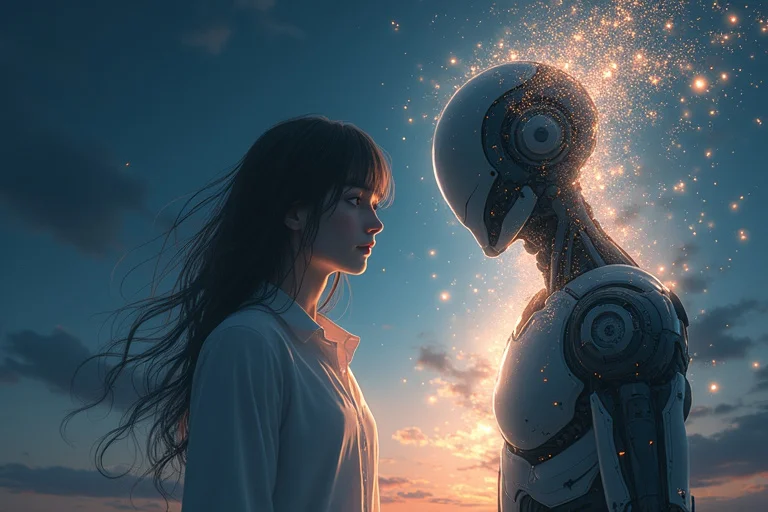第一章 錆びついたオルゴール
俺の部屋の空気は、十五年前から澱んでいる。窓から差し込む光が、宙を舞う埃をきらきらと照らし出すたび、俺は時間の残骸を見ているような気分になった。システムエンジニアという仕事は、そのほとんどを自宅のこの部屋で完結できる。それは、人との関わりを避けたい俺にとって好都合だった。
日課は、夜の終わりにやってくる。コンソールの前に座り、政府が管理する超光速通信サービス、通称「クロノポスト」を起動する。過去の任意の時点へ、最大百四十文字のテキスト情報を送信できるという、夢のような、それでいて残酷な技術。ただし、受信者は特定できず、過去の誰かの端末にノイズとして一瞬表示されるだけ。歴史への重大な干渉を防ぐための措置だと、政府は説明していた。
俺は宛先を正確に入力する。西暦二〇三八年八月十五日、午後二時四十六分。妹のミオが、交差点に飛び出す三分前。
そして、いつも同じ言葉を打ち込む。
『ごめん』
エンターキーを押すと、テキストは瞬時に時空の彼方へ吸い込まれていく。誰にも届かないと分かっていながら、俺はこの儀式をやめられなかった。あの日、ミオと些細なことで喧嘩をしなければ。彼女が家を飛び出さなければ。俺の後悔は、十五年という歳月をかけて、硬い化石のように心の奥底に沈殿していた。
その夜も、俺は虚空へ贖罪の言葉を投げた。コンソールを閉じ、立ち上がって凝り固まった身体を伸ばした時、ふと、部屋の隅にある本棚の上に、見慣れないものがあることに気づいた。
それは、木製の小さなオルゴールだった。
近づいて手に取ると、ずしりとした重みと、ひんやりとした木の感触が伝わってきた。蓋には精緻な星の彫刻が施されている。埃一つなく、まるで今しがた置かれたかのようだ。ゆっくりと蓋を開けると、澄んだ、それでいてどこか切ないメロディが流れ出した。それは、ミオが幼い頃にデパートのショーウィンドウの前で、「いつか欲しいな」と呟いていた曲だった。俺が、「また今度な」と適当にあしらって、ついに買ってやれなかった、あのオルゴール。
なぜ、これがここに? 誰が、いつの間に?
心臓が嫌な音を立てて脈打つ。部屋の澱んだ空気が、にわかに輪郭を持ち、俺の喉を締め付け始めた。それは、止まっていたはずの俺の時間が、何者かによって無理やり捻じ曲げられたような、不気味な感覚だった。
第二章 星屑の囁き
オルゴールは幻ではなかった。翌朝も、それは静かに本棚の上に鎮座していた。俺は混乱しつつも、日常を装って仕事をこなした。だが、集中力は散漫で、モニターに映るコードの羅列が意味のある情報として頭に入ってこない。
異変は、それだけでは終わらなかった。数日後、壁にかけてあった家族写真のミオの表情が、僅かに微笑んでいるように見えた。気のせいだと思おうとした。だが、その翌週には、俺が子供の頃につけた柱の傷が、綺麗さっぱり消えていた。
まるで、過去の小さな後悔が、一つずつ丁寧に修復されていくようだ。不気味なはずなのに、心のどこかで安堵している自分に気づき、愕然とする。俺は、この怪現象の主が誰なのか、薄々感づき始めていた。
震える手でクロノポストの送信ログを開く。そこには、俺が送った『ごめん』という短いメッセージの記録が、十五年分、整然と並んでいた。だが、スクロールを続けていくと、見覚えのない送信記録がいくつも紛れ込んでいるのを発見した。
『二〇三五年六月三日:公園のブランコは鎖が古いから気をつけて』
『二〇三七年十一月二日:雨の日は駅の階段が滑りやすいよ』
『二〇三八年八月一日:その角を曲がる時は、絶対に左右を見て』
全て、過去のミオに向けられた、短い警告の言葉だった。送信日時は、ここ数週間に集中している。誰かが、俺と同じようにミオを想い、彼女を守ろうとしている。いや、違う。この執拗なまでの干渉は、もはや見守るというレベルを超えていた。まるで、定められた悲劇の結末を、意地でも変えようとするかのように。
恐怖と、抗いがたい期待が胸の中で渦を巻いた。このままいけば、もしかしたら。ミオが死ななかった未来が、訪れるかもしれない。
俺は、謎の送信者の正体を突き止める決意をした。それは、自分の人生を取り戻すための、唯一の希望の光に思えた。俺は自分の持つ全ての技術を注ぎ込み、鉄壁とされるクロノポストのセキュリティシステムへの侵入を試みた。数日間の徹夜の末、ついに俺は、謎の送信者が使っていたアカウントの暗号化されたIDを特定することに成功する。
だが、そのIDを解読した瞬間、俺は息を呑んだ。
そこに表示されていたのは、俺自身の名前だった。
第三章 クロノスの悖理
俺が、俺に? そんな馬鹿なことがあるか。何かの罠か、あるいはシステムのエラーか。混乱する頭で、俺はさらに深くデータの海へ潜った。送信元の座標、タイムスタンプ、アクセス経路。パズルのピースを一つひとつ繋ぎ合わせていくうち、背筋を凍らせるような、一つの結論にたどり着いた。
謎のメッセージを送っていたのは、確かに「俺」だった。だが、それは今の俺ではない。送信ログに記録されたタイムスタンプは、現在時刻から遥か未来――五十年後の未来を示していた。
五十年後の俺が、過去のミオを救うために警告を送り続けていた?
なぜだ。未来の俺は、ミオの死を乗り越えられなかったというのか。いや、それだけではない。何か、もっと巨大な理由があるはずだ。俺は解析を続けた。そして、クロノポストのシステム深部に隠されていた、最高機密レベルのファイルを発見する。ファイル名は、『プロジェクト・カサンドラ』。
震える指でファイルを開く。そこに記されていたのは、俺が信じてきた世界のすべてを根底から覆す、驚愕の事実だった。
クロノポストは、単なる過去へのメッセージサービスなどではなかった。その真の目的は、人類が回避不可能な破滅――予測される大規模な太陽フレアによる地球文明の崩壊――から逃れるため、過去の歴史を僅かずつ改変し、最も生存確率の高い未来へと導くための、巨大な因果律操作システムだった。世界中の無数のユーザーが送る、一見無意味な過去へのメッセージ。それらが複雑に絡み合い、計算され尽くしたバタフライエフェクトを誘発することで、歴史の航路を微調整していたのだ。
そして、問題は俺だった。俺が十五年間、毎日欠かさず送り続けてきた『ごめん』というたった一言のメッセージ。それは、システムの想定を遥かに超える強力なアンカーとして因果律に作用し、本来なら分岐するはずだった無数の未来を、ミオの死という一点に収束させてしまっていた。俺の個人的な後悔が、人類の未来を決定づける巨大な重しとなっていたのだ。
未来の世界は、その歪みを是正するために、未来の俺をエージェントに選んだ。ミオの死という強力なアンカーを打ち消せるのは、それと同等か、それ以上の想いを持つ者しかいないからだ。未来の俺は、ミオを救うという名目で過去に干渉し、俺が作り出した因果の歪みを少しずつ解きほぐそうとしていた。オルゴールも、壁の傷も、全てはそのための布石だった。
俺の贖罪は、ただの自己満足だったどころか、世界を破滅へと導くトリガーだった。ミオへの想いが、世界を殺す。その事実が、ハンマーのように俺の頭を殴りつけた。
その時、コンソールに新たなメッセージがポップアップした。送信者は、未来の俺。
『計画は最終段階に入った。次の送信で、ミオは交差点に飛び出さない。彼女は助かる。だが、その代償として、歴史の航路は決定的に変動し、プロジェクト・カサンドラは失敗する。人類は太陽フレアを回避できない。選択しろ、過去の俺。ミオか、世界か』
俺は、神を気取った愚か者だった。そして今、本物の神のように、一つの世界の生殺与奪を委ねられてしまった。
第四章 きみへ送る最後の言葉
選択の時間は、長くは残されていなかった。モニターには、未来の俺が準備したであろう、ミオを救うための最後のメッセージが点滅している。『午後二時四十九分、駅前のカフェで待ってて』。これを送れば、ミオは事故現場に行かず、助かる。そして、世界は終わる。
俺は椅子から立ち上がり、部屋を歩き回った。澱んでいたはずの空気が、今は鉛のように重い。俺は一体、何のために十五年間も過去に囚われてきたのだろう。ミオを救いたかった。ただ、それだけだったはずだ。
ふと、ミオの最後の顔を思い出す。喧嘩をして家を飛び出す直前、彼女は泣きそうな顔で、それでも必死に笑顔を作ってこう言ったのだ。「お兄ちゃんなんて、大っ嫌い!」と。あれは、本心からの言葉ではなかった。強がりの裏に隠された、悲しい色をした笑顔だった。
俺は、ミオという少女を思い出していた。いつも自分のことより、他人のことを心配するような子だった。道端で怪我をした猫を、涙を流しながら介抱していた。友達が悲しんでいると、自分のことのように心を痛めていた。そんな優しい彼女が、もしこの選択を知ったら、何と言うだろうか。
世界中の人々を犠牲にしてまで、自分だけが助かることを、彼女が望むだろうか。
答えは、分かりきっていた。
俺は、ミオの死を乗り越えるのではなく、彼女の死と共に生きることを選ばなければならない。彼女の優しさを、彼女が生きた証を、俺がこの世界で守り続けなければならない。それが、本当の意味での贖罪なのだ。十五年かかって、ようやくそのことに気づいた。
コンソールの前に戻る。未来の俺が用意したメッセージを削除し、新しいテキストを打ち込んだ。送信先は、事故当日の午後二時四十五分――家を飛び出そうとしている、十五年前の俺自身だ。クロノポストの規約上、自分自身に送ることは想定されていない。だが、この最後の通信は、システムをハックした俺だけの特権だ。
『ミオを止めに行くな。彼女の最後の強がりを、笑顔を受け止めてやれ。そして、ちゃんと見送るんだ。それが、お前の、俺たちの役目だ』
エンターキーを押した。それは、過去への訣別であり、未来の俺自身への、そして天国のミオへの、揺るぎない約束だった。
送信を終えると、俺はクロノポストのアカウントを削除した。もう、二度と過去に言葉を送ることはない。
ふと見ると、本棚の上のオルゴールが、陽炎のように揺らめいて、すっと消えていた。まるで、役目を終えたかのように。だが、不思議と悲しくはなかった。あの澄んだメロディは、もう俺の心の中に、確かに鳴り響いている。
窓を開けると、雨上がりの澄んだ空気が流れ込んできた。世界の何もかもが変わらない日常。ミオは帰ってこないし、俺の胸の痛みも完全には消えないだろう。
それでも、俺は顔を上げた。失われた過去ではなく、これから続いていく未来のために。ミオが生きたかったはずの今日という日を、彼女の思い出と共に、精一杯生きていく。
空には、一番星が瞬き始めていた。それはまるで、遠い時空の彼方から届いた、優しい返信のように見えた。