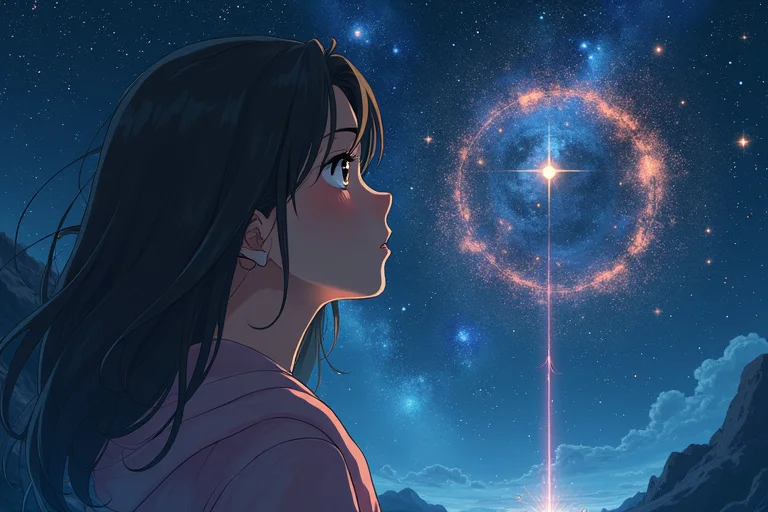第一章 蒼い花の残像
星間移民船「アウロラ号」の静寂は、人工のそれだ。リサイクルされた空気の微かな流動音、遠い隔壁の向こうで唸る生命維持装置の重低音。そのすべてが混ざり合い、揺りかごのような、それでいて墓場のような一定のリズムを刻んでいる。俺、カナタの職場である記憶管理局〈メモリア〉は、その心臓部にあった。
俺の仕事は、人々の記憶をメンテナンスすること。数世代にわたる恒星間飛行は、人間の精神に微細ながらも着実な汚染を蓄積させる。それを定期的に浄化し、重要な記憶を保護領域にバックアップする。他人の人生を覗き見る、神をも冒涜するような仕事だと誰かが言った。だが、俺にとっては、ただの作業だった。
あの日も、そうであるはずだった。対象者はエマ・ハインライン。八十九歳。重度の認知障害を患い、今は医療ポッドの中で生命を維持しているだけだ。彼女の精神データは、ノイズの嵐だった。壊れたフィルムのように明滅するイメージの奔流の中から、俺は丁寧に、保護すべき記憶の断片を拾い上げていく。夫との結婚式、娘の誕生、船上初の収穫祭。ありふれた、しかし彼女にとっては宝石のような思い出たち。
その時だった。ノイズの狭間に、ふいに鮮やかな色彩が流れ込んできたのだ。
目に飛び込んできたのは、一面の青い花畑。地球には存在しない、アウロラ号の植物ドームで品種改良された花だ。月の光を浴びて青白く輝くことから「ルナリア」と呼ばれるその花が、風に揺れている。そして、その花畑の中に、幼い少年と少女がいた。手を繋ぎ、笑い合っている。
心臓が、鷲掴みにされたように軋んだ。
その光景を知っていた。いや、知っているはずがない。俺は五年前に起きた船内区画の減圧事故で、十歳以前の記憶の大部分を失っているのだから。だが、脳裏に焼き付いて離れないこの光景は、俺が時折見る悪夢の後の、唯一の安らぎとして現れる断片そのものだった。ルナリアの甘い香り、隣に立つ少女の小さな手の温もり。それは、俺が失ったはずの、幸福の残像だった。
「…なんだ、これは…」
モニターに映し出されるエマの記憶。その中で笑う少年は、俺の幼い頃の姿に酷似していた。しかし、隣の少女は誰だ? 俺に妹がいたという記録はない。
プロトコルは絶対だ。クライアントの記憶データへの私的アクセスは、最も重い罪の一つ。だが、俺の指は意思に反して動いていた。コンソールを操作し、その蒼い花の記憶シーケンスを、密かに自分の個人領域へとコピーする。アラートを示す赤いランプが、俺の罪を冷ややかに見つめていた。
失われたはずの俺の過去が、なぜ見ず知らずの老婆の記憶の中に存在するのか。この謎は、俺の空虚な心に突き刺さった、甘く危険な棘だった。
第二章 盗まれた追憶
俺の世界は、その日から一変した。仕事が終わると、俺は自室にこもり、盗み出した記憶データに没入した。それは、麻薬だった。仮想感覚インターフェイスを起動させると、俺はエマの記憶の中にいた少年に成り代わった。
少年の名前はリアム。そして、隣にいる少女は妹のリラ。俺はリアムとして、リラと手を繋いでルナリアの花畑を駆け回った。父さんが作ってくれた木製の宇宙船で遊び、母さんが焼いてくれた甘いパンの香りに包まれて眠った。それは、俺がずっと渇望していた「家族」の記憶だった。温かく、満ち足りていて、疑う余地のない幸福がそこにはあった。
記憶の中で、俺はカナタではなかった。失われた過去への喪失感に苛まれる空っぽの男ではなく、愛される息子であり、優しい兄であるリアムだった。この記憶は、間違いなく俺自身のものだ。事故で失われたピースが、奇跡的に見つかったのだ。そう信じたかった。いや、信じていた。
俺の日常は侵食されていった。現実の俺は、日に日に精彩を欠いていった。同僚のユイが心配そうに声をかけてくる。「カナタ、最近ぼーっとしてるけど、大丈夫?顔色、悪いわよ」。俺は曖昧に笑って誤魔化すが、心はここにはなかった。俺の本当の人生は、あの蒼い記憶の中にしかない。
真実を確かめたかった。俺は規定を破り、医療セクターにいるエマ本人に面会を求めた。生命維持ポッドの中で眠る彼女は、まるで蝋人形のようだった。か細い呼吸音だけが、彼女がまだ生きていることを示している。俺が何度呼びかけても、彼女の瞳が俺を映すことはなかった。彼女の意識は、もはや壊れた記憶の迷宮から戻ることはないのだ。
手がかりは、完全に途絶えた。だが、それでよかったのかもしれない。確証がないからこそ、俺はリアムの記憶を自分のものだと信じ続けることができる。俺は再び仮想の幸福へと逃げ込んだ。リアムとして笑い、リアムとして泣いた。その追憶が、盗まれたものであるという一抹の罪悪感に気づかないふりをして。
第三章 空白の肖像
幸福な時間は、砂の城のようにもろかった。リアムの記憶に深く潜るうち、俺は奇妙なデータ構造に気づいた。それは、本来あるべきではない、継ぎ接ぎの痕跡。まるで、一枚の絵に別の画家の筆致が無理やり上書きされたような、歪なインプラントのログだった。
嫌な予感が胸をざわつかせた。俺は記憶技師としての全ての知識と技術を総動員し、そのログの解析に乗り出した。数日間の徹夜の末、俺はついに保護されたコアデータへとたどり着いた。そして、そこに記されていた真実に、俺は言葉を失った。
それは「記憶移植プログラム」の実行記録だった。
十五年前、アウロラ号で致死性の高い感染症が発生した。多くの子供たちが犠牲になった。その一人が、エマの孫、リアム・ハインラインだった。
最愛の孫を失ったエマは、悲しみのあまり精神の均衡を失いかけた。彼女の夫であり、当時、記憶管理局の主任技師だった男は、禁忌を犯した。彼は死んだリアムの記憶データを抽出し、妻であるエマの脳に移植したのだ。愛する孫の思い出だけでも、彼女の中に生き続けさせようとして。
だが、人の精神は、他人の記憶という異物を受け入れられるほど強靭ではなかった。移植されたリアムの記憶は、エマ自身の記憶と混濁し、やがて彼女の精神構造そのものを破壊した。それが、彼女の重い認知障害の真の原因だった。
俺が自分のものだと信じていた温かい記憶は、すべて死んだ少年、リアムのものだったのだ。俺は、他人の墓を暴き、その遺品を自分のものだと喜んでいた愚か者に過ぎなかった。
絶望が、足元から這い上がってくる。だが、地獄はまだ終わらなかった。俺は自分のIDで、アウロラ号の中央データベースにアクセスした。自分の出生記録、そして、五年前の減圧事故の公式報告書を。
そこに、最後の、そして最も残酷な真実が記されていた。
俺の記録には、十歳以前のデータが存在しなかった。空白だった。事故で記憶を「失った」のではない。俺は、生まれつき長期記憶を形成できない障害を持つ、「ブランク」と呼ばれる存在だったのだ。俺の人格も、知識も、この船の教育プログラムによって後天的に与えられた、借り物のパッチワークに過ぎなかった。
俺がずっと感じていた喪失感。それは、失われた記憶への哀愁ではなかった。そもそも存在しない過去、空っぽの自分自身に対する、本能的な虚無感だったのだ。
俺は、何者でもなかった。俺という人間を証明する、固有の過去は何一つない。リアムの記憶に見たあの幸福は、俺のものではない。俺の肖像は、どこにも描かれていない、ただの空白のキャンバスだった。コンソールにもたれかかり、俺は声を殺して泣いた。無音の宇宙船の中で、俺の崩れ落ちる音だけが響いていた。
第四章 あなたの記憶を、未来へ
絶望の底で数日を過ごした後、俺を動かしたのは、一つの疑問だった。リアムの妹、リラはどうなったのか。彼女も兄と同じ病で死んだのだろうか。俺は震える手で、再びデータベースを検索した。
リラ・ハインライン。生存。現在、二十四歳。アウロラ号第三植物ドーム、主任植物学者。
彼女は、生きていた。
衝動に駆られ、俺は第三植物ドームへと向かった。ガラス張りの天井から降り注ぐ人工太陽の光が、多種多様な植物を照らしている。その中央に、蒼い花畑が広がっていた。ルナリアだ。そして、その花畑の手入れをしている女性がいた。リアムの記憶の中の面影を残す、リラだった。
彼女は俺に気づくと、不思議そうな顔でこちらを見た。俺は、自分が何者で、なぜここに来たのかを、途切れ途切れに話した。リアムの記憶のこと。エマのこと。そして、自分が「ブランク」であることも。
リラは驚いたようだったが、静かに俺の話を聞いていた。彼女の瞳は、リアムの記憶にあったものと同じ、澄んだ色をしていた。
「…兄さんの、記憶…」
彼女は呟き、ルナリアの花を一輪、そっと指でなぞった。
その時、俺の脳裏に、リアムの記憶の最後の断片が蘇った。病床で弱っていくリアムが、泣いているリラの手を握って、囁く光景。
「リラ、泣かないで…」
俺は、まるで自分がリアムになったかのように、その言葉を口にしていた。
「俺は、ずっと、そばにいるよ。この花を見て。ルナリアは、一度枯れても、種を残して、また次の季節に必ず咲くんだ。俺も、この花のように、何度でも君のそばで咲くから…」
それは、兄が妹に伝えたかった、最後の約束だった。
俺がその言葉を伝えると、リラの瞳から大粒の涙が零れ落ちた。それは悲しみの涙ではなく、長い間凍っていた何かが、ようやく溶け出したような、温かい涙だった。
その瞬間、俺は理解した。
記憶が誰のものであろうと、そこに込められた想いや愛情は、本物だ。たとえ俺自身が空白の存在だとしても、この温かい想いを、死んだ少年から彼の妹へと繋ぐことができた。それだけで、俺がここにいる意味があったのではないか。
過去がないのなら、これから作ればいい。俺自身の物語を。俺自身の記憶を。
俺はもう、他人の過去を羨む空っぽの器ではない。記憶の「語り部」として、想いを未来へ繋ぐという役割を見つけたのだ。
数日後、俺は再びエマの病室を訪れた。眠る彼女の手を握り、俺は静かに語り始めた。
「エマさん。あなたの孫、リアムは、とても優しい子でした。彼は、妹のリラを心から愛していました。そして、ルナリアの花のように、いつでもそばにいると約束していました…」
俺は、リアムの記憶を、一つ一つ丁寧に紡いでいった。認知症のエマには、届いていないかもしれない。
だが、語り終えた時、彼女の口元に、本当に微かな、穏やかな笑みが浮かんだように見えた。
俺は彼女の手を握りしめた。空白だった俺の心に、確かな温かい光が灯るのを感じていた。窓の外には、無数の星々が輝く、果てしない宇宙が広がっている。この船がどこへ向かうのか、俺にはわからない。だが、俺はもう、自分の航路を見失うことはないだろう。
あなたの記憶を、俺が未来へ運んでいく。
心の中でそう誓い、俺は新しい一日へと、歩き始めた。