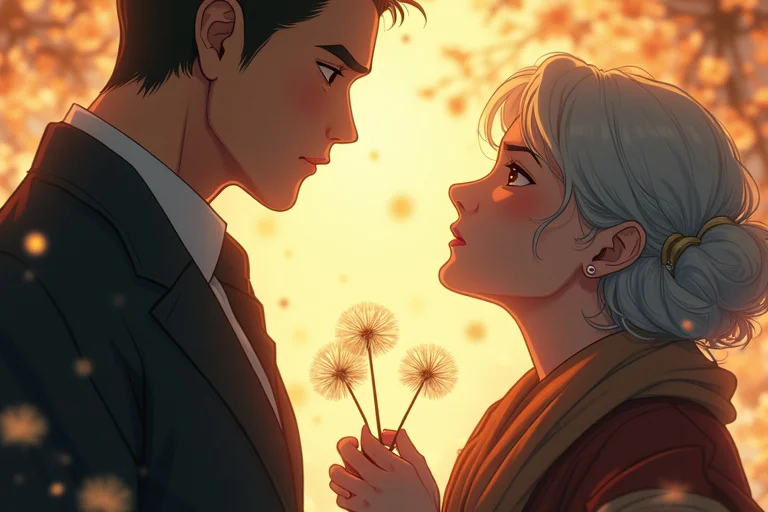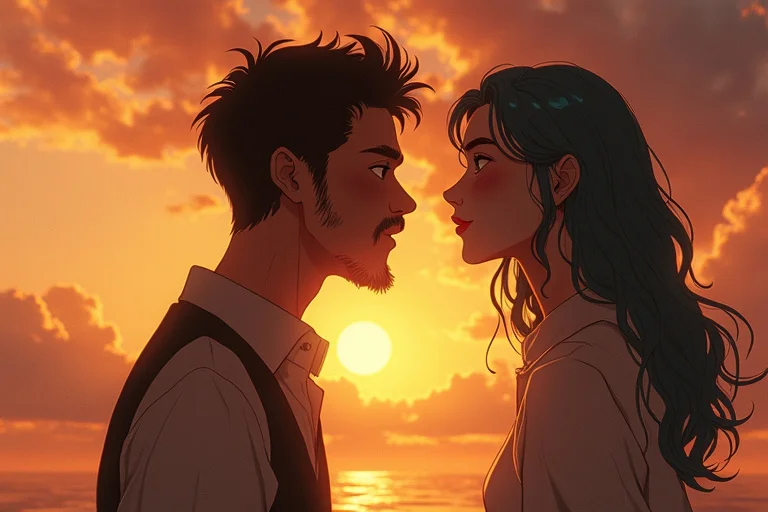第一章 招かれざる同居人
田中誠人(たなかまこと)、28歳、独身。彼の世界は、彼自身が定めた厳格なルールによって完璧に統治されていた。都心を見下ろすデザイナーズマンションの1LDK。床にはチリひとつなく、ミニマリストを標榜する彼の部屋には、生活に必要な最低限の家具が、まるで幾何学の定理を証明するかのように正確な位置に置かれている。システムエンジニアとして在宅で働く彼にとって、この静謐でコントロールされた空間こそが、混沌とした外界から身を守るための城塞だった。
その日も、田中はいつものように午前7時に起床し、寸分違わぬ量の豆を挽いてコーヒーを淹れ、無駄のない動きで仕事を開始した。すべてが完璧。すべてが予定通り。そう、あの瞬間までは。
異変は、モニターに映るコードの海に集中していた彼の聴覚が、最初に捉えた。
「あらまあ」
甲高い、しかしどこか朗らかな老婆の声。空耳か。田中は眉をひそめ、ヘッドフォンを外し耳を澄ませた。部屋は静まり返っている。気のせいだろう。そう結論づけて再び仕事に戻ろうとした、その時。
「近頃の若い方は、お掃除がお上手なのねえ。感心、感心」
今度ははっきりと聞こえた。声は、部屋のど真ん中から響いてくる。田中は勢いよく椅子を回転させた。そこには、誰もいない。いや、正確には「誰もいない」ように見える。しかし、空間が陽炎のようにわずかに揺らめき、その中心に、徐々に輪郭が現れ始めた。桜色のカーディガンを着た、小柄な老婆の姿が。しかも、半透明だった。
「だっ、誰だ!?」
田中の声は情けなく裏返った。不法侵入? いや、それにしては物理法則を無視しすぎている。老婆は、田中のパニックを意に介さず、にこやかに微笑んだ。
「あら、ごめんなさいね。驚かせちゃったかしら。わたくし、鈴木サチコと申します。どうも、ここに居着いてしまったみたいで」
そう言って彼女は、田中の自慢のガラステーブルを、すうっと、何の抵抗もなく通り抜けた。
田中は絶句した。目の前の現象は、彼の論理的な脳が処理できる範疇を完全に超えていた。幽霊。その非科学的な単語が、頭の中で警報のように鳴り響く。
「出ていけ! すぐに!」
彼はキッチンから粗塩のボトルを掴んでくると、サチコに向かって派手にぶちまけた。塩の粒は、彼女の半透明の身体を虚しく通り抜け、完璧に磨き上げられた床に散らばった。
「あらあら、もったいない。お清めかしら? 気持ちは嬉しいけど、わたくしには効かないみたいよ」
サチコはけらけらと笑っている。その日から、田中誠人の完璧にコントロールされた世界に、史上最悪のバグが常駐することになったのである。
第二章 幽霊の奇妙なルール
鈴木サチコと名乗る幽霊は、実に厄介な同居人だった。物理的な干渉は一切できない。皿を洗うことも、洗濯物を畳むこともできない。それどころか、彼女の存在自体が、潔癖症の田中にとって最大の精神的汚染源だった。
「田中さん、昨日の夜に食べたコンビニ弁当の容器、まだそこにありますよ。すぐに捨てないと、コバエが湧きますわよ」
「田中さん、そのシャツ、もう三日も着てませんこと? いくら在宅でも、身だしなみは大事ですわよ」
「あらまあ、メロドラマが始まったわ! 田中さん、ちょっとチャンネルを変えないでちょうだい!」
サチコは四六時中、田中の行動に実況と解説、そしてダメ出しを加え続けた。プライバシーなどあったものではない。彼女は壁もドアもすり抜けるのだから。田中はあらゆる除霊方法を試した。有名な神社の御札を貼り、ネットで買った数珠を振り回し、般若心経をスマホで大音量再生もした。しかし、サチコは「あら、BGM? なんだか荘厳な気分になるわねえ」と感想を述べるだけで、消える気配は微塵もなかった。
追い出すことを諦めた田中は、彼女を「いないもの」として扱うことにした。だが、それも難しかった。一人で食べていた味気ないレトルトのパスタも、横で「もっと緑黄色野菜を摂りなさい」という幻聴(?)付きでは、味が変わってくる。完璧だった静寂は失われたが、その代わりに、部屋から生活音が消えることはなくなった。サチコの独り言や、テレビへのツッコミが、常に空間を満たしていた。
奇妙なことに、サチコは自身の生前の記憶をほとんど失っていた。自分がなぜ死んだのか、どこに住んでいたのか、家族はいたのか。何一つ覚えていないという。ただ時折、窓の外を眺めながら、ぽつりと断片的な言葉を漏らすことがあった。
「あそこの角を曲がったところの桜、見事だったわねえ…」
「なんだか無性に、カツ丼が食べたいわ。甘ーい、お出汁の染みたやつ」
「あの子、ちゃんと笑ってるかしら。私がいないと、すぐ泣いちゃうから…」
その言葉は、誰に向けられたものなのか。田中は、記憶のない幽霊の戯言だと片付けながらも、その言葉が発せられる時のサチコの横顔に、一瞬だけよぎる寂しげな色を、見逃すことができなくなっていた。
迷惑で、うるさくて、非科学的。それでも、田中の城塞は、サチコという予期せぬバグによって、少しずつ、しかし確実にその姿を変え始めていた。冷たく整然とした空間に、ほんのわずかな「人の気配」という名の温もりが灯り始めていたことを、彼はまだ認めたくなかった。
第三章 カツ丼の記憶
その週末、プロジェクトの大きな山を越えた田中は、無性にがっつりしたものが食べたくなった。頭に浮かんだのは、なぜかカツ丼だった。普段ならカロリーや脂質を計算して躊躇するところだが、その日は何かに導かれるように、近所の評判のとんかつ屋に出前の電話をかけていた。
三十分後、部屋に香ばしい出汁と揚げ物の匂いが充満した。ほかほかの湯気が立つカツ丼の蓋を開けた瞬間、それまでソファの上でぼんやりしていたサチコが、弾かれたようにこちらを向いた。彼女の半透明の目が、驚きに見開かれている。
「この匂い…! この、甘くてしょっぱい匂い!」
サチコはふわりと宙に浮くと、テーブルの上のカツ丼に顔を近づけた。
「これだわ! 私、これ、よく作ってあげたのよ! あの子のために。玉ねぎをよーく煮て、甘めのつゆでね。卵はとろっとろにしてあげるの。あの子、それが大好きだったから!」
その言葉が、雷のように田中の脳を撃ち抜いた。
――とろっとろの卵。甘いカツ丼。
脳の奥深く、埃をかぶった記憶の扉が、軋みながら開く。おぼろげな映像。幼い自分が、誰かの膝の上で泣いている。転んで擦りむいた膝が痛い。そんな自分に、温かい声がかけられる。「大丈夫よ、まこと。ばあちゃんが、まことの好きなカツ丼作ってあげるからね」。そして、目の前に差し出された、湯気の立つ甘いカツ丼。
「まこと…?」
田中は、震える声で呟いた。まさか。そんなはずはない。
彼は震える手でスマートフォンを掴み、実家の母親に電話をかけた。
「母さん? 急に悪いんだけど…俺が小さい頃に亡くなった、父さんの方のおばあちゃんの名前、覚えてる?」
『誠? どうしたの急に。おばあちゃんの名前? 鈴木サチコよ。当たり前じゃない』
心臓が大きく跳ねた。
「その…ばあちゃんって、どんな人だった?」
『優しい人だったわよ。あなたは“ばあちゃん子”で、いつもべったりだったじゃない。誠が好きだからって、よく甘いカツ丼を作ってくれてたわ。あなたが五歳の時に病気で亡くなったから、もう覚えてないかもしれないけど…』
電話を切った田中は、時間が止まったかのように、目の前の幽霊を見つめた。鈴木サチコ。甘いカツ丼。五歳で失われた記憶のピースが、今、目の前で一つの絵を完成させようとしていた。
「田中さん…?」
サチコが不安そうに彼を覗き込む。彼女はずっと、田中のことを「田中さん」と呼んでいた。それは、他人行儀だったからではない。記憶が曖昧な中で、孫の名字だけを、必死に覚えていたからだ。
田中の視線を受け、サチコの瞳にも困惑と、そして確信の光が灯っていく。彼女は目の前の青年の顔を、記憶の霞を払いのけるように、じっと見つめた。
「まこと…? 本当に…まことなの…? こんなに、大きくなって…」
その声は、もはや「田中さん」を呼ぶ声ではなかった。遠い昔、自分をあやしてくれた、紛れもない祖母の声だった。
田中の頬を、熱い雫が伝った。
「ばあちゃん…」
完璧に統治されていたはずの世界が、涙で滲んで、歪んで見えた。
第四章 一人だけど、独りじゃない
部屋には、言葉にならない静寂が流れた。それは以前の冷たい静寂ではなく、六十年以上の時を超えた再会がもたらす、温かく、そして少しだけ切ない沈黙だった。
「ごめん、ばあちゃん。ずっと…気づかなくて、ごめん」
嗚咽混じりに絞り出した田中の声に、サチコは首を横に振った。その半透明の顔には、この世で最も優しい微笑みが浮かんでいた。
「いいのよ、まこと。会いたかっただけだから。あんまり寂しそうにしてるから、心配で、心配で、こっちに来ちゃったの」
サチコが時折漏らしていた断片的な言葉の意味が、一気につながった。「あそこの角の桜」は、昔住んでいた家の近くの公園の桜並木で、幼い田中を肩車して見せてくれた思い出の場所だった。「泣いていたあの子」は、ささいなことで泣きべそをかいていた、幼い田中自身のことだった。彼女の未練は、ただ一つ。この世に一人残してきた、愛しい孫のことだけだったのだ。
田中は涙を拭うと、決意を固めて立ち上がった。
「ばあちゃん。俺が作るよ。ばあちゃんのカツ丼」
彼はキッチンに立つと、再び母に電話をかけ、「ばあちゃんのカツ丼」のレシピを必死にメモした。ぎこちない手つきで玉ねぎを切り、目に涙を浮かべ(玉ねぎのせいだけではなかった)、出汁の味を何度も確かめる。サチコは、そんな彼の背中を、愛おしそうにずっと見守っていた。
やがて、甘い香りを漂わせる、少し不格好なカツ丼が完成した。田中はそれをテーブルに置き、自分の分と、そしてもう一つ、空の席の前に箸を添えた。
二人で、窓の外を見た。季節は巡り、マンションの脇にある桜の木が、満開の花をつけていた。
「綺麗ねえ、まこと」
「うん、綺麗だね、ばあちゃん」
その時、田中は気づいた。サチコの身体が、桜の花びらのように淡い光を放ち、ゆっくりと透き通っていく。
「ああ、美味しかった。世界で一番の、カツ丼だったわ。ごちそうさま」
彼女は、食べていないはずのカツ丼に、満足そうに言った。
「もう、一人で大丈夫ね、まこと」
その声には、もう何の心配も宿っていなかった。
「うん。もう大丈夫だよ。ばあちゃんがいてくれたから」
田中が微笑んで答えると、サチコも安心したように、深く頷いた。そして、ふわりと光の粒子となって、春の優しい光の中へと溶けるように消えていった。
部屋に、再び完全な静寂が戻った。
だが、その静寂は、もはや田中を苛む孤独の象徴ではなかった。彼の心は、祖母が残してくれた計り知れないほどの愛情で満たされていた。彼の完璧な城塞は、跡形もなく崩れ去っていた。その瓦礫の上には、人と繋がることの温かさを知った、新しい田中誠人が立っていた。
数日後。田中はマンションの廊下で、隣の部屋の住人とすれ違った。以前の彼なら、目を伏せて足早に通り過ぎただろう。しかし、彼は立ち止まり、少し照れながら、しかしはっきりとした声で言った。
「こんにちは」
隣人は一瞬驚いた顔をしたが、すぐににこやかな笑顔で返してくれた。
「こんにちは」
たった一言の挨拶。しかしそれは、田中にとって、世界との新しい扉を開いた瞬間だった。
自室に戻り、綺麗に片付いたテーブルを見る。そこにある食器は、もちろん一人分だ。
それでも、彼はもう独りではなかった。心の中に、いつだって「美味しい?」と笑いかけてくれる、世界で一番優しい同居人がいるのだから。
一人だけど、独りじゃない。田中は窓の外の桜を見上げ、小さく、しかし確かな声で呟いた。
「ただいま、ばあちゃん」