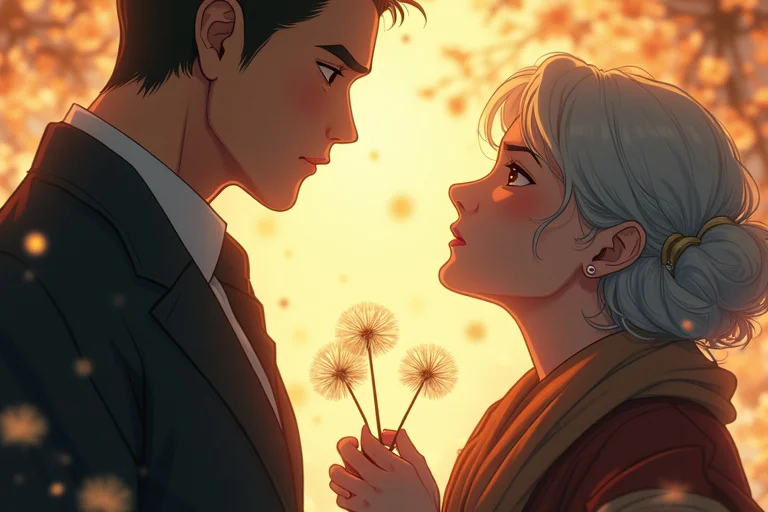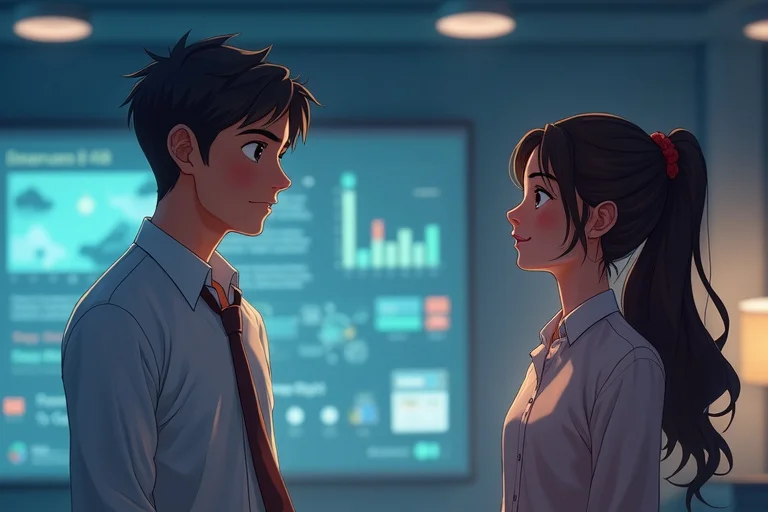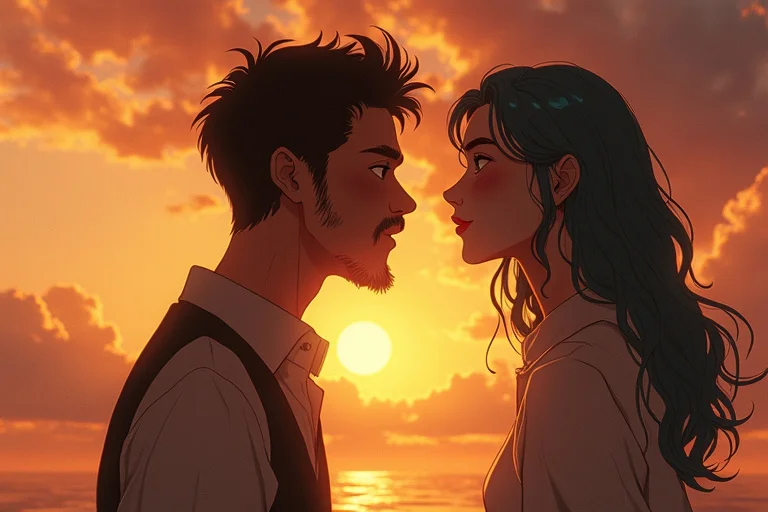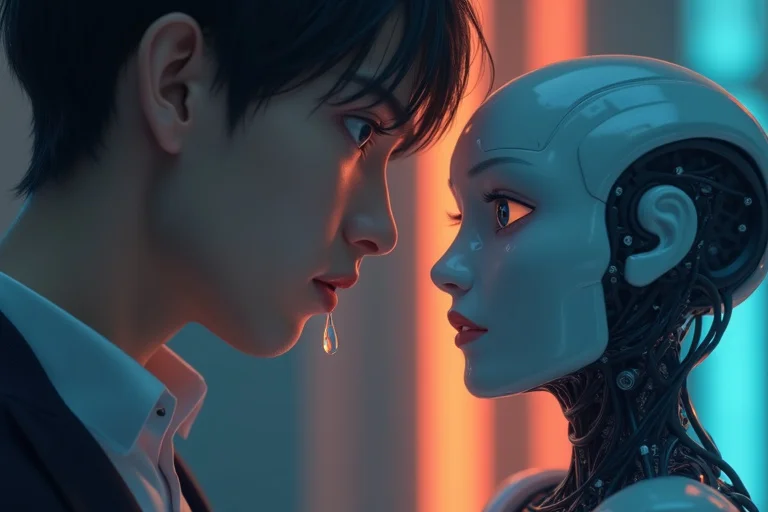斎藤誠(さいとうまこと)、28歳、独身。彼の人生は、心配と不安という二種類の糸で織り上げられた、非常に繊細なタペストリーのようなものだった。トーストを焼けば「この焼き加減は発がん性物質を誘発しないだろうか」と悩み、電車に乗れば「この吊り革は、前世でどんな罪を犯した者が握ったのだろうか」と、壮大なスケールで思い悩む。彼にとって、日常とはすなわち、無数の地雷が埋め込まれた戦場に他ならなかった。
そんな斎藤の平穏(本人はそう思っている)なアパート暮らしに、ある土曜の昼下がり、最大級の地雷が投下された。カタン、と郵便受けから軽い音がして、前の部屋の住人から回覧板が差し込まれたのだ。そこには「203号室へお回しください」という、何の変哲もない付箋。問題は、その203号室にあった。
昨日、隣に引っ越してきた新しい住人。斎藤はドアスコープという名の潜望鏡から、その姿を捉えていた。陽光を味方につけた艶やかな黒髪、知性を感じさせる涼やかな目元、荷物を運ぶ仕草さえも洗練された、まるでファッション誌から抜け出してきたかのような女性。斎藤の心臓は、老朽化したエンジンよろしく、けたたましい音を立ててオーバーヒートしかけた。
回覧板を渡す。たったそれだけの行為が、彼の中では「未接触の知的生命体とのファーストコンタクト」に匹敵する、超高難易度ミッションへと昇華されたのである。
作戦名は「オペレーション・ネイバーフッド」。斎藤は、まず緻密な情報収集から始めた。彼女の生活リズムを把握するため、壁に耳を当て、水の流れる音、微かなテレビの音、くしゃみの回数まで記録する。それは最早、諜報員のそれに近かった。
「ふむ…午前中は活動的だが、午後は静かになる。おそらく、昼食後に読書でもしているに違いない。ならば、思考が最もクリアになる午後3時前後がベストタイミングか…?」
ブツブ-ツと呟きながら、彼は部屋の中を歩き回り、完璧なシミュレーションを開始した。
「失礼します。お隣の、201号室の、斎藤です」
壁に向かって、彼は何度もお辞儀の角度を調整する。45度は丁寧すぎる。30度が最適か。いや、初対面なら33度が誠実さの黄金比かもしれん。声のトーンは?ドの音か、レの音か。低すぎると不審がられ、高いと軽薄に思われる。
服装も問題だった。クローゼットの中身を全てベッドの上にぶちまけ、一人ファッションショーが開催される。チェックのシャツはオタクっぽい。黒のTシャツは威圧感がある。悩みに悩んだ末、彼は「最も害のない人間」を演出できる、ベージュのチノパンと白のポロシャツという、究極の無難コーデに身を包んだ。
そして運命の土曜日、午後3時14分。斎藤が円周率に無限の可能性を見出し、設定した決行時刻。彼は深呼吸を繰り返し、心臓に「落ち着け、まだ爆発するな」と言い聞かせた。手には、まるで国家機密の書類のように、回覧板を固く握りしめている。
「よし」。
覚悟を決め、音を立てないよう、スパイ映画の主人公さながらにドアノブを回す。廊下へと続く光が、彼の顔を荘厳に照らし出した。隣の203号室まで、わずか三歩。人類にとっての月面着陸に等しい、偉大な三歩を踏み出そうとした、まさにその瞬間だった。
ガチャリ。
世界から、音が消えた。斎藤の思考が完全に停止する。あろうことか、目の前の203号室のドアが、内側から開いたのだ。
そこには、予想通り、あの女神が立っていた。手にはゴミ袋を持っている。
斎藤の脳内で、何百回と繰り返したシミュレーションのデータが、火花を散らしてショートした。「相手から出てくる」という、あまりにも初歩的で、あまりにも致命的なパターンが、彼の計画には含まれていなかったのだ。
女神――高橋と名乗るであろう彼女――は、目の前に仁王立ちする斎藤を見て、少しだけ目を丸くした。
どうする?どうすればいい?挨拶か?会釈か?逃げるか?斎藤の頭の中を、あらゆる選択肢が猛スピードで駆け巡り、そして衝突し、最終的に彼が導き出した答えは、そのどれでもなかった。
彼は、スッと背筋を伸ばし、美しいほどの「気をつけ」の姿勢を取った。そして、胸に抱えていた回覧板を両手で持ち、静かに、厳かに、まるで神聖な儀式を執り行う神官のように、水平に前方へと滑らせたのだ。
ヒュルルル……。
斎藤の手を離れた回覧板は、まるで最新鋭のドローンのように、無音で滑空した。それは美しい放物線を描き、高橋さんの足元に、ストン、と完璧に着地した。
静寂。蝉の声だけが、やけに大きく聞こえる。
高橋さんは、自分の足元にある回覧板と、彫像のように固まった斎藤の顔を、二、三度、不思議そうに往復させた。
終わった。俺の社会的な生命は、今、この廊下で完全に終わった。斎藤は、魂が口から抜け出ていくのを感じていた。
だが、その時だった。高橋さんが、くすりと小さく笑ったのだ。
彼女はゆっくりと屈んで回覧板を拾い上げると、悪戯っぽい笑みを浮かべて言った。
「あの…もしかして、これが今流行りの『非接触型回覧板デリバリー』ってやつですか?なんだか…すごくアーティスティックですね」
「え?」
斎藤の口から、間抜けな声が漏れた。
「私、高橋です。こんなに独創的なご挨拶、生まれて初めてです。もしかして、お仕事、デザイナーか何かですか?」
彼女は、斎藤の理解不能な奇行を、何か最先端の表現方法だと勘違いしたらしい。その目は、尊敬と好奇心でキラキラと輝いている。
「い、いえ、あの、ただの事務職で…」
しどろもどろに答える斎藤に、彼女は「ご謙遜を」と微笑んだ。
「これからよろしくお願いしますね、ミステリアスなお隣さん」
こうして、極度の心配性が引き起こした前代未聞の奇行は、本人の意図とは180度違う形で、最高の第一印象を演出してしまった。
斎藤誠の心配の種は、一つ解決するどころか、「ミステリアスな芸術家(という誤解)」を維持しなければならないという、遥かに巨大で厄介なものへと進化を遂げた。彼の戦いは、まだ始まったばかりである。