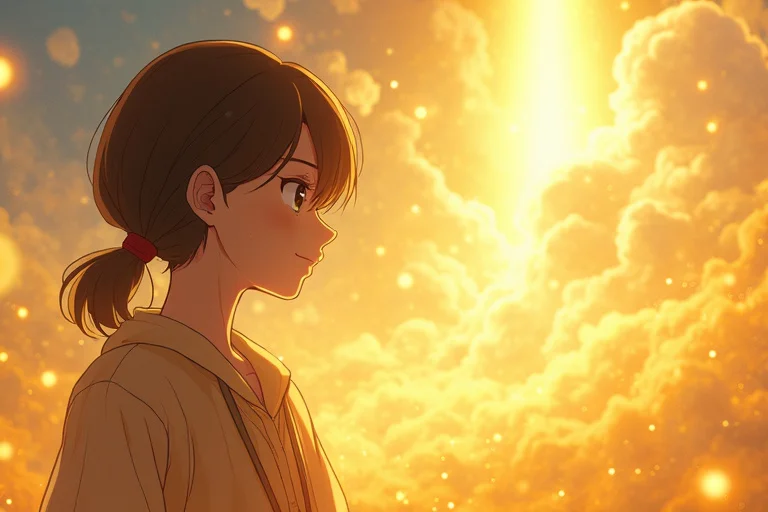佐藤健太、三十二歳。彼の人生のモットーは「平穏無事」である。キーボードのタイプ音が機関銃の掃射のように響き、鳴りやまない電話が空襲警報に聞こえるオフィスで、彼の精神はすり減る一方だった。もはや、週末に趣味の盆栽を眺め、クラシック音楽を聴くだけでは、心のささくれは癒えない。
そんな彼が、ネットの海で一条の光を見つけた。
『世界一静かなカフェ Silentium』
レビューには熱のこもった言葉が並んでいた。「針一本落ちる音すら許されない、究極の静寂空間」「ここでは、呼吸すらアートになる」。佐藤は歓喜した。これだ。私が求めていたサンクチュアリは、ここにあったのだ。
決戦の土曜日。佐藤は万全の態勢で臨んだ。衣擦れの音すら立てぬよう、全身を上質なコットンで固め、靴は靴底に特殊な静音加工が施されたウォーキングシューズを選んだ。ポケットの中の小銭は抜き、スマートフォンはマナーモードではなく電源オフ。完璧だ。
目的のカフェは、路地裏にひっそりと佇んでいた。オーク材の重厚な扉には、真鍮のプレートで「Silentium」とだけ刻まれている。佐藤は深呼吸を一つして、まるで貴重な文化財に触れるかのように、そっと扉を押した。
途端、世界から音が消えた。
外の喧騒が嘘のように遮断され、店内は水底のような静寂に満たされていた。客たちは皆、まるで精巧な蝋人形のように席につき、微動だにしない。カウンターの中の店員ですら、忍びのように無音で動いている。佐藤は感動に打ち震えた。ここが、約束の地か。
案内された席に着き、メニューに目を落とす。それはタブレットだったが、タップ音などという野蛮なものは許されない。視線でカーソルを動かし、瞬きで決定する最新鋭のシステムだ。佐藤は「静寂のブレンドコーヒー」を厳かに注文した。
周囲を観察すると、その徹底ぶりに改めて感心させられた。隣の席の老婦人は編み物をしているが、毛糸が擦れる音一つしない。向かいの学生は分厚い学術書を読んでいるが、ページをめくる音も皆無。一体どうなっているんだ。彼らは静寂のプロフェッショナル集団なのか。
やがて、コーヒーが運ばれてきた。店員は恭しくカップを差し出し、パントマイムで「ごゆっくりどうぞ」と優雅に伝えてくる。佐藤がカップをソーサーに戻そうとした瞬間、その店員が電光石火の速さで間に割って入り、衝撃吸収用の特殊なジェルコースターを滑り込ませた。カチャリという音すら、ここでは禁忌なのだ。
佐藤は恍惚とした。これこそが究極の贅沢。彼はゆっくりとカップを口に運び、芳醇な香りの液体を一口、喉に流し込んだ。そして、その温かさが胃の腑に染み渡った、まさにその時だった。
ぐぅぅぅうううううううう……。
静寂の殿堂に、あまりにも場違いで、あまりにも生命感あふれる音が響き渡った。佐藤健太の、腹の虫である。
時が、止まった。
いや、元々止まっているように見えたのだが、今度は次元の違うレベルで凍りついた。編み物をしていた老婦人の指が痙攣し、学術書を読んでいた学生の目が大きく見開かれる。店内のすべての客、すべての店員の視線が、音源である佐藤の腹部に、レーザー光線のように突き刺さった。
音を立ててはいけない。声を出してはいけない。しかし、この沈黙は耐えられない。佐藤の額から、滝のような汗が流れ落ちた。
そのとき、店長らしき長身痩躯の男が、能楽師のような摺り足で、しかし鬼の形相で佐藤ににじり寄ってきた。そして、蚊の鳴くような、いや、蚊の羽音すら聞こえないほどの囁き声で言った。
「お客様……当店の名を、ご存知で?」
絶体絶命。万事休す。佐藤が人生を諦めかけた、その瞬間だった。
向かいの席の学生が、バッと立ち上がった。そして、悲壮な覚悟を決めた顔で、自らの腹を力強く叩き始めたのだ。「犯人は私です!この私が、不届きにも腹を鳴らしたのです!」と、その全身が雄弁に語っていた。
すると、それを合図にしたかのように、隣の老婦人もおもむろに立ち上がり、編み棒を指揮棒のように振りながら、自分のお腹をさすって悲しげな表情を浮かべる。「いいえ、わたくしですわ。昨夜の煮物が…」とでも言いたげな、見事なサイレント演技だ。
そこからは、阿鼻叫喚のパントマイム合戦だった。あちらの席ではサラリーマン風の男が、自分がくしゃみをしそうだとアピールし、周囲の客が全力で彼の鼻をつまんで阻止している。こちらの席では、カップルが「私よ」「いや俺だ」と無音の痴話喧嘩を繰り広げている。静寂を破った罪を、誰もが我先にとなすりつけ合っているのだ。
佐藤は呆然と、その光景を眺めていた。ここは、世界一静かなカフェではなかったのか。違う。ここは、静寂というお題で繰り広げられる、世界一カオスな即興劇の舞台だったのだ。常連客たちは、予期せぬ「音」というハプニングを、最高のスパイスとして楽しんでいたのである。
鬼の形相だった店長は、いつの間にか満足げな笑みを浮かべ、このサイレント・ドタバタ劇をうっとりと見渡している。そして、主役である佐藤に向き直り、深々とお辞儀をすると、パントマイムでこう伝えた。「ブラボー!お客様!最高のパフォーマンスでした!」
店を出る際、店長がそっと一枚のメモを渡してきた。
『またのお越しを、心よりお待ちしております。次回はぜひ、しゃっくりでのご参加を』
帰り道、佐藤は込み上げてくる笑いを抑えきれなかった。車のクラクションも、雑踏のざわめきも、なぜかさっきまでよりずっと心地よく聞こえる。彼が本当に求めていたのは、物理的な無音ではなく、日常のしがらみから解放される「心の平穏」だったのだ。そして彼は、それを世界で一番静かで、世界で一番やかましいカフェで見つけることができた。
翌週の土曜日。佐藤健太は、炭酸水を一気飲みしながら、あの重厚な扉に向かって歩いていた。彼の顔には、もはやストレスの色はなく、次なる舞台に胸を躍らせる、一流のコメディアンのような笑みが浮かんでいた。