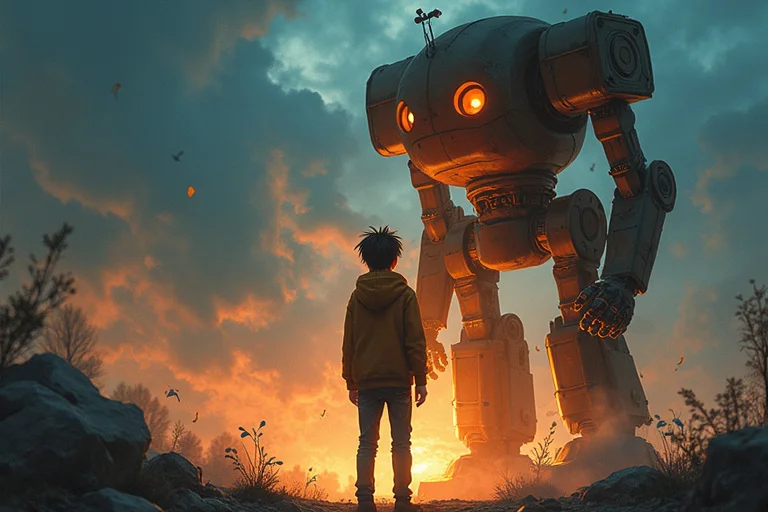第一章 生前死亡届と笑わない男
田中誠一、四十五歳、独身。市役所戸籍係に勤めて二十三年。彼の人生は、ミリ単位で引かれた定規の目盛りのように正確無比だった。朝は六時ちょうどに起床し、寸分違わず淹れたコーヒーを飲み、七時十五分の電車に乗る。彼のデスクは常に完璧に整頓され、書類の角度一つにも彼の哲学が宿っていた。同僚たちは彼を「歩く六法全書」「感情を忘れたアンドロイド」と陰で呼んだが、田中はそれをむしろ誇りに思っていた。無駄な感情は、ミスの温床でしかない。
そんな彼の鉄壁の日常に、亀裂が入ったのは、ある蒸し暑い夏の日の午後だった。
窓口の呼び出しボタンが鳴り、田中が「次の方、どうぞ」と無機質な声をかけると、カウンターの向こうに、ひょっこりと小柄な老婆が現れた。紫色の派手なシャツに、鳥の巣のようにくしゃくしゃに結い上げた白髪。顔には、まるで油絵のように深い皺が刻まれている。
「これを、お願いしたいんじゃが」
老婆はしわくちゃの手で、一枚の紙を田中の前に滑らせた。
『死亡届』。
田中は慣れた手つきでそれを受け取り、記載事項を確認し始めた。死亡者氏名、鈴木ハナ。本籍、住所、生年月日……。しかし、彼の目はある一点で釘付けになった。死亡年月日。そこには、インクの匂いも新しい文字で、こう書かれていた。
『明日』
田中は眉一つ動かさず、顔を上げた。目の前の老婆は、ニコニコと人懐っこい笑みを浮かべている。
「あの……鈴木さん、で、お間違いないでしょうか」
「いかにも。ワシが鈴木ハナじゃ」
「失礼ですが、この死亡届は、どなたの……」
「ワシのじゃよ」
老婆は胸を張った。田中は数秒間、思考を停止させた。彼の脳内データベースに、このケースは存在しない。生きた人間が、自らの死亡届を、しかも未来の日付で提出する。前代未聞であり、非論理的であり、何よりも、規則違反だ。
「……受理できません」田中は、感情を押し殺した声で言った。「死亡届は、ご本人が亡くなられた後、親族の方などが提出するものです。ご存命の方が、ご自身のものを提出することは……」
「堅いのう、あんた。ワシは明日死ぬことに決めたんじゃ。死んでからじゃと、自分で持ってこれんじゃろ。だから、先に済ませとこうと思ってな。親切心じゃよ、親切心」
「死ぬことに、決めた……?」
「そうじゃ。人生最後のビッグイベントじゃからの。段取りは大事にせんとな」
老婆はケラケラと笑った。その皺だらけの顔が、太陽の下で干された梅干しのように、さらにくしゃりとなった。田中は眩暈を覚えた。これは彼の理解の範疇を完全に超えている。彼の世界は白と黒、是と否で構成されている。こんな冗談のような灰色は存在しない。
「お引き取りください。これは悪質な悪戯と見なします。これ以上業務を妨害されるようでしたら、警備員を呼びます」
田中の声は、冬の朝の空気のように冷え切っていた。
しかし、老婆は全く動じなかった。彼女はカウンターに肘をつき、いたずらっぽく片目をつぶった。
「そうかい。まあ、ええわ。じゃあ、明日また来るわ。ちゃんと、死んでからな」
そう言い残すと、鈴木ハナと名乗る老婆は、軽やかな足取りで去っていった。残されたのは、インクの新しい『明日』という日付と、田中の混乱しきった心だけだった。その日、彼は生まれて初めて、業務報告書に「特異事例:生前死亡届の提出未遂」と記入することになった。定規で引かれた彼の人生に、初めてインクの染みが落ちた瞬間だった。
第二章 史上最悪の葬儀
翌日、田中は一日中、落ち着かなかった。窓口に立つたびに、あの紫色のシャツが視界の端をちらつくような気がした。もちろん、鈴木ハナが来ることはなかった。当たり前だ。あれは、ただの老人の気まぐれな悪戯だったのだ。そう自分に言い聞かせ、田中は山積みの書類に意識を集中させようとした。
しかし、その日の夕方、事件は起きた。
「鈴木ハナ様の死亡届をお願いします」
現れたのは、泣き腫らした目をした中年女性だった。彼女が差し出した死亡届には、昨日と同じ名前があった。そして、死亡年月日の欄には、昨日の老婆が予言した通りの『本日』の日付が記されていた。死因は、心不全。田中はゴクリと唾を飲んだ。
偶然か。いや、それにしても出来すぎている。
「ご愁傷様です」
田中は形式通りの言葉を述べながらも、彼の内なる「規則」の警報がけたたましく鳴り響いていた。何かがおかしい。あの老婆の、悪戯っぽい笑みが脳裏に焼き付いて離れない。
週末、田中は柄にもない行動に出た。新聞の訃報欄で鈴木ハナの葬儀の案内を見つけると、彼は黒いネクタイを締め、香典を握りしめて、その式場へと向かった。別に義理があるわけではない。ただ、この胸のざわめきを鎮めるには、自分の目で確かめるしかなかった。
葬儀場は、町の小さな斎場だった。しかし、その雰囲気は異様だった。悲しみに包まれているはずの空間に、どこかチグハグな空気が漂っている。泣き崩れる親族たち。しかし、その涙はまるで舞台役者のように大げさで、嗚咽の声には妙な節回しがついていた。そして、祭壇に飾られた遺影のハナさんは、満面の笑みでこちらにピースサインをしていた。
田中はそっと棺に近づき、中の遺体を覗き込んだ。そこに横たわっていたのは、確かに鈴木ハナだった。だが、その顔は蝋人形のように不自然なほど滑らかで、死化粧というにはあまりに濃すぎた。まるで、眠っているというよりは、「眠っているフリ」をしているように見えた。
疑惑は確信に変わった。
田中は葬儀を抜け出し、死亡届に記載されていたハナさんの住所、古い木造アパートへと向かった。鍵はかかっていなかった。彼は罪悪感を覚えながらも、そっとドアを開ける。
部屋はがらんとしていたが、机の上に一冊の大学ノートが置かれているのが見えた。表紙には、震える文字でこう書かれていた。
『人生最後の舞台計画書 〜笑ってサヨナラ大作戦!〜』
田中はノートを手に取り、ページをめくった。そこに書かれていたのは、常軌を逸した、しかし驚くほど緻密な計画だった。
自分の「死」を壮大なコメディショーとして演出し、偽の葬儀を開く。参列者は、金で雇った劇団員たち。目的は、疎遠になっていた一人息子や友人たちを驚かせ、呆れさせ、そして最後には大笑いさせること。
「ワシの葬式は、最高に面白いお祭りにするんじゃ!」
「涙は禁止!笑いと拍手で送るべし!」
そんな威勢のいい言葉が、ページを埋め尽くしていた。手品の手順、すべるジョーク集、劇団員への演技指導まで、詳細に書き込まれている。
田中は全身の力が抜けるのを感じた。これは、不謹慎という言葉では生ぬるい。死を冒涜し、公文書を偽造し、人々を欺く、前代未聞の詐欺劇だ。彼の信じる「正しさ」や「秩序」が、ガラガラと音を立てて崩れていく。
怒りがこみ上げてきた。こんな馬鹿げたことは許されない。彼は、このふざけた計画を企てた張本人、生きているはずの鈴木ハナを探し出し、法の裁きを受けさせなければならない。
ノートの最後のページに、小さなメモが挟まっていた。「最終舞台:シーサイド劇場にて」。田中はノートを掴み、アパートを飛び出した。彼の心は、正義感と、そして今まで感じたことのない奇妙な好奇心で燃えていた。
第三章 人生最後のアンコール
シーサイド劇場は、かつてストリップ小屋として賑わった後、今は廃墟同然となっている海辺の建物だった。潮風に錆びついたトタン屋根が、夕陽を浴びて物悲しく光っている。田中は、軋むドアを押し開け、中へと足を踏み入れた。
薄暗いホールの中、ほこりっぽい匂いが鼻をついた。客席の椅子はところどころ壊れ、ステージの上だけが、裸電球の心許ない光に照らされている。
その光の中心に、彼女はいた。
紫色のシャツではなく、スパンコールのついた派手なドレスを身にまとった鈴木ハナが、マイクを握って立っていた。彼女は田中に気づくと、ニヤリと笑った。
「ようこそ、田中さん。あんたが最初のお客さんじゃ」
「鈴木さん……!あなたという人は!」
田中の声は、怒りで震えていた。「公文書偽造、詐欺……これがどれほどの罪になるか分かっているんですか!」
「堅いのう、相変わらず。まあ、そこに座りんしゃい。ショーが始まるで」
ハナさんは悪びれる様子もなく、ステージの袖を指さした。田中は憤慨しながらも、なぜかその場を動けなかった。彼女の纏う空気が、単なる悪戯好きの老人のそれではないことに、気づき始めていた。
「どうして、こんなことを……」
田中の問いに、ハナさんはふっと遠い目をした。
「あんた、ワシがただの暇を持て余したクソババアじゃと思うとるじゃろ」
彼女はドレスの胸元を少し開き、そこから一枚の診断書を取り出した。田中はステージに上がり、それを受け取る。そこに書かれていたのは「末期癌」「余命一ヶ月」という、絶望的な言葉だった。
「医者は言ったわ。『穏やかに、残された時間を大切に』とな。冗談じゃない。ワシの人生は、ちっとも穏やかじゃなかった。夫は早くに死ぬし、女手一つでバカ息子を育てて、毎日ひいこら言いながら働いて……。泣いてる暇なんてなかったんじゃ。だから、最後くらい、ワシらしく、大笑いして終わりたいと思った」
彼女の声は、震えていなかった。むしろ、誇らしげにさえ聞こえた。
「ワシが死んだら、あの子はきっと後悔する。些細なことで喧嘩して、もう何年も口もきいとらん。あの子は、ワシが死んだら、きっと自分を責めて、一生泣いて暮らす。それだけは、嫌なんじゃ。だから、最後に一発、ドデカいイタズラを仕掛けて、『うちのオフクロは最後まで救いようのないアホだったな』って、笑って欲しかったんじゃよ」
その時だった。劇場の錆びた扉が、ギイ、と音を立てて開いた。
「母さん……」
そこに立っていたのは、偽の葬儀で見かけた中年男性――ハナさんの一人息子、健司だった。彼は劇団員から真相を聞き、母を探しに来たのだ。その目は、涙で真っ赤だった。
「なんで……なんでこんなこと……!」
「泣くな、バカ息子!」
ハナさんは息子の顔を見ると、カッと目を見開き、マイクを握りしめた。「さあ、たった一人の観客のために!鈴木ハナ、人生最後のアンコールショーの始まりじゃ!」
スポットライト(ただの裸電球だが)を浴び、彼女はショーを始めた。シルクハットから無理やり出した鳩(のおもちゃ)は床に落ち、意味不明なダジャレは劇場内に虚しく響き渡った。それは、お世辞にも面白いとは言えない、痛々しいほどに下手くそなショーだった。
健司は、その姿を見て、嗚咽を漏らした。しかし、次の瞬間、彼の口から漏れたのは、泣き声の混じった、押し殺したような笑い声だった。
「へたくそ……なんだよ、それ……」
彼は涙を流しながら、笑っていた。必死に息子を笑わせようとする母の、不器用で、滑稽で、そしてあまりにも深い愛情に満ちた姿に。
田中は、その光景をただ呆然と見つめていた。規則。正しさ。秩序。彼が信じてきたすべてが、目の前で溶けていくようだった。人生は、そんな単純なものじゃない。白と黒だけじゃない。こんなにも不格好で、不合理で、そして、どうしようもなく愛おしい瞬間のために、人は生きているのかもしれない。
気づけば、田中の頬にも温かいものが伝っていた。そして、彼は、生まれて初めて、腹の底から声を上げて笑った。涙でぐしゃぐしゃになりながら、ただひたすらに笑い続けた。それは、四十五年間、彼の内側に凍りついていた何かが、ついに溶け出した音だった。
第四章 ハートマークの受理日
それから三週間後、鈴木ハナは本当に亡くなった。今度の葬儀は、本物だった。
しかし、その会場の雰囲気は、以前の偽りの葬儀とはまるで違っていた。祭壇には、シーサイド劇場でスベり倒していた時の、満面の笑みの写真が飾られ、BGMにはチャップリンの映画音楽が陽気に流れていた。
参列者は皆、すすり泣きながらも、その口元には優しい笑みが浮かんでいた。健司は弔辞で、涙と笑いをこらえながら言った。
「僕の母は、世界一料理が下手で、世界一頑固で、そして、世界一くだらない、最高のコメディアンでした。母さん、最後のショー、全然面白くなかったけど、最高だったよ」
会場は、温かい拍手と、しのび笑いに包まれた。
数日後、市役所の窓口。田中は、健司が提出した本物の死亡届を、静かに受け取った。彼は一つ一つの項目を、祈るように確認し、そして、特別な想いを込めて受理印を押した。彼のデスクの隅には、以前まであった精巧な盆栽の代わりに、小さなサボテンの鉢植えが置かれていた。少しトゲトゲしているが、なんだか愛嬌のある、不格好なサボテンだ。
その日の午後、若いカップルが婚姻届を提出しに来た。田中はいつものように書類をチェックする。すると、備考欄の隅に、ボールペンで描かれた小さなハートマークを見つけた。
以前の彼ならば、即座に「規則違反です。この落書きは認められません。新しい用紙に書き直してください」と、氷のような声で告げただろう。
しかし、田中は違った。彼は何も言わずに修正テープを取り出すと、その小さなハートマークを、誰にも気づかれないように、そっと丁寧に消した。そして、顔を上げ、カップルに書類を返しながら、こう言った。
「おめでとうございます。末永く、お幸せに」
その声は、自分でも驚くほど、温かく響いていた。カップルは「ありがとうございます!」と満面の笑みで頭を下げる。
田中は、二人を見送りながら、小さく、本当に小さく、微笑んだ。
人生は、定規で引かれた線の上だけを歩くものではないらしい。時にはみ出したり、曲がったり、おかしな落書きがあったりするからこそ、面白いのかもしれない。
窓の外では、真夏の太陽が、まるでスポットライトのように、世界を明るく照らしていた。彼の人生という名の舞台に、ささやかなユーモアという名の彩りが、確かに加わった瞬間だった。