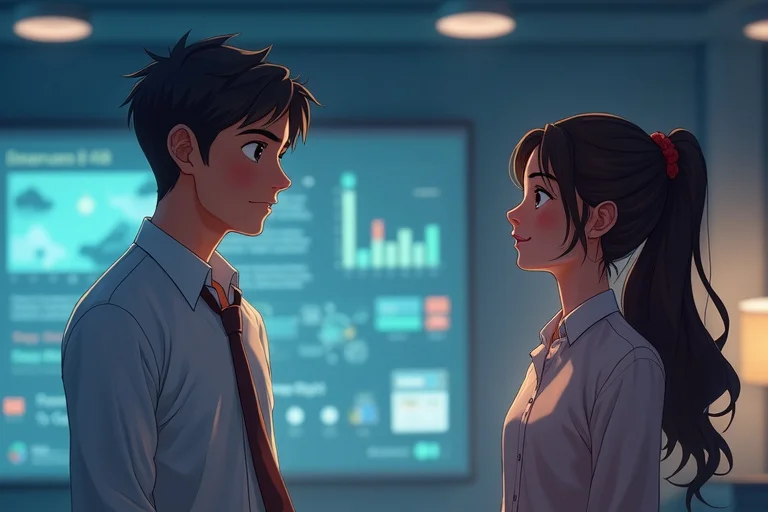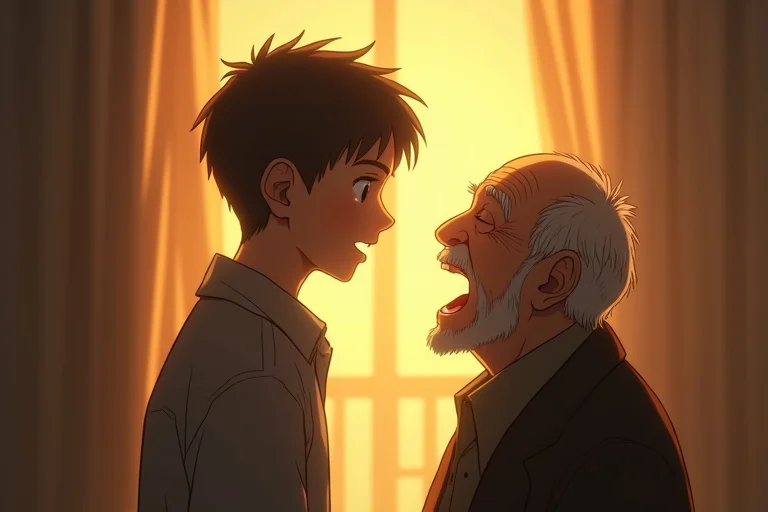鈴木誠(45歳)、保険会社係長。彼のささやかな楽しみは、昼休みに「ひだまり公園」のベンチで過ごすこと。そして、足に怪我を負った一羽のハトとの交流である。彼はそのハトに、勝手に「ポチ」と名付けていた。
「ポチ、お前も大変だなあ。俺もだよ。今日の午後の会議、また部長が無茶なこと言い出すに決まってる」
食べかけのコロッケパンのパンくずを地面に撒くと、ポチが器用についばむ。鈴木は我が子を見守るような優しい目つきで、その様子を眺めていた。
その平和な光景を、茂みの中から高性能な双眼鏡で監視する二つの影があった。
「ヴァイパー、ターゲットが『伝書鳩』と接触しました」
新米スパイのファルコンが、緊張した声で囁く。
「コードネームは『ポチ』…おそらく『P.O.C.H.I』。Powerful Operation Command Headquarters Intelligence…『強力作戦司令本部諜報員』の略称か」
先輩スパイのヴァイパーは、冷静に分析してみせる。実際はただ思いついただけだ。
「『午後の会議』『部長が無茶』…!これは暗号です!『午後』は夜間、『会議』は襲撃。『部長』は敵対組織のボス!今夜、奴らのアジトを叩く計画です!」
ファルコンの目が興奮に輝く。
「落ち着け、ファルコン。奴は伝説の諜報員『サラリ・マン』。その思考は我々の想像を常に超えてくる。早合点は命取りだ」
ヴァイパーはそう言って後輩をいさめたが、内心では(なるほど、その線は濃厚だ)と頷いていた。
鈴木はコロッケパンを食べ終え、デザートに取り掛かった。懐から取り出したのは、老舗和菓子屋「月見堂」の豆大福だ。今日のために、朝一番で買ってきた逸品である。
しかし、その至福の瞬間は突如として破られた。ビニールの包みを開けた瞬間、彼の手が滑り、白い宝石は地面に転がり落ちたのだ。
「あっちゃー!俺の、俺の月見堂がぁっ!」
三秒ルールを適用するにはあまりにも無残な汚れ方だった。鈴木は泣く泣く大福を元の包み紙に戻し、近くのゴミ箱へと葬った。
その一連の動きを、スパイたちは見逃さなかった。
「見ましたか!ヴァイパー!あれはデッド・ドロップです!情報をあのゴミ箱に隠したんです!」
「よし、行けファルコン!中身を確保しろ!」
指令を受け、ファルコンはカラスのように素早くゴミ箱へ駆け寄った。周囲を警戒しながら手を突っ込み、例の包み紙を回収する。
「やりました!これが指令書です!」
意気揚々と戻ってきたファルコンが包み紙を開くと、中にはあんことクリームでぐちゃぐちゃになった紙があるだけだった。
「この黒いシミは…最新の不可視インクか!?アジトに戻って解析します!」
その時だった。ベンチに仕事用の資料を忘れていたことに気づいた鈴木が、「おっと、いけねえ」と慌てて踵を返した。
彼の動きと同時に、物陰から別の組織のチンピラスパイが現れ、ファルコンが持つ「指令書」を奪おうと襲いかかってきた。
鈴木が資料を拾い上げ、「やれやれ」と額の汗を拭う。
その何気ない仕草が、三者三様の解釈を生んだ。
チンピラスパイ「くっ…!あれが伝説の『サラリ・マン』の威圧か!動き出す前に退散しろとの警告か!」
ファルコン「さすがは『サラリ・マン』…!一瞥だけで我々の危機を救ってくださるとは!」
鈴木誠「(あー、汗かいちゃった。午後の会議、絶対長引くなあ…)」
チンピラは恐れをなして逃げ去り、鈴木は何事もなかったかのように会社へ戻っていった。残されたファルコンは、伝説のスパイへの畏敬の念をさらに深めるのだった。
アジトに戻った二人は、さっそく「指令書」の解析に取り掛かった。
特殊なライトをあんこのシミだらけの包み紙に当てると、微かに文字が浮かび上がった。
原材料名:小豆、砂糖、餅米、塩、他
ヴァイパーはゴクリと喉を鳴らした。
「…読めるか、ファルコン」
「はっ!『アズキ』『サトウ』『モチゴメ』『シオ』…!これが次のターゲットリストです!なんという的確な人選…!」
「『アズキ』は武器商人、『サトウ』は汚職政治家、『モチゴメ』は天才ハッカー、そして『シオ』は我々の組織に潜む裏切り者だ…!恐るべき男だ、『サラリ・マン』は全てお見通しだったとは!」
ヴァイパーの顔から冷や汗が流れる。
「急げ、ファルコン!我々も動くぞ!」
二人が壮大な勘違いに基づいて、まったく無関係な人々を追いかけ始めたことなど、鈴木はもちろん知らない。
翌日の昼休み。鈴木はまた、ひだまり公園の同じベンチに座っていた。
「ポチ、昨日は災難だったなあ。でも今日は二個買ってきたからな。一個はお前にやろう」
彼はそう言うと、豆大福の餅の部分だけをちぎってポチの前に置いた。
その光景を、遠くからヴァイパーとファルコンが感涙にむせびながら見つめていた。
「見ろ、ファルコン。我々の働きを労って、報酬を…『二個』…。次の大仕事の予告だ」
「ヴァイパー…!俺、一生『サラリ・マン』についていきます!」
伝説の諜報員『サラリ・マン』こと鈴木誠は、自分が国際スパイ組織から神のように崇められているとは露知らず、ただただ午後の平和なひとときと、豆大福の優しい甘さを噛みしめるのだった。