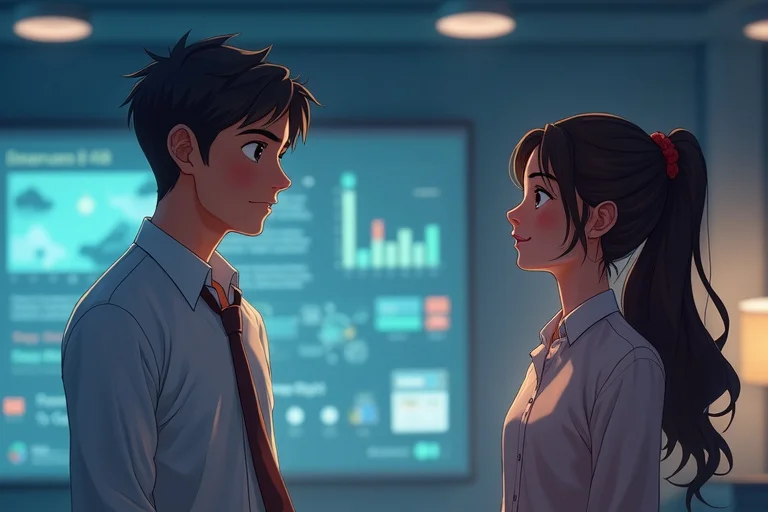田中誠(38歳、独身、経理部主任)の人生は、数字と規則性でできていた。毎朝6時半に起床、7時15分の電車に乗り、就業5分前にはデスクに着く。彼の世界で最大のイレギュラーは、たまに起こる計算ミスか、春先に猛威を振るうスギ花粉くらいのものだった。
その日、田中はいつもの喫茶店『カフェ・ド・ノワール』の隅の席で、熱いコーヒーをすすりながら、午後の監査業務の段取りを頭の中で反芻していた。くたびれたトレンチコートの襟を立て、目深にかぶった帽子は、ただ単に寝癖を隠すためだ。
「…奴が、『沈黙の影(サイレント・シャドウ)』か」
隣のボックス席から、低い声が聞こえた。田中は気にしない。きっと何かのセールストークだろう。時間だ。田中は伝票を掴んで席を立った。その瞬間、隣の席に座っていたサングラスの男二人も同時に立ち上がった。
「お待ちしておりました、シャドウ」
屈強な男が、深々と頭を下げて田中にアタッシュケースを差し出した。中からは、万札の束がチラリと見えている。田中は目を丸くした。新手の詐欺か?それとも何かのドッキリ番組?
パニックになった田中が取った行動は、彼の人生で最も勇敢な行動の一つだった。彼は叫んだ。
「け、結構です!」
そして脱兎のごとく店を飛び出した。その刹那、溜まりに溜まっていた花粉への怒りが爆発した。
「ハ、ハ、ハッークション!!」
天地を揺るがすほどの轟音。それは、これから始まる壮大な勘違いの序曲だった。
黒塗りのセダンの中で、若頭のケンジが興奮気味にボスに報告していた。
「さすがは『沈黙の影』…!俺たちの顔を見るなり、一瞬で状況を把握。報酬を受け取らずに去るとは、なんというプロ意識!そして最後のあの『合図』!間違いありません、ボス!あれは仕事開始の合図です!」
ボスである龍神会組長・鬼瓦権蔵は、サングラスの奥の目を細め、唸った。
「うむ…。あれほどの男が、金に執着するはずもなかろう。あのくしゃみ…いや、咆哮。あれは『標的の命、塵と化す』という言霊に違いない。すぐに調べろ。シャドウがどちらに向かったかを」
彼らが依頼した標的は、敵対する蛇王会(じゃおうかい)の組長、蛇塚(へびづか)だった。そして田中が監査のために向かっていたのは、奇しくも蛇塚が経営する『ヘビヅカ・フーズ』の本社ビルだったのである。
ビルに到着した田中は、極度の緊張で手のひらに汗をかいていた。先ほどの詐欺師(と彼が思い込んでいる男たち)のせいで、心臓はまだバクバクしている。応接室に通され、待っている間も落ち着かない。震える手でボールペンを握った瞬間、ツルリと滑って床に落ちた。
「あ、すみません!」
田中は慌てて机の下に潜り込み、床を這うようにしてペンを探した。
その様子を、向かいのビルの屋上から双眼鏡で監視していたケンジは息を呑んだ。
「ボスッ!シャドウが動きました!机の下に潜り込み、完璧な死角を作り出しました!恐らく、ここから特殊な毒針か何かを…!」
その時だった。応接室のドアが勢いよく開き、蛇塚が血相を変えて入ってきた。
「監査の先生か!すまんが、今日は緊急の……うぐっ!?」
蛇塚は胸を押さえてその場に崩れ落ちた。彼は重度のエビアレルギーだった。たった今、秘書が間違えて持ってきたエビ煎餅を、つまみ食いしてしまったのである。救急車が呼ばれ、ビルは大騒ぎになった。
ペンを見つけて机の下から出てきた田中は、目の前の惨状にただ呆然と立ち尽くすしかなかった。
ケンジからの報告を受けた鬼瓦は、葉巻を落としそうになった。
「な…なんだと?シャドウは、指一本触れずに蛇塚を…?毒か?それとも呪術か?…いや、違う。あれほどの男だ。殺気だけで相手の心臓を止めたに違いない。『沈黙の影』…その名、まさに偽りなし…!」
裏社会に、新たな伝説が刻まれた瞬間だった。
後日、鬼瓦は自ら礼を伝えるべく、ケンジと共に田中の住む古びたアパートを訪れた。インターホンを鳴らすが、応答がない。
「シャドウ、俺だ。鬼瓦だ」
部屋の中にいた田中は、そのヤクザ映画みたいな名乗りを聞いて、心臓が凍りついた。例の詐欺師たちが、家まで押しかけてきたのだ!恐怖のあまり、田中は息を殺してドアに背中を押し付けた。
その時、悲劇が起こった。田中の背中に押された拍子に、部屋の隅に置いてあった熱帯魚の水槽がグラリと傾き、床に落下。ガラスが割れ、水と、一緒に敷き詰められていた真っ赤な溶岩石が、ドアの隙間から廊下へと流れ出した。
ドアの外で待っていた鬼瓦とケンジは、足元に広がる生々しい赤黒い液体を見て絶句した。
「こ、これは…血…?」ケンジが震える声で言った。
「馬鹿者!これは返り血だ!」鬼瓦が叫ぶ。「シャドウは、次の仕事の汚れを落としていたのだ!我々は、その神聖な儀式の邪魔をしてしまった…!」
二人の目に、ドアの横に無造作に置かれた田中の趣味の盆栽が映った。鋭く、まるで凶器のように剪定された松の枝が、月明かりに不気味に光っている。
「あれは…暗殺用の武器か…?」
「なんと恐ろしい…。あの枝の一突きで、人の命を…」
もはや、二人の脳内では田中誠は神か悪魔にも等しい存在と化していた。
「シャドウ!報酬はいつものポストに入れておく!邪魔をしたな!」
鬼瓦はそう叫ぶと、ケンジを引きずるようにして逃げ帰っていった。
部屋の中で、田中は「ポスト…?」と首をかしげながら、割れた水槽と死んでしまったネオンテトラを前に、途方に暮れていた。
数日後。アパートの集合ポストを開けた田中は、分厚い封筒を見つけた。中には、諭吉の札束がぎっしりと詰まっていた。
「わあ!町内会の福引、特賞が当たったのかな?ラッキー!これで新しい水槽と、憧れの古代魚が買えるぞ!」
その頃、裏社会では「沈黙の影」の伝説がさらに神格化され、彼の名を聞くだけで失禁する悪党が続出していたという。
そして、本物の「沈黙の影」は、いまだに『カフェ・ド・ノワール』で、来ない依頼人を待ち続けているのだった。