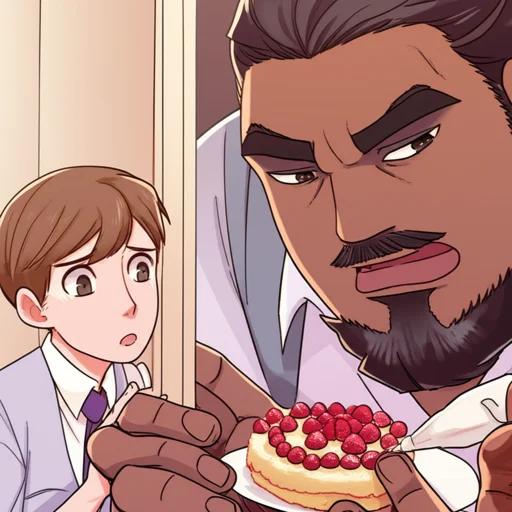第一章 死者からのクレーム
佐藤健人の世界は、A4サイズの紙と、そこに引かれた罫線でできていた。市役所の戸籍係として勤めて八年。彼の毎日は、出生、婚姻、そして死亡という人生の三大イベントを、定められた書式に則って処理するだけの、インクと紙の匂いがする単調な繰り返しだった。彼はその正確さと几帳面さを誇りに思っていたが、同時に、自分の人生がまるで書き損じを許されない公文書のように、窮屈で色褪せていることにも気づいていた。
その日も、健人は山積みの書類と格闘していた。蛍光灯の白い光が、彼の黒縁メガネに反射する。窓の外では子供たちの笑い声が聞こえたが、それはまるで遠い国の出来事のようだった。その時だ。カウンターに、バンッ、と大きな音が響いた。
見ると、派手なアロハシャツを着た老人が、仁王立ちでこちらを睨みつけていた。日に焼けた顔には深い皺が刻まれ、真っ白な髪は無造作に逆立っている。年の頃は七十代半ばだろうか。
「おい、若いの」老人はしゃがれた声で言った。「ワシは死んどらんぞ」
健人は眉をひそめた。また酔っぱらいか、認知症の老人だろうか。彼はマニュアル通りの冷静さで応対する。
「お客様、どのようなご用件でしょうか」
「用件もクソもあるか! ワシは田中一郎だ。三年前に、ここでワシの死亡届が出されたはずだが、あれは真っ赤な嘘っぱちだ! 取り消せ!」
田中一郎。その名前には聞き覚えがあった。健人は手元の端末で検索をかける。確かに、三年前に「田中一郎」氏の死亡届を処理したのは、自分自身だった。死因は心不全。享年七十二歳。手続きに不備は一切なかったはずだ。
「お客様、恐れ入りますが、ご本人確認を……」
「本人だと言っとるだろうが!」老人はカウンターを再び叩いた。「この顔を見ろ! この声を聞け! これ以上、どんな証明がいる!」
その勢いに、健人はたじろいだ。彼の目は冗談を言っているようには見えなかった。むしろ、その瞳の奥には、長すぎる昼寝から覚めたばかりのような、奇妙な生命力があふれていた。
「ですが、田中様は公式に亡くなられたことになっております。手続き上、一度受理された死亡届を……」
「手続き、手続きって、お前はそれしか言えんのか!」老人は呆れたように首を振った。「いいか、若いの。人生はな、A4の紙一枚で終わらせていいほど、安っぽくねえんだよ」
その言葉は、健人の心の最も柔らかな部分を、予期せず突き刺した。彼の世界を構成していた罫線が、一瞬、ぐにゃりと歪んだ気がした。この日を境に、佐藤健人の退屈で正確な日常は、天国からのクレームという、前代未聞の不条理によって、根底から覆されることになるのだった。
第二章 人生という名のサンバ
自称・田中一郎の老人は、健人の生活に、まるで台風のように割り込んできた。
「身元を調査する」という名目で連絡先を交換してしまったのが運の尽きだった。翌朝から、健人のスマートフォンは、田中からの意味不明なメッセージと着信で鳴りやまなくなった。
『若いの、今すぐ海に行くぞ! クラゲがワシを呼んでる!』
『サンバカーニバルの衣装、お前の分も用意した。サイズはLでよかったか?』
健人はその都度、「業務に支障が出ますので」と丁重に断ったが、田中は全く意に介さなかった。ある日の昼休み、健人が公園のベンチでコンビニのサンドイッチを頬張っていると、どこからともなく陽気なサンバのリズムが聞こえてきた。まさか、と思う間もなく、七色の羽飾りをつけた田中が、屈強な男たちと共に現れ、健人の周りで踊り始めたのだ。
「さあ、若いの! 人生は楽しまなきゃ損だ! ステップはこうだ、ワン、ツー、スリー!」
「や、やめてください! 人が見ています!」
健人は顔を真っ赤にして抵抗するが、田中に腕を引かれ、無理やり踊りの輪の中に引きずり込まれる。ぎこちない動きで手足をばたつかせる健人の姿に、周囲の親子連れからクスクスと笑い声が漏れた。屈辱的だった。だが、太陽の光を浴び、汗をかき、馬鹿馬鹿しいリズムに身を任せているうちに、健人の心の中に、今まで感じたことのない奇妙な高揚感が芽生え始めていた。いつも自分を縛り付けていた「他人の目」という鎖が、少しだけ緩んだような気がした。
その一方で、健人は職務として田中の身元調査を進めていた。驚くべきことに、警察に照会した指紋は、故・田中一郎氏のものと完全に一致した。親族は既に他界しており、確認のしようがない。書類上も、物理的な証拠も、目の前の老人が「本人」であることを示している。死者が蘇るなど、ありえない。だが、事実は目の前にあった。
ある夜、健人は田中に呼び出され、古びたジャズバーにいた。
「ワシな、昔は役所のあんたみたいに、クソ真面目な男だったんだ」
カウンターでグラスを傾けながら、田中はぽつりと言った。
「やりたいことも言えず、言われたことだけをこなす毎日。それで、いい人生だったなんて言えるか?」
その問いは、健人自身の胸に突き刺さった。健人は自分の人生を肯定できるだろうか。規則と前例に守られた、安全だが色のない日々。
「……田中さんは、後悔していないんですか。もっと早く、こうしていればよかった、とか」
健人が尋ねると、田中はニヤリと笑った。
「後悔? 馬鹿言え。ワシの人生は、三年前から始まったんだ。今は、毎日がリターンマッチよ」
その笑顔は、夕焼けのように温かく、そして少しだけ寂しそうに見えた。健人は、この破天荒な老人の奔放さの裏に、何か深い理由が隠されているのではないかと感じ始めていた。彼の人生をかき乱すこの台風は、ただの迷惑な存在ではなく、自分に何かを教えようとしているのかもしれない。健人の心は、規則正しい書類棚から飛び出した一冊の本のように、どこへ向かうかわからないまま、ページがめくられていくのを感じていた。
第三章 二人で一人の証明写真
健人の心は揺れていた。田中一郎という男の存在は、彼の信じてきた「正しさ」の定義そのものを曖昧にしていた。書類の上では死んでいる男が、目の前で誰よりも生き生きと人生を謳歌している。この矛盾をどう解釈すればいいのか。
決定的な転機は、ある雨の日に訪れた。健人は、田中のアパートを半ば強引に訪ねた。何か手がかりがあるはずだと信じていたからだ。散らかった部屋の中、健人の目は、壁に飾られた一枚の古い写真に釘付けになった。
それは、二人の中年男性が、ぎこちなく肩を組んで写っている写真だった。一人は、今目の前にいる田中一郎にそっくりな、陽気で快活そうな男。そしてもう一人は、まるでその対極にいるかのように、控えめで、内気そうな、寂しげな笑みを浮かべた男だった。健人は息を呑んだ。その内気そうな男の顔は、故・田中一郎氏の死亡届に添付されていた顔写真と瓜二つだったのだ。
「……この人は、誰なんですか」
健人の震える声に、今までのおどけた態度が嘘のように、老人は静かに目を伏せた。
「……そいつが、本物の田中一郎だ。ワシの、たった一人の親友だよ」
老人の本当の名前は、鈴木次郎といった。
彼が語り始めた物語は、健人の想像を遥かに超える、切なくも温かいものだった。本物の田中一郎は、鈴木とは正反対の性格で、極度に内気で、自分の意見をほとんど口にしない男だったという。彼はたくさんの夢を持っていた。世界中を旅すること、大勢の前で歌うこと、派手なダンスを踊ること。だが、その夢を誰かに語ることさえできず、ただ胸の中にしまい込んだまま、病でこの世を去った。
「あいつの口癖はな、『もし人生をやり直せたら』だった」
鈴木の声は、雨音に混じって静かに響いた。
「死ぬ間際、あいつはワシに言ったんだ。『次郎、俺の代わりに生きてくれ。俺ができなかったことを、全部やってくれ』ってな。だからワシは、あいつになったんだ。あいつの夢を、この身体で叶えるために」
それは、親友の無念を晴らすための、壮大で、馬鹿げていて、そして何よりも美しい嘘だった。指紋の一致も、生前の田中が「俺が生きていた証だ」と冗談めかして、鈴木の指紋を自分のものとして役所に登録していたという、愛すべき悪戯の結果だった。
「ワシは、あいつの人生を盗んだ詐欺師だ。あんたが正しい。書類の上では、ワシは存在しない人間だ」
鈴木はそう言って、自嘲気味に笑った。
健人は言葉を失った。彼の信じてきた「正しさ」が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちていく。書類上の真実。法律上の正義。それらは、一人の男が親友のために捧げた、この途方もない愛情の前で、果たしてどれほどの意味を持つのだろうか。健人の内面で、規則と感情が激しくぶつかり合っていた。A4用紙の罫線でできた世界が、完全に消え去った瞬間だった。
第四章 世界で一番温かい嘘
翌日、健人は市役所の自分の席で、一枚の書類を前に、長い時間動けずにいた。それは、鈴木次郎を公文書偽造の疑いで告発するための内部報告書だった。規則に従えば、これを提出するのが彼の仕事であり、彼の「正しさ」だった。だが、彼の指は鉛のように重く、動かなかった。
脳裏に蘇るのは、サンバのリズムに無理やり乗せられた、あの屈辱的で、しかし妙に楽しかった昼下がり。ジャズバーで聞いた「人生はリターンマッチだ」という言葉。そして、親友を想う鈴木の、寂しげで温かい笑顔。
健人はゆっくりと立ち上がると、その報告書をシュレッダーにかけた。細断された紙片が、まるで彼の過去の価値観の残骸のように見えた。そして彼は、故・田中一郎の戸籍謄本の備考欄に、新しいペンで、震える手で、しかし確かな意思を持って、一行を書き加えた。
『特記事項:田中一郎氏、本日、人生を謳歌するため再臨。当職、心よりこれを祝福す。』
それは公務員として、決して許される行為ではなかった。だが、佐藤健人という一人の人間にとっては、人生で最も「正しい」行いだと確信できた。
数日後、市役所の窓口に、アロハシャツ姿の鈴木がひょっこり顔を出した。
「よう、若いの。世話になったな」
「……いえ」健人は少し照れながら応えた。「次は何をされるんですか?」
「次は、あいつが一番やりたがってた月旅行の計画でも立てるかな! まあ、まずは手始めに富士登山からだがな!」
鈴木はガハハと豪快に笑うと、健人に向かって敬礼し、背を向けた。その背中は、以前よりも少しだけ大きく、そして誇らしげに見えた。
健人は、夕日に染まる空に向かって、軽やかな足取りで去っていく鈴木の背中を、窓からずっと見送っていた。彼の机の上には、いつの間にか一枚の写真が置かれていた。それは、サンバカーニバルの日、七色の羽飾りの前で、困惑しながらも満面の笑みを浮かべている健人と、悪戯っぽく笑う鈴木が写っている写真だった。
写真の中の自分は、今まで見たことのないほど、生き生きとした顔をしていた。
健人はそっと写真に触れ、フッと小さく笑みを漏らした。彼の世界を縛っていた罫線はもうない。そこには、少しくらい書き損じがあってもいい、不条理で、予測不能で、だからこそ愛おしい、無限の白紙が広がっていた。
人生は、A4用紙一枚で測れるほど、安っぽくはない。
そのことを教えてくれた、天国からのクレームと、世界で一番温かい嘘つきに、健人は心の中で、そっと感謝した。