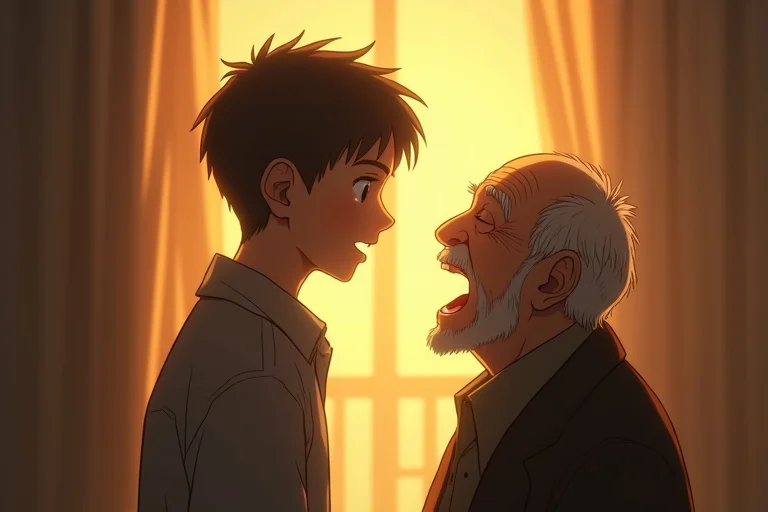佐藤健太の事務所のドアは、今日も家賃の督促状でデコレーションされていた。事務所といっても、日当たりの悪い六畳一間のアパートで、同居人はホコリくらいなものだ。鳴らない電話を眺めながら、コンビニの塩むすびをかじっていたその時、ドアが重々しくノックされた。
現れたのは、息をするたびにダイヤモンドとシルクの匂いがしそうな老婦人だった。西園寺アサミと名乗った彼女は、イタリア製の革張りのソファでもあるかのように、健太のせんべい布団の端に腰掛けた。
「探していただきたいのです。我が家の宝、エリザベス三世を」
差し出された写真には、雪のように白く、サファイアの瞳を持つ気品あふれるペルシャ猫が写っていた。首輪には、健太の家賃三十年分はありそうなダイヤが輝いている。
「お任せください、奥様。私、佐藤健太は、ただの探偵ではございません」
健太は胸を張った。彼の秘密。それは、動物と話せるという、にわかには信じがたい特殊能力だった。
「成功報酬は、これでいかがでしょう」
テーブルに置かれたのは、分厚い札束だった。百万円。健太の目が、エリザベスの首輪のダイヤと同じくらい輝いた。
健太は早速、聞き込み調査を開始した。向かった先は、近所の公園。彼の長年の情報提供者、ハトのヤマさんが縄張りにしている場所だ。
「よう、探偵。何の用だ」
砂場の中央でふんぞり返るヤマさんは、その筋の者もかくやという凄みのある声で言った。
「ヤマさん、白いペルシャ猫を見なかったか? 首にキラキラしたやつを付けてる」
「てめぇ、手ぶらで情報を引き出そうって了見か? こちとらハトの世界も厳しいんでな。まずは誠意を見せやがれ、誠意を」
健太はため息をつき、なけなしの金で買った高級生食パンを差し出した。ヤマさんは満足げにうなずき、パンを一口ついばむ。
「フワフワの白いやつなら、駅前のカラスどもが騒いでたぜ。『光るエンジェルがサウスサイドへ向かった』とかなんとか。ま、せいぜい頑張りな」
次に健太が向かったのは、駅前の電線を縄張りとするカラス集団、自称「漆黒の翼(ブラック・ウィング)」だ。リーダーのジェットは、やたらとカタカナ語を操る意識高い系のカラスだった。
「ヘイ、ケンタ。何か我々のビジネスにシナジーを生むようなインフォメーションかい?」
「ジェット、頼む。白い猫の行方を知らないか?」
「ギブ・アンド・テイクがビジネスの基本だ。君のオファーは?」
健太はポケットから、昨日コンビニで買ったアイドルのキラキラシールを取り出した。ジェットは満足げにそれを受け取ると、片翼を上げた。
「グッドなディールだ。そのホワイト・プリンセスなら、ドブ川のヌシがコンタクトしたとの情報がある。彼とのネゴシエーションが、君のネクストステージの鍵となるだろう。幸運を祈るよ、グッドラック」
言われた通り、健太は街の南側を流れる、お世辞にも綺麗とは言えないドブ川へやってきた。澱んだ水面を覗き込むと、ぬらり、と巨大な影が姿を現した。体長一メートルはあろうかという、巨大な鯉。ヌシ様だ。
「若者よ、何を求める」
ヌシ様は、水面に口を出し、やけに哲学的な口調で言った。
「ヌシ様、白い猫を探しておりまして…」
「探すとは何か。見つけるとは何か。真実とは、失われた時にこそその形を現すもの。お主が真に探すべきは猫にあらず、お主自身の心の内なる…」
ダメだ、話が通じない。健太が頭を抱え、途方に暮れたその時、ヌシ様がポツリと呟いた。
「…まあ、良い。お主の探し物は、先ほどからずっと、お主の背後におるぞ」
健太は弾かれたように振り返った。そこにいた。西園寺夫人が血眼で探していた、真っ白で気品あふれるペルシャ猫が……いや、違う。そこにいたのは、ドブ川の水で薄汚れて灰色になり、目つきは完全にすさんで、道端の石ころを前足で無意味に転がしている、やさぐれた猫だった。
健太が息をのむと、その猫はふてぶてしい声で言った。
「あァ? あんたがオフクロに雇われた探偵かい。ご苦労なこった。あんなお上品な生活、こっちから願い下げなんだよ。アタシはここで、自由ってもんを謳歌するのさ。夜露死苦」
口調は完全に昭和のレディース総長だった。エリザベス三世の気品は、ドブ川のヘドロと共にどこかへ消え去っていた。健太は天を仰いだ。この猫を、あの夫人の元へどうやって返せというのか。百万円が、夕陽の彼方へ飛んでいく幻を見た。
「とにかく、帰りましょう、エリザベスさん」
「うるせぇな! アタシはエリだ! 気安く三世とかつけんじゃねぇ!」
説得は完全に決裂していた。健太が再び頭を抱えた、その時だった。
「まあ! 健太さん、こんなところまで…」
最悪のタイミングで、心配した西園寺夫人が現れてしまったのだ。健太の背筋を冷たい汗が伝う。夫人は、やさぐれたエリザベスを見て、眉をひそめた。
「あら、可哀想に。汚れてしまった野良猫さん…」
終わった。全てが終わった。健太が諦めかけた瞬間、エリザベスは夫人の顔をじっと見つめた。そして、そのすさんだ瞳が、ふっと懐かしむように緩んだ。
彼女は、健太にしか聞こえない小声で、ポツリと呟いた。
「……やっぱ、オフクロの膝の上で食う、あのちゅ〜るが一番なんだよな…」
次の瞬間だった。エリザベスは、全身の力を抜き、これ以上ないほどか弱く、そして愛らしい声で、天性の女優のように鳴いた。
「ミャアオォ……ン……」
その声を聞いた途端、西園寺夫人の顔がぱっと輝いた。
「エリザベス! ああ、私のエリザベスなのね!」
夫人は駆け寄り、薄汚れた猫を力いっぱい抱きしめた。エリザベスは、夫人の胸の中で、完璧な「か弱く、迷子になっていたセレブ猫」を演じきっていた。
後日、健太の口座には約束の百万円が振り込まれていた。彼はまず滞納していた家賃を全額支払い、残った金で高級生食パンと、最新のアイドルキラキラシールを山ほど買った。
アパートの窓から夕日に染まる街を眺めていると、どこからか声が聞こえた。
『探偵、借りは返したぜ』
『ケンタ、君とのアライアンスは、常に我々にサクセスをもたらしてくれるな』
公園のヤマさんと、駅前のジェットからだった。
「まったく、世話の焼ける奴らだ」
健太は苦笑いしながら、買ってきたばかりのパンを一口かじった。それは、いつもの塩むすびより、ほんの少しだけ温かい味がした。