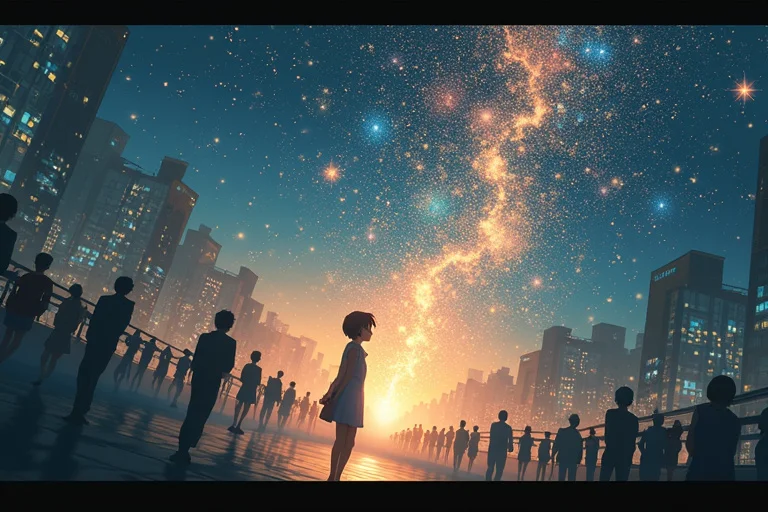第一章 天災は隣室にやってくる
佐藤健太、三十五歳、市役所市民課勤務。彼の人生は、寸分の狂いもなく引かれた方眼紙そのものだった。起床は六時ちょうど。朝食はトーストとブラックコーヒー。七時十五分に家を出て、寸分違わぬ歩幅で駅へ向かう。彼の辞書に「アドリブ」や「想定外」という言葉は存在しない。そんな健太の完璧な世界に、ある日、隕石が衝突した。
その隕石は、隣の202号室に引っ越してきた。男の名は鈴木はじめ。季節感ゼロの派手なアロハシャツに、うさん臭い笑顔を貼り付けたその男は、挨拶に来るなりこう言ったのだ。
「どうも! 俺、22世紀から来たお笑い芸人! 未来のお笑いを救うため、伝説のツッコミ師を探しに来たんです!」
健太は、目の前の男が発する言葉を脳内で処理するのに三十秒を要した。そして、彼の整然とした世界から導き出された唯一の結論を口にした。
「結構です」
ピシャリとドアを閉める。これが、健太と自称タイムトラベラーとの記念すべきファーストコンタクトだった。
しかし、天災は一度訪れれば、しばらく居座るのが常だ。翌朝から、健太の平穏な日常は鈴木によって猛烈な浸食を受け始めた。ゴミ出しの曜日を間違えれば、「わざとボケて俺のツッコミを待ってるんですね!」と喝采を送られ、アパートの廊下で鳩に餌をやろうとする鈴木に「条例違反です。即刻やめてください」と冷静に指摘すれば、「完璧な間! その冷徹な瞳! やはりあなたこそが伝説のツッコミ師、サトケンさんだ!」と目を輝かせる始末。
健太にとって、鈴木は理解不能なエラーコードであり、駆除すべきバグだった。彼は徹底的に無視を決め込んだ。だが、鈴木のエネルギーは無尽蔵だった。健太が眉間に皺を寄せれば寄せるほど、鈴木の笑顔は太陽のように燃え盛るのだった。
「ああ、サトケンさん。その無表情の奥に、沸々と煮えたぎるツッコミのマグマが見えますよ!」
健太は深くため息をついた。この男のせいで、ここ数日、胃のあたりがキリキリと痛む。彼の緻密な人生計画に、「隣人トラブル」という名の、最も厄介な項目が追記された瞬間だった。
第二章 不本意なツッコミ修行
鈴木はじめという天災との共同生活(健太は断固として認めていないが)が始まって一ヶ月。健太の日常は、もはや方眼紙ではなく、前衛芸術家がインクをぶちまけたキャンバスのようだった。
ある土曜日の午後、事件は起きた。アパートの大家である鬼瓦さん――その名の通り、鬼のような形相で住人たちに恐れられている老婆――が、血相を変えて怒鳴り込んできたのだ。原因は、鈴木がベランダで始めた家庭菜園。ミニトマトを育てるだけのはずが、なぜか蔓が隣の健太のベランダにまで侵食し、物干し竿に絡みついていた。
「あんたたち! いい加減にしなさい! ベランダは物干し以外の目的で使うんじゃないと、規約に書いてあるだろう!」
鬼瓦さんの怒号に、健太は背筋を伸ばし、マニュアル通りの謝罪を口にしようとした。その瞬間、鈴木がひょっこり顔を出した。
「大家さん! これはただのトマトじゃないんです! 宇宙トマト! 22世紀のテクノロジーで、食べると十年は若返るんですよ!」
「馬鹿なこと言ってんじゃないよ!」
鬼瓦さんの怒りは頂点に達した。健太はこめかみを押さえた。もう終わりだ。このアパートを追い出される。しかし、その時、自分でも信じられない言葉が口から滑り出た。
「……鈴木さん。それは無理があります。このトマトの種袋、近所のホームセンターで二百円でしたよ。それに、若返るならまずあなたが食べるべきだ。その寝癖、どう見ても実年齢より老けて見えます」
しん、と場が静まり返る。健太の冷静かつ的確すぎる指摘。それは紛れもなく、完璧な「ツッコミ」だった。
次の瞬間、鬼瓦さんが「フッ」と鼻で笑った。そして、信じられないことに、ぷっと吹き出したのだ。
「あんた……面白いこと言うじゃないか」
鈴木は「見たか! これがサトケンさんの天賦の才!」とばかりに胸を張る。結局、鬼瓦さんは「まあ、ちゃんと管理するなら……」と、呆れたように言い残して去っていった。
その日を境に、奇妙な現象が起こり始めた。健太が真面目に注意すればするほど、鈴木の奇行はエスカレートし、なぜかそれが周囲に小さな笑いを生んでいく。コンビニの列に割り込もうとする鈴木に「一から数え直しますか?」と冷たく言えば、後ろに並んでいた子供が笑い出す。公園で奇妙な健康体操を始める鈴木に「それはどこの関節を痛めるための運動です?」と問えば、お年寄りたちが微笑む。
健太は混乱していた。自分はただ、規則と常識に従って、この迷惑な男を矯正しようとしているだけだ。なのに、なぜ。人々が笑うたび、胸の奥に小さな灯りがともるような、むず痒い感覚が芽生えていた。それは、これまで感じたことのない温かい感情だった。迷惑なはずの鈴木の存在が、いつしか健太のモノクロームだった世界に、少しずつ色を与え始めていることに、彼はまだ気づいていなかった。
第三章 最後のボケ、最初の一歩
季節は秋に移ろい、アパートの周りの木々が赤や黄色に染まり始めていた。あれほど騒々しかった鈴木が、ここ数日、妙に静かだった。健太が訝しんでいると、ある雨の夜、彼がドアをノックした。
「サトケンさん、ちょっといいですか」
いつものアロハシャツではなく、くたびれたセーター姿の鈴木は、まるで別人のように弱々しく見えた。健太は黙って彼を部屋に招き入れた。
鈴木は、健太が淹れたインスタントコーヒーを一口飲むと、ぽつりと語り始めた。
「……嘘、なんですよ」
「何がです」
「未来から来たって話。俺、タイムトラベラーなんかじゃありません。ただの、売れない芸人です」
健太は言葉を失った。鈴木は、震える手でコーヒーカップを置き、続けた。
「半年前、医者に言われたんです。もう、長くないって。あと、半年くらいかなって」
部屋に、雨音だけが響く。鈴木の言葉が、健真の整然とした世界を根底から揺さぶっていく。
「芸人として、何も成し遂げられなかった。でも、死ぬ前に、どうしても最高の相方を見つけて、一度でいいから、腹の底から人を笑わせてみたかった。そんな時、偶然見かけたんです。市役所の窓口で、クレーマー相手に一切表情を変えず、淡々と正論だけで論破していくあなたを」
鈴木は顔を上げ、初めて見るような、寂しげな笑顔で健太を見た。
「衝撃でした。この人だ、って。俺の人生最後のボケを、完璧に拾ってくれる最高のツッコミは、この人しかいない、って。だから……未来を救う、なんて大げさな嘘をつきました。俺が救ってほしかったのは、お笑いの未来なんかじゃなくて、俺自身の、残り少ない未来だったんです」
健太の頭の中は、真っ白なノイズで満たされた。これまでの日々が、走馬灯のように駆け巡る。迷惑だと思っていた奇行の数々。うさん臭いと思っていた笑顔。そのすべてが、一人の男の、命を懸けた切実な願いだったと知った。怒りよりも、悲しみよりも先に、胸を締め付けるような痛みがこみ上げてきた。
「なぜ……なぜ、そんな」
「ごめんなさい、サトケンさん。あなたの大事な時間を、俺のわがままに付き合わせて」
鈴木は深く頭を下げた。健太は、何も言えなかった。ただ、目の前の男の、震える肩を見つめていた。方眼紙の世界は完全に崩壊し、その瓦礫の中から、これまで知らなかった感情が芽生えていた。それは、誰かを守りたいという、不器用で、どうしようもなく人間的な衝動だった。
健太は立ち上がり、押し入れから一枚のチラシを取り出した。それは、先日ポストに入っていた市民センターのイベント案内だった。
「……鈴木さん」
健太は、震える指でチラシの一角を指さした。そこには「誰でもステージ!飛び入り参加歓迎!」と書かれていた。
「やりましょう。二人で」
それは、健太が人生で初めて、マニュアルではなく、自分の心に従って下した決断だった。
第四章 スタンドアップ・フィナーレ
市民センターの小ホールは、満員とはいかないまでも、近所の顔見知りでほどよく埋まっていた。舞台袖で、健太は生まれて初めて経験する緊張に、心臓が口から飛び出しそうだった。隣に立つ鈴木は、いつものアロハシャツ姿だったが、その顔色は紙のように白い。
「サトケンさん、やっぱり俺……」
弱音を吐きかけた鈴木の背中を、健太は、ぱしん、と軽く叩いた。
「あなたのボケは、俺がいないと成立しないでしょう。行きますよ、相方」
鈴木は目を見開き、そして、ふっと笑った。それは、健太が今まで見た中で、最高に力の抜けた、いい笑顔だった。
コンビ名、『タイムトラベラーズ』。
舞台に上がった二人は、まるで何年も連れ添ったコンビのように、息の合った掛け合いを始めた。
「どうもー! 22世紀から来ました!」
「嘘つけ。お前の戸籍、ここの市役所にあるの俺は知ってるぞ」
鈴木の突拍子もないボケ。健太の冷静沈着なツッコミ。それは、この数ヶ月で彼らが築き上げてきた日々の集大成だった。鬼瓦大家さんの話、宇宙トマトの話、公園での奇妙な体操の話。彼らの日常そのものがネタになり、観客席から次々と温かい笑いが巻き起こる。健太は、笑い声の渦の中で、不思議な高揚感に包まれていた。人を笑わせることは、こんなにも心地よく、満たされることなのか。
最後のネタが終わり、二人は深々と頭を下げた。鳴りやまない拍手の中、舞台袖に戻った瞬間、鈴木の膝が崩れた。
「……最高、だったな。サトケン」
「ええ、最高でしたよ。鈴木さん」
息を切らしながら笑い合う二人。その瞬間、彼らは確かに、最高の相方だった。
それから一月後、鈴木はじめは、静かに旅立った。
彼の部屋はすぐに空になり、健太の日常は、まるで何もなかったかのように元に戻った。朝は六時に起き、市役所へ通う。しかし、彼の世界はもう、以前の方眼紙ではなかった。
市役所の窓口で、書類の不備に苛立つお年寄りに、彼は言った。
「大丈夫ですよ。僕の隣に住んでた男なんて、未来から来たって言い張ってたんですから。それに比べれば、日付の間違いなんて可愛いもんですよ」
お年寄りはきょとんとし、やがてくすりと笑った。その笑顔を見て、健太の胸にも温かい光が灯る。
ある晴れた日の昼休み、健太はアパートの屋上に上がり、青い空を見上げた。そこには、憎らしいほどに陽気な、あの男の笑顔が浮かんでいるようだった。
健太は空に向かって、静かに呟いた。
「大げさなんですよ、鈴木さん。未来を救う、だなんて」
その表情は、彼自身も気づかないうちに、穏やかな微笑みに満ちていた。彼の心の中では、隣室のタイムトラベラーが、今も最高のボケをかまし続けている。そして健太は、これからもずっと、その最高の相方であり続けるのだ。