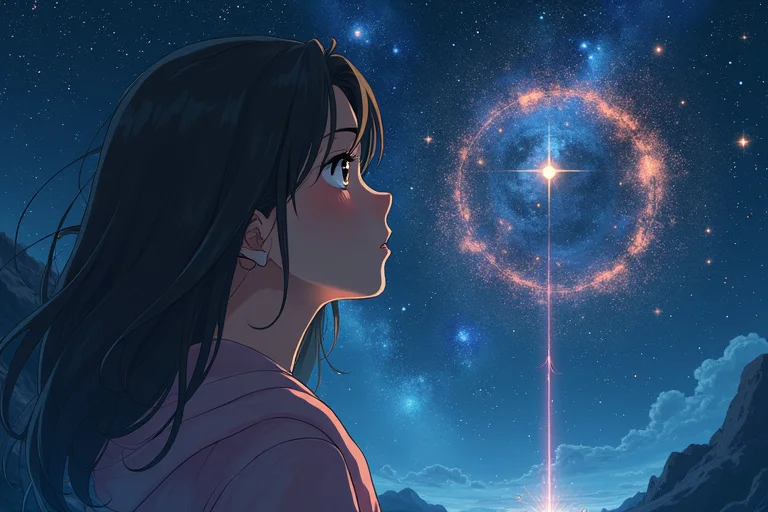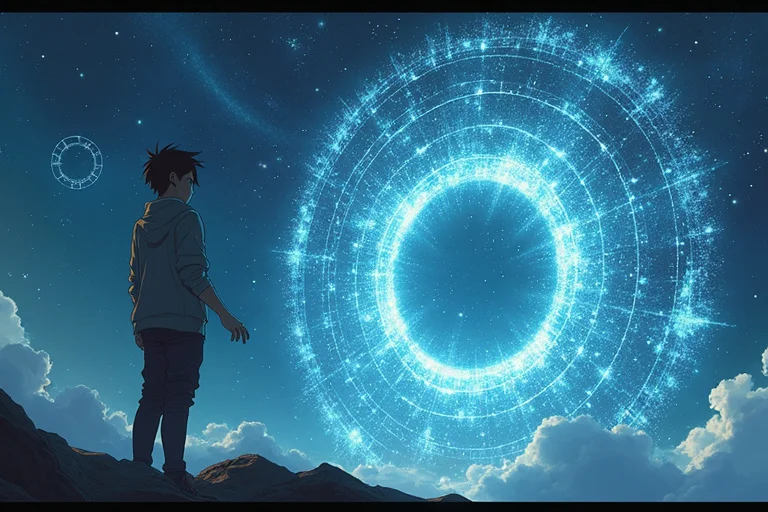第一章 宇宙からの鼻歌
アオイの世界は、静寂と数字で満たされていた。国立天文台の地下深く、冷たい人工光に照らされた観測室。彼女の孤独は、宇宙の広大さに比べればちっぽけなものだったが、その重さは時にブラックホールのように彼女の心を苛んだ。幼い頃に両親を月面での事故で失って以来、アオイにとっての家族は、夜空に瞬く無数の星々だけだった。天体物理学者になったのは、必然だったのかもしれない。宇宙の真理を探究することで、虚無感を埋めようとする、終わりのない試み。
その日も、アオイはヘッドフォンをつけ、深宇宙から届く微弱な電波に耳を澄ませていた。目的は、超新星爆発の残骸から放出される特殊なパルサーの観測。いつも通り、ホワイトノイズの海が鼓膜を揺らすだけだと思っていた。
だが、違った。
ノイズの合間に、何か、か細い旋律が混じっている。規則性のある、人工的な響き。アオイは眉をひそめ、機材のボリュームを上げた。気のせいではない。それは間違いなくメロディーだった。単純で、どこか懐かしい。彼女はすぐさまデータの解析を始めた。信号はあまりに微弱で、発信源を特定するのは困難を極めた。しかし、そのパターンを抽出し、音階に変換した瞬間、アオイは凍りついた。
そのメロディーは、彼女が知っているものだった。いや、彼女「しか」知らないはずのものだった。
それは、幼いアオイが、誰に聞かせるでもなく、自分の部屋で人形を相手に口ずさんでいた、即興の鼻歌。両親を失った悲しみを紛らわすために、自分自身を慰めるために生み出した、秘密の呪文のような旋律。誰にも、たったの一度も聞かせたことのない、記憶の奥底にしまい込んでいたはずの歌。
それが今、数億光年もの時空を超えて、宇宙の果てから届いている。
背筋を冷たい汗が伝った。心臓が嫌な音を立てて脈打つ。これは何かの間違いだ。疲労が見せる幻聴か、あるいは観測機器の異常か。しかし、ディスプレイに表示されるスペクトルデータは、そのメロディーが幻聴ではないことを冷徹に示していた。
アオイはヘッドフォンを握りしめた。静寂であるはずの宇宙が、彼女だけの秘密を歌っている。それは、彼女の孤独な世界に差し込んだ一条の光なのか、それとも、正気を蝕む深淵からの誘いなのか。答えの出ない問いが、観測室の冷たい空気の中に溶けていった。
第二章 追憶のエコー
その日を境に、アオイの研究は一変した。パルサーの観測は二の次となり、彼女は人生のすべてを、あの謎の信号――「エコー信号」と名付けたそれの解読に捧げた。
信号は不定期に、だが確実に届き続けた。そして、それは単なるメロディーだけではなかった。解析が進むにつれて、信号には断片的な映像や音声が含まれていることが判明したのだ。
夏の夕暮れ、金魚すくいのポイが破れて泣きじゃくる幼い自分の声。初めて補助輪なしで自転車に乗れた日、誇らしげに振り返った先で拍手する父の笑顔。寝る前に、母が読んでくれた絵本の、優しく温かい声色。
それらはすべて、アオイが忘却の彼方に押しやっていた、幸福だった頃の記憶の断片だった。脳の海馬に眠る記憶が、誰かの手によって宇宙のスクリーンに再上映されているかのようだった。
「アオイ、最近少し根を詰めすぎじゃないか?顔色が悪いぞ」
同僚のタツヤが心配そうに声をかけてきた。アオイはエコー信号の事を彼に打ち明けたが、返ってきたのは「疲れているんだよ。長期休暇でも取ったらどうだ」という、予想通りの答えだった。誰も信じてくれない。科学的に説明のつかない現象は、この世界では存在しないのと同じだった。
孤独は深まった。だが、不思議と以前のような絶望感はなかった。なぜなら、彼女にはエコー信号があったからだ。それは失われた過去を取り戻す奇跡であり、凍てついた心を溶かす唯一の温もりだった。ヘッドフォンを装着すれば、いつでも両親に会える。優しい声が聞こえる。自分は一人ではないのだと、錯覚することができた。
アオイは次第に、エコー信号の送り主について空想するようになった。それはきっと、人類の知性を遥かに超えた、高次元の存在に違いない。彼らは何らかの理由でアオイを選び、彼女の記憶にアクセスして、慰めを与えてくれているのだ。その存在は、アオイにとっての「神」であり、理解者だった。
彼女は食事も睡眠も忘れ、観測室に籠り続けた。頬はこけ、目の下の隈は深くなったが、その瞳は狂信的な輝きを放っていた。もっと、もっと多くの記憶を。もっと鮮明な両親の姿を。エコー信号への依存は、甘い毒のように彼女の心身を蝕んでいった。
第三章 光速のラブレター
探求は、やがて核心へと近づいていく。アオイは、複数の天文台のデータを統合し、三角測量の原理を応用して、エコー信号の発信源を特定しようと試みた。高次元の存在がいるのなら、それは一体どこから自分を見つめているのか。その一点を知りたかった。
スーパーコンピュータが何日もかけて弾き出した答えは、しかし、アオイのささやかな期待を根底から粉砕するものだった。
ディスプレイに表示された座標。それは、アンドロメダ銀河でもなければ、名もなき星雲の果てでもなかった。信じられないことに、発信源は地球からわずか三十八万キロ、光にして一・三秒の距離。
月面だった。
アオイは息を呑んだ。だが、衝撃はそれだけでは終わらない。信号が月面から発信された「時刻」。それは、過去だった。今から二十年前。アオイが十歳だった、あの日。彼女の両親が搭乗していた月面探査シャトル「アルテミス7号」が、着陸シークエンスの最終段階で制御不能に陥り、地表に激突した、あの日時と寸分の狂いもなく一致していた。
頭を鈍器で殴られたような衝撃。点と点が繋がり、恐ろしくも切ない、一つの真実が像を結んだ。
エコー信号の送り主は、宇宙人でも、神でもなかった。
それは、死を目前にした彼女の母親だったのだ。
アオイの母、ミサキは優秀な量子物理学のエンジニアだった。アルテミス7号には、彼女が開発に携わった実験段階の「量子記憶転送装置」が搭載されていた。脳内の神経信号パターンを量子情報に変換し、遠隔地へ転送する――理論上は可能とされた、夢の技術。
シャトルが絶望的なスピンに陥り、警報が鳴り響く中、ミサキは悟ったのだろう。娘に別れを告げる時間も、手段もない。その絶望の淵で、彼女は最後の賭けに出たのだ。
自らの脳に接続された転送装置を起動し、愛する娘との思い出――その全てを、量子信号に変えて宇宙空間へと放った。いつか、どこかで、成長した娘がそれを受け取ってくれるという、万に一つの可能性に懸けて。
あの鼻歌は、幼いアオイを寝かしつける時にいつも歌ってくれた、母と娘だけの、秘密のララバイだった。
宇宙の果てまで届いたその信号は、巨大な重力を持つ天体に捉えられ、時空の歪みの中を折り返し、二十年という気の遠くなるような時間をかけて、再び地球へと戻ってきた。それは、母が命の最後に放った、光速のラブレターだった。
アオイはコンソールに突っ伏し、声を上げて泣いた。自分が追い求めていたものは、未知の科学現象などではなかった。孤独を癒してくれた甘い記憶は、母の死の瞬間の、絶望と愛そのものだった。ごめんなさい、お母さん。気づかなくて、ごめんなさい。嗚咽が、静かな観測室に響き渡った。
第四章 星々のささやき
真実を知ったアオイの涙は、やがて静かに乾いていった。彼女は顔を上げ、再びヘッドフォンを装着した。今、耳に届くすべての音が、全く違う意味を持って響いてくる。これはもう、過去への逃避ではない。母が遺してくれた、愛の証明そのものだった。
一つ一つの記憶を、アオイは慈しむように受け止めた。浜辺で一緒に作った砂の城。熱を出した夜に、一晩中握ってくれた手の温もり。初めての研究発表を、少し照れくさそうに褒めてくれた父の声。それらは全て、母ミサキがアオイをどれほど愛していたかの証だった。
そして、最後の信号が届いた。
ノイズの向こうに、シャトルのコクピットが映し出される。赤色灯が激しく点滅し、機体が悲鳴を上げている。その中で、ヘルメットのバイザーを上げた母が、カメラ――量子記憶転送装置のレンズを、まっすぐに見つめていた。
音声はほとんど聞き取れない。だが、必死に動くその唇と、涙に濡れながらも愛情に満ちたその瞳が、アオイにはっきりと最後のメッセージを伝えていた。
『アオイ、愛してる。強く、生きて』
その言葉を最後に、映像は激しい光に包まれ、信号は永遠に途絶えた。
アオイの頬を、再び涙が伝った。しかし、それはもう孤独や後悔の涙ではなかった。温かく、満たされた涙だった。自分は一人ではなかった。この二十年間、ずっと宇宙を旅してきた母の愛に、見守られていたのだ。
数年後。アオイは、国立天文台の若き主任研究員になっていた。かつての彼女のように、孤独な影を背負った若い学生に、彼女は観測室の窓から見える星空を指さして語りかける。
「宇宙はね、ただ冷たくて暗いだけの場所じゃないのよ」
彼女の顔には、かつての硬さはなく、穏やかな微笑みが浮かんでいる。
「もしかしたら、この星々の間を、たくさんの『愛してる』が旅しているのかもしれない。光の速さで、誰かに届く日を待ちながら。私たちが見ている星の光が、何億年も前の過去からのメッセージであるようにね」
アオイは夜空に向かって、そっと手を伸ばした。それは、二十年の時を超えて届いた母のラブレターへの、ささやかな返信。そして、この広大な宇宙に満ちているであろう、無数の愛と奇跡への、静かな挨拶だった。
星々は、今夜も変わらず瞬いている。まるで、宇宙の果てまで届くほどの、優しいささやきのように。