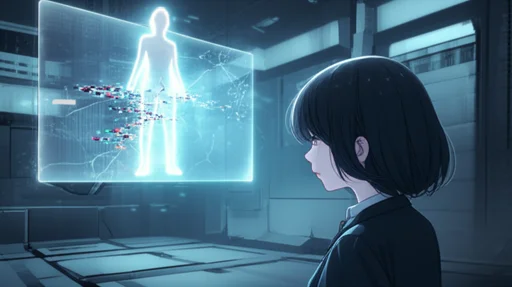第一章 三度目の命日に届いた手紙
六月の湿った空気が、図書館の古い本の匂いと混じり合い、水無月蒼(みなづき あおい)の肺を静かに満たしていく。司書として働くこの場所は、彼女にとって世界の全てだった。高窓から差し込む午後の光が埃を金色に照らし、時の流れを可視化しているようにも見える。だが、蒼の時間は、三年前のあの日からずっと止まったままだった。
恋人だった結城隼人(ゆうき はやと)が、山の単独行で滑落死してから、今日でちょうど三年になる。警察からの一報、駆け付けた病院の白い廊下、嘘のように静かな彼の寝顔。その全てが、色褪せることのない映像として脳裏に焼き付いている。
仕事を終え、重い足取りでアパートへの道を歩く。夕暮れの空は、悲しみを溶かしたような紫色に染まっていた。郵便受けを覗くと、見慣れた封筒が一つ。心臓が、嫌な予感と微かな期待で跳ねる。白い封筒には、宛名も差出人も書かれていない。ただ、中央に一つ、インクで描かれた小さな星のマークがあるだけ。
これで、三通目だ。
震える指で封を開けると、中から一枚の便箋が現れた。そこに綴られているのは、間違いなく隼人の筆跡だった。丸みを帯びながらも、力強い、彼だけの文字。
『蒼へ。
元気でやっているかい? こちらは相変わらずだよ。
三年目の挑戦状だ。僕が遺した最後の星を探してほしい。
ヒントは、僕たちが初めて宇宙を共有した場所。
君なら、きっと見つけ出せる。
隼人』
ありえない。死んだ人間から手紙が届くはずがない。頭では分かっているのに、心はこの奇跡を信じたがっていた。一昨年は「僕らの始まりの音を探して」、去年は「空に一番近い丘で待つ」というメッセージだった。最初の二通は、悪質ないたずらか、あるいは彼の死を受け入れられない自分が見せた幻覚だと思い込もうとした。だが、三年連続となれば、話は違う。そこには明確な意志が存在する。
蒼は、三通の手紙をテーブルに並べた。インクの匂いまでが、彼が生きていた頃の記憶を呼び覚ます。隼人は星が好きだった。夜空を見上げては、星座の神話を熱っぽく語ってくれた。彼の瞳は、いつも遠い宇宙の輝きを宿していた。
「最後の星……」
蒼は呟いた。誰が、何のために? 隼人は本当に、死後の世界から自分に語りかけているのだろうか。それとも、これは彼の死に隠された、何か重大な秘密に繋がる鍵なのだろうか。止まっていた蒼の時間が、この不可解な謎によって、軋みを立てて動き始める予感がした。彼女は、この謎を解き明かすことを、固く心に誓った。それは、隼人にもう一度会うための、唯一の道しるべのように思えたのだ。
第二章 星屑の記憶を辿って
「初めて宇宙を共有した場所」。隼人からの新たなヒントを胸に、蒼は記憶の海を泳いだ。二人で見た映画、貸し借りした本、歩いた並木道。思い出は星の数ほどあったが、「宇宙」というキーワードで絞り込むと、一つの場所が鮮やかに浮かび上がった。市立プラネタリウムだ。
付き合い始めて間もない頃、はにかみながら彼が誘ってくれた場所。ドーム型の天井に満天の星が映し出された瞬間、隣に座る隼人の横顔が、星の光を受けてきらきらと輝いていたのを、蒼は昨日のことのように覚えていた。
数年ぶりに訪れたプラネタリウムは、少し古びてはいたが、変わらぬ静寂で彼女を迎えた。受付の女性に事情を話し、隼人の名前を告げると、意外な答えが返ってきた。
「結城さん……ああ、隼人くんですね。よく覚えていますよ。星にとても詳しい学生さんで、閉館後も熱心に職員に質問をしたりしていましたから」
何か手がかりはないかと尋ねる蒼に、職員は少し考え込み、「そういえば」と口を開いた。「隼人くん、よく妹さんと一緒に来ていましたよ。小春ちゃん、だったかしら」
結城小春。隼人の五歳年下の妹。兄の死後、葬儀で顔を合わせて以来、疎遠になっていた。快活な兄とは対照的に、どこか影のある、物静かな少女だった。蒼は小春の連絡先を尋ね、数年ぶりに電話をかけた。電話口の小春の声は、記憶よりもずっと低く、硬質だった。
喫茶店で向かい合った小春は、美しく成長していたが、その瞳には人を寄せ付けない鋭い光が宿っていた。
「兄の手紙?……何かの間違いじゃないですか」
小春は冷たく言い放った。蒼が三通の手紙を見せても、彼女は眉一つ動かさない。
「姉さん、まだ兄のことが忘れられないんですか。もう三年ですよ。死んだ人間は戻ってこない。そんなもので希望を持つなんて、兄も浮かばれない」
その言葉は、刃物のように蒼の心を切りつけた。だが、その瞳の奥に、一瞬だけ悲しみとも苦しみともつかない感情が揺らめいたのを、蒼は見逃さなかった。
「小春ちゃん、あなた何か知ってるんじゃないの?」
「何も知りません」
ぴしゃりと言い放ち、小春は席を立った。「兄のことは、もう忘れてあげてください」。そう言い残して、彼女は去っていった。
冷たく突き放されたことで、蒼の心には逆に火が灯った。小春は嘘をついている。彼女のあの態度は、何かを守ろうとする者のそれだ。
蒼は、過去の二通の手紙の謎を改めて考え直した。「始まりの音」は、二人が初めて話した図書館の視聴覚室で見つけた、隼人が好きだった宇宙音楽のCD。「空に一番近い丘」は、彼に連れられて行った、街を見下ろす丘のベンチ。そこには、小さな望遠鏡のレンズキャップが隠されていた。
CD、レンズキャップ、そしてプラネタリウム。点と点が、まだ線にならない。だが、全てが隼人の愛した「宇宙」に繋がっている。蒼は、隼人が遺した星屑のような記憶を一つ一つ拾い集めながら、真実という名の星座を完成させるため、思考を巡らせ続けた。小春の冷たい瞳の奥にある真実を、必ず突き止めなければならない。
第三章 優しい嘘と残酷な真実
プラネタリウムの職員に再度話を聞くと、隼人が生前、特定の観測記録を熱心に見ていたことが分かった。それは、一般公開されていない、古いアナログの観測日誌だった。蒼は、特別な許可を得て、古びた書庫のような記録室へと足を踏み入れた。
黴と紙の匂いが混ざった空気が鼻をつく。膨大な記録の中から、隼人が見ていたという年代のファイルを探し出す。その一冊を引き抜いた瞬間、中から何かが滑り落ちた。鍵だ。古めかしい、小さな真鍮の鍵。鍵には、「第三倉庫」と彫られたプレートが付いていた。
第三倉庫。そこは、プラネタリウムの裏手にある、今は使われていない機材置き場だった。錆びた扉に鍵を差し込むと、ぎしりという重い音を立てて開いた。中は薄暗く、埃っぽい。その中央に、ぽつんと置かれた木箱があった。
蒼は、祈るような気持ちで木箱の蓋を開けた。中に入っていたのは、一冊の大学ノートと、ベルベットの小さな袋だった。ノートの表紙には、見覚えのある、しかし隼人のものではない、丸く整った文字でこう書かれていた。
『水無月蒼様へ』
息を呑んでページをめくる。そこに綴られていたのは、小春の文字だった。
『このノートをあなたが見つけているということは、兄の最後の願いを、私が果たせたということなのだと思います。ごめんなさい、蒼さん。ずっと、あなたに嘘をついていました』
心臓が氷水に浸されたように冷たくなる。ページをめくる指が震えた。
そこに書かれていたのは、想像を絶する真実だった。
隼人は、山で滑落死したのではなかった。
彼はずっと、遺伝性の重い心臓病を患っていた。余命宣告を受け、自分の死が近いことを知っていたのだ。そして三年前の今日、彼は病院のベッドで、静かに息を引き取った。滑落事故というのは、あまりにも突然の別れで蒼を深く傷つけないように、そして気丈な彼らしい最期を演出するために、隼人自身が考案し、小春に託した「優しい嘘」だった。
『兄は、最後まであなたのことばかり心配していました。自分が死んだ後、あなたが悲しみで立ち止まってしまうことを、何より恐れていました。だから、未来のあなたに手紙を書くことにしたんです。「僕がいなくなっても、蒼には空を見上げて、前を向いて歩いてほしい。だから、僕からの挑戦状として、少しずつ謎を解かせてほしい。僕との思い出を、悲しいだけじゃなく、力に変えられるように。その手伝いを、小春、お前に頼む」と』
涙が、ノートの上に次々と落ちて、インクを滲ませた。小春が蒼に冷たく当たった理由も、そこには書かれていた。兄の遺志を継ぐ重圧。兄の心を最後まで独占した蒼への、ほんの少しの嫉妬。そして何より、嘘をつき続ける罪悪感。彼女もまた、一人で大きな悲しみを背負っていたのだ。
蒼はノートを抱きしめ、その場に崩れるようにして泣いた。隼人の死の真相。それは、残酷であると同時に、あまりにも深い愛情に満ちていた。彼はずっと、死の淵にありながら、自分のことではなく、遺される蒼の未来だけを案じていたのだ。
第四章 きみが遺した最後の星
どれくらい泣き続けたのか。ふと顔を上げると、倉庫の入口に小春が立っていた。その瞳は赤く腫れ、蒼と同じように涙の跡があった。
「……ごめんなさい」
か細い声で謝罪する小春を、蒼は黙って抱きしめた。温かい涙が、蒼の肩を濡らした。言葉はなかった。ただ、二人の間には、隼人という一人の人間を深く愛した者同士の、静かな理解が流れていた。
「兄からの、最後の贈り物です」
小春が指差したのは、ノートと一緒に箱に入っていたベルベットの袋だった。蒼がおそるおそる袋の口を開けると、中から銀色のネックレスが滑り落ちた。ペンダントトップは、五つの小さな宝石で作られた、カシオペア座を模した星の形をしていた。
ノートの最後のページに、隼人の筆跡で、最後のメッセージが遺されていた。
『蒼へ。
この手紙を読んでいる頃には、君はもう真実を知っているんだろうな。驚かせたか? ごめんよ。でも、これが僕なりの最後のわがままだったんだ。
僕にとって、君は夜空で一番明るく輝く星だった。道に迷ったとき、いつも僕を照らしてくれる、たった一つの道しるべだった。
だから、僕がいなくなっても、君には君の空で輝き続けてほしい。
僕が遺したかった「最後の星」は、どこか遠い宇宙にあるんじゃない。
それは、他の誰でもない、君自身のことだ。
蒼、君が僕の、最後の星(ラスト・コンステレーション)だよ。
愛してる。さよならは言わない。また、いつか星空のどこかで。
隼人』
涙で視界が歪む。ペンダントを握りしめると、まるで彼の体温が伝わってくるような温かさを感じた。彼は死んだのではない。彼の愛は、このペンダントに、小春の心に、そして自分の心の中に、永遠に生き続けるのだ。事故死という突然の理不尽な死ではなく、愛する人のために全てを準備した彼の覚悟に満ちた死を知り、蒼の心にあった三年来の澱が、静かに溶けていくのを感じた。止まっていた時間が、再び優しく流れ始めた。
その夜、蒼はアパートのベランダに出て、夜空を見上げた。三年前と同じ星々が、変わらずに瞬いている。けれど、その輝きは、もう悲しみの色を帯びてはいなかった。
蒼は、隼人が遺した星のネックレスを首にかけた。ひんやりとした金属の感触が、肌に彼の存在を教えてくれる。
「ありがとう、隼人。ありがとう、小春ちゃん」
呟きは、星々の瞬きに吸い込まれていった。
隼人が遺した謎は、彼の死の真相を明らかにし、そして、彼の最大の愛を蒼に教えてくれた。喪失の痛みは消えないだろう。だが、それはもう、彼女を縛り付ける鎖ではなかった。未来へ歩むための、優しい光だった。
蒼は、澄み切った夜空に浮かぶカシオペア座を見つけた。まるで隼人が微笑みかけているように、星々は力強く、そして穏やかに輝いていた。
彼女は、その輝きを目に焼き付け、静かに微笑んだ。明日からは、きっと、もう少しだけ強く生きていける。彼の愛という名の、消えない星を胸に抱いて。