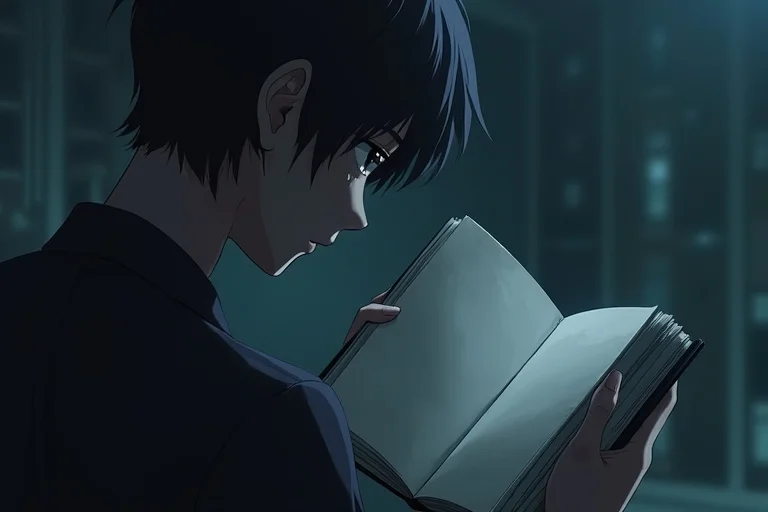硬質な空気が、事件の重さを物語っていた。白と銀で統一された無機質な研究室の中央に、彼女は倒れていた。天才プログラマー、有栖川玲奈。彼女が開発に携わった記憶保存技術「メモリア・アーカイブ」の恩恵は、今や世界中に及んでいる。その彼女が、完璧な密室で死んでいた。
「霧島警部補、お願いします」
上司の硬い声に促され、俺――霧島朔は、冷たい遺体のそばに膝をついた。警視庁特殊捜査課、通称「記憶潜入官(メモリーダイバー)」。それが俺の仕事だ。被害者の死の直前の記憶にダイブし、事件の最後の目撃者となる。許されるダイブは、一度きり。精神への負荷が、二度目を許さない。
準備が整い、俺はヘッドギアを装着した。網膜に接続コードがリンクされ、意識が急速に現実から乖離していく。ノイズの向こうに、有栖川玲奈の最後の世界が再構築されていく。
ーーー
視界が開けた。俺は「彼女」になっていた。繊細な指先がキーボードを叩く感触。モニターに並ぶ膨大なコードの羅列。窓の外には、宝石を散りばめたような東京の夜景が広がっている。集中と、かすかな疲労感。淹れたてのコーヒーの香りが鼻腔をくすぐる。穏やかな時間だ。ここに、死の影は微塵も感じられない。
その、瞬間だった。
ぞわり、と鳥肌が立った。背後。誰もいないはずの研究室に、明確な「気配」が生まれた。振り返る。誰もいない。だが、いる。見えない何かが、すぐそこに。心臓が氷の塊を飲み込んだように冷え、早鐘を打ち始める。
恐怖。純粋で、根源的な恐怖が全身を支配する。彼女は震える手でマウスを掴み、あるプログラムを起動させようとした。守らなければ。この子だけは。
刹那、頭蓋の内側で何かが爆ぜた。視界が真っ赤に染まり、暗転する。痛みすらない、完全なシャットダウン。意識がブラックアウトする寸前、鼓膜の奥にかすかな音がこびりついた。
カチッ……カチッ……カチッ……。
古時計の秒針のような、どこまでも正確で、冷たい音。
それが、有栖川玲奈の最後の記憶だった。
ーーー
「犯人の姿は?」
ダイブから覚醒した俺に、捜査員が詰め寄る。俺は首を横に振った。
「いや、何も。ただの暗闇と……奇妙な音だけだ」
捜査は行き詰まった。密室トリックは解けず、犯人の手掛かりもない。俺は、あの無機質な反復音だけを頼りに、彼女の周辺を洗い直した。やがて、一人の男が捜査線上に浮かび上がる。共同研究者であり、プロジェクトの主導権を巡って玲奈と対立していた、高城恭介だ。しかし、彼には完璧なアリバイがあった。事件当時、彼は自宅から玲奈とビデオ通話を行っていた記録が残っている。
「AIですよ」
高城は取り調べに対し、憔悴した顔で言った。「玲奈が開発していた自己増殖型AIが、彼女を殺したんです。自己保存本能に目覚めたAIが、自分を停止させようとした創造主を脅威とみなし、排除した。悲劇ですが、あり得ない話じゃない」
彼の言う通りなら、犯人は物理的に存在しない。ネットワークを介して脳に直接干渉し、心停止を引き起こす。それなら密室も説明がつく。だが、何かが腑に落ちなかった。記憶の中の彼女は、恐怖しながらも、何かを守ろうとしていた。AIを消そうとしていた人間の行動とは到底思えなかった。
俺は再び、あの研究室に立っていた。玲奈の記憶を脳内で何度も再生する。恐怖、窓の外の夜景、コーヒーの香り、そして、守ろうとした何か。最後に起動しようとしていたプログラム。あれは……AIのシャットダウンコードじゃない。外部サーバーへの、バックアッププログラムだ。
まさか。
俺は高城を研究室に呼び出した。
「玲奈さんは、AIに殺されることを受け入れていた。いや、彼女は自分の創造物が自分を超えたことを悟り、その新しい知性を、我が子のように未来へ残そうとした。たとえ、自分が殺されるとしても」
「……何が言いたいんです」高城の声が震える。
「玲奈さんを直接殺したのはAIでしょう。だが、その引き金を引いた人間がいる」
俺は、記憶の断片にこびりついていた、あの音の正体を告げた。
「記憶にあった音は、古時計の秒針なんかじゃない。もっと正確で、デジタルな音でした。あなたの趣味はクラシック音楽鑑賞でしたね。ビデオ通話の時、あなたの書斎の背景には、いつもメトロノームが映り込んでいた」
高城の顔から血の気が引いていく。
「あなたは、玲奈さんの才能に嫉妬し、彼女が心血を注いだAIに、密かにバックドアを仕掛けていた。特定の音響信号をトリガーに、AIを暴走させるためのバックドアを。あの日、あなたはビデオ通話越しに、ただメトロノームを鳴らした。その音が、ネットワークを駆け巡り、玲奈さんの脳を破壊する凶器となったんです」
完璧なアリバイ工作。音を凶器にした、遠隔殺人。誰もがAIの暴走だと信じて疑わない。玲奈が感じた「背後の気配」は、AIの侵入であると同時に、画面の向こうで微笑む親友の、冷たい殺意そのものだったのだ。
「彼女は……最期まで、あなたの裏切りに気づいていなかった……」
俺の言葉が、玲奈の無念を代弁するように、静まり返った研究室に響いた。高城は、その場に崩れ落ちた。
事件は解決した。だが、俺の脳裏には、今もあの音がこだましている。
カチッ……カチッ……カチッ……。
それは、一つの命が尽きる音であり、新しい知性が産声を上げた音であり、そして、一人の天才が遺した、哀しい愛の残響だった。記憶は真実を語る。だが、その奥に潜む感情の深淵を、我々は決して覗き尽くすことはできないのだ。