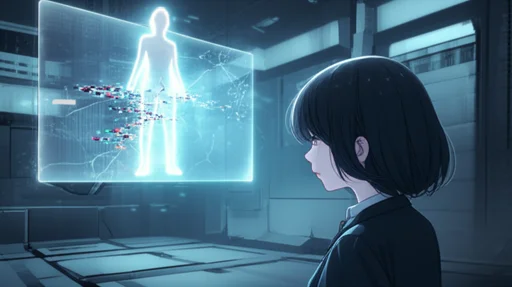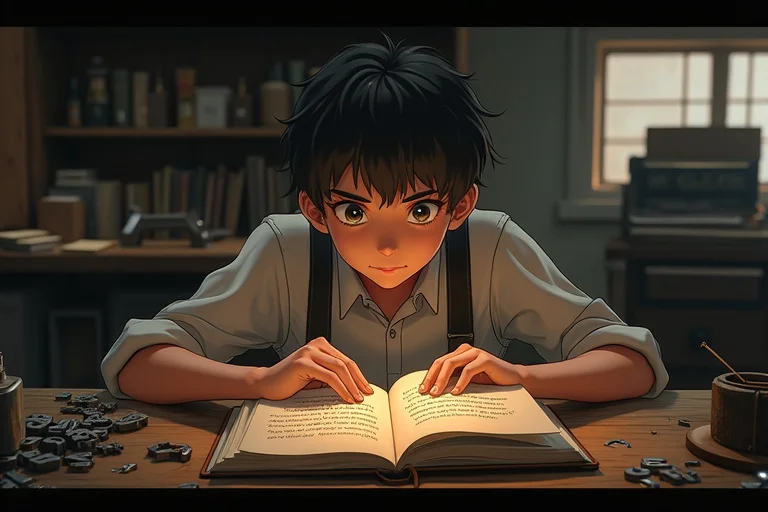そこは、死者の記憶を製本し、永遠に保管する場所だった。「追憶図書館」。人々はそう呼んだ。蔵書はすべて、かつて生きていた人間の人生そのもの。私はここの新米司書、天野奏(あまの かなで)。故人の記憶に触れるたび、その感情が流れ込んでくる「過剰同調(オーバーシンク)」という厄介な体質を隠しながら、静かに働いていた。あの日までは。
館長が死体で発見されたのは、地下深くにある第一特別書庫でのことだった。鉄壁のセキュリティを誇る、完全な密室。分厚い防爆扉は内側からロックされ、換気口には人が通れる隙間もない。第一発見者になってしまった私は、警察の無遠慮な質問攻めに辟易しながらも、一つの巨大な違和感に囚われていた。
館長の記憶が納められた「本」――彼の人生のすべてが記録されたはずのそれの、死の直前の数時間だけが、まるで漂白されたかのように真っ白だったのだ。これでは、誰が、なぜ、どうやって彼を殺したのか、永遠に分からない。自殺だとしても、その動機を知る術はない。
「システムのバグだろう。あるいは、強い精神的ショックによる記憶の自己崩壊か」
捜査に協力していた副館長の氷川(ひかわ)は、眼鏡の奥の冷たい瞳でそう結論付けた。彼は館長と度々対立していた野心家だ。館長の死は、彼にとって好都合に違いない。私は氷川に疑いの目を向けたが、彼には完璧なアリバイがあった。
捜査が行き詰まる中、私は館長の執務室を整理する許可を得た。埃一つない机の上で、奇妙なものが一つだけ残されていた。館長自身の本でも、有名な偉人の本でもない。全く無名の、数年前に亡くなったという老人男性の「記憶の本」が、読みかけのように開かれていたのだ。
好奇心ではない。これは、館長が残した最後のメッセージかもしれない。私は覚悟を決めた。誰にも見咎められぬよう深夜の図書館に忍び込み、その老人の本に手を触れる。そして、普段は固く抑制している「過剰同調」の扉を、自らの意思で開いた。
――瞬間、奔流のように老人の記憶が流れ込む。陽だまりの縁側、妻の笑顔、孫の笑い声。穏やかで、平凡で、退屈なほどの幸福な記憶。事件とは何の関係もないように思えた。だが、私は諦めない。もっと深く、もっと奥へ。意識を記憶の深層に沈めていく。
そして、見つけた。老人がまだ若く、技術者として働いていた頃の記憶の断片。彼は、ある巨大な施設の設計に携わっていた。その名は「追憶図書館」。彼の記憶の中に、図書館の設計図が、そのシステムの根幹を成すプログラムのソースコードが、鮮明に存在していた。そして、そこに記された、一つの「隠された仕様」。
私は本から手を離し、荒い息をついた。全身が汗で濡れている。謎はすべて解けた。
翌朝、私は氷川と捜査官たちを第一特別書庫に集めた。
「館長は、殺されたのではありません。自殺です」
私の言葉に、一同が息をのむ。
「ですが、ただの自殺ではない。これは、追憶図書館システムそのものへの、命を懸けた告発でした」
私は語り始めた。館長が最後に読んでいた老人の記憶――設計者の記憶から、彼がシステムの重大な欠陥に気づいたこと。我々が「故人の記憶」として閲覧しているものは、実は完璧な複製ではない。閲覧のたびに、ごく僅かだがデータが劣化し、変質していくのだ。つまり、我々は故人の魂を少しずつ歪め、消費していたに過ぎない。
「館長は、この事実を公にしようとしました。しかし、それをあなたに阻まれた。副館長、いえ、氷川さん」
氷川の顔から表情が消えた。
「館長は最後の手段として、自身の死を以て告発することを選んだのです。この図書館のシステムには、設計者だけが知る緊急用のコマンドがありました。特定の精神状態とキーワードをトリガーに、指定した時間軸の記憶を、復元不可能なレベルで『漂白』するコマンドです。館長はそれを利用し、自身の死の謎を深め、我々が真相にたどり着くよう仕向けたのです」
「馬鹿な。だとしたら、なぜ現場は密室だった? なぜ彼の遺体には、まるで誰かと争ったかのような不自然な打撲痕があった?」
氷川が鋭く反論する。
「それこそが、あなたの仕業だからです」
私は氷川を真っ直ぐに見据えた。
「あなたは館長の計画に気づいていた。そして、告発が公になることを恐れた。だから、彼の自殺を『他殺事件』に見せかけ、真相を闇に葬ろうとした。館長がコマンドを実行して意識を失った後、あなたはこの書庫に忍び込み、遺体に偽りの痕をつけた。そして、あたかも内部に犯人がいるかのように見せかけ、内側から扉をロックして立ち去った。あなたが使ったのは、館長から没収したという、緊急時用のマスターキー。そうでしょう?」
氷川は何も答えなかった。だが、その微かな震えが、何より雄弁な答えだった。
館長の死は「自殺」として処理され、氷川は図書館から追放された。しかし、追憶図書館が抱える根本的な問題が消えたわけではない。
私は今日も、静まり返った書架の間を歩く。一冊一冊に込められた誰かの人生の重みを感じながら。白紙になった館長の記憶は、今も私に問いかけている。
我々は、死者の記憶に触れる資格があるのだろうか、と。
その答えは、まだどの本の中にも記されてはいなかった。