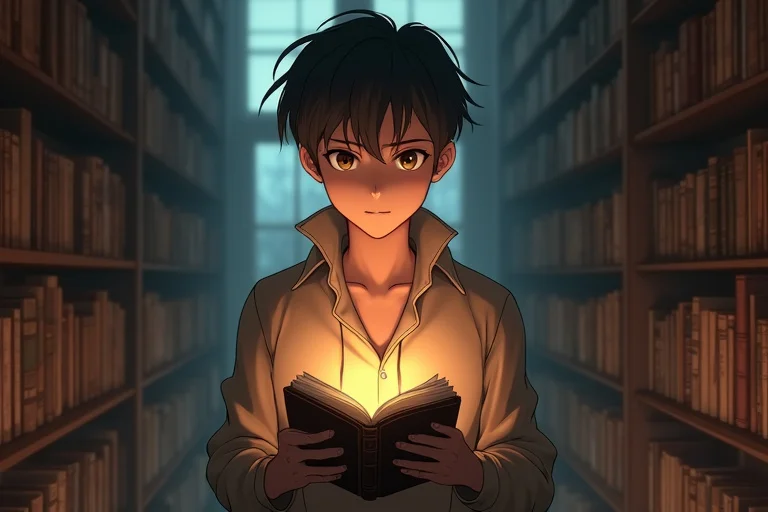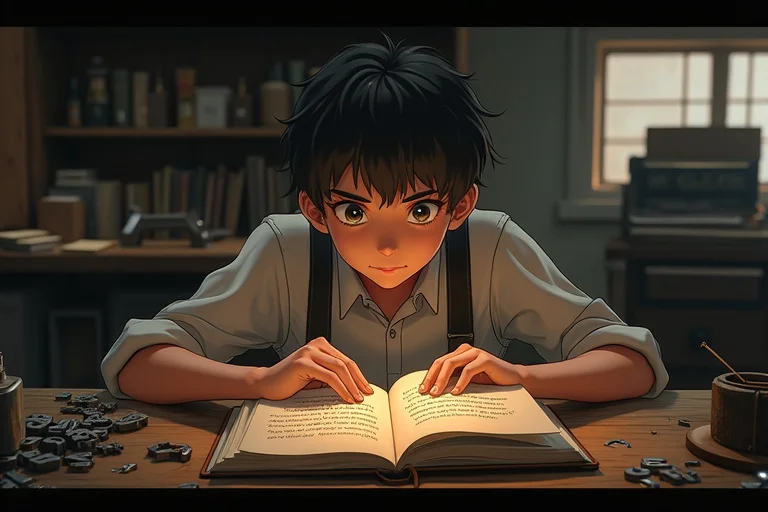古書のインクと埃が混じり合った匂いが、霧島聡の書斎には満ちていた。壁という壁を埋め尽くす本棚は、彼が生きてきた時間の証人であり、唯一無二の城壁でもあった。その静寂を破ったのは、一本の電話だった。一年前、山道で足を滑らせて亡くなった親友、高遠誠の妻、美咲からだった。
「すみません、霧島さん。主人のかつての書斎を片付けているのですが、どうしても気になるものがあって……」
数日後、高遠家に招かれた霧島が美咲から手渡されたのは、一冊の古びた植物図鑑と、そこに貼られた一枚の蔵書票(エクスリブリス)だった。蔵書票のデザインは奇妙だった。中央に描かれているのは、懐中時計を持たないウサギ、片眼鏡をかけたフクロウ、そして一本の古びた鍵を銜えたカラス。三体の動物が、まるで何かを囲むように配置されている。
「夫は亡くなる直前、この蔵書票をじっと眺めては、何事か呟いていたんです。『最後のピースが嵌まらない』と……。ただの事故だったと頭では分かっているのですが、もしかしたら、この蔵書票が何かを知っているのではないかと」
美咲の潤んだ瞳が、霧島の心の奥底に眠っていた探求心に火をつけた。高遠はただの編集者ではなかった。その鋭い嗅覚で、幾度となく社会の不正を暴きかけていた男だ。彼の死が、本当にただの事故だったのか。霧島は、その疑念をずっと拭えずにいた。
「この謎、解いてみよう。君が遺した、最後の物語だと思ってね」
心の中で親友に語りかけ、霧島はその奇妙な蔵書票を自宅に持ち帰った。それが、深い霧に覆われた真実へと続く、危険な小道の入り口だとは、まだ知る由もなかった。
霧島の調査は、まず蔵書票の図案そのものから始まった。時計を持たないウサギは『不思議の国のアリス』を彷彿とさせるが、物語のウサギは常に時間に追われている。片眼鏡のフクロウは知性の象徴か。鍵を銜えたカラスは、秘密の守り手か、それとも運び手か。神話、寓話、紋章学。書棚から引き抜いた知識を総動員しても、三つのシンボルを結びつける決定的な糸は見つからない。まるで、意味ありげに見えて、何の意味も持たない絵遊戯のようだ。
焦りが募る中、霧島は視点を変え、高遠の生前の足取りを追い始めた。彼が最後に担当していた企画は、新興の医療系ベンチャー企業『ネオ・ライフ社』の特集記事。表向きは革新的な技術で世間の注目を集めていたが、その裏では治験データの改竄や、認可を巡る黒い噂が絶えなかった。高遠は、その闇の核心に迫っていたのかもしれない。
「ウサギ、フクロウ、カラス……。まさか、情報提供者のコードネームか?」
その仮説に辿り着いた時、背筋に冷たいものが走った。もしそうなら、高遠の死は事故ではない。彼は消されたのだ。だが、だとしても、彼らが持つ情報がどこにあるというのか。蔵書票は、依然として沈黙を守っている。雨が窓ガラスを叩く音が、思考の行き詰まりを告げているかのようだった。
手詰まりになった霧島は、再び原点に立ち返った。蔵書票が貼られていた、何の変哲もない植物図鑑。高遠はなぜ、この本を選んだのか。ページを一枚一枚、指先で確かめるようにめくっていく。インクの染み、紙の焼け具合。そこに特別な細工は見当たらない。諦めかけたその時、あるページの片隅に、月の光を反射して微かに光る何かを見つけた。
それは、文字を書いた跡ではない。何か硬いもので押し付けられたような、ごく僅かな紙の凹み――圧痕だった。
霧島は息を呑み、机の引き出しから鉛筆を取り出すと、その圧痕の上をそっと撫でるように塗りつぶした。すると、まるで魔法のように、黒鉛の下から文字列が浮かび上がってきたのだ。
「SB-734-K」
銀行の貸金庫の番号だ。膝から力が抜けるのを感じた。高遠は、蔵書票の図案で霧島の目を眩ませ、本当に重要な情報を、この圧痕という古典的な手法で隠していたのだ。そして、あの動物たちはやはりコードネームだった。時間にルーズでいつも遅刻してくるフリージャーナリスト(時計のないウサギ)、博識だが専門分野以外の視野が狭い大学教授(片眼鏡のフクロウ)、そして決定的な証拠の『鍵』を握る内部告発者(鍵を銜えたカラス)。高遠は彼らから得た情報を一つにまとめ、誰にも知られぬよう貸金庫に封印したのだ。蔵書票は、それ自体が暗号なのではなく、暗号の在処を示すための、壮大なミスディレクションだった。
「見事だよ、高遠。君らしい、実に回りくどいやり方だ」
霧島は、震える手で美咲に電話をかけた。
貸金庫の中から現れたのは、小さなUSBメモリと数枚の内部文書だった。そこには、ネオ・ライフ社が行っていた非人道的な臨床試験の記録と、それを隠蔽するための金の流れを示す生々しいデータが収められていた。高遠の死が、口封じのための計画的な殺人であったことは、もはや疑いようもなかった。
霧島は匿名で、その証拠一式を信頼できる大手新聞社の社会部に送付した。数週間後、テレビも新聞もネオ・ライフ社のスキャンダルで持ちきりになり、関係者は次々と司直の手に落ちていった。
事件が世の喧騒から消え去ったある日の午後、霧島は自らの書斎で、静かにコーヒーを淹れていた。窓から差し込む柔らかな光が、机の上に置かれた一枚の蔵書票を照らし出す。時計を持たないウサギ、片眼鏡のフクロウ、鍵を銜えたカラス。今や全ての意味を理解したその絵は、まるで親友の不敵な笑みを写し取っているかのようだった。
彼の遺した物語は、決して悲劇では終わらなかった。霧島が、その最後のページを書き加えたのだ。カップから立ち上る湯気の向こうで、蔵書票の動物たちが、親友の魂と共に、安らかに眠っているように見えた。霧島は静かに目を閉じ、友の冥福と、守り抜かれた真実の重みを、胸の奥で噛み締めていた。