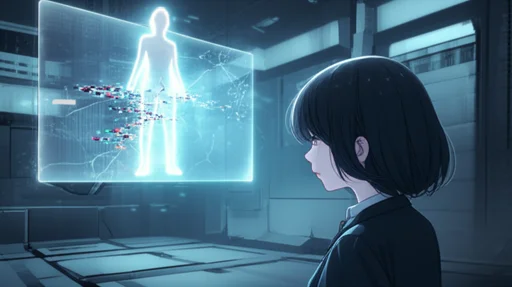古書の黴びた匂いと、静寂だけが満ちる店「時雨堂」。その主である俺、霧島聡は、カウンターの奥で分厚い革装丁の本の修繕をしていた。雨垂れが窓ガラスを叩く音だけが、世界のすべてであるかのような午後だった。客のいないこの空間こそが、俺の砦であり、聖域だった。
「ごめんください」
鈴を転がすような声が、その静寂を破った。顔を上げると、入り口に一人の若い女性が立っていた。湿った空気を含んだ黒髪が、白い頬に張り付いている。その瞳は、何かを必死に訴えかけていた。
「霧島聡さん、でいらっしゃいますか」
「……そうだが」
「高遠美月、と申します。父、高遠譲二の娘です」
高遠譲二。その名を聞いた瞬間、俺の指先で修繕用の針が鈍く光った。五年前、煙のように消えたかつての相棒。刑事としての俺の唯一の光であり、そして、深い闇でもあった男。
「親父さんは……見つかったのか」
「いいえ」美月はかぶりを振った。その仕草に、長い間抱え込んできたであろう疲労の色が滲む。「でも、父の書斎から、こんなものが見つかったんです」
彼女が差し出したのは、一枚の古びた便箋だった。そこには、万年筆で書かれたと思しき、意味をなさない文字列が羅列されているだけだった。暗号だ。それも、極めて個人的な。
「警察はただの悪戯だと。でも、私にはわかるんです。これは、霧島さんに宛てた父からのメッセージです。どうか、解読していただけませんか」
断るべきだった。高遠が関わった最後の事件は、俺の心に今も癒えない傷を残している。もう二度と、あの世界の泥水をすするつもりはなかった。だが、彼女の瞳の奥に、かつての相棒の面影が揺らめいた。俺は、まるで呪縛にでもかかったように、静かに頷いていた。
便箋を睨みつける日々が始まった。文字列は一見、無秩序に見えたが、そこには高遠らしい癖が隠されていた。二人で追いかけた過去の事件、通い詰めた安酒場の名前、俺が好んで読んでいた古典文学の一節。それらが、複雑な換字式の鍵になっていた。パズルのピースが一つ、また一つとはまっていくたびに、俺の心臓は嫌な音を立てて脈打った。
『青い琥珀を探せ』
『クラブ・カリギュラに巣食う亡霊を祓え』
青い琥珀。聞いたことのない代物だ。クラブ・カリギュラは、数年前に噂で聞いたことがある。政財界の大物が集う、非合法のプライベートサロン。高遠は、失踪直前にこのクラブを嗅ぎ回っていたのだろうか。
さらに調査を進めると、クラブの会員の一人が、数週間前にヨットからの転落事故で死んでいることがわかった。警察は事故として処理したが、状況には不審な点が多々あった。点と点が繋がり、おぼろげながら線が見え始める。高遠はクラブの不正を暴こうとし、何らかの証拠――おそらくそれが「青い琥訪」なのだろう――を手に入れた。だが、そのために何者かに追われ、身を隠さざるを得なくなった。美月に手紙を残したのは、唯一信頼できる俺に、後を託すためだ。俺は、そう結論づけた。
雨が降りしきる夜だった。ついに、暗号の最後の部分を解き明かした。高遠が俺だけに伝えたかった、核心のメッセージ。俺はそこに記された言葉を読み、全身の血が凍りつくのを感じた。
『この手紙を読んでいるのが聡なら、頼む。美月を信じるな』
脳を鈍器で殴られたような衝撃。なぜだ?娘である美月を、なぜ。思考が追いつかないうちに、店のドアベルがけたたましく鳴った。そこに立っていたのは、高遠美月だった。雨に濡れた彼女は、しかし、初めて会った時のような儚げな雰囲気は微塵もなかった。その唇は、嘲るかのように歪んでいる。
「さすがですね、霧島さん。もうお分かりになりましたか?」
声の温度が、氷点下まで下がっていた。
「父が隠した『青い琥珀』は、どこです?」
全てを悟った。美月は、父を裏切り、クラブ・カリギュラ側に寝返っていたのだ。いや、あるいは最初から、父を騙していたのかもしれない。高遠は、娘の裏切りに気づき、彼女から逃れるために姿を消した。そして、娘では決して解読できない暗号で、俺に真実を伝えようとしたのだ。俺に暗号を解かせ、琥珀の在り処を突き止めさせることこそが、美月の真の目的だった。
「お父さんは、君を心の底から心配していた」俺は静かに言った。「君が、道を踏み外さないようにと」
「感傷に浸るのはそこまでにして。さあ、琥珀はどこ?」美月がハンドバッグに手をかけた。その中には、おそらく冷たい金属の塊が潜んでいるのだろう。
絶体絶命。だが、俺の頭は、皮肉にも探偵だった頃のように冴え渡っていた。高遠の暗号、その裏の裏を読め。奴ならどこに隠す?最も安全で、最も意外な場所。
「……心当たりはある」俺は、わざとらしく天井を仰いだ。「高遠が言っていた。初めて二人で事件を解決したあの公園。思い出のベンチの下に、未来への希望を埋めた、と」
その瞬間、美月の冷徹な仮面がわずかに揺らいだ。高遠が、そんな感傷的なことを口にするはずがない。俺の言葉が、彼女の知らない「父と相棒の絆」を突きつけたのだ。その一瞬の動揺が、命取りだった。俺はカウンターの下に隠していた警察への直通ブザーを、力一杯押し込んでいた。
数日後、時雨堂に一通の封書が届いた。差出人は、保護された高遠譲二からだった。駆けつけた警官によって美月とクラブの人間は逮捕され、事件は解決した、と聞かされていた。
『ありがとう、相棒。あとは頼んだ』
短い文面の下に、一冊の古書のタイトルとページ数が記されていた。店の片隅、誰にも気づかれずに埃をかぶっていたその本を開く。指定されたページに、指先が触れるほどの厚みがあった。本の中心をくり抜いた空間に、小さな青い石が埋め込まれていた。まるで、深海の夜を閉じ込めたかのような、妖しい光を放つ琥珀。――いや、特殊なデータチップだった。高遠は最初から、俺のこの店こそが、最も安全な隠し場所だと知っていたのだ。
俺はチップを静かに握りしめた。窓の外では、長く続いた雨が上がり、淡い陽光が街を洗い流していた。止まっていた俺の時間が、再び動き出す。そんな予感がした。