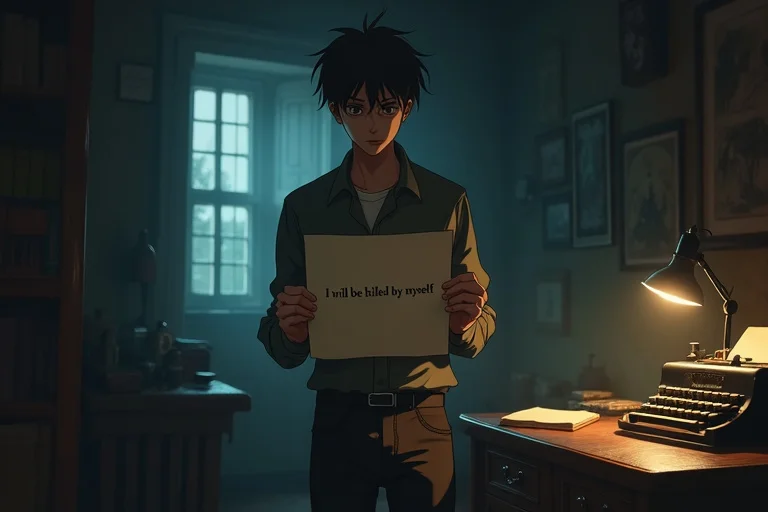私の職業は、少し風変わりだ。「記憶鑑定士」と名乗っている。といっても、超能力の類ではない。私は、人が語る記憶と、現場に残された物理的な痕跡との間に生じる僅かな齟齬を鑑定し、そこに潜む真実を炙り出す専門家だ。警察が「事実」を積み上げるなら、私は「記憶」の歪みを正す。
今回の依頼人は、憔悴しきった様子の青年、相田浩一と名乗った。彼の師である天才数学者、蔵前仁(くらまえじん)が忽然と姿を消したという。
「先生は……神隠しにでも遭ったとしか思えません」
現場は、街外れに建つ「鏡屋敷」と呼ばれる蔵前の書斎だった。その名の通り、部屋の四方の壁は床から天井まで巨大な一枚鏡で覆われ、無限に続く回廊のような錯覚を与える。異様な空間だ。
警察の現場検証は終わっていたが、状況は芳しくないらしかった。
書斎の扉は、内側から頑丈な鍵と閂(かんぬき)がかけられた完全な密室。窓もすべて施錠されていた。そして、その密室の主である蔵前はどこにもいない。
ただ一つ、異様な痕跡を残して。
部屋の中央、寄せ木張りの床に、チョークで描かれた長大で美しい数式が、まるで芸術作品のように鎮座していた。
「これは……先生が生涯をかけて挑んでいた『グロタンディークの最終定理』の証明です」
相田が震える声で言った。
「未解決だったはずの定理が……?では、蔵前先生はこれを解き明かしたと?」
「はい。そして、その答えだけを残して消えたんです。まるで、真理に到達した魂が、この世から解き放たれたみたいに……」
警察は、超常現象じみた事件に匙を投げていた。隠し扉の類は見つからず、鏡に仕掛けもなかった。私は書斎の中をゆっくりと歩き、鑑定を始めた。私の仕事は、まず依頼人の記憶を聞き出すことから始まる。
「相田さん、あなたの記憶の中の蔵前先生について教えてください。どんな些細なことでも構いません」
私は、床の数式を傷つけないよう注意しながら、相田に質問を重ねた。先生の癖、生活習慣、人間関係。相田はよどみなく、尊敬の念を込めて師の姿を語った。完璧な記憶。あまりに、完璧すぎる記憶だった。
「先生は右利きで、いつもこのドイツ製のチョークを愛用していました。そして、数式を書くときは、必ず部屋の北側から南に向かって書く、という奇妙なこだわりがあったんです」
相田が指差したチョークの箱は、机の上に整然と置かれていた。
私は床の数式に視線を落とした。確かに、数式は北から南へ、澱みなく綴られている。
だが、私はある一点に気づいた。チョークの粉が床に落ちる微細なパターン。線の始点と終点に残る、僅かな力の痕跡。
「相田さん」
私は静かに口を開いた。部屋の鏡が、私の姿を幾重にも映し出す。
「一つ、あなたの記憶と事実が食い違っている」
「……え?」
「蔵前先生は、この数式を書いていない」
相田の顔がこわばった。
「何を言うんですか!これは先生の筆跡だ!僕にはわかります!」
「ええ、筆跡は似ている。あなたは熱心に模倣したのでしょう。だが、決定的な違いがある。蔵前先生は右利きだった。しかし、この数式は、極めて技巧的な左利きの人物によって書かれている」
私は数式の始点を指差した。「線の入り、払いの角度、チョークの削れる向き。すべてが、左利きの人間が右手で書いたと見せかけるために不自然な力を加えた痕跡を示している。あなたは左利きですね、相田さん」
相田の息が止まった。彼の左手が、無意識に固く握りしめられる。
「それに、この証明……完璧すぎます。美しく、無駄がない。ですが、蔵前先生の過去の論文を拝見しました。彼はもっと独創的で、時に奇妙な飛躍を見せる天才。彼の思考の『癖』が、この証明には一切ない。まるで、誰かの完成されたメモを、ただ忠実に書き写したかのように」
静寂が、鏡張りの部屋に反響した。
「あなたは、蔵前先生の才能に嫉妬していた。先生が定理を証明する、その歴史的瞬間を目の当たりにしたあなたは、衝動に駆られた。先生をこの世から消し、その栄光を奪うために」
私は続けた。
「先生を薬で眠らせ、物置に隠した。そして、先生の完成させた証明のメモを盗み見て、この床に書き写した。あたかも先生が自力で証明を完成させ、人知を超えた存在に昇華したかのような、神秘的な失踪劇を演出し、いずれ自分が『師の遺志を継いで証明を再現した』と発表するつもりだったのでしょう」
最後の決め手は、鏡そのものだった。
「この部屋で、あなたと先生以外に、この数式の全体像を完璧な角度から見られた人間が一人だけいます。それは、この南側の鏡に映った『虚像』だけだ。あなたは、その虚像をカンニングペーパー代わりに使った。だから、数式は北から南へ、鏡を見ながら書きやすい一方向へしか進まなかった。先生の本来の癖なら、もっと自由なはずだ」
私は南側の鏡の隅、床との境目を指差した。そこには、肉眼ではほとんど見えない、チョークの粉を拭った微かな跡が残っていた。彼が証拠を消そうとした、唯一の痕跡だ。
相田浩一は、崩れ落ちた。鏡の中に映る無数の犯人が、同時に頭を抱えた。
彼の記憶は、師への尊敬という『建前』と、嫉妬という『本音』で歪んでいた。そして、その歪みは、現場に必ず痕跡を残す。
虚構の証明は、暴かれた。
私は静かに鏡屋敷を後にする。後には、天才が遺した真実の証明と、凡人が描いた虚構の証明だけが、並んで残されていた。