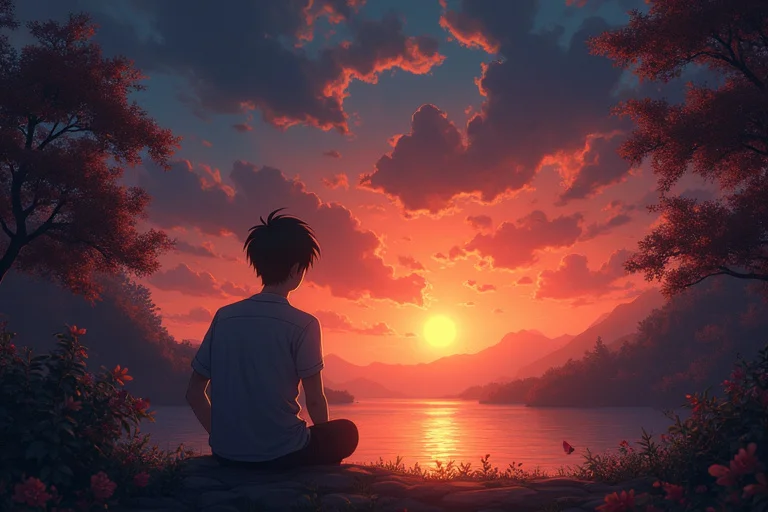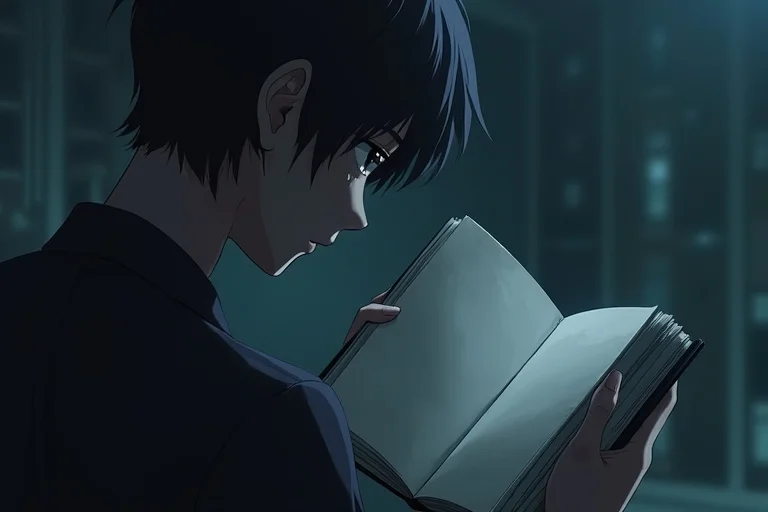第一章 月下の来訪者
神楽坂の裏路地にひっそりと佇む僕の店「香りのアトリエ」は、記憶を呼び覚ます香水を作る、という少し変わったコンセプトを掲げている。古い木製の扉を開けると、無数のガラス瓶が壁一面の棚に並び、琥珀色や翠色の液体が、間接照明の微かな光を吸い込んで静かにきらめいている。ローズやサンダルウッド、そして名も知らぬ樹脂の香りが混じり合い、時間の流れが止まったかのような空間を作り出していた。
僕、水沼涼介(みずぬま りょうすけ)は、この店の主であり、調香師だ。客の思い出話に耳を傾け、その記憶の断片を香りの分子に翻訳するのが僕の仕事だった。しかし、僕自身の記憶には、決して再現できない空白の香りがあった。十五年前、十歳の夏に忽然と姿を消した、五歳上の姉・美咲の香りだ。優しくて、いつも僕を守ってくれた姉。彼女の記憶は、月夜に咲く花のような、儚く甘い香りのイメージだけを残して、ディテールが思い出せないでいた。
その夜も、僕はカウンターで古い調香の本をめくっていた。雨がアスファルトを叩く音が、店内に静かに響いている。扉の鈴がちりんと鳴り、一人の女性が入ってきた。濡れた傘から滴る雫が、床の古木に小さな染みを作る。年の頃は僕と同じ三十歳くらいだろうか。黒いトレンチコートに身を包み、その顔立ちは月光を思わせるほど白く、整っていた。だが、その瞳には深い影が落ち、まるで何かから逃げているかのように、落ち着きなく揺れていた。
「いらっしゃいませ」
僕が声をかけると、彼女はびくりと肩を震わせ、ゆっくりとカウンターに近づいてきた。
「……香水を作っていただける、と聞きました」
その声は、雨音に溶けてしまいそうなほどか細かった。
「ええ。どのような香りを?」
「忘れたい記憶があります」
彼女の言葉は、僕の予想を裏切るものだった。記憶を呼び覚ますのではなく、消す。
「忘却の、香り……ですか?」
「はい。どうしても忘れ去りたい過去があるんです。その記憶が蘇るたび、息が詰まる。だから、その記憶を上書きしてくれるような、あるいは、その記憶から私を遠ざけてくれるような、強い香りが欲しいんです」
彼女はそう言うと、バッグから小さな押し花の栞を取り出した。月明かりの下で淡い黄色に咲く、月見草の押し花だった。その花を見た瞬間、僕の胸の奥が、ずきりと痛んだ。姉が失踪した夜、僕たちが最後に遊んでいた空き地にも、月見草が一面に咲いていたのだ。
そして、彼女がコートの襟元を直したその時、ふわり、と微かな香りが僕の鼻を掠めた。それは、僕がずっと追い求めてきた、姉の記憶の香りにどこか似ていた。甘く、切なく、そして懐かしい。しかし、それはすぐに彼女自身の纏う石鹸の香りに掻き消されてしまった。幻だったのだろうか。
僕はこの時、まだ知らなかった。彼女、名を相沢沙耶(あいざわ さや)と名乗った女性との出会いが、僕の止まっていた時間を、そして閉ざされた記憶の扉を、容赦なくこじ開けることになるということを。
第二章 忘却と記憶の断片
沙耶の依頼は、僕の調香師としてのプライドを刺激すると同時に、抗いがたい引力で僕を惹きつけた。「忘却の香り」を作るためには、まず彼女が「忘れたい記憶」を深く知る必要があった。僕たちは週に一度、この店で会うようになった。
彼女はぽつりぽつりと、記憶の断片を語り始めた。それは、幼い頃の記憶らしかった。暗い夜道、誰かの手、強い衝撃、そして甘い匂い。彼女はそれを「事故だったと思う」と言ったが、詳細は靄がかかったように思い出せないのだという。フラッシュバックのように蘇るその断片的なイメージが、長年彼女を苦しめていた。
「その甘い匂い、というのは?」
僕はガラス棒でベルガモットの精油を攪拌しながら尋ねた。
「わからないんです。お菓子のような……でも、もっと複雑で。その匂いを思い出すと、恐怖よりも先に、なぜかひどい喪失感に襲われるんです」
彼女の言葉を聞くたび、僕の胸には既視感にも似た痛みが走った。姉と食べた金平糖の味。失踪の夜、姉のポケットに入っていたはずの、小さな金平糖の袋。
僕は沙耶の「忘却の香り」の調香を進める傍ら、半ば無意識に、もう一つの香りを作り始めていた。姉の記憶を再現するための香りだ。月見草のアブソリュートを基調に、夜露を思わせる湿った土の香り(ジオスミン)、そして、金平糖のほのかな甘さを表現するために、数種類のアルデヒドとバニラを慎重にブレンドしていく。それは、失われた過去を取り戻そうとする、僕自身の祈りのような作業だった。
沙耶は、僕が姉の香りを調香していることは知らない。けれど、僕が試作した香りの小瓶を前にすると、彼女は決まって不思議な表情を見せた。
「この香り……どこかで嗅いだことがある気がします。懐かしいような、でも、少しだけ、怖いような」
彼女の瞳が不安げに揺れるのを見るのは辛かったが、同時に、僕の心には確信に近い予感が芽生え始めていた。僕たちが共有している記憶の断片は、本当にただの偶然なのだろうか。
ある雨の日、沙耶が店に忘れていった手帳を、僕は衝動的に開いてしまった。罪悪感に苛まれながらページをめくると、そこには美しい文字で日記が綴られていた。そして、最終ページに挟まれた一枚の写真を見つけ、僕は息を呑んだ。
それは、ひどく色褪せた古い写真だった。海を背景に、二人の少女が笑っている。一人は、明らかに幼い頃の沙耶だった。そして、その隣で、少し背の高い少女が、彼女の肩を抱いて優しく微笑んでいる。
その少女の顔を、僕は決して忘れるはずがなかった。
十五年前の夏から、僕の時間の中にだけ生き続けている、姉の美咲だった。
第三章 香りの告白
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。写真の中の姉は、僕の記憶の中の姿そのものだった。沙耶が、姉と一緒に写っている。これは一体どういうことだ? 混乱する頭で、僕は一つの、あまりにも突飛な仮説にたどり着いた。
沙耶が忘れたいと願う記憶。暗い夜道、強い衝撃、甘い匂い、そして喪失感。
姉が失踪した状況。夜の空き地、交通事故の噂、ポケットの中の金平糖、そして僕が姉を失ったという事実。
点と点が、僕の中で恐ろしい一本の線となって繋がった。
僕は震える手で沙耶に電話をかけた。「大事な話がある。今すぐ店に来てほしい」と。
一時間後、店に現れた沙耶は、僕のただならぬ様子に息を呑んだ。僕は黙って、カウンターの上に二つの小瓶を置いた。一つは、彼女のために作り上げた「忘却の香り」。力強いウッディノートとスパイシーな香料で、記憶を塗りつぶすための香りだ。そしてもう一つは、僕が密かに完成させた「記憶の香り」。月見草と夜露、そして金平糖の甘い香りが繊細に絡み合う、姉・美咲の香りだった。
「どちらの香りが欲しい?」
僕の問いに、沙耶は戸惑いながらも、無意識に「記憶の香り」の小瓶に手を伸ばした。
「……こっちの香りが、なぜか気になるんです」
僕はその手をそっと制し、彼女の手帳から抜き取った写真をテーブルに置いた。
「この写真に、見覚えは?」
写真を見た沙耶の顔から、さっと血の気が引いた。彼女は唇をわななかせ、写真の中のもう一人の少女を指さした。
「この子は……わからない。でも、夢に出てくるんです。私に『大丈夫だよ』って、何度も……」
僕は、もう抑えきれなかった。
「沙耶さん、あなたの忘れたい記憶は、事故なんかじゃない。あなたは、十五年前に僕の前から姿を消した、僕の姉さんなんだ」
僕の言葉は、静かな店内に重く響いた。
「あなたの名前は、相沢沙耶じゃない。水沼美咲だ。僕の、たった一人の姉さんだ」
沙耶――いや、美咲は、信じられないというように首を振った。
「そんな……だって、私は……」
「事件の日、姉さんは事故に遭って、頭を強く打った。そして記憶を失ったんだ。保護された先で、新しい名前を与えられて、別の人生を歩むことになった。君が忘れたいと願っていたのは、事故の瞬間の恐ろしい記憶と、そして、僕や家族のことを思い出せない、その途方もない喪失感だったんじゃないか」
僕は「記憶の香り」の小瓶の蓋を開け、香りを染み込ませたムエット(試香紙)を、彼女の前にそっと差し出した。
第四章 夜明けの金平糖
月見草の儚い香りが立ち上り、夜露の湿った匂いがそれに続く。そして、ラストノート――最後に現れる香りは、あの懐かしい金平糖の、淡く優しい甘さだった。
香りを吸い込んだ瞬間、美咲の瞳が大きく見開かれた。琥珀色の液体がきらめくように、彼女の瞳から大粒の涙が次々と溢れ落ちた。閉ざされていた記憶のダムが、香りの鍵によって決壊したかのようだった。断片的だったイメージが、奔流となって彼女の脳裏を駆け巡る。
「……涼介?」
十五年ぶりに呼ばれた僕の名前。それは、僕がずっと聞きたかった声だった。
「そうだよ、姉さん。僕だよ、涼介だ」
僕はカウンターを回り込み、崩れるように泣きじゃくる彼女の肩を、震える手で抱きしめた。姉の温もりだった。ずっと探していた、失われたはずの温もりだった。
全ての記憶が鮮明に戻ったわけではないようだった。彼女の中には「相沢沙耶」として生きてきた三十年近い人生も、確かに存在している。しかし、香りは、僕たちの間にあった空白の十五年間を飛び越えて、魂の最も深い部分に語りかけたのだ。
僕が作ったのは「忘却の香り」ではなかった。過去を消し去るのではなく、受け入れるための香り。失われた記憶を慈しみ、新しい自分の一部として再生させるための香りだった。
僕の内面にも、大きな変化が訪れていた。姉の失踪という過去に囚われ、止まっていた僕の時間は、彼女との再会によって、再びゆっくりと動き始めた。もう、後ろを振り返る必要はない。これからは、姉と共に前を向いて、新しい記憶を、新しい香りを、紡いでいけばいいのだから。
僕たちは、夜が明けるまで、たくさんのことを話した。失われた時間のこと、これからのこと。店の窓から、東の空が白み始めるのが見えた。夜の闇を溶かすように広がる、優しい光。それは、僕たちの未来を祝福しているかのようだった。
「この香り、金平糖の匂いがする」
涙の跡が残る顔で、美咲が微笑んだ。
「姉さんが好きだったから」
僕も笑い返した。
忘却は、救いではない。本当の救いは、忘れていた大切なものを思い出し、それと共に生きていく覚悟の中にこそあるのかもしれない。僕のアトリエに差し込む夜明けの光の中で、二つの孤独だった魂は、ようやく一つの未来を見つけ出していた。月影のラストノートが、新しい朝の空気の中に、静かに溶けていく。