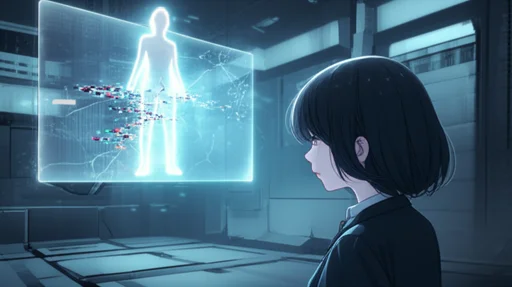調律師である俺、響 渡(ひびき わたる)の耳は、少しばかり特殊だ。一度聞いた音は、それがどんな些細な物音であっても、楽譜に書き起こせるほど正確に記憶してしまう。人々はそれを才能と呼ぶが、俺にとっては世界のノイズを拾い集め続ける、呪いにも似たものだった。
その日、俺が訪れたのは、霧深い湖のほとりにひっそりと佇む古い洋館だった。依頼主は、先日亡くなった天才ピアニスト・月島玲子の娘だという。依頼内容は、母の形見であるグランドピアノの調律。重厚な扉を開けると、ひやりとした空気と共に、沈黙が俺の鼓膜を撫でた。
案内された部屋の中央には、黒曜石のように鈍い光を放つグランドピアノが鎮座していた。埃ひとつなく磨き上げられているが、その佇まいにはどこか主を失った寂寥感が漂う。娘さんの話では、警察は玲子さんの死を長年の闘病の末の衰弱死と判断したらしい。彼女は静かに微笑み、「母の音が、また聴きたくて」とだけ呟いた。
鍵盤に指を置く。一つ、また一つと音を確かめていく作業は、死者との対話にも似ていた。玲子さんの指癖、情熱、そして苦悩までが、弦の震えを通して伝わってくるようだった。調律は順調に進むかに見えた。だが、ある特定の和音を鳴らした瞬間、俺の全身に鳥肌が立った。
本来の澄んだ音に混じって、ごく微かな、しかし決して聞き過ごすことのできない「異音」が響いたのだ。チッ、と短く鳴る、金属同士が擦れるような鋭い音。それは、ピアノが奏でるべき調和を乱す、明らかな不協和音だった。
一度や二度ではない。特定の鍵盤、特定の組み合わせで叩いた時のみ、そのノイズは顔を出す。まるで、ピアノ自体が何かを訴えかけているかのようだった。俺は調律を中断し、ピアノの内部をくまなく調べた。しかし、ハンマーにも弦にも、どこにも異常は見当たらない。
「母は亡くなる数日前、ずっと同じ曲を練習していました。聞いたこともない、不思議なメロディでした」
娘さんの言葉が、脳裏で反響する。俺は記憶を頼りに、彼女が口ずさんだメロディを再現してみた。すると、どうだろう。例のノイズが、楽譜の休符を埋めるように、リズミカルに、そして意図的に配置されていることに気づいた。これは単なる故障ではない。何者かが仕掛けた、音の暗号だ。
俺はポケットから手帳を取り出し、全ての意識を耳に集中させた。短い音(・)と長い音(-)。ノイズの連なりは、疑いようもなくモールス信号を形成していた。脳内で音を文字に変換していく。指先が興奮に震えた。
『ニカイ…マド…タンスノウラ…タスケテ』
二階、窓、箪笥の裏、助けて。
玲子さんの死は、衰弱死などではない。彼女は何者かに監禁され、このピアノを通して、最後のSOSを発信していたのだ。そして、そのメッセージはまだ終わっていなかった。信号は続く。
『アノヒトガ…ムスメヲ』
血の気が引いた。全身から急速に温度が奪われていく。犯人は、玲子さんを殺害した後、娘さんをも手にかけようとしている。いや、もうすでに…。目の前にいる穏やかな「娘」は、いったい誰なんだ?
「素晴らしい耳をお持ちですね、響さん」
背後からかけられた声に、心臓が凍りついた。振り返ると、さっきまでの儚げな微笑みを消し去った「娘」が、冷たい光を宿した瞳で俺を見つめていた。その手には、鈍く光るスパナが握られている。
「まさか、母の遺言に気づくなんて。あのピアノは高く売れるはずだったのに、あなたのような厄介な調律師を呼んでしまったのは、私の計算違いでした」
彼女は玲子さんの実の娘ではなかった。遺産を狙い、本物の娘をどこかに監禁している遠縁の親戚。まず玲子さんをゆっくりと毒殺し、次に娘になりすまして遺産を相続する計画だったのだ。玲子さんは、迫りくる死の恐怖の中、最後の力でピアノに細工を施し、本物の娘の居場所を示すメッセージを遺した。犯人がピアノを売却する際に、誰かが気づいてくれることを信じて。
「二階の窓際の部屋ですね。箪笥の裏に、本当の娘さんが」
俺は平静を装い、ゆっくりと告げた。彼女の顔が一瞬、驚愕に歪む。その隙を、俺は見逃さなかった。
渾身の力でピアノの最低音の鍵盤を叩きつける。轟音と共に、俺はそばにあった椅子を蹴り倒し、彼女の足元めがけて滑り込ませた。バランスを崩した犯人が体勢を立て直すより早く、俺は部屋を飛び出し、震える手で警察に電話をかけた。
やがて駆け付けた警察によって、犯人は捕らえられ、二階の部屋の隠し扉の奥から、衰弱しきった本物の娘さんが無事に保護された。
後日、俺はもう一度、あの屋敷を訪れた。依頼人は、救出されたばかりの、まだ顔色の悪い本当の娘さんだった。俺は全ての不協和音を取り除き、完璧に調律されたピアノで、玲子さんが遺した最後の曲を弾いた。そこにはもう、苦痛の信号はなかった。ただ、娘を想う母の愛情に満ちた、どこまでも優しく、そして美しいメロディだけが、静かな湖畔の屋敷に響き渡っていた。
俺の耳に残ったその音は、呪いではなく、確かな温もりを持っていた。