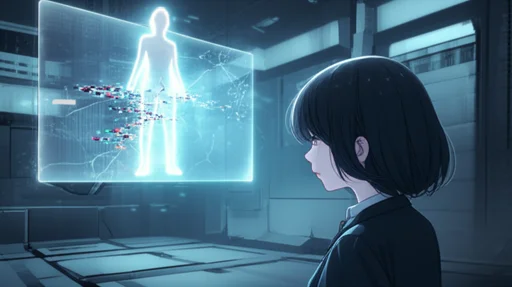ガタン、と古びた路面電車が揺れる。窓の外には、ガス灯の滲む光に濡れた石畳が続いていた。僕、時枝湊(ときえだみなと)の仕事は、少し変わっている。「記憶鑑定士」――それが僕の肩書だ。人の記憶に触れ、そこに焼き付いた映像を追体験する。ただし、万能ではない。僕が見ることができるのは、恐怖、歓喜、悲嘆といった、強い情動の奔流に刻まれた記憶の断片だけだ。日常の澱んだ記憶は、靄がかかったように判然としない。
今回の依頼人は、今をときめく天才マジシャン、セロ・ミカミの恋人でありアシスタントの、如月栞(きさらぎしおり)と名乗る女性だった。依頼内容は、一週間前に起きた「人間消失事件」の鑑定。
「満員の観客が見守る中、彼は舞台中央のガラス箱に入り……忽然と姿を消しました。それは彼の十八番のイリュージョン。でも、彼は二度と現れなかったんです」
警察の捜査は難航していた。関係者全員のアリバイは完璧。何より、観客の誰もが「事件」だとは認識していなかった。彼らにとって、それはただ「完璧なショー」の記憶でしかなかったからだ。
「時枝さん、あなたの力で、観客たちの記憶から何か見つけ出してください。何か、ほんの些細な違和感でもいいんです」
栞さんの切実な声に押され、僕は警視庁の灰谷(はいたに)刑事と共に、ショーの観客数名と会うことになった。灰谷刑事は、僕のようなオカルト紛いの能力者を苦々しく思っているのが、その仏頂面から見て取れた。
鑑定は困難を極めた。観客たちの記憶は、期待と興奮、そして驚愕というポジティブな感情で満ち溢れていた。セロ・ミカミがガラス箱に入る。スモークが焚かれ、眩い光が舞台を包む。そして、光が晴れた時、箱は空っぽになっている。観客席から湧き上がる割れんばかりの拍手と歓声。僕が何度記憶に潜っても、そこに「恐怖」や「不安」といった事件性を示す感情の棘は見つけられなかった。
「見たかね、時枝君。彼らにとっちゃ、最高のエンターテインメントだったんだ。あんたの出る幕はない」
灰谷刑事が吐き捨てるように言った。僕も、今回ばかりは自分の無力さを痛感していた。
行き詰まった僕は、最後の望みをかけて依頼人である栞さん自身の記憶を鑑定させてもらうことにした。彼女の許可を得て、そっとそのこめかみに指を触れる。
流れ込んできたのは、ミカミへの深い愛情と、ショーの成功を祈る純粋な思い。だが、その温かい記憶の奔流の底に、チクリと刺さる微かな棘を見つけた。ショーが始まる直前の、舞台袖の記憶だ。
――『いい加減にしろ、影山!お前のせいで、また昔みたいになるのはごめんだ!』
ミカミが誰かを激しく詰っている。相手は、温厚な人柄で知られる舞台監督の影山だった。影山は何も言わず、ただ静かに俯いている。栞さんの記憶の中のその光景は、ミカミへの心配という「不安」の感情に彩られていた。これだ。僕が探していた、事件に繋がる唯一の感情の断片。
「灰谷刑事、犯人は影山です」
僕は確信を持って告げた。灰谷刑事は眉をひそめる。
「馬鹿を言え。彼はショーの間、ずっと舞台袖の監督席にいた。完璧なアリバイだ」
「そのアリバイこそが、トリックなんです。犯人は、僕の能力の弱点を知っていたか、あるいは無意識に利用したんです」
僕たちは劇場へと向かい、舞台袖で影山と対峙した。僕は彼に、僕の推理を語り始めた。
「あなたは、観客全員を共犯者に仕立て上げた。ミカミが消えた瞬間を、誰一人として『殺人』の現場として記憶させなかった。なぜなら、それは最高の『イリュージョン』だったからです」
ミカミの消失トリックは、ガラス箱の底が開き、舞台下の奈落へと繋がる通路を通って楽屋へ戻るというものだった。観客もスタッフも、その段取りを信じきっている。だが、影山はその通路の途中でミカミを待ち伏せし、殺害した。誰も見ていない、文字通りの暗闇の中で。
「観客の記憶は『驚き』と『興奮』。スタッフの記憶は『いつも通りの手順』。そこには、僕の能力が反応する『恐怖』は存在しない。時計の秒針が、一瞬止まって見える『クロノスタシス』のように、あなたは誰も認識しない一瞬の空白を狙って犯行に及んだ」
影山は、静かに聞いていたが、やがてゆっくりと顔を上げた。その目は、僕が今まで見たこともないような、深い憎悪と悲しみに満ちていた。
「……時枝君、君なら気づいてくれると信じていたよ」
彼の口から語られたのは、衝撃の真実だった。
かつて、僕とミカミ、そして影山は、同じ師匠の下でマジックを学ぶ仲間だった。ミカミは、影山の考案したトリックを盗んで名を上げ、さらには僕の家族が巻き込まれたある機材事故の責任を、全て影山一人に押し付けたのだ。
「あいつは、君の家族の命さえ、自分の栄光のための踏み台にした。そして私は、全てを失った。この復讐は、あいつへの罰であると同時に、君への挑戦状でもあったんだ。君のその『力』で、誰もが騙されたこの完全犯罪を見破れるのか、とね」
栞さんの記憶にあったミカミの言葉。『また昔みたいになる』――それは、影山が事故の真相を暴露しようとしていることへの、ミカミの焦りだったのだ。その言葉に紐づいた過去の記憶を手繰り寄せたことで、僕は全ての真実にたどり着いた。
影山は、僕の目の前で静かに両手を差し出した。駆けつけた警官たちが彼を拘束していく。彼の供述通り、ミカミの亡骸は、劇場の地下深く、今は使われていない古い資材置き場の奥から発見された。
事件は解決した。だが、僕の心には、路面電車の窓を叩く雨音のような、鈍い痛みが残り続けていた。僕の力は、人の記憶を覗く。しかし、その記憶に刻まれた真実の重さまでは、鑑定することなどできはしないのだ。僕はただ、雨に濡れる街を眺めながら、自らの無力さと、これから向き合うべき過去の影を、静かに見つめていた。